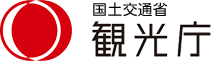7月長官会見要旨
最終更新日:2025年8月1日
日時:2025年7月16日(水)16:15~17:05
場所:国土交通省会見室
場所:国土交通省会見室
冒頭発言
(訪日外国人旅行者数(2025年6月)について)
本年6月の訪日外国人旅行者数は、約338万人となり、6月としては、過去最高となりました。
昨年同月と比べた伸び率は8%です。
本年1月から6月までの6か月間の累計では、約2,152万人となり過去最速で2,000万人を超えました。
本年6月の出国日本人数は、約105万人となりました。昨年同月と比べた伸び率は13%です。
(インバウンド消費動向調査2025年4-6月期(1次速報)について)
2025年の4月から6月期の訪日外国人旅行消費額は約2.5兆円と推計され、これは昨年の同期比で約18%の増となり、四半期としては過去最高額となりました。
ビジネス客や留学生を含む全目的の訪日外国人1人当たりの旅行支出は、約23.9万円となり、四半期として過去最高であった前年同期とほぼ同額となっております。
なお、この訪日観光支出がもたらす波及効果は、過去の状況で見ると訪日外国人消費額のおおむね2倍程度で推移しており、これを踏まえると、この4月から6月期の波及効果は、5兆円程度と推測ができます。
(参事官(旅行振興)の設置について)
日本人による国内旅行の消費額は、2024年に過去最高の25兆円となり、現在の観光立国推進基本計画における国内旅行消費額の2025年目標値22兆円を達成したところです。
今後、更なる国内旅行の活性化に向けて、日本人の国内旅行需要を高めていくことが重要と考えております。
一方で、日本人による海外旅行者、所謂アウトバウンドの数については、昨年2024年は1,300万人と、回復傾向にありますが、コロナ前の2019年水準をまだ下回っております。
今後、好調な訪日外国人旅行者との相乗効果を生み出して、このアウトバウンドの需要をさらに喚起していく必要があると考えております。
また、観光分野では長期的に人手不足状態が続いており、直近では観光需要の回復等に伴って人手不足感がさらに高まっています。今後、観光人材の確保育成を強力に推進し、旺盛な観光需要をしっかりと取り込んでいく必要があります。
以上のような観点から観光庁におきましては本年の7月1日に旅行振興の参事官を新設いたしました。このような政策課題に取り組みまして観光立国の実現に寄与してまいりたいと考えております。
本年6月の訪日外国人旅行者数は、約338万人となり、6月としては、過去最高となりました。
昨年同月と比べた伸び率は8%です。
本年1月から6月までの6か月間の累計では、約2,152万人となり過去最速で2,000万人を超えました。
本年6月の出国日本人数は、約105万人となりました。昨年同月と比べた伸び率は13%です。
(インバウンド消費動向調査2025年4-6月期(1次速報)について)
2025年の4月から6月期の訪日外国人旅行消費額は約2.5兆円と推計され、これは昨年の同期比で約18%の増となり、四半期としては過去最高額となりました。
ビジネス客や留学生を含む全目的の訪日外国人1人当たりの旅行支出は、約23.9万円となり、四半期として過去最高であった前年同期とほぼ同額となっております。
なお、この訪日観光支出がもたらす波及効果は、過去の状況で見ると訪日外国人消費額のおおむね2倍程度で推移しており、これを踏まえると、この4月から6月期の波及効果は、5兆円程度と推測ができます。
(参事官(旅行振興)の設置について)
日本人による国内旅行の消費額は、2024年に過去最高の25兆円となり、現在の観光立国推進基本計画における国内旅行消費額の2025年目標値22兆円を達成したところです。
今後、更なる国内旅行の活性化に向けて、日本人の国内旅行需要を高めていくことが重要と考えております。
一方で、日本人による海外旅行者、所謂アウトバウンドの数については、昨年2024年は1,300万人と、回復傾向にありますが、コロナ前の2019年水準をまだ下回っております。
今後、好調な訪日外国人旅行者との相乗効果を生み出して、このアウトバウンドの需要をさらに喚起していく必要があると考えております。
また、観光分野では長期的に人手不足状態が続いており、直近では観光需要の回復等に伴って人手不足感がさらに高まっています。今後、観光人材の確保育成を強力に推進し、旺盛な観光需要をしっかりと取り込んでいく必要があります。
以上のような観点から観光庁におきましては本年の7月1日に旅行振興の参事官を新設いたしました。このような政策課題に取り組みまして観光立国の実現に寄与してまいりたいと考えております。
質疑応答
(問)観光庁長官就任にあたっての抱負をお伺いします。また、政府の目標達成に向けた今後の課題面をどう捉えているのか、そして特に注力したい施策があればお聞かせください。
(答)
まず、私自身のことですが、観光庁には2019年から2022年の3年間在席し、前半2年間は観光地域振興部長、そして後の1年間は次長を務めさせていただきました。
この3年間においては、最初の半年が経過した後に、新型コロナウイルスの影響が拡大し、それ以降のほとんどの期間は観光に対する厳しい状況の中で、観光関連の業界や皆様をどのように支援し、事業継続と雇用をどのように守っていくかということに全力を注いでおりました。
そのような先行き不透明な状況が現在解消されて、様々な前向きな取組ができるようになっているこの観光を取り巻く現状、現在の環境というものは、当時の苦境と比較して考えたときに、本当に嬉しく思いますし、ありがたいことであると感じています。
その上での抱負になりますが、まずは2030年訪日客数6,000万人・消費額15兆円という政府目標の達成に向けて、ボトルネックや課題を把握した上で、来年3月の基本計画の改定等の重要課題にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
目標達成に向けた現状ですが、先ほど述べました通り、今年の上半期の累計では訪日客数は約2,152万人と、過去最速で2,000万人を突破し、消費額も約4. 8兆円と、いずれも昨年を上回るペースで推移しており、非常に好調であります。
一方で、三大都市圏以外の地方部における訪日外国人旅行者の1人当たりの宿泊数を2泊とするといった現行基本計画の目標については現時点ではまだ達成できておりません。
このような現状や課題を踏まえて、注力したい点は、大きく2つあります。一つ目は好調なインバウンドの流れを確固たるものにするためにも、地域社会・経済に好循環を生む「持続可能な観光地域作り」を力強く推進してまいりたいと考えています。
もう一点は特別な体験の提供や、地方部での滞在を促進するためのコンテンツ造成を通じて「地方誘客の促進」に引き続き取り組んでまいりたいと考えています。
これから様々な方のご意見に耳を傾けながら、これらの施策を進めてまいりたいと考えています。
(問)1月から6月の訪日外国人旅行者数について、最速で2,000万人を突破したということですがその受け止めをお聞かせください。あわせて、今後の見通しについて長官の見解をお伺いします。
(答)
繰り返しになりますが、本年6月の訪日外国人旅行者数は約338万人となりました。昨年よりも約8%の増加、6月として過去最高です。
そして本年前半の累計では約2,152万人と、こちらも前年同期比で21%の増加であり過去最速で2,000万人を突破し、上半期の数字としても過去最高となっております。
具体的には、インバウンドの約8割を占めるアジア諸国が、前年同期比で19%の増、そして欧米豪・中東諸国が、前年同期比で28%の増となっております。
堅調な訪日需要と、航空便の回復等により、おおむねインバウンドは好調な状況であり、力強い成長軌道に乗っていると受け止めております。
今後の見通しにつきましては、インバウンドは様々な要素の影響を受けることから現時点で申し上げることは差し控えたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、2030年6,000万人という政府目標の達成に向けて、引き続き訪日者数の増加に向けた戦略的なプロモーションを実施するなど、訪日者数の更なる拡大に取り組むとともに、地方誘客についても積極的に進めてまいりたいと考えています。
(問)この度、旅行振興担当参事官を設置されたが、観光庁として参事官室を設置したり組織を改編するのは久しぶりだと思います。日本人の国内旅行・アウトバウンドや人材育成等を切り離して独立させたということも含めて、組織改正の狙いをお伺いします。
(答)
組織の新設の狙いについては冒頭発言したとおりですが、インバウンドをこれから進めるにあたり、相手国との双方向の交流を進めることが極めて重要であり、そのためにも一方向で来ていただくだけではなくて、こちらからもお伺いするというアウトバウンドの需要を進めていくことが重要であると考えています。
国際相互理解の増進による諸外国との友好関係の更なる深化や航空ネットワークの維持や拡大にも資する双方向の交流拡大に向けて、インバウンドとの相乗効果を生み出しながら、アウトバウンド需要の喚起のための施策を進めてまいりたいと思います。
こういった観点から、旅行振興参事官で相乗効果をきちんと生み出すような施策を考えていただきたいということで新しい組織を作りました。
アウトバウンドのみならず国内旅行の需要の喚起も重要な課題ですので、そのためにも、観光人材の確保や育成といった政策課題についても力を入れて取り組んでまいりたいという趣旨です。
(問)秡川前長官からの引継ぎにあたり、何かメッセージや留意点として伝えられたことがあれば、ご披露いただきたい。
(答)
秡川前長官からは様々なことを引き継いでおりますが、重要なものは大きく2点あったと認識しています。
一つ目は現在のインバウンドの好調な状況を踏まえて、現在検討中の次期観光立国推進基本計画の策定をしっかりやっていってほしいということです。
もうひとつは観光庁の働き方改革です。前長官のもとでしっかりと進めてきたので、私の体制になっても続けてほしいということです。
付言しますと、次期観光立国推進基本計画については、6,000万人15兆円の政府目標に向けたボトルネックや課題の整理を行った上で、地方誘客のより一層の促進や人手不足対策の取組等も含め必要な取組の検討を深めて、本年度末までの策定に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
二つ目の働き方改革ですが、秡川前長官時代から休暇取得やテレワークの促進、職員間のコミュニケーションの活性化を積極的に進めてきたところです。
私としても今後、職場の上下左右の風通しを良くするなど、こういった取組を加速させるとともに、職員の声をよく聞きながら、私のモットーであります「明るく楽しく仕事をする」職場作りを実行してまいります。
秡川前長官から託されたバトンをしっかりと受け継ぎ、観光産業の一層の発展のために誠心誠意取り組んでまいりたいと考えています。
(問)オンライン宿泊予約サイトのアゴダの問題についてお伺いします。同社を巡っては、利用者から相談が相次いでいると認識しておりますが、観光庁で把握している事実関係と今後の対応、さらにアゴダ社の再発防止策に対してどのように受け止めているのか、ご所見をお願いします。
(答)
観光庁といたしましては、旅行者が安全・安心に旅行を楽しんでいただくことは、観光立国を推進していくうえで大変重要であると考えております。
アゴダにつきましては、観光庁として、アゴダを巡ってトラブルが生じているといった利用者の声が寄せられていたことから、本年3月からアゴダに対して、トラブルの改善を申し入れてきたところです。
このような観光庁からの申し入れも踏まえ、アゴダにおいてはトラブルが生じている第三者サプライヤー経由の宿泊商品の販売を停止することを6月26日から講じたということです。
また、今後はAIを活用した事前監視システムの導入や第三者サプライヤーへの管理体制の強化等の対応を行う旨を昨日、会社として公表したものと承知しており、観光庁にもその報告がありました。
観光庁といたしましては、引き続きこの予約トラブルの発生状況や、アゴダが公表した改善策の進捗状況をこれからも確認を続けていくこととしており、必要に応じて適切な対応を行ってまいりたいと考えております。
あわせて、一般消費者の皆様に対しましても、旅行予約サイトを利用する際には、利用規約や約款、あるいは問い合わせ先について、あらかじめよくご確認いただくということを観光庁のホームページ上でも一層の注意喚起を行ったところであり、引き続きそのような取組を進めてまいりたいと考えております。
(問)こういった事案は、個社の問題なのか、それとももう少し広く横串を刺して把握すべき事案なのか、その辺のご所見をお伺いします。
(答)
現時点におきましては、アゴダ以外の宿泊予約サイトを運営する事業者において同様のトラブルが多く生じているという事実関係を承知しておりません。
今後、利用者からそういった声が多いということでありましたら、アゴダ以外の予約トラブルに対しても適切に対応してまいりたいと考えております。
(問)インバウンドの消費額について、4~6月の四半期で過去最高ということですが、1~6月の上半期で見ても過去最高ということでよろしいでしょうか。また、4~6月の四半期で過去最高となった背景や要因、長官の受け止め、上半期の消費額に対しての評価や背景についてお伺いします。先ほど2030年15兆円という目標に対する課題や注視していきたい点があれば教えてください。また、観光庁は富裕層インバウンド誘致の施策も展開していますが、こういった取組も消費額に影響しているのかお伺いいたします。
(答)
まず4月から6月期のこの訪日外国人旅行消費額は、2. 5兆円で、四半期としては過去最高であります。
この背景ですが、中国の訪日客数の回復や、欧米豪を初めとする訪日客数が増加していること、さらに平均泊数の増加などが要因として考えられます。
1月から6月期の上半期の消費額についても、累計4.8兆円でこちらも上半期としては過去最高であり、インバウンドは力強い成長軌道に乗っていると受け止めております。
富裕層の誘客につきましては、観光庁ではこれまでも消費単価の高い高付加価値旅行者の誘致促進を目指し、地方の14のモデル観光地に対する、旅行会社等の招請を通じた魅力的なコンテンツの磨き上げや販路形成のためのプロモーションといった集中的な支援、体験コンテンツの造成や宿泊施設を核とした面的な取組への支援などに取り組んできたところであり、このような取組も成果として表れてきている面があるのではないかと考えております。
観光庁といたしましては、引き続き高付加価値旅行者をはじめとするインバウンドの誘客拡大と消費額の更なる高みを目指して取り組んでまいりたいと考えております。
(問)消費額15兆円達成に向けた足元の課題などがあればお伺いします。
(答)
様々な課題があると思いますが、例えば地方部における宿泊数につきましては、先ほど述べたとおり、まだ現行の基本計画の目標に達していないこともありますので、地方部の宿泊数を伸ばして長期滞在を進めていくことは、今後の消費額の拡大に向けて大事なポイントだと考えております。
(問)7月以降多くの市場において訪日旅行者数がピークになる時期になるかと思いますが、そこに向けてのご所感をお伺いします。もう1点、7月5日に地震の予言日とされた日がありましたが、その前後で旅行需要の変化があったかをお伺いします。
(答)
まず1点目について、インバウンドは様々な要素の影響を受けるということで、見通しについて申し上げることはなかなか難しいところでありますが、7月は夏の学校休暇等があり、訪日旅行者数が年間を通じても多くなる時期でありますので、観光需要は高まることが期待されております。
我が国の原風景と言えるような風光明媚な景観や町並み、あるいは地域で大切に受け継がれてきた地場産業、そして豊かな自然環境の恵みを受けた地域固有の食文化など魅力的な観光資源が日本各地には数多く存在しており、こういったものはインバウンドの皆様にも強く訴求すると考えております。
7月5日の地震の噂につきましては、まず、地震の予知については内閣府や気象庁から現在の科学的知見から、日時と場所を特定した予知は困難であるということは繰り返し発信していただいております。
観光庁としましては、5月にJNTOの香港事務所を通じて、旅行を判断する際は、こうした公的機関による科学的な情報を参照してほしいという旨を中国語で発信するとともに、この発信内容についてJNTOから旅行会社等に対しても情報提供を行うといった対応を進めてきたところであります。
7月5日以降の状況に関しては、現時点で明確なことは申し上げられませんが、7月5日以降に訪日旅行販売キャンペーンを実施している現地の旅行会社や香港の消費者からの訪日旅行の問い合わせが大きく増加している旅行会社があると承知をしております。
このような動きの増加が、訪日旅行者数の増加につながる具体的な時期については、明確なことは今申し上げられませんが、引き続き香港以外の市場も含め、訪日者数の動向あるいは航空便の減便、旅行キャンセルの状況などを注視してまいりたいと考えております。
(問)統合型リゾートIRについてお伺いします。北海道でも経済界などからIR誘致を求める声も出ている状況です。先月、秡川前長官が札幌の観光フォーラムで講演された際も、IRは新しい観光拠点になるという趣旨のお話をされていました。観光庁はIRの候補地として北海道に注目されているのかなという受け止めもできるかと思うのですが、村田長官は、北海道のIRの可能性をどう見ていらっしゃるかお考えをお聞かせください。
(答)
IRにつきましては、カジノだけではなく、MICE施設やホテル、そして送客施設等が一体で整備され、多くの観光客を呼び込む滞在型観光の拠点であり、観光振興だけではなく、地方創生に繋がる効果が期待できるものと認識しております。
そしてこのIRの整備でありますが、IR整備法上、自治体の発意に基づき行われるものでありまして、国としては、自治体と自治体が選定した事業者から申請された区域整備計画につきまして、認定の可否を判断する立場でございます。
そのため、国として、また私個人としても特定の地域の評価についてのコメントは差し控えさせていただきたいというふうに思います。
(問)関連でもう1点、秡川前長官が札幌の講演のときに、IRの候補地の選定についてそう遠くない時期に決まると発言されていましたが今観光庁として選定スケジュール、検討しているものがありましたらどのような状況かお聞かせください。
(答)
IR整備法では、区域整備計画の認定の数について3つを上限とするということになっており、認定の申請は政令で定める期間内にしなければならないと定められております。
この政令を定めるに当たりましては、IR整備法の附帯決議におきまして、各地方公共団体による申請を公平に受けられる期間とすることとされております。
このため認定の申請期間を定めるに当たりましては、公平性を確保する観点から、申請主体である自治体の状況をよく見極めた上で判断する必要がありまして、自治体の状況を注視してまいりたいというふうに考えております。
現時点で決まったスケジュールはございません。
(問)観光の足として、鉄道だけではなくバスやタクシーも役割があると思いますが、先ほどのご発言にあるような地方誘客の面で隅々まで観光客をといったところでも活躍があるかと思いますが、バスとタクシーそれぞれの業界に期待やメッセージがあればお願いします。
(答)
国内外の観光客の方に日本各地の魅力ある観光地を訪れていただくためには、先ほど申し上げた観光コンテンツの開発や情報発信といった取組とあわせて、「観光の足」の確保を図っていくことは非常に重要な課題であると考えております。
このような観点からバスやタクシー、こういった皆様に対しましても大きく期待を寄せているところではありますが、他方で、人口減少、担い手が不足する中で、どのようにしてこの「観光の足」の確保を図っていくかは大変重要な課題であると認識しております。
現在、国土交通省全体におきましても、「交通空白」の解消に向けては関係部局と連携しながら様々な取組が進められております。
具体的には、日本版ライドシェアあるいは公共ライドシェアの導入、レンタカーの利用環境の整備、連節バスやジャンボタクシーの導入、また自動運転バスの社会実装など、あらゆる手段を総動員して対策を講じていく必要があると考えており、観光庁としても、関係部署と連携しながら、このような地域の取組をしっかり後押ししていくことで、「観光の足」の確保に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
バスやタクシーは非常に重要な公共交通機関でありますので、私どもとしてもぜひ連携して取組を進めてまいりたいと考えております。
(問)アゴダの件で、3月に改善要請を出されていると思いますが、その趣旨について教えてください。
(答)
3月の申し入れの趣旨は、その頃にアゴダを巡り予約に関するトラブルが生じていると、利用者の声が寄せられたということでありましたので、行政指導として、観光庁からアゴダに対して、そのような利用者に対する予約のトラブルが実際生じているのか、生じているならば改善をすべきだと申し入れてきました。
(問)国内旅行の活性化の観点で、「何度も地域に通う旅」といった第2のふるさとづくりについて今後の取組方針をお伺いします。もう一点、「国内旅行需要の平準化」について、ワーケションやブレジャー、休み方改革を含めた休暇取得分散化などの施策に関して現時点で認識している課題をお伺いします。
(答)
まず1点目について、「何度も地域に通う旅、帰る旅」を定着させる第2のふるさとづくりやワーケーションは、地域住民との交流を通じた来訪者の関係人口の増加に繋がる取組だと考えております。
観光庁ではこれまで、第2のふるさとづくりの推進に向けて、令和6年度までに累計36地域でモデル実証を実施するとともに、ワーケーションの推進に向けて、地域と企業のマッチング支援や令和6年度までに78件のモデル事業の創出等を実施してきました。
今年度は、これらの取組を「第2のふるさとづくりプロジェクト」として統合し、地域との繋がりの創出に加えて、地域への経済波及効果と事業の持続可能性が両立した先駆的なモデル事業の創出を実施しています。
観光庁としましては、第2のふるさとづくりやワーケーションの推進を通じた関係人口の増加に繋げ、新たな交流市場の拡大に向けた取組を進めてまいりたいと考えています。
2点目の国内旅行の需要の平準化ですが、今ご指摘いただきましたように、日本では、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆などに旅行する方が多く、特定の時期に観光客が集中する実態があります。
国内旅行の平準化については、ご指摘のように休暇の取得促進と分散化を進めていくことが、重要であると考えております。
観光庁におきましては、休暇を取得しやすい職場環境を整えて、旅行を楽しむことを積極的に促進する企業を紹介する「ポジティブ・オフ」運動を行っており、現在2,800を超える企業・団体から賛同いただいています。
またワーケーションにつきましても平準化のための取組として捉えており、今申し上げたようなモデル事業の造成にも取り組んでおります。
旅行の平準化と言う意味におきましては、平日での旅行が多く重要な平準化が見込まれる、高齢者層の方々の国内宿泊旅行経験率がコロナ以降まだ回復していない状況があります。いわゆる経験率が低下している状況が続いていますので、高齢者の方々が旅行しやすい環境を整備するユニバーサルツーリズムの促進を図っております。
こうした取組を通じて、国内旅行需要の平準化も引き続き進めてまいりたいと考えております。
(問)香港市場についてお伺いします。まず6月の客足が3割以上減とありますがこれの評価と対策、9月から飛行機便が減便ではなく運休するということも出ていますが、こういったリスクはいつまで続きそうなものか、対策を合わせてお伺いします。
(答)
香港については、香港ではご案内の通り、日本の漫画やその内容をもとにした風水師の予言等によりまして、7月5日に日本で大地震が起こるという噂がSNS等によって広がり、旅行のキャンセルが生じたという状況であると認識をしております。
一部の航空会社におきましては、日本路線の減便を行っている会社があると承知しておりますが、これは航空会社におきまして、今後の経済状況の見通しなどの様々な要素を総合的に判断した結果であるというふうに考えております。
そういった要因により、香港市場で33%の減となったことは事実として受け止めておりますが、先ほど申し上げたように今後についてはまた新たな動きが出つつあると理解をしております。
(問)関連して、今回、災害は起きていないが、先に風評被害だけが起きているという状況です。去年災害に強い観光地を目指すレジリエンスサミットを開催しましたが、これが何かの役に立ったのかお伺いします。実務者会議は18日から開かれ、香港の件は特に話題になっていないようですが、これがどのように役立てられるのかお伺いします。
(答)
昨年の観光レジリエンスサミットでは、近年で自然災害の頻発化・激甚化あるいは新型コロナの世界的な流行というようなことがありましたので、観光分野の脆弱性というのが改めて認識されました。
そういった中で、観光レジリエンスの向上というものが重要なテーマになりつつあったということであります。
昨年の観光レジリエンスサミットにおいては、観光レジリエンス向上に向けた取り組みの方向性として、危機や自然災害による影響の予防や最小化、また危機や自然災害による影響の吸収、回復過程の適用と変革、の二つの柱に基づく仙台声明を採択したところです。
仙台声明は、昨年議論した内容ですが、実際に自然災害等が発生した際の対策を念頭に置いたものであります。
しかしながら、観光レジリエンスサミットで、各国と共有した問題意識、これは正確な情報発信ということもありましたので、観光庁としては、今回の地震の噂に対し、気象庁やJNTOと連携しまして、正確かつ迅速な情報発信に努めてきました。
こうした取組もありまして、香港はマイナス33%ですが全体の訪日客数は、6月として過去最高になっている状況と考えております。
(問)消費額に関してお伺いします。四半期、上半期いずれも過去最高ということですが、昨年に比べて伸び率は鈍化しているかと思うが、その要因や受け止めをお伺いします。また、1人あたりの支出額は増えているが、前年同期比ではマイナスになっている点について、どう分析しているか教えていただきたい。
(答)
1人当たりの消費額については、マイナスではありますが1%未満ということで、こちらはほぼ同額と私どもとしては考えていいのではないかと思います。
伸び率の鈍化につきましては、6月は香港の噂の影響等もあり、マイナスとなっている国もあり、総合的に影響している可能性はありますが、まだ私どもとして一義的な要因を把握しているわけではございません。
(問)1人当たり消費額について、中国がマイナス12.5パーセントとなっていますが、かつての爆買いといったところから何かトレンドの変化などがあるのか、分析があればお伺いします。
(答)
(観光庁事務方より)中国については、ご指摘のとおり買い物代などの低下もあり、1人あたりの支出は減っている状況であります。ただし、このトレンドが今後継続的に進んでいくのかどうかについては、実際の数字を見ていかないとはっきりしないと思いますので、今後も注視していきたいと思います。
(問)香港は訪日客数のなかで結構な割合を占めているが、一連の噂によって旅行者はだいぶ減り、脆弱性というか観光が受ける影響の大きさを示したと思う。これまでも旅行者に対する情報発信をされてきたかと思うが、改めて届ける形での情報提供の難しさがあると思った。長官としてどのよう受け止めているかお伺いしたい。
(答)
情報発信のあり方について、政府としてできることは、気象庁長官によるこれはデマであるということの明確な情報発信や、JNTOを通じて現地の皆様に対応することがあります。
秡川前長官も香港のメディアの取材に応じて、そういったことは心配しないで来てほしいといったメッセージも出していました。しかし、結果的にはこのような数字となり、絶対これをやれば良いという解決方法が、今あるわけでありません。
今回のことを教訓にして、どういったことができるか、引き続き考えてまいりたいと思います。
(答)
まず、私自身のことですが、観光庁には2019年から2022年の3年間在席し、前半2年間は観光地域振興部長、そして後の1年間は次長を務めさせていただきました。
この3年間においては、最初の半年が経過した後に、新型コロナウイルスの影響が拡大し、それ以降のほとんどの期間は観光に対する厳しい状況の中で、観光関連の業界や皆様をどのように支援し、事業継続と雇用をどのように守っていくかということに全力を注いでおりました。
そのような先行き不透明な状況が現在解消されて、様々な前向きな取組ができるようになっているこの観光を取り巻く現状、現在の環境というものは、当時の苦境と比較して考えたときに、本当に嬉しく思いますし、ありがたいことであると感じています。
その上での抱負になりますが、まずは2030年訪日客数6,000万人・消費額15兆円という政府目標の達成に向けて、ボトルネックや課題を把握した上で、来年3月の基本計画の改定等の重要課題にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
目標達成に向けた現状ですが、先ほど述べました通り、今年の上半期の累計では訪日客数は約2,152万人と、過去最速で2,000万人を突破し、消費額も約4. 8兆円と、いずれも昨年を上回るペースで推移しており、非常に好調であります。
一方で、三大都市圏以外の地方部における訪日外国人旅行者の1人当たりの宿泊数を2泊とするといった現行基本計画の目標については現時点ではまだ達成できておりません。
このような現状や課題を踏まえて、注力したい点は、大きく2つあります。一つ目は好調なインバウンドの流れを確固たるものにするためにも、地域社会・経済に好循環を生む「持続可能な観光地域作り」を力強く推進してまいりたいと考えています。
もう一点は特別な体験の提供や、地方部での滞在を促進するためのコンテンツ造成を通じて「地方誘客の促進」に引き続き取り組んでまいりたいと考えています。
これから様々な方のご意見に耳を傾けながら、これらの施策を進めてまいりたいと考えています。
(問)1月から6月の訪日外国人旅行者数について、最速で2,000万人を突破したということですがその受け止めをお聞かせください。あわせて、今後の見通しについて長官の見解をお伺いします。
(答)
繰り返しになりますが、本年6月の訪日外国人旅行者数は約338万人となりました。昨年よりも約8%の増加、6月として過去最高です。
そして本年前半の累計では約2,152万人と、こちらも前年同期比で21%の増加であり過去最速で2,000万人を突破し、上半期の数字としても過去最高となっております。
具体的には、インバウンドの約8割を占めるアジア諸国が、前年同期比で19%の増、そして欧米豪・中東諸国が、前年同期比で28%の増となっております。
堅調な訪日需要と、航空便の回復等により、おおむねインバウンドは好調な状況であり、力強い成長軌道に乗っていると受け止めております。
今後の見通しにつきましては、インバウンドは様々な要素の影響を受けることから現時点で申し上げることは差し控えたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、2030年6,000万人という政府目標の達成に向けて、引き続き訪日者数の増加に向けた戦略的なプロモーションを実施するなど、訪日者数の更なる拡大に取り組むとともに、地方誘客についても積極的に進めてまいりたいと考えています。
(問)この度、旅行振興担当参事官を設置されたが、観光庁として参事官室を設置したり組織を改編するのは久しぶりだと思います。日本人の国内旅行・アウトバウンドや人材育成等を切り離して独立させたということも含めて、組織改正の狙いをお伺いします。
(答)
組織の新設の狙いについては冒頭発言したとおりですが、インバウンドをこれから進めるにあたり、相手国との双方向の交流を進めることが極めて重要であり、そのためにも一方向で来ていただくだけではなくて、こちらからもお伺いするというアウトバウンドの需要を進めていくことが重要であると考えています。
国際相互理解の増進による諸外国との友好関係の更なる深化や航空ネットワークの維持や拡大にも資する双方向の交流拡大に向けて、インバウンドとの相乗効果を生み出しながら、アウトバウンド需要の喚起のための施策を進めてまいりたいと思います。
こういった観点から、旅行振興参事官で相乗効果をきちんと生み出すような施策を考えていただきたいということで新しい組織を作りました。
アウトバウンドのみならず国内旅行の需要の喚起も重要な課題ですので、そのためにも、観光人材の確保や育成といった政策課題についても力を入れて取り組んでまいりたいという趣旨です。
(問)秡川前長官からの引継ぎにあたり、何かメッセージや留意点として伝えられたことがあれば、ご披露いただきたい。
(答)
秡川前長官からは様々なことを引き継いでおりますが、重要なものは大きく2点あったと認識しています。
一つ目は現在のインバウンドの好調な状況を踏まえて、現在検討中の次期観光立国推進基本計画の策定をしっかりやっていってほしいということです。
もうひとつは観光庁の働き方改革です。前長官のもとでしっかりと進めてきたので、私の体制になっても続けてほしいということです。
付言しますと、次期観光立国推進基本計画については、6,000万人15兆円の政府目標に向けたボトルネックや課題の整理を行った上で、地方誘客のより一層の促進や人手不足対策の取組等も含め必要な取組の検討を深めて、本年度末までの策定に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
二つ目の働き方改革ですが、秡川前長官時代から休暇取得やテレワークの促進、職員間のコミュニケーションの活性化を積極的に進めてきたところです。
私としても今後、職場の上下左右の風通しを良くするなど、こういった取組を加速させるとともに、職員の声をよく聞きながら、私のモットーであります「明るく楽しく仕事をする」職場作りを実行してまいります。
秡川前長官から託されたバトンをしっかりと受け継ぎ、観光産業の一層の発展のために誠心誠意取り組んでまいりたいと考えています。
(問)オンライン宿泊予約サイトのアゴダの問題についてお伺いします。同社を巡っては、利用者から相談が相次いでいると認識しておりますが、観光庁で把握している事実関係と今後の対応、さらにアゴダ社の再発防止策に対してどのように受け止めているのか、ご所見をお願いします。
(答)
観光庁といたしましては、旅行者が安全・安心に旅行を楽しんでいただくことは、観光立国を推進していくうえで大変重要であると考えております。
アゴダにつきましては、観光庁として、アゴダを巡ってトラブルが生じているといった利用者の声が寄せられていたことから、本年3月からアゴダに対して、トラブルの改善を申し入れてきたところです。
このような観光庁からの申し入れも踏まえ、アゴダにおいてはトラブルが生じている第三者サプライヤー経由の宿泊商品の販売を停止することを6月26日から講じたということです。
また、今後はAIを活用した事前監視システムの導入や第三者サプライヤーへの管理体制の強化等の対応を行う旨を昨日、会社として公表したものと承知しており、観光庁にもその報告がありました。
観光庁といたしましては、引き続きこの予約トラブルの発生状況や、アゴダが公表した改善策の進捗状況をこれからも確認を続けていくこととしており、必要に応じて適切な対応を行ってまいりたいと考えております。
あわせて、一般消費者の皆様に対しましても、旅行予約サイトを利用する際には、利用規約や約款、あるいは問い合わせ先について、あらかじめよくご確認いただくということを観光庁のホームページ上でも一層の注意喚起を行ったところであり、引き続きそのような取組を進めてまいりたいと考えております。
(問)こういった事案は、個社の問題なのか、それとももう少し広く横串を刺して把握すべき事案なのか、その辺のご所見をお伺いします。
(答)
現時点におきましては、アゴダ以外の宿泊予約サイトを運営する事業者において同様のトラブルが多く生じているという事実関係を承知しておりません。
今後、利用者からそういった声が多いということでありましたら、アゴダ以外の予約トラブルに対しても適切に対応してまいりたいと考えております。
(問)インバウンドの消費額について、4~6月の四半期で過去最高ということですが、1~6月の上半期で見ても過去最高ということでよろしいでしょうか。また、4~6月の四半期で過去最高となった背景や要因、長官の受け止め、上半期の消費額に対しての評価や背景についてお伺いします。先ほど2030年15兆円という目標に対する課題や注視していきたい点があれば教えてください。また、観光庁は富裕層インバウンド誘致の施策も展開していますが、こういった取組も消費額に影響しているのかお伺いいたします。
(答)
まず4月から6月期のこの訪日外国人旅行消費額は、2. 5兆円で、四半期としては過去最高であります。
この背景ですが、中国の訪日客数の回復や、欧米豪を初めとする訪日客数が増加していること、さらに平均泊数の増加などが要因として考えられます。
1月から6月期の上半期の消費額についても、累計4.8兆円でこちらも上半期としては過去最高であり、インバウンドは力強い成長軌道に乗っていると受け止めております。
富裕層の誘客につきましては、観光庁ではこれまでも消費単価の高い高付加価値旅行者の誘致促進を目指し、地方の14のモデル観光地に対する、旅行会社等の招請を通じた魅力的なコンテンツの磨き上げや販路形成のためのプロモーションといった集中的な支援、体験コンテンツの造成や宿泊施設を核とした面的な取組への支援などに取り組んできたところであり、このような取組も成果として表れてきている面があるのではないかと考えております。
観光庁といたしましては、引き続き高付加価値旅行者をはじめとするインバウンドの誘客拡大と消費額の更なる高みを目指して取り組んでまいりたいと考えております。
(問)消費額15兆円達成に向けた足元の課題などがあればお伺いします。
(答)
様々な課題があると思いますが、例えば地方部における宿泊数につきましては、先ほど述べたとおり、まだ現行の基本計画の目標に達していないこともありますので、地方部の宿泊数を伸ばして長期滞在を進めていくことは、今後の消費額の拡大に向けて大事なポイントだと考えております。
(問)7月以降多くの市場において訪日旅行者数がピークになる時期になるかと思いますが、そこに向けてのご所感をお伺いします。もう1点、7月5日に地震の予言日とされた日がありましたが、その前後で旅行需要の変化があったかをお伺いします。
(答)
まず1点目について、インバウンドは様々な要素の影響を受けるということで、見通しについて申し上げることはなかなか難しいところでありますが、7月は夏の学校休暇等があり、訪日旅行者数が年間を通じても多くなる時期でありますので、観光需要は高まることが期待されております。
我が国の原風景と言えるような風光明媚な景観や町並み、あるいは地域で大切に受け継がれてきた地場産業、そして豊かな自然環境の恵みを受けた地域固有の食文化など魅力的な観光資源が日本各地には数多く存在しており、こういったものはインバウンドの皆様にも強く訴求すると考えております。
7月5日の地震の噂につきましては、まず、地震の予知については内閣府や気象庁から現在の科学的知見から、日時と場所を特定した予知は困難であるということは繰り返し発信していただいております。
観光庁としましては、5月にJNTOの香港事務所を通じて、旅行を判断する際は、こうした公的機関による科学的な情報を参照してほしいという旨を中国語で発信するとともに、この発信内容についてJNTOから旅行会社等に対しても情報提供を行うといった対応を進めてきたところであります。
7月5日以降の状況に関しては、現時点で明確なことは申し上げられませんが、7月5日以降に訪日旅行販売キャンペーンを実施している現地の旅行会社や香港の消費者からの訪日旅行の問い合わせが大きく増加している旅行会社があると承知をしております。
このような動きの増加が、訪日旅行者数の増加につながる具体的な時期については、明確なことは今申し上げられませんが、引き続き香港以外の市場も含め、訪日者数の動向あるいは航空便の減便、旅行キャンセルの状況などを注視してまいりたいと考えております。
(問)統合型リゾートIRについてお伺いします。北海道でも経済界などからIR誘致を求める声も出ている状況です。先月、秡川前長官が札幌の観光フォーラムで講演された際も、IRは新しい観光拠点になるという趣旨のお話をされていました。観光庁はIRの候補地として北海道に注目されているのかなという受け止めもできるかと思うのですが、村田長官は、北海道のIRの可能性をどう見ていらっしゃるかお考えをお聞かせください。
(答)
IRにつきましては、カジノだけではなく、MICE施設やホテル、そして送客施設等が一体で整備され、多くの観光客を呼び込む滞在型観光の拠点であり、観光振興だけではなく、地方創生に繋がる効果が期待できるものと認識しております。
そしてこのIRの整備でありますが、IR整備法上、自治体の発意に基づき行われるものでありまして、国としては、自治体と自治体が選定した事業者から申請された区域整備計画につきまして、認定の可否を判断する立場でございます。
そのため、国として、また私個人としても特定の地域の評価についてのコメントは差し控えさせていただきたいというふうに思います。
(問)関連でもう1点、秡川前長官が札幌の講演のときに、IRの候補地の選定についてそう遠くない時期に決まると発言されていましたが今観光庁として選定スケジュール、検討しているものがありましたらどのような状況かお聞かせください。
(答)
IR整備法では、区域整備計画の認定の数について3つを上限とするということになっており、認定の申請は政令で定める期間内にしなければならないと定められております。
この政令を定めるに当たりましては、IR整備法の附帯決議におきまして、各地方公共団体による申請を公平に受けられる期間とすることとされております。
このため認定の申請期間を定めるに当たりましては、公平性を確保する観点から、申請主体である自治体の状況をよく見極めた上で判断する必要がありまして、自治体の状況を注視してまいりたいというふうに考えております。
現時点で決まったスケジュールはございません。
(問)観光の足として、鉄道だけではなくバスやタクシーも役割があると思いますが、先ほどのご発言にあるような地方誘客の面で隅々まで観光客をといったところでも活躍があるかと思いますが、バスとタクシーそれぞれの業界に期待やメッセージがあればお願いします。
(答)
国内外の観光客の方に日本各地の魅力ある観光地を訪れていただくためには、先ほど申し上げた観光コンテンツの開発や情報発信といった取組とあわせて、「観光の足」の確保を図っていくことは非常に重要な課題であると考えております。
このような観点からバスやタクシー、こういった皆様に対しましても大きく期待を寄せているところではありますが、他方で、人口減少、担い手が不足する中で、どのようにしてこの「観光の足」の確保を図っていくかは大変重要な課題であると認識しております。
現在、国土交通省全体におきましても、「交通空白」の解消に向けては関係部局と連携しながら様々な取組が進められております。
具体的には、日本版ライドシェアあるいは公共ライドシェアの導入、レンタカーの利用環境の整備、連節バスやジャンボタクシーの導入、また自動運転バスの社会実装など、あらゆる手段を総動員して対策を講じていく必要があると考えており、観光庁としても、関係部署と連携しながら、このような地域の取組をしっかり後押ししていくことで、「観光の足」の確保に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
バスやタクシーは非常に重要な公共交通機関でありますので、私どもとしてもぜひ連携して取組を進めてまいりたいと考えております。
(問)アゴダの件で、3月に改善要請を出されていると思いますが、その趣旨について教えてください。
(答)
3月の申し入れの趣旨は、その頃にアゴダを巡り予約に関するトラブルが生じていると、利用者の声が寄せられたということでありましたので、行政指導として、観光庁からアゴダに対して、そのような利用者に対する予約のトラブルが実際生じているのか、生じているならば改善をすべきだと申し入れてきました。
(問)国内旅行の活性化の観点で、「何度も地域に通う旅」といった第2のふるさとづくりについて今後の取組方針をお伺いします。もう一点、「国内旅行需要の平準化」について、ワーケションやブレジャー、休み方改革を含めた休暇取得分散化などの施策に関して現時点で認識している課題をお伺いします。
(答)
まず1点目について、「何度も地域に通う旅、帰る旅」を定着させる第2のふるさとづくりやワーケーションは、地域住民との交流を通じた来訪者の関係人口の増加に繋がる取組だと考えております。
観光庁ではこれまで、第2のふるさとづくりの推進に向けて、令和6年度までに累計36地域でモデル実証を実施するとともに、ワーケーションの推進に向けて、地域と企業のマッチング支援や令和6年度までに78件のモデル事業の創出等を実施してきました。
今年度は、これらの取組を「第2のふるさとづくりプロジェクト」として統合し、地域との繋がりの創出に加えて、地域への経済波及効果と事業の持続可能性が両立した先駆的なモデル事業の創出を実施しています。
観光庁としましては、第2のふるさとづくりやワーケーションの推進を通じた関係人口の増加に繋げ、新たな交流市場の拡大に向けた取組を進めてまいりたいと考えています。
2点目の国内旅行の需要の平準化ですが、今ご指摘いただきましたように、日本では、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆などに旅行する方が多く、特定の時期に観光客が集中する実態があります。
国内旅行の平準化については、ご指摘のように休暇の取得促進と分散化を進めていくことが、重要であると考えております。
観光庁におきましては、休暇を取得しやすい職場環境を整えて、旅行を楽しむことを積極的に促進する企業を紹介する「ポジティブ・オフ」運動を行っており、現在2,800を超える企業・団体から賛同いただいています。
またワーケーションにつきましても平準化のための取組として捉えており、今申し上げたようなモデル事業の造成にも取り組んでおります。
旅行の平準化と言う意味におきましては、平日での旅行が多く重要な平準化が見込まれる、高齢者層の方々の国内宿泊旅行経験率がコロナ以降まだ回復していない状況があります。いわゆる経験率が低下している状況が続いていますので、高齢者の方々が旅行しやすい環境を整備するユニバーサルツーリズムの促進を図っております。
こうした取組を通じて、国内旅行需要の平準化も引き続き進めてまいりたいと考えております。
(問)香港市場についてお伺いします。まず6月の客足が3割以上減とありますがこれの評価と対策、9月から飛行機便が減便ではなく運休するということも出ていますが、こういったリスクはいつまで続きそうなものか、対策を合わせてお伺いします。
(答)
香港については、香港ではご案内の通り、日本の漫画やその内容をもとにした風水師の予言等によりまして、7月5日に日本で大地震が起こるという噂がSNS等によって広がり、旅行のキャンセルが生じたという状況であると認識をしております。
一部の航空会社におきましては、日本路線の減便を行っている会社があると承知しておりますが、これは航空会社におきまして、今後の経済状況の見通しなどの様々な要素を総合的に判断した結果であるというふうに考えております。
そういった要因により、香港市場で33%の減となったことは事実として受け止めておりますが、先ほど申し上げたように今後についてはまた新たな動きが出つつあると理解をしております。
(問)関連して、今回、災害は起きていないが、先に風評被害だけが起きているという状況です。去年災害に強い観光地を目指すレジリエンスサミットを開催しましたが、これが何かの役に立ったのかお伺いします。実務者会議は18日から開かれ、香港の件は特に話題になっていないようですが、これがどのように役立てられるのかお伺いします。
(答)
昨年の観光レジリエンスサミットでは、近年で自然災害の頻発化・激甚化あるいは新型コロナの世界的な流行というようなことがありましたので、観光分野の脆弱性というのが改めて認識されました。
そういった中で、観光レジリエンスの向上というものが重要なテーマになりつつあったということであります。
昨年の観光レジリエンスサミットにおいては、観光レジリエンス向上に向けた取り組みの方向性として、危機や自然災害による影響の予防や最小化、また危機や自然災害による影響の吸収、回復過程の適用と変革、の二つの柱に基づく仙台声明を採択したところです。
仙台声明は、昨年議論した内容ですが、実際に自然災害等が発生した際の対策を念頭に置いたものであります。
しかしながら、観光レジリエンスサミットで、各国と共有した問題意識、これは正確な情報発信ということもありましたので、観光庁としては、今回の地震の噂に対し、気象庁やJNTOと連携しまして、正確かつ迅速な情報発信に努めてきました。
こうした取組もありまして、香港はマイナス33%ですが全体の訪日客数は、6月として過去最高になっている状況と考えております。
(問)消費額に関してお伺いします。四半期、上半期いずれも過去最高ということですが、昨年に比べて伸び率は鈍化しているかと思うが、その要因や受け止めをお伺いします。また、1人あたりの支出額は増えているが、前年同期比ではマイナスになっている点について、どう分析しているか教えていただきたい。
(答)
1人当たりの消費額については、マイナスではありますが1%未満ということで、こちらはほぼ同額と私どもとしては考えていいのではないかと思います。
伸び率の鈍化につきましては、6月は香港の噂の影響等もあり、マイナスとなっている国もあり、総合的に影響している可能性はありますが、まだ私どもとして一義的な要因を把握しているわけではございません。
(問)1人当たり消費額について、中国がマイナス12.5パーセントとなっていますが、かつての爆買いといったところから何かトレンドの変化などがあるのか、分析があればお伺いします。
(答)
(観光庁事務方より)中国については、ご指摘のとおり買い物代などの低下もあり、1人あたりの支出は減っている状況であります。ただし、このトレンドが今後継続的に進んでいくのかどうかについては、実際の数字を見ていかないとはっきりしないと思いますので、今後も注視していきたいと思います。
(問)香港は訪日客数のなかで結構な割合を占めているが、一連の噂によって旅行者はだいぶ減り、脆弱性というか観光が受ける影響の大きさを示したと思う。これまでも旅行者に対する情報発信をされてきたかと思うが、改めて届ける形での情報提供の難しさがあると思った。長官としてどのよう受け止めているかお伺いしたい。
(答)
情報発信のあり方について、政府としてできることは、気象庁長官によるこれはデマであるということの明確な情報発信や、JNTOを通じて現地の皆様に対応することがあります。
秡川前長官も香港のメディアの取材に応じて、そういったことは心配しないで来てほしいといったメッセージも出していました。しかし、結果的にはこのような数字となり、絶対これをやれば良いという解決方法が、今あるわけでありません。
今回のことを教訓にして、どういったことができるか、引き続き考えてまいりたいと思います。
以上