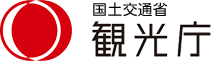10月長官会見要旨
最終更新日:2025年11月7日
日時:2025年10月15日(水)16:15~16:50
場所:国土交通省会見室
場所:国土交通省会見室
冒頭発言
(訪日外国人旅行者数(2025年9月)について)
本年9月の訪日外国人旅行者数は、約327万人となり、9月として過去最高となりました。昨年同月と比べた伸び率は14%増となりました。また1月から9月までの9ヶ月間累計では約3,165万人となり過去最速で3,000万人を超えました。
本年9月の出国日本人数は、約139万人となりました。昨年同月と比べた伸び率は15%の増です。また、1月から9月までの9ヶ月間累計では約1,086万人となり、1,000万人を超えました。
(インバウンド消費動向調査2025年7-9月期(1次速報)について)
本年の7月から9月期の訪日外国人旅行消費額は、第3四半期としては最高となる約2.1兆円と推計され、前年同期比で約11%の増となりました。
ビジネス客や留学生を含む全目的の訪日外国人1人当たり旅行支出は、約21.9万円となり前年同期とほぼ同額となっています。
観光・レジャー目的で絞ると1人当たりの旅行支出は約20.6万円となり、前年比で4.5%の減となっております。
なお訪日観光支出がもたらす波及効果は過去の例で見ますと、訪日外国人消費額のおおむね2倍程度で推移しており、これに倣うと7月から9月期は約4兆円程度と推測ができるところでございます。
本年9月の訪日外国人旅行者数は、約327万人となり、9月として過去最高となりました。昨年同月と比べた伸び率は14%増となりました。また1月から9月までの9ヶ月間累計では約3,165万人となり過去最速で3,000万人を超えました。
本年9月の出国日本人数は、約139万人となりました。昨年同月と比べた伸び率は15%の増です。また、1月から9月までの9ヶ月間累計では約1,086万人となり、1,000万人を超えました。
(インバウンド消費動向調査2025年7-9月期(1次速報)について)
本年の7月から9月期の訪日外国人旅行消費額は、第3四半期としては最高となる約2.1兆円と推計され、前年同期比で約11%の増となりました。
ビジネス客や留学生を含む全目的の訪日外国人1人当たり旅行支出は、約21.9万円となり前年同期とほぼ同額となっています。
観光・レジャー目的で絞ると1人当たりの旅行支出は約20.6万円となり、前年比で4.5%の減となっております。
なお訪日観光支出がもたらす波及効果は過去の例で見ますと、訪日外国人消費額のおおむね2倍程度で推移しており、これに倣うと7月から9月期は約4兆円程度と推測ができるところでございます。
質疑応答
(問)1~9月の訪日客数は累計で3千万人を突破しました。長官の受け止めと今後の見通しを教えてください。今年は残り3カ月となりましたが年間累計値は昨年の3,687万人を上回るペースで進んでいるのかなど年末に向けた意気込みもお願いします。
(答)
冒頭申し上げた通り、本年1月から9月の訪日外国人旅行者数の累計は約3,165万人と前年同期比で約18%の増加であり、過去最速で3,000万人を突破いたしました。
堅調な訪日需要と、航空便の回復等によりまして、インバウンドは好調な状況であります。引き続き、力強い成長軌道に乗っているものと受け止めております。
インバウンドにつきましては様々な要素の影響を受けることから今後の見通しについて申し上げることは差し控えたいと思いますが、10月以降は紅葉シーズンでありますし、また年末にはクリスマス、あるいは年末年始に合わせた旅行需要の高まりということもありますので期待をしたいと思っております。
引き続き、戦略的な訪日プロモーション、また地方誘客を積極的に進めてまいりたいと考えております。
(問)9月の訪日客数の増加要因や背景について教えてください。日本で7月に大災害が起きるというSNS上のうわさの影響が現在もどの程度及んでいるのか、お考えがあれば教えてください。
(答)
9月の訪日旅行者数は、冒頭申し上げました通り約327万人となり、前年同月よりも14%増加して、9月としては過去最高となったところです。これは昨年2月から20ヶ月連続で毎月の過去最高を記録しているという状況です。
地域別で見ますと、インバウンドの約7割を占めるアジア諸国が前年同月比で10%の増加、そして欧米豪・中東諸国については前年同月比で26%増加し、このようなことが原因であると考えております。
堅調な訪日需要と航空便の回復等によりインバウンドは好調な状況であり、引き続き力強い成長軌道に乗っているものと受け止めております。
またSNS上の噂の影響でありますが、香港については前年同月比で約12%の減少となっていますが、これは2回の大型台風16号と18号の影響を受けて航空便の欠航が相次いだことが主な要因であると考えております。
(問)来週に開会予定の臨時国会での首相指名選挙に向けて、現在は与野党間の党首会談などが続いています。自民党の高市新総裁は外国人政策強化に前向きな姿勢を示しており、野党からも同様な規制強化を求める声があがっています。今後の観光政策の議論を観光庁としどのように進めていく方針でしょうか。特に、オーバーツーリズム対策の強化など今後のお考えと検討状況を教えてください。
(答)
まずインバウンドにつきましては申し上げましたとおり旅行者数、そして消費額ともに非常に好調な状況が続いております。
一方で都市部を中心として、一部地域への旅行客の偏在傾向も見られるところであり、観光客が集中する一部の地域や時間帯等によってはいわゆる過度の混雑やマナー違反による地域住民の生活への影響、旅行者の満足度の低下への懸念、こういったことが生じている状況であります。
これまでも政府としては既に取りまとめられた「オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた対策パッケージ」に基づき、地域の実情に応じた取組を国として総合的に支援しているところですが、インバウンドの受入れが国民生活に悪影響を与えないように、国民生活との両立のための施策を徹底していくということを大前提として、観光の持続可能性を高める取組を一層進めていく必要があると考えております。
現在、交通政策審議会の観光分科会においても観光立国推進基本計画の改定に向けた議論を行っていただいておりますが、その中でもこういった課題への対応は大きな論点の一つとなっています。
こうした議論も踏まえて、観光庁としましては地方誘客の促進やご指摘のオーバーツーリズム対策をはじめとした施策の強化、そのために必要な予算の確保も含めて今後もしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
(問)先月下旬、旅行業界の大型イベント「ツーリズムEXPOジャパン」が愛知県で初めて開催され、速報値で当初の目標を上回る12万6,900万人が来場しました。開催結果について、長官の振り返りをお願いします。
(答)
世界最大級の旅の祭典であります「ツーリズムEXPOジャパン2025愛知・中部北陸」は9月25日から4日間、愛知県にて初めて開催されました。来場者数は当初目標としていた10万人を超えて、今お伝えいただきましたように13万人近い数字となりました。
これは愛知・中部北陸の事業者の皆様や自治体の皆様が一丸となって、このエキスポの出展者募集や集客のプロモーションにご尽力された結果であると認識をしております。
私自身も会場を回らせていただきましたが、中部圏の9県合同ブースあるいは北海道や沖縄などの国内各地のブースだけではなくて、香港、台湾、韓国等のアジアの国そして世界中の国々の海外ブースも非常に多くの人で賑わっておりまして、本当に多くの方がこのエキスポに期待を寄せていたことを肌で実感してきたところです。
この他にも観光大臣会合等が開催されまして、持続可能な観光に向けた観光のDX、あるいは地方誘客についても議論がされるなど全体として充実した内容となっていたものと思っております。
このエキスポについては大いに盛り上がり、より一層のインバウンドそしてアウトバウンドの双方向の交流拡大や地方誘客のきっかけに繋がる機会となったと感じております。
来年は9月に東京で開催されると承知しておりますが、次回も大いに期待していきたいと思っております。
(問)先日、観光小売業界の17団体が訪日外国人旅行者の免税制度維持も含めて国土交通省の中野大臣らに提出しました。制度の維持に対する長官のご所感をお伺いします。
(答)
観光庁で行っているインバウンド消費動向調査によれば、ショッピングが訪日旅行の主な目的の一つになっておりますし、また実際に2024年の訪日外国人による買物消費については、約2.4兆円の市場規模となっております。
外国人旅行者向けの消費税免税制度は、こういった買物消費を下支えする重要な制度であると認識しております。
観光庁としましては、引き続きこの免税制度を活かしながら、特に地方部でのインバウンド消費の一層の拡大に取り組むとともに、来年11月にリファンド方式になることが予定されていますので、リファンド方式の着実な実施に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
(問)先日13日をもって大阪関西万博が閉幕しました。日本人国内旅行やインバウンドへの影響など、周辺都市への観光客流動について、どのように振り返るか、長官のご所感をお願いします。
(答)
大阪・関西万博は、4月13日に開幕し、今週10月13日をもって閉幕しました。
観光庁としましては、大阪・関西万博をきっかけとして日本の各地に誘客するため、関係団体と連携して取り組んできたところです。
日本人国内旅行への影響に関しては、本年4月から6月の調査結果によると、大阪府を主目的地とした国内旅行の延べ旅行者数は、前年同期比で約8割増加しております。
また、宿泊業における関係団体によれば、大阪府内のホテルの稼働率は上昇傾向であると伺っております。
インバウンドへの影響としては、特に欧州圏の外国人宿泊客が増えているといった声も聞いております。
民間等の調査によると、大阪・関西万博に訪れた訪日旅行者の方は、京都、関東、奈良の順に国内各地を訪問しており、特に欧州の方はいわゆるゴールデンルートに加え、広島市、金沢市、高山市への滞在が見られるというデータもあると承知しております。
業界団体からの聞き取りによれば、周辺都市への影響としては、本年4月から9月の主な旅行会社各社の関西方面への旅行商品の取り扱い額については、他の方面と比べて、約10から15%高い伸び率となっていると聞いております。
このような状況を総合的に踏まえると、大阪・関西万博を契機として大阪方面を中心とした日本人の国内旅行の増加、そして訪日旅行者の関西地以外への誘客ということに一定の効果を生んだものと認識しております。
(問)今回公表された7月から9月の消費動向の内訳に関して、先ほどの免税制度の話でもありましたが、買物消費の割合としては25%と、一定の割合があるかと思いますが、前年同時期比では若干その額としても下がっており、全体的にモノ消費からコト消費に移っているなど、そういった部分の長官のご所感をお伺いします。
(答)
まず全体的なところでは、この7月から9月の訪日外国人旅行消費額は約2.1兆円と推計されており、これは冒頭でも触れた通り、訪日数の伸びを背景に前年を上回っております。これは中国や欧米を始めとする好調な訪日客数の増加、また、平均泊数の増加によるものが大きいと考えております。
消費額を費目別に見ると、前年同期と比較して、宿泊費、飲食費、交通費、娯楽等サービス費は増加した一方で買物代はわずかに減少しているという状況になっています。
この1月から9月期の旅行消費額は累計約6.9兆円で、これは1月から9月期としては過去最高であり、力強い成長軌道に乗っていると受け止めています。
費目別で見ますと、1人当たりの訪日外国人の旅行支出では、買物代は5.5万円で、前年同期比で約11%の減となっています。また、いわゆる娯楽等サービス費については1.1万円、前年同期比では約9%の増となっています。
このことから、7月から9月期については、結果として買物代は減少している一方で、娯楽等サービス費は伸びているというデータとなっています。
この買物代と娯楽等サービス費の増減が、今ご指摘いただいたような一定の傾向を示すかどうかということについては、今後もう少し状況を注視していく必要があるかと考えております。
ただ、私どもとしては、買物消費は非常に重要な要素だというのは先ほど申し上げた通りでありますし、一方で、いわゆるコト消費という体験型の観光資源の磨き上げとについても力を入れて取り組んでいるところであり、どちらも我が国の観光資源として非常に重要な要素だと考えておりますので、今後もどちらも促進するような施策を進めてまいりたいと思っています。
(問)先ほどの3,000万人の受け止めでも力強い成長軌道に乗っており、訪日需要もかなり強い状況の中で戦略的な今後の訪日プロモーションも続けていきたいというお話もありましたが、消費がこれまで買い物がかなり人気というところから色々なニーズが多様化していく中で、観光庁としてどういった戦略プロモーションが重要になってくるとお考えかお伺いします。
(答)
まずこの1月から9月までの状況を振り返りますと、この間にはいわゆる科学的根拠のない情報あるいは日本での記録的な猛暑といった外的要因で訪日を控える動きが一定程度生じたということは認識をしており、こういった科学的根拠のない情報については、海外旅行者の訪日意欲に対して影響が及ばないよう、適時適切な情報発信に取り組んでいかなければいけないという思いを持ったところであります。
それから、これは何度も申し上げていますが、地方誘客が大きな私どものテーマになっていますので、こういった我が国の日本各地の魅力をいかに発信し、海外の方にお届けできるかという観点を意識しながら、戦略的な訪日プロモーションを行っていく必要があると考えております。
(問)大阪万博の閉幕後のいわゆるアフター万博にについて、万博の盛り上がりを今後の観光にどのようにつなげていくのか所見をお伺いします。
(答)
先ほども申し上げましたが、13日に閉会式が行われ、閉会式には私も出席させていただき、最後までこの熱気に溢れた万博の盛り上がりを会場全体で感じたところです。
そして来場者の笑顔やパビリオンのスタッフの皆さんとの交流の姿も拝見し、国際相互理解の増進による諸外国との友好関係の更なる深化がイベントを通じて、個人レベルでも進んでいることを実感したところです。
観光庁としましては、万博を契機とした訪日旅行者の日本全国への誘客に取り組んできたところであり、こういったことをこれからも進めてまいりたいと思っておりますし、また、万博においては世界各国からの魅力の発信を通じて特に日本人の来場者の方が、海外、世界各国への関心を高めていただいたのではないかと思っており、こういった関心の高まりが今後のアウトバウンドの拡大にも繋がるのではないかと期待をしているところです。
そして、更に申し上げますと2027年の3月には横浜で「国際園芸博覧会GREEN × EXPO2027」が開幕するということで、万博と同様に国内外から多くの来場者を期待しているところです。
1年半後ということで、このような2つの博覧会が間を空けずに我が国で開催される機会を活かし、更なる日本への誘客と、海外からの魅力発信を通じたアウトバウンド、双方向の国際交流を促進してまいりたいと思っております。
(問)2025年7月から9月期の1人当たりの旅行支出が、前年に比べて0.2%下がっているということですが、観光客数は伸びていますけれども旅行支出があまり伸びていないということになりますが、これは要因としてはどのようなことがあるでしょうか。
(答)
インバウンド消費額は、1人当たりの消費額と人数の掛け算になります。1人当たりの消費額というのは、ほぼ同額になっています。
全体の中身を見ますと買物代が昨年の同時期に比べて10%強、減っております。
一方で、娯楽等サービス費は、約9%増えておりまして、昨年のこの時期は例えば円安ということもあったと思いますが、様々な要因が絡んでおりますので、一概に特定の要因による結果かどうかということについては、もう少し前後の時期も見た上で、分析をしていく必要があるのではと思っております。
(問)為替が一つの要因と考えられるのでしょうか。
(答)
昨年の反動という意味では、そういったことも一つの要素にはあると思います。
(観光庁事務方より)為替の件について補足させていただきます。先ほど円高という話がありましたが、ユーロに対しては円安の傾向で、ドルに対しては円高の傾向となっておりますので、その辺りが国によって多少影響があったかと思います。また、買物代が下がっている一方で、業務なども含めた全目的に関しては、宿泊費の方が伸びているところもあり、その兼ね合いの中で全体として減となっているということかと思います。
(問)オーバーツーリズムに関して、自民党が10日にオーバーツーリズムの対策プロジェクトチームを立ち上げ、観光庁からヒアリングしたということですが、観光庁としてどういった問題意識を持っているのかお伺いします。
(答)
オーバーツーリズムの対策については、先ほど観光庁の考え方をお話したところでありますが、自民党の観光立国調査会でも、地方誘客・オーバーツーリズム対策PTが立ち上げられて議論を始められたということです。
観光庁としては、オーバーツーリズム対策や地方誘客に対して、どういった施策を行っているか、あるいは今後どのように進めていきたいかということについて、ヒアリングを受けました。こうした考え方は先ほど申し上げたとおりであり、例えば予算要求の内容等も含めて先生方のご意見にお答えしたものです。
(問)オーバーツーリズムもありつつ、観光客が伸びていることですけれども、この観光客の伸びというのを今より政策として加速させるという考えなのでしょうか。それともオーバーツーリズムの対策があまり間に合っていないからこそ自民党のチームになってきていると思うのですが、少し慎重にペースを抑えるような考えはないのでしょうか。ペースを加速させるというようなスタンスを続けるのか、その考え方についてのスタンスをお伺いします。
(答)
観光庁としては、2030年訪日客数6,000万人・旅行消費額15兆円との大きな目標がありますので、それに向けて、今、着実に施策を進めているスタンスであります。その実現に向けて各種施策を進めていく際に、一部の地域で地域住民への国民生活に対して影響が出ている状況があります。
また、これから益々外国人観光客の方が増えていくことが他の地域でも起こりうる可能性はありますので、そういったことがないようにインバウンドの増加と、国民生活の両立を並行して進めていくことが大事な観点であると思っております。
(問)つまり今のペースを加速させる、すなわちインバウンドを増やしていくという方向は変わらないということでしょうか。
(答)
はい。
(問)消費額について、直近の大手百貨店の上半期決算発表で免税売上高が減ったっていうデータ分析がありそれがまさにこの買い物代の減少と紐づいているのと思う。訪日客にどこでお金を落としてもらえるかという全体の最適解を探る中で、観光業界としてコト消費や体験型観光に強化している中で、買い物代の比率や実額は今後も減少傾向が続くからコト消費とかに強化していると捉えて良いのでしょうか。加えて、仮にこの買い物代のところを再び増加に転じさせるとしたら、必要な取り組みをどのように考えているのか教えてください。
(答)
これという最適な消費の比率はないと思っております。先ほども触れたが通り、観光庁としては、コト消費はこれから伸ばしていく余地があるだろうということ で、日本各地の体験型の旅行商品や観光資源の磨き上げに支援をさせていただいているところです。
こういったことで外国の方が地方で長期滞在をし、体験型も含めて多くの消費をしていただくということは非常に重要なこれから伸びる要素があると思っております。
他方で買い物についても、アジアの方が比率多いという傾向がありますが、アジアの方にとっては買い物が日本の非常に大きな魅力の一つになっておりますので、今後減らしていっていいとかあるいは減るだろうということを私どもとしては全く思っておりません。特に地方部の免税店を今増やしていることもありますので、地方部での魅力的な商品の買い物についても、これからもっと伸ばしていきたいなと思っております。
(答)
冒頭申し上げた通り、本年1月から9月の訪日外国人旅行者数の累計は約3,165万人と前年同期比で約18%の増加であり、過去最速で3,000万人を突破いたしました。
堅調な訪日需要と、航空便の回復等によりまして、インバウンドは好調な状況であります。引き続き、力強い成長軌道に乗っているものと受け止めております。
インバウンドにつきましては様々な要素の影響を受けることから今後の見通しについて申し上げることは差し控えたいと思いますが、10月以降は紅葉シーズンでありますし、また年末にはクリスマス、あるいは年末年始に合わせた旅行需要の高まりということもありますので期待をしたいと思っております。
引き続き、戦略的な訪日プロモーション、また地方誘客を積極的に進めてまいりたいと考えております。
(問)9月の訪日客数の増加要因や背景について教えてください。日本で7月に大災害が起きるというSNS上のうわさの影響が現在もどの程度及んでいるのか、お考えがあれば教えてください。
(答)
9月の訪日旅行者数は、冒頭申し上げました通り約327万人となり、前年同月よりも14%増加して、9月としては過去最高となったところです。これは昨年2月から20ヶ月連続で毎月の過去最高を記録しているという状況です。
地域別で見ますと、インバウンドの約7割を占めるアジア諸国が前年同月比で10%の増加、そして欧米豪・中東諸国については前年同月比で26%増加し、このようなことが原因であると考えております。
堅調な訪日需要と航空便の回復等によりインバウンドは好調な状況であり、引き続き力強い成長軌道に乗っているものと受け止めております。
またSNS上の噂の影響でありますが、香港については前年同月比で約12%の減少となっていますが、これは2回の大型台風16号と18号の影響を受けて航空便の欠航が相次いだことが主な要因であると考えております。
(問)来週に開会予定の臨時国会での首相指名選挙に向けて、現在は与野党間の党首会談などが続いています。自民党の高市新総裁は外国人政策強化に前向きな姿勢を示しており、野党からも同様な規制強化を求める声があがっています。今後の観光政策の議論を観光庁としどのように進めていく方針でしょうか。特に、オーバーツーリズム対策の強化など今後のお考えと検討状況を教えてください。
(答)
まずインバウンドにつきましては申し上げましたとおり旅行者数、そして消費額ともに非常に好調な状況が続いております。
一方で都市部を中心として、一部地域への旅行客の偏在傾向も見られるところであり、観光客が集中する一部の地域や時間帯等によってはいわゆる過度の混雑やマナー違反による地域住民の生活への影響、旅行者の満足度の低下への懸念、こういったことが生じている状況であります。
これまでも政府としては既に取りまとめられた「オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた対策パッケージ」に基づき、地域の実情に応じた取組を国として総合的に支援しているところですが、インバウンドの受入れが国民生活に悪影響を与えないように、国民生活との両立のための施策を徹底していくということを大前提として、観光の持続可能性を高める取組を一層進めていく必要があると考えております。
現在、交通政策審議会の観光分科会においても観光立国推進基本計画の改定に向けた議論を行っていただいておりますが、その中でもこういった課題への対応は大きな論点の一つとなっています。
こうした議論も踏まえて、観光庁としましては地方誘客の促進やご指摘のオーバーツーリズム対策をはじめとした施策の強化、そのために必要な予算の確保も含めて今後もしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
(問)先月下旬、旅行業界の大型イベント「ツーリズムEXPOジャパン」が愛知県で初めて開催され、速報値で当初の目標を上回る12万6,900万人が来場しました。開催結果について、長官の振り返りをお願いします。
(答)
世界最大級の旅の祭典であります「ツーリズムEXPOジャパン2025愛知・中部北陸」は9月25日から4日間、愛知県にて初めて開催されました。来場者数は当初目標としていた10万人を超えて、今お伝えいただきましたように13万人近い数字となりました。
これは愛知・中部北陸の事業者の皆様や自治体の皆様が一丸となって、このエキスポの出展者募集や集客のプロモーションにご尽力された結果であると認識をしております。
私自身も会場を回らせていただきましたが、中部圏の9県合同ブースあるいは北海道や沖縄などの国内各地のブースだけではなくて、香港、台湾、韓国等のアジアの国そして世界中の国々の海外ブースも非常に多くの人で賑わっておりまして、本当に多くの方がこのエキスポに期待を寄せていたことを肌で実感してきたところです。
この他にも観光大臣会合等が開催されまして、持続可能な観光に向けた観光のDX、あるいは地方誘客についても議論がされるなど全体として充実した内容となっていたものと思っております。
このエキスポについては大いに盛り上がり、より一層のインバウンドそしてアウトバウンドの双方向の交流拡大や地方誘客のきっかけに繋がる機会となったと感じております。
来年は9月に東京で開催されると承知しておりますが、次回も大いに期待していきたいと思っております。
(問)先日、観光小売業界の17団体が訪日外国人旅行者の免税制度維持も含めて国土交通省の中野大臣らに提出しました。制度の維持に対する長官のご所感をお伺いします。
(答)
観光庁で行っているインバウンド消費動向調査によれば、ショッピングが訪日旅行の主な目的の一つになっておりますし、また実際に2024年の訪日外国人による買物消費については、約2.4兆円の市場規模となっております。
外国人旅行者向けの消費税免税制度は、こういった買物消費を下支えする重要な制度であると認識しております。
観光庁としましては、引き続きこの免税制度を活かしながら、特に地方部でのインバウンド消費の一層の拡大に取り組むとともに、来年11月にリファンド方式になることが予定されていますので、リファンド方式の着実な実施に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
(問)先日13日をもって大阪関西万博が閉幕しました。日本人国内旅行やインバウンドへの影響など、周辺都市への観光客流動について、どのように振り返るか、長官のご所感をお願いします。
(答)
大阪・関西万博は、4月13日に開幕し、今週10月13日をもって閉幕しました。
観光庁としましては、大阪・関西万博をきっかけとして日本の各地に誘客するため、関係団体と連携して取り組んできたところです。
日本人国内旅行への影響に関しては、本年4月から6月の調査結果によると、大阪府を主目的地とした国内旅行の延べ旅行者数は、前年同期比で約8割増加しております。
また、宿泊業における関係団体によれば、大阪府内のホテルの稼働率は上昇傾向であると伺っております。
インバウンドへの影響としては、特に欧州圏の外国人宿泊客が増えているといった声も聞いております。
民間等の調査によると、大阪・関西万博に訪れた訪日旅行者の方は、京都、関東、奈良の順に国内各地を訪問しており、特に欧州の方はいわゆるゴールデンルートに加え、広島市、金沢市、高山市への滞在が見られるというデータもあると承知しております。
業界団体からの聞き取りによれば、周辺都市への影響としては、本年4月から9月の主な旅行会社各社の関西方面への旅行商品の取り扱い額については、他の方面と比べて、約10から15%高い伸び率となっていると聞いております。
このような状況を総合的に踏まえると、大阪・関西万博を契機として大阪方面を中心とした日本人の国内旅行の増加、そして訪日旅行者の関西地以外への誘客ということに一定の効果を生んだものと認識しております。
(問)今回公表された7月から9月の消費動向の内訳に関して、先ほどの免税制度の話でもありましたが、買物消費の割合としては25%と、一定の割合があるかと思いますが、前年同時期比では若干その額としても下がっており、全体的にモノ消費からコト消費に移っているなど、そういった部分の長官のご所感をお伺いします。
(答)
まず全体的なところでは、この7月から9月の訪日外国人旅行消費額は約2.1兆円と推計されており、これは冒頭でも触れた通り、訪日数の伸びを背景に前年を上回っております。これは中国や欧米を始めとする好調な訪日客数の増加、また、平均泊数の増加によるものが大きいと考えております。
消費額を費目別に見ると、前年同期と比較して、宿泊費、飲食費、交通費、娯楽等サービス費は増加した一方で買物代はわずかに減少しているという状況になっています。
この1月から9月期の旅行消費額は累計約6.9兆円で、これは1月から9月期としては過去最高であり、力強い成長軌道に乗っていると受け止めています。
費目別で見ますと、1人当たりの訪日外国人の旅行支出では、買物代は5.5万円で、前年同期比で約11%の減となっています。また、いわゆる娯楽等サービス費については1.1万円、前年同期比では約9%の増となっています。
このことから、7月から9月期については、結果として買物代は減少している一方で、娯楽等サービス費は伸びているというデータとなっています。
この買物代と娯楽等サービス費の増減が、今ご指摘いただいたような一定の傾向を示すかどうかということについては、今後もう少し状況を注視していく必要があるかと考えております。
ただ、私どもとしては、買物消費は非常に重要な要素だというのは先ほど申し上げた通りでありますし、一方で、いわゆるコト消費という体験型の観光資源の磨き上げとについても力を入れて取り組んでいるところであり、どちらも我が国の観光資源として非常に重要な要素だと考えておりますので、今後もどちらも促進するような施策を進めてまいりたいと思っています。
(問)先ほどの3,000万人の受け止めでも力強い成長軌道に乗っており、訪日需要もかなり強い状況の中で戦略的な今後の訪日プロモーションも続けていきたいというお話もありましたが、消費がこれまで買い物がかなり人気というところから色々なニーズが多様化していく中で、観光庁としてどういった戦略プロモーションが重要になってくるとお考えかお伺いします。
(答)
まずこの1月から9月までの状況を振り返りますと、この間にはいわゆる科学的根拠のない情報あるいは日本での記録的な猛暑といった外的要因で訪日を控える動きが一定程度生じたということは認識をしており、こういった科学的根拠のない情報については、海外旅行者の訪日意欲に対して影響が及ばないよう、適時適切な情報発信に取り組んでいかなければいけないという思いを持ったところであります。
それから、これは何度も申し上げていますが、地方誘客が大きな私どものテーマになっていますので、こういった我が国の日本各地の魅力をいかに発信し、海外の方にお届けできるかという観点を意識しながら、戦略的な訪日プロモーションを行っていく必要があると考えております。
(問)大阪万博の閉幕後のいわゆるアフター万博にについて、万博の盛り上がりを今後の観光にどのようにつなげていくのか所見をお伺いします。
(答)
先ほども申し上げましたが、13日に閉会式が行われ、閉会式には私も出席させていただき、最後までこの熱気に溢れた万博の盛り上がりを会場全体で感じたところです。
そして来場者の笑顔やパビリオンのスタッフの皆さんとの交流の姿も拝見し、国際相互理解の増進による諸外国との友好関係の更なる深化がイベントを通じて、個人レベルでも進んでいることを実感したところです。
観光庁としましては、万博を契機とした訪日旅行者の日本全国への誘客に取り組んできたところであり、こういったことをこれからも進めてまいりたいと思っておりますし、また、万博においては世界各国からの魅力の発信を通じて特に日本人の来場者の方が、海外、世界各国への関心を高めていただいたのではないかと思っており、こういった関心の高まりが今後のアウトバウンドの拡大にも繋がるのではないかと期待をしているところです。
そして、更に申し上げますと2027年の3月には横浜で「国際園芸博覧会GREEN × EXPO2027」が開幕するということで、万博と同様に国内外から多くの来場者を期待しているところです。
1年半後ということで、このような2つの博覧会が間を空けずに我が国で開催される機会を活かし、更なる日本への誘客と、海外からの魅力発信を通じたアウトバウンド、双方向の国際交流を促進してまいりたいと思っております。
(問)2025年7月から9月期の1人当たりの旅行支出が、前年に比べて0.2%下がっているということですが、観光客数は伸びていますけれども旅行支出があまり伸びていないということになりますが、これは要因としてはどのようなことがあるでしょうか。
(答)
インバウンド消費額は、1人当たりの消費額と人数の掛け算になります。1人当たりの消費額というのは、ほぼ同額になっています。
全体の中身を見ますと買物代が昨年の同時期に比べて10%強、減っております。
一方で、娯楽等サービス費は、約9%増えておりまして、昨年のこの時期は例えば円安ということもあったと思いますが、様々な要因が絡んでおりますので、一概に特定の要因による結果かどうかということについては、もう少し前後の時期も見た上で、分析をしていく必要があるのではと思っております。
(問)為替が一つの要因と考えられるのでしょうか。
(答)
昨年の反動という意味では、そういったことも一つの要素にはあると思います。
(観光庁事務方より)為替の件について補足させていただきます。先ほど円高という話がありましたが、ユーロに対しては円安の傾向で、ドルに対しては円高の傾向となっておりますので、その辺りが国によって多少影響があったかと思います。また、買物代が下がっている一方で、業務なども含めた全目的に関しては、宿泊費の方が伸びているところもあり、その兼ね合いの中で全体として減となっているということかと思います。
(問)オーバーツーリズムに関して、自民党が10日にオーバーツーリズムの対策プロジェクトチームを立ち上げ、観光庁からヒアリングしたということですが、観光庁としてどういった問題意識を持っているのかお伺いします。
(答)
オーバーツーリズムの対策については、先ほど観光庁の考え方をお話したところでありますが、自民党の観光立国調査会でも、地方誘客・オーバーツーリズム対策PTが立ち上げられて議論を始められたということです。
観光庁としては、オーバーツーリズム対策や地方誘客に対して、どういった施策を行っているか、あるいは今後どのように進めていきたいかということについて、ヒアリングを受けました。こうした考え方は先ほど申し上げたとおりであり、例えば予算要求の内容等も含めて先生方のご意見にお答えしたものです。
(問)オーバーツーリズムもありつつ、観光客が伸びていることですけれども、この観光客の伸びというのを今より政策として加速させるという考えなのでしょうか。それともオーバーツーリズムの対策があまり間に合っていないからこそ自民党のチームになってきていると思うのですが、少し慎重にペースを抑えるような考えはないのでしょうか。ペースを加速させるというようなスタンスを続けるのか、その考え方についてのスタンスをお伺いします。
(答)
観光庁としては、2030年訪日客数6,000万人・旅行消費額15兆円との大きな目標がありますので、それに向けて、今、着実に施策を進めているスタンスであります。その実現に向けて各種施策を進めていく際に、一部の地域で地域住民への国民生活に対して影響が出ている状況があります。
また、これから益々外国人観光客の方が増えていくことが他の地域でも起こりうる可能性はありますので、そういったことがないようにインバウンドの増加と、国民生活の両立を並行して進めていくことが大事な観点であると思っております。
(問)つまり今のペースを加速させる、すなわちインバウンドを増やしていくという方向は変わらないということでしょうか。
(答)
はい。
(問)消費額について、直近の大手百貨店の上半期決算発表で免税売上高が減ったっていうデータ分析がありそれがまさにこの買い物代の減少と紐づいているのと思う。訪日客にどこでお金を落としてもらえるかという全体の最適解を探る中で、観光業界としてコト消費や体験型観光に強化している中で、買い物代の比率や実額は今後も減少傾向が続くからコト消費とかに強化していると捉えて良いのでしょうか。加えて、仮にこの買い物代のところを再び増加に転じさせるとしたら、必要な取り組みをどのように考えているのか教えてください。
(答)
これという最適な消費の比率はないと思っております。先ほども触れたが通り、観光庁としては、コト消費はこれから伸ばしていく余地があるだろうということ で、日本各地の体験型の旅行商品や観光資源の磨き上げに支援をさせていただいているところです。
こういったことで外国の方が地方で長期滞在をし、体験型も含めて多くの消費をしていただくということは非常に重要なこれから伸びる要素があると思っております。
他方で買い物についても、アジアの方が比率多いという傾向がありますが、アジアの方にとっては買い物が日本の非常に大きな魅力の一つになっておりますので、今後減らしていっていいとかあるいは減るだろうということを私どもとしては全く思っておりません。特に地方部の免税店を今増やしていることもありますので、地方部での魅力的な商品の買い物についても、これからもっと伸ばしていきたいなと思っております。
以上