
規制緩和推進計画の再改定について
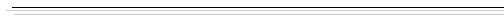

本年3月28日に閣議決定された「規制緩和推進計画の再改定について」においては、昨年12月の行政改革委員会の意見をはじめとした内外からの意見・要望を踏まえ、全事業分野における需給調整規制の廃止、運賃規制の緩和等を中心に、新規事項を盛り込むとともに、既存事項についても可能な限り実施内容等の具体化を図ることにしています。
なお、主な事項は次のとおりです。
-
 1.需給調整規制、運賃規制等関係
1.需給調整規制、運賃規制等関係
- (1)国内航空運送事業の参入規制の見直し
- ○ダブル・トリプルトラック化基準を、平成9年度に廃止する。
- ○需給調整規制の廃止につき、それに必要となる生活路線の維持方策、空港制約のある空港に係る発着枠の配分ルール等を確立した上で、所要の法改正を行い平成11年度に実施する。
- (2)航空運賃制度について規制の緩和
- ○運賃の一層の弾力化、上限価格制への移行については、需給調整規制の廃止といった他の関連事項と並行して検討し、措置する。
- (3)タクシー事業の参入規制の見直し
- ○平成9年度から需給調整基準について、過去5年間の実績に基づき算出された基準車両数に一定割合(9年度は1割、実施状況を見ながら次年度以降さらに緩和)を上乗せする透明化及び弾力化措置を講じ、段階的緩和を進めるとともに、需給調整規制の廃止につき、それに必要となる安全の確保、消費者保護等の措置を確立した上で、所要の法改正を行い遅くとも平成13年度までに実施することとし、その前倒しに努める。
- (4)タクシー事業の運賃規制・事業区域規制・最低車両数規制等の見直し
- ①運賃については、平成9年度から10%の幅の中であれば自由に運賃の設定を認めるゾーン制を導入するとともに、初乗距離を短縮(2KM→1KM)する運賃を認める。また、需給調整規制の廃止の検討と並行して、速やかに上限価格制を検討の上、遅くとも平成13年度までに措置することとし、その前倒しに努める。
- ②事業区域については、平成9年度から統合・拡大に着手し、3年以内に現行の事業区域数1,911(基本的に市町村単位)をほぼ半減させる。
- ③最低車両数については、平成9年度に東京の60両、大阪・名古屋・横浜の30両を、10両に圧縮する等縮減措置を講じる。
- (5)乗合バス事業の参入規制等の見直し
- ○需給調整規制の廃止につき、生活路線の維持方策の確立を前提に、所要の法改正を行い遅くとも平成13年度までに実施する。
- ○需給調整規制の廃止の際には、上限価格制を検討の上、措置する。
- (6)貸切バス事業の参入規制の見直し
- ○平成9年度に一定の実働率(年間平均60%等)以上の場合には増車を認めることとし需給調整基準の弾力化及び透明化を図るとともに、需給調整規制の廃止につき、それに必要となる安全の確保、消費者保護等の措置を確立した上で、所要の法改正を行い平成11年度に実施する。
- (7)貸切バス事業の運賃規制・最低車両数規制・事業区域規制等の見直し
- ①運賃について、平成9年度に割引運賃の導入等一層の弾力化を図るとともに、需給調整規制の廃止に併せて届出制へ移行する。
- ②最低車両数については、平成9年度に最大10両を大型車を保有している場合には最大5両に縮減する。
- ③事業区域規制については、平成9年度から拡大・統合に着手し、3年以内に現行の市郡単位等を都府県単位に統合する。
- (8)鉄道の参入規制の見直し
- ○需給調整規制の廃止につき、所要の法改正を行い平成11年度に実施する。(貨物鉄道については、国鉄改革の枠組みの中で日本貨物鉄道株式会社の完全民営化等経営の改善が図られた段階で実施することとし、おおむね5年後を目標年度とする。)
- (9)貨物鉄道運賃の届出制への移行
- ○運賃・料金については、需給調整規制の廃止に併せて届出制へ移行する。
- (10)港湾運送事業の免許制及び料金認可制の見直し
- ○需給調整規制の廃止を含む見直しにつき、平成9年度における行政改革委員会の監視活動及びその結論を踏まえて適切に措置する。
- (11)国内旅客船事業等の参入規制の見直し
- ○需給調整規制の廃止につき、それに必要となる生活航路の維持方策等を確立した上で、所要の法改正を行い遅くとも平成13年度までに実施する。
- ○貨物フェリーの需給調整規制の廃止につき、国内旅客船事業に係る需給調整規制の廃止の時期に併せて実施する。
- (12)船腹調整事業の計画的解消
- ○モーダルシフトの担い手となるコンテナ船、RORO船を平成10年度末までに船腹調整事業の対象外とする。その他の船舶については、荷主の理解と協力を得ながら4年間を目途に所要の環境整備に努め、その達成状況を踏まえて同事業への依存の解消時期の具体化を図ることとするが、同事業の解消の前倒しにつき中小・零細事業者に配慮しつつ引き続き検討する。
-
 2.上記以外の主な事項
2.上記以外の主な事項
- (1)トラック等の車検制度の見直し
- ○国際的動向を踏まえつつ、道路運送車両法改正後の状況の変化を把握し、有効期間の延長の可能性を検討する。
- ○特に、トラック等の検査証の有効期間については、平成9年度に集中的に調査を実施し、その結果、安全確保、公害防止の面で支障がない場合には、延長する。
- (2)分解整備検査制度の見直し
- ○分解整備検査については、国際的な状況も踏まえ、安全の確保を図りつつ、その必要性を含めた制度のあり方について、平成9年度6月を目途に方針を決定し、早急に所要の措置を講じる。
- (3)乗合バスの一時不足の場合、貸切バスの使用を認める
- ○平成9年度に乗合バスの一時不足の場合に貸切バスの使用を認める。
- (4)日本籍船への日本人船長・機関長2名配乗体制の実現
- ①日本人船長・機関長2名配乗体制については、日本人船員の確保策等と併せて対応する必要があることから、海運造船合理化審議会の審議結果(平成9年6月予定)を踏まえて早急に所要の対応をする。
- (5)鉄道の各種技術基準の緩和
- ○内燃動車、新幹線車両に係る定期検査の周期につき、所要の安全性が確認されたものを延伸するための走行試験を平成9年度に開始する等、各種技術基準の見直しを行う。
- (6)貨物フェリーの許可の調整措置の廃止
- ○貨物フェリーの許可の調整措置について、内航RORO船を船腹調整事業の対象外とする時期(平成10年度末までに措置)に併せて廃止し、貨物フェリー事業と内航RORO船事業との競争条件を整備する。
- (7)旅行業の登録の有効期間の延長
- ○旅行業の登録に係る有効期間について、所要の消費者保護措置を検討の上、3年から5年に延長する。
- (8)EDIによる港湾物流情報システムの構築
- ○入出港に係る手続きで電子情報処理化になじむものについて、平成11年に更改予定の海上貨物通関情報処理システムとの連携を考慮して、より総合的な電子情報処理化を推進する。
-
 3.その他
3.その他
- (運輸政策局関係)
- ○倉庫管理指導員の更新講習の廃止及び有効期間の撤廃
- ○倉庫の主要構造等の変更認可事項の見直し
- ○倉庫業に係る役員変更届出の申請負担軽減
- ○トラックターミナル事業に係る役員変更届出の申請負担軽減
- ○貨物運送取扱事業の事業計画の軽微な変更に係る届出の簡素化
- ○貨物運送取扱事業に係る役員変更届出の申請負担軽減
- ○一般貨物自動車運送事業と第二種利用運送事業を兼業している場合の事業計 画変更届出等の提出窓口の統一
- ○一般貨物自動車運送事業と貨物運送取扱事業を一体的に経営する事業者によ る事業計画変更認可申請等の一元化
- ○鉄道に係る貨物運送取扱事業の許可について運用の弾力化
- ○航空に係る貨物運送取扱事業の許可について運用の弾力化
- ○事業協同組合等に関する運輸大臣の権限について、その一部を都道府県知事 に委任する方向で見直し
- ○旅行業の合併時の審査の簡素化及び迅速化
- (鉄道局関係)
- ◯索道の技術基準に係る仕様等の基準から性能基準への移行
- ○鉄道事業に係る役員変更届出の申請負担軽減
- ○索道事業に係る役員変更届出の申請負担軽減
- (自動車交通局関係)
- ○大臣許可(一般貨物自動車運送事業の特別積合せ貨物運送)の地方運輸局長への権限の委任の検討
- ○特別積合せ貨物運送に関する同一市町村内の営業所の移転に係る事業計画変更認可の見直し
- ○運行系統の新設・変更のための事業計画変更認可に係る申請書類の提出部数の削減の検討
- ○一般貨物自動車運送事業の運輸に関する協定の認可の廃止
- ○自動車運送事業の事業用自動車の数を変更する際の事業者証明書の交付の手続の統一
- ○沖縄県におけるトラック事業の事業用車両の保管場所と営業所との距離規制の緩和の検討
- ○事業用自動車車体への名称記載義務の緩和の検討
- ○乗合バスの営業政策的割引の届出を行う際の添付書類の簡素化
- ○乗合バス免許申請の処理の迅速化
- ○乗合バス事業の免許申請、事業計画変更認可申請時の各運行系統に配置する最大の事業用自動車に関する記載事項の省略の検討
- ○バス事業の管理の受委託基準の緩和の検討
- ○バス運賃変更認可申請書の記載事項の簡素化の検討
- ○有償スクールバス等の規制のあり方の検討
- ○自家用バス登録手続の簡素化
- ○バス停留所の新設手続の届出化
- ○貸切バス事業に係る役員変更届出の申請負担軽減
- ○乗合バス事業に係る役員変更届出の申請負担軽減
- ○高速バス運行経路の変更(乗せ替え)に係る免許申請の処理の迅速化
- ○タクシー事業の分割譲渡、譲受の容認の方向での検討
- ○旅客自動車運送事業の輸送実績報告の簡素化
- ○一般旅客自動車運送事業の各種報告書の押印省略
- ○旅客自動車運送事業等に係る許認可等の申請書類の郵送による提出の容認
- ○旅客自動車運送事業等に係る許認可等の申請書類の郵送による提出の容認
- ○タクシー事業に係る役員変更届出の申請負担軽減
- ○バスターミナル事業に係る役員変更届出の申請負担軽減
- ○レンタカーのマイクロバスの規制の緩和の検討
- ○封印委託制度の見直し
- ○熱害警報装置と同様なもの(OBDⅡ)に対する事前確認の廃止
- ○過回転防止装置付き車両の近接騒音測定の取扱についての事前確認手続きを不要化
- ○予備審査における海外メーカーの外注試験施設使用の容認
- ○構造変更時における日本向け打刻以外の車台番号が打刻されたホモロカーの容認
- ○大型自動車に係る速度表示装置装着義務の廃止の検討
- ○特殊自動車についてリア・オーバーハングの規制の適用除外の検討
- ○JATMA YEAR BOOK 未掲載タイヤの取扱いの検討
- (海上交通局関係)
- ○一般旅客定期航路事業の事業計画変更の認可事項の対象範囲の縮小
- ○一般旅客定期航路事業等に係る役員変更届出の申請負担軽減
- ○一般旅客定期航路事業の航路又は使用船舶の変更時の安全確認検査航海の原則廃止
- ○外航貨物定期航路事業に係る事業開始等の届出内容の見直し
- ○内航海運に係る事業計画変更時の添付書類の簡素化
- ○自家用船舶の届出の際の日本内航海運組合総連合会意見書添付の廃止
- ○港湾運送事業に係る役員変更届出の申請負担軽減
- (海上交通局、海上技術安全局)
- ○臨調法による船舶建造許可申請手続きの大幅な簡素化
- ○臨調法の改廃を含む建造許可制度の抜本的見直し
- (海上技術安全局)
- ○水先の必要な範囲の見直し
- ○中間検査における推進用機関及び発電用機関の開放検査の合理化
- ○定期検査及び中間検査の受検時期の弾力化
- ○内燃機関の製造認定事業場における完成検査の方法の合理化
- ○船員労務供給事業の許可期間の延長検討
- ○海技従事者資格の取得等に必要な乗船履歴の緩和の検討
- ○マルシップ乗船者に係る船員個票審査の簡素化
- ○外国船舶での乗船履歴に関する証明方法の簡素化
- ○航海実歴認定制度に関する申請手続きの簡素化
- (港湾局)
- ○港湾区域における鉄道施設、送電施設等に係る港湾区域での占用期間の長期化
- ○港湾区域における鉄道施設、送電施設等に係る港湾区域での占用許可の更新手続の簡素化
- ○港湾区域と河川区域が重複している場合であって、港湾管理者と河川管理者が同一の場合の鉄道施設等の占用手続きの実質的な簡素化
- (航空局)
- ○飛行計画等に係る通報の電子化
- ○航空機装備品に係る修理改造認定事業場の認定の有効期間の倍化
- ○航空機に係る整備改造認定事業場の認定の有効期間の倍化
- ○航空従事者技能証明申請書等のOCR化
- (海上保安庁)
- ○LPG内航船の休日荷揚申請内容の事後変更の容認
- ○液化ガスタンカーの本邦初入港時における安全対策確約書の簡素化
- ○タンカーの本邦初入港時における安全対策確約書の必要性についての見直し
- (気象庁)
- ○気象測器検定の有効期間の延長の検討
なお、次の担当課において、引き続き規制緩和に関する内外の意見・要望を受け付けます(E-Mailによる送付も可能)。
-
(連絡先)
電話(大代表)03―3580―3111
-
大臣官房文書課 規制緩和担当
(内線5156 FAX 03‐3593‐0474)
E‐Mail:KBXA-HOKI@so.motnet.go.jp
-
運輸政策局政策課 規制緩和担当
(内線5535 FAX 03‐3580‐3086)
E‐Mail:USX1-SEISAKU@so.motnet.go.jp
-
運輸政策局国際業務第一課 規制緩和担当(国際関係)
(内線5682 FAX 03‐3580‐4447)
E‐Mail:USX2-KOKU1@so.motnet.go.jp
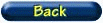
 1.需給調整規制、運賃規制等関係
1.需給調整規制、運賃規制等関係
 2.上記以外の主な事項
2.上記以外の主な事項 3.その他
3.その他
 1.需給調整規制、運賃規制等関係
1.需給調整規制、運賃規制等関係
 2.上記以外の主な事項
2.上記以外の主な事項 3.その他
3.その他