| 平成15年9月19日 |
| <問い合わせ先> |
| 住宅局市街地建築課 |
| (内線39653) |
| 都市・地域整備局市街地整備課 |
| (内線32742) |
| TEL:03-5253-8111(代表) |
- 調査報告の位置づけ
- 都市再生プロジェクト事業推進費調査として、国土交通省の都市・地域整備局と住宅局が共同で実施。
- 「再開発による都市中心部再生支援の新たなスキーム検討委員会」(委員長:日端康雄慶應義塾大学大学院教授、副委員長:中井検裕東京工業大学大学院教授)を設置して検討。
- 「活力創造型」のアプローチ(都市再生のブレーク・スルー)
- 都市再生における再開発の役割は、民間投資を都市中心部の更新活動に振り向け、活力停滞と人口空洞化のベクトルを逆転させること。
- 国境を越えた都市間競争の時代に、新しい産業機能・高次の交流機能など、わが国経済の牽引車となり得る活力を民間投資で生み出す「活力創造型」のアプローチが必要。
- 「ギャップ・ファンド方式」の補助制度導入を提案
- 「ギャップ・ファンド方式」は、建設費等の「開発コスト」と賃料等から算出される「エンドバリュー」(収益還元価値)の差額を補填する補助方式。英国の都市再生で実施。
【メリット】個々の事業に応じて公的補助を「必要最小限かつ成立可能な額」に精査することで、公的補助全体を効率化しつつ、事業箇所を増大。
→「全国都市再生」の推進を図り、地方都市中心部において活力創造型の民間投資を連鎖的に引き出し、停滞する地域経済をプラスのスパイラルに転換。
- 「ギャップ・ファンド方式」は、建設費等の「開発コスト」と賃料等から算出される「エンドバリュー」(収益還元価値)の差額を補填する補助方式。英国の都市再生で実施。
- 保留床売却益に頼らない「賃貸運営型」を支援
- 従来の再開発は、地価上昇を前提に保留床売却益で収支を合わせる型が多かったが、経済環境が変化。
- これからは、土地の高度利用よりも街の機能更新を重視し、小規模地権者が共同で市場ニーズに合ったビルを建て、経営ノウハウのある主体に一括委託するなど、持続性ある事業スタイルが重要。
- 法的制度の合理化の論点
- 権利変換手法を柱とした市街地再開発事業の仕組みは、世界的にも非常に緻密な制度。制度の根幹を変更すべき理由は見あたらない。
- 一方、各方面から要望のあった、特定建築者の選定時期の早期化、区域内に鉄道等が建設される場合の一敷地一筆原則の合理化、組合の破綻処理手続き等については、論点整理が必要。
ギャップ・ファンド方式補助のイメージ(市街地再開発事業)
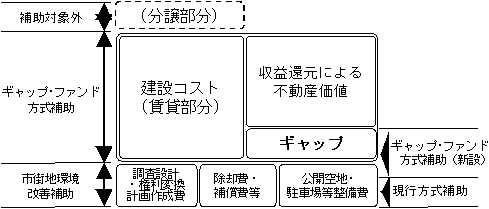
|
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport
