| 平成16年10月22日 |
| <問い合わせ先> |
| 海事局安全基準課(技術基準関連) |
|
(内線43952、43953) |
| 海技資格課(免許関連) |
|
(内線45316、45357) |
|
TEL:03-5253-8111(代表) |
- 1・2級の小型船舶操縦士免許については、これまで5トン未満の船舶に限定して乗船できる免許(5トン限定免許)を設けるとともに、免許を取得するための身体検査基準のうち弁色力(色を識別する能力)について「色盲又は強度の色弱でないこと」を基準にしていましたが、航行の安全を確保しつつ、より簡素で合理的な免許制度とするため、
- 現在の小型船舶操縦士免許の5トン限定区分を廃止する。
- 弁色力の基準を「夜間において船舶の灯火の色を識別できること」に改める。
- また、小型船舶の技術基準についても、従来より簡素な構造設備で長距離の沿岸周遊クルージング等ができるよう、2級小型船舶操縦士の免許に対応する水域(沿岸水域)を航行する小型船舶の技術基準を新たに設けます(省令改正)。
- ソフトの要件(免許)とハードの要件(技術基準)が整合されること等により、マリンレジャーの健全な発展につながることが期待されます。
- その他大型の海技士免状取得の促進のため、6級海技士(航海)に係る登録船舶職員養成施設の区分を新設する等の省令改正を行います。
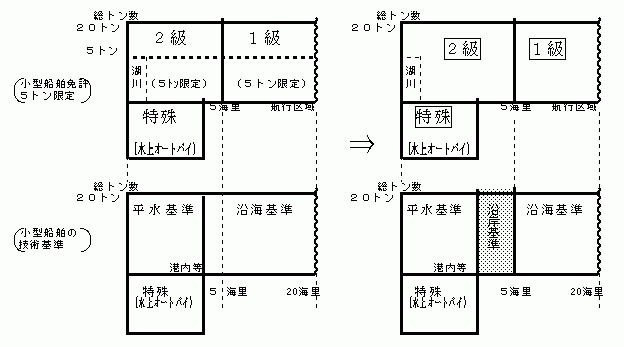
<スケジュール>
![]() 小型船舶操縦士の免許関係及び大型の海技資格に係るもの
小型船舶操縦士の免許関係及び大型の海技資格に係るもの
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正
16年10月22日 公布(予定)
11月 1日 施行(小型船舶操縦士の弁色力については、17年1月1日)
- 小型船舶安全規則等の一部改正
16年10月28日 公布(予定)
11月 1日 施行
参考
(1)小型船舶免許の5トン限定区分の廃止に係る経緯
![]() 総トン数20トン未満のボートに乗ることができるボート免許制度は、平成15年6月に現在の1級・2級・特殊(水上オートバイ専用)の免許区分となった。
総トン数20トン未満のボートに乗ることができるボート免許制度は、平成15年6月に現在の1級・2級・特殊(水上オートバイ専用)の免許区分となった。
![]() 1級及び2級の免許については、5トンの限定区分を設けていたが、制度の更なる簡素・合理化が必要との要望が内外から寄せられていたため、本年3月より有識者による検討会を開催し、5トン限定区分の免許のあり方について検討を行い、本年8月6日に
1級及び2級の免許については、5トンの限定区分を設けていたが、制度の更なる簡素・合理化が必要との要望が内外から寄せられていたため、本年3月より有識者による検討会を開催し、5トン限定区分の免許のあり方について検討を行い、本年8月6日に
- 5トン限定区分を本年秋頃を目途に廃止すること
- 現在5トン限定の付されている免許受有者は、移行のための講習等を要せず、5トン以上の船に乗ることができることとすること
- 乗ろうとする船舶に習熟することが重要であり、そのための講習や乗船機会の確保のための情報提供を積極的に行っていくこと
(2)小型船舶免許に係る身体検査基準の見直しに係る経緯
小型船舶操縦士試験における身体検査基準のうち弁色力(色を識別する能力)に関しては、これまで「色盲又は強度の色弱でないこと」を基準に、色覚に関する検査を実施してきたところであるが、小型船舶操縦士に必要な弁色力の検査方法としてよりふさわしい方法がないか等の観点から、昨年4月より有識者等による検討を行い、本年9月に
- 小型船舶操縦士に係る弁色力の基準を「夜間において船舶の灯火の色 を識別できること」に変更するとともに、色覚に関する検査を廃止し、 夜間の灯火の色を呈示する検査器による検査に替えること
- 当該検査に不合格となる場合でも、航路標識の彩色を識別できるとき は航行時間を昼間に限定した免許が取得できること
(3)小型船舶の技術基準の見直しに係る経緯
現在、小型船舶操縦士免許受有者の多くは、2級免許(日本全国周辺の沿海区域に接する海岸から5海里以内の水域及び平水区域を航行できる免許)を持っている。
一方、小型船舶の構造設備については、2級免許に対応する小型船舶に対する技術基準が設けられていないため、日本各地の沿岸を周遊するような長距離のクルージングを楽しみたい場合などには、沿海区域(日本全国周辺の海岸から20海里以内の水域)の技術基準に適合した船舶を使用する必要がある。
こうした背景から、今般、沿岸周辺の水域を航行する小型船舶について、ソフト要件(免許)の航行区域に係る規制区分と整合させた新たなハード要件(小型船舶の技術基準)を設けることにより、小型船舶の利用環境の整備を図ることとする。
なお、この技術基準は、沿海区域の技術基準に比べて航海用具、救命設備、無線設備等の一部を緩和したものとする。
![]()
All Rights Reserved, Copyright (C) 2004, Ministry of Land, Infrastructure and Transport
