| 平成16年3月30日 |
|
<問い合わせ先> |
| 政策統括官付政策調整官付 |
| (内線53113、53114) |
| TEL:03-5253-8111(代表) |
わが国は現在、これまでにない、大きな変革の時代を迎えようとしています。
歴史的に増加の一途をたどってきた総人口が、2006年をピークに継続的な減少に転じます。世界を見渡した時、人口が減少する状況において国力を上げることは容易ではありません。この有史以来の状況は、生産力の低下をはじめさまざまな影響をもたらすと考えられます。また、中国を筆頭に東アジア諸国の経済的台頭も、アジアにおけるわが国の相対的な地位に影響を及ぼしかねません。
このような状況のなかにある今日、次の日本を開くための新たな国土ビジョンが求められています。
こうしたなか、平成14年11月に国土審議会基本政策部会から「国土の将来展望と新しい国土計画制度のあり方」についての報告がなされ、今後の地域づくりに際しては、「モビリティの向上」と「広域的な対応」が重要で、『二層の広域圏』を念頭においた対応が基本であると指摘されています。(『二層の広域圏』のポイントがわかる参考資料2参照)
この指摘をもとに、“モビリティの向上”の観点から『二層の広域圏』の形成に向けて、交通体系整備や交通サービスの今後の方向性を検討するため、国土計画、地域マネジメント、交通などに造詣の深い学識経験者からなる「二層の広域圏に資する総合的な交通体系に関する検討委員会」(委員長:森地茂・東京大学大学院工学系研究科教授)において、調査、検討を進め、ここに中間報告をとりまとめました。これは、“新しい国のかたちをつくる”ための総合的な交通体系のあり方を提案したものです。
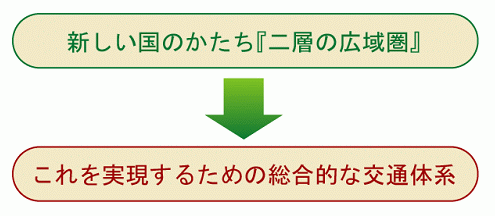
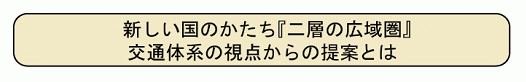
『二層の広域圏』とは、2つの視点から日本の国土構造を考えるものです。1つめの視点は、海外との関係や国内の競争力を高める意図から、国のあり方を考えるものです。2つめの視点は、誇りをもった暮らし方や人と自然との関係から、人びとが生活する地域社会のあり方を考えるものです。
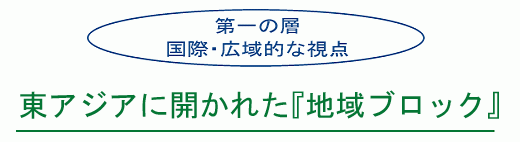
都道府県を越えた、欧州の中規模一国に匹敵する『地域ブロック』の圏域を形成。これにより、地域の独自性を活かした東アジア諸国などとの国際交流や連携を実現し、経済的にも国の活力を維持、向上していこうという考えです。
ここでは東アジアゲートウェイ機能を充実させ、国内外との競争力を高めるとともに、『地域ブロック』同士の交流・連携の促進、地域の活性化を促す仕組みの構築などを進めます。
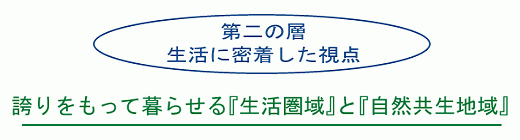
交通1時間圏・人口30万人前後のエリアを『生活圏域』としてとらえ、人口の減少下にあっても、現在の水準の生活関連サービスを維持し、地域の活力を保っていこうという考えです。さらに生活圏域の形成に困難を伴う中山間地のエリアを『自然共生地域』などとしてとらえ、国土保全や水循環、景観保全などの機能を確保していこうとするものです。
『生活圏域』では、地域で立案する地域の交通計画を進め、多様な主体による使いやすい交通手段を充実させ、さらにはモビリティの向上による『生活圏域』の形成や拡大を図ります。また『自然共生地域』では救命救急医療体制を支援する移動手段の確保、隣接する『生活圏域』との確実な交流・連携の促進などを進めます。
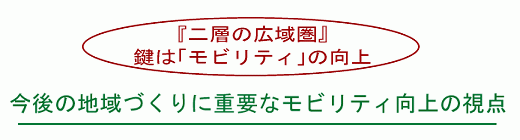
国内外、圏域内外の機能分担と相互補完を円滑に行なえるよう、人やモノの移動の利便性やさまざまな地域資源の流動性といった「モビリティ」の向上を図ることが、『二層の広域圏』の形成の鍵となります。
|
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。 |
![]()
All Rights Reserved, Copyright (C) 2004, Ministry of Land, Infrastructure and Transport
