|
平成17年9月15日
|
|
<問い合わせ先>
|
|
河川局河川計画課 |
|
(内線35333) |
|
TEL:03-5253-8111(代表) |
内閣府が実施した「水害・土砂災害等に関する世論調査」について、その結果を分析しました。(【 】内は内閣府資料の番号)
- 1.自然災害によって被害を受けたり、危険を感じたことのある人が増加【1(1)】
- 台風で29.1%、川のはん濫で11.2%の人々が、被害を受けたり身近に危険を感じたと答えている。また、被害や危険を感じたことがなと答えた人は、6.4%減少(54.1%(H11)→47.7%(H17))している。ここ数年の自然災害の頻発により国民の関心が高まってきていると考えられる。
- 2.国民は、水害・土砂災害対策を優先的に実施すべきと考えている 【2(3)】
- 国民の約7割が、予算制約下において他の施策を遅らせても、水害・土砂災害対策を優先的に実施すべきと考えている。(図−1)
- 3.国民は、災害が起きてからの復旧対策よりも、予防対策を望んでいる 【2(4)】
- 国民の約8割が、災害を受けてから事後的に行う復旧対策より、堤防などの整備により災害を事前に防ぐ予防対策を望んでいる。かけがえのない命や重要な資産を守ることが強く望まれていると考えられる。(図−2)
-
図−1 予算制約下での水害・土砂災害対策の優先度 図−2 予防対策と復旧対策の優先度
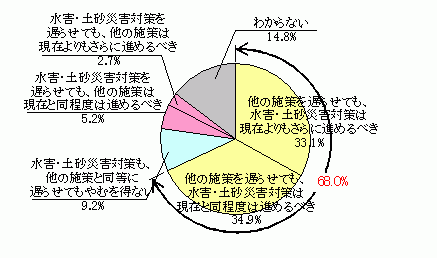
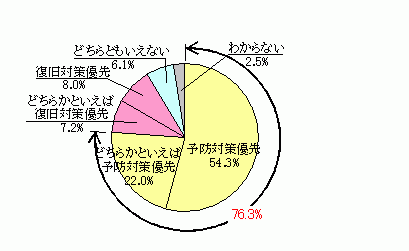
- 4.国民は、防災のためには土地利用制限強化の必要性を感じている 【2(5)】
- 災害を防ぐ方法の1つとして、低地に建物を建てることを制限するなど、土地利用の制限を強化する必要性を感じている人は、約1割増加(54.1%(H11)→66.5%(H17))しており、防災意識が高まっていることが読み取れる。なお、都市規模別に見ると、大都市75.1%、中都市68.8%、小都市61.5%、町村56.7%で、土地利用制限の強化が必要と回答しており、災害に対して脆弱な地域を開発してきた都市部において、土地利用制限強化の必要性がより強く認識されていると考えられる。
- 5.災害時における防災情報の周知度が高まってきている 【4(1)】
- 「水防警報」が微減(26.1%(H11)→25.9%(H17))している他はすべて増加しており、防災情報の周知度が高まってきている。特に、「避難勧告や避難指示」(60.6%(H11)→75.5%(H17)14.9%増)、「警戒水位」(57.3%(H11)→64.2%(H17)6.9%増)が大幅な増加となっている。昨年度に破堤等の水害が多く発生し、多くの人々が避難を余儀なくされたことなどの影響と考えられる。
(図−3)
-
図−3 「避難勧告・指示」の周知度
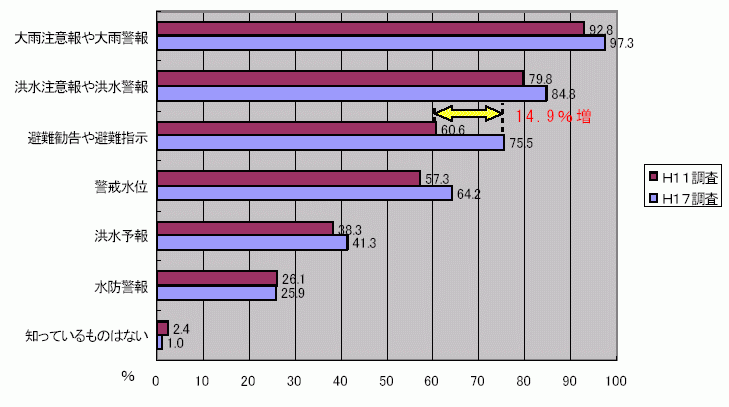
- 6.危険な場所の最新情報、水位・雨量の細かな情報が求められている 【4(2)】
- 国民の48.0%が「危険な場所についての頻繁な最新の情報」、45.5%が「身近な川について細かな場所ごとの水位や雨量を示す情報」を、水害や土砂災害が発生する危険性がある時の防災情報として必要と思っている。先の設問で、「避難勧告や指示」に対する周知度が増加しているように、災害からの避難に対して意識が高まっていることから、実際の避難判断に必要となる頻繁で細かな情報を求めているものと考えられる。
- 7.最も望ましい避難情報提供は職員による巡回 【4(4)ア】
- 避難勧告や避難指示が出される場合における、最も望ましい伝達方法については、「市町村職員や消防職員(広報車による巡回等)」25.9%、「防災行政無線(広報のため公園等に設置されているスピーカなど)」17.0%、テレビ(14.0%)の順となっており、避難の判断のための重要な災害情報の伝達については、信頼できる人からフェース・トウ・フェースで伝えられることが望まれていると考えられる。(図−4)
-
図−4 最も望ましい避難情報提供手法
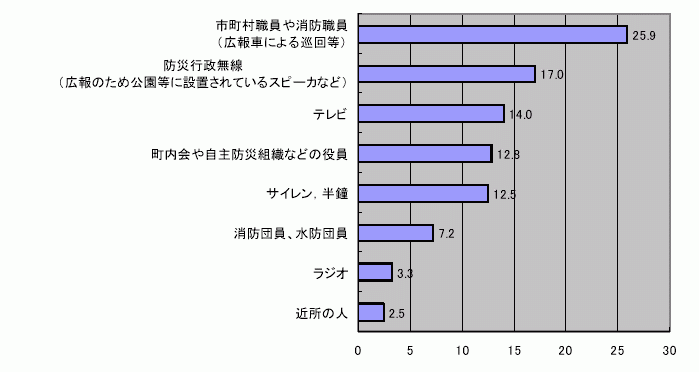
(資料)
 本調査の概要は内閣府ホームページで掲載
本調査の概要は内閣府ホームページで掲載
http://www8.cao.go.jp/survey/index.html
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。
|

(ダウンロード)
|

All Rights Reserved, Copyright (C) 2005, Ministry of Land, Infrastructure and Transport


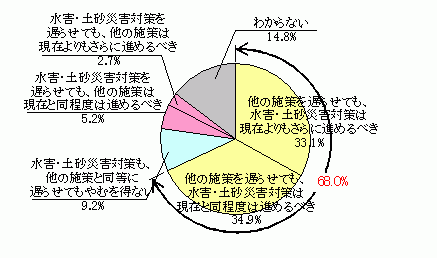
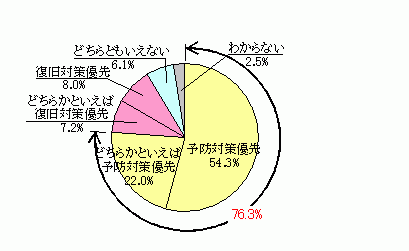
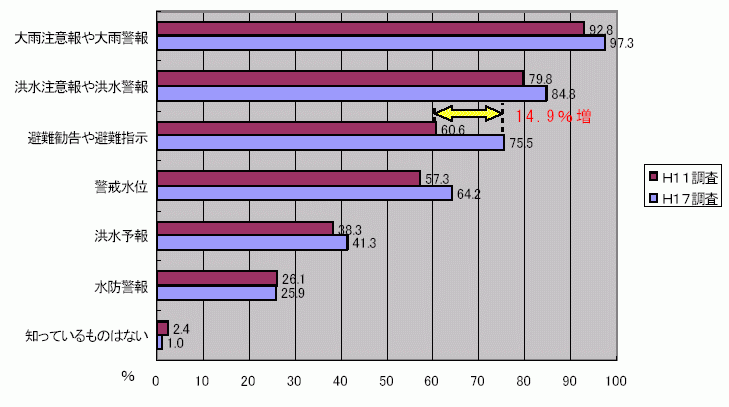
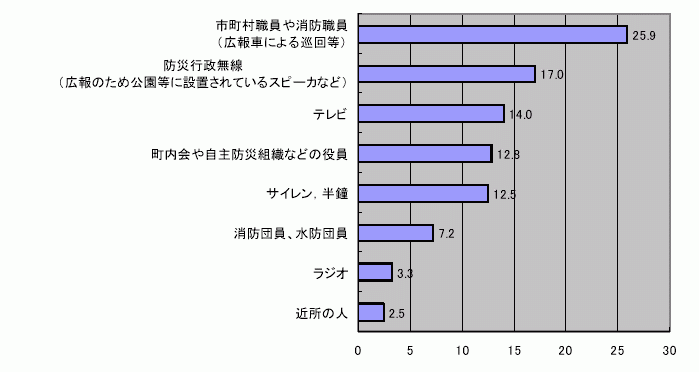
![]() 本調査の概要は内閣府ホームページで掲載
本調査の概要は内閣府ホームページで掲載
![]()