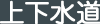平成14年7月26日
各厚生労働大臣認可 担当者 様
水道用水供給事業者
水道行政の推進につきましては、種々の御協力を賜り、感謝いたしております。 平成14年7月23日に開催された総合規制改革会議において、「中間とりまとめ-経済活性化のための重点的に推進すべき改革-」がまとめられましたので、別添の通り、情報提供いたします。なお、「上水道事業の民間経営の推進」については、地方公共団体による判断とされているところです。 ※ 全文を入手されたい方は、http://www8.cao.go.jp/kisei/siryo/020723/を御参照下さい。
第2章 民間参入・移管拡大による官製市場の見直し
2.官民役割分担の再構築 多様化するニーズに対応した公共サービスの提供を実現するためには、民営化、民間事業体の参入、PFI(Private Finance Initiative)、民間委託、あるいはこれらを包括するPPP(Public Private Partnership)など様々な手法を駆使することが必要であり、かつ、それにより政府部門の効率化を図っていく必要がある。効果的・効率的な「競争」の導入は社会的費用を縮減させるということを十分勘案し、政府部門は、直接的関与ではなく、極力多様な主体・手法の活用を志向するよう価値観の転換を図るべきである。
(1)行政関与の在り方の見直し
行政関与の可否に関する基準は、平成8年に行政改革委員会において、1)公共財、2)外部性、3)市場の不完全性、4)独占力、5)自然(地域)独占、6)公平の確保 といった「市場の失敗」による基準を提示しているが、これに行政の非効率、責任の不明確、既得権益の擁護といった「政府の失敗」を比較考量するとともに、極力費用便益分析等を行い、行政活動の範囲を限定することが必要である。
なお、上記基準では、基本原則として「民間でできるものは民間にゆだねる」という考え方を示しているが、現在においては、「民間でできるものは官は行わない」という基本理念を確立すべきである。
また、行政関与の必要性が確認されたものであっても、そのすべての役割を政府部門が担う必要はなく、1)行政処分、2)インフラ(公共財)の整備・維持管理、3)住民等への財・サービスの提供 という公共サービスの提供について、どの役割をどのような方法によりどの程度まで政府部門が担うかを検証することが重要である。
当該公共サービスの提供全体としては民間にゆだねることができない場合であっても、政府部門がすべてを実施するのではなく、競争環境や公正性確保の仕組みを整備しつつ、従来担ってきた機能の分離、委託可能な範囲の拡大等、積極的に民間参入の拡大を進めていくことが必要である。
民間参入の形態としては、
1)事業譲渡:事業を民間企業に売却する方式
2)株式会社化:いったん政府部門の出資による株式会社を設立し、事業を承継し、逐次に株式を公開して最終的には全株を放出して完全民営化する方式
3)経営委託:政府部門が担っている業務の包括的管理ないしは経営を一括して、期間や一定の条件をあらかじめ定め、事業のリスクや会計上の責任を含めて民間事業者にゆだねる手法。
4)業務委託:政府部門が担っている業務の一部を民間に委託する手法。
といった方法が考えられる。
今後、民間参入の拡大を進めていくに当たっては、各事業・事務について、その固有の特性、地域事情等実態を踏まえた検証を行い、積極的な民間参入の拡大を実施するものとする。次項では、上下水道及び公営ガスについて提言しているが、これらは喫緊の課題として推進すべきものであり、それらの例に倣って他の事業・事務についても民間参入の拡大を進めていくべきである。なお、以下の例は当会議におけるヒアリング等を通じ民間参入の拡大の検討対象の例示として挙がったものであって、現に政府部門が行っている事業・事務のうち民間参入の拡大の検討対象すべてを含むものではない。
その際、以下のような考え方を踏まえ、包括的な移管に馴染みにくいものについては、機能・役割の仕分けをして、政府部門の担うべき機能・役割を極力限定した上で、効果的な民間参入の拡大を設計すべきである。
1) 「住民等への財・サービスの提供」の多くは、原則完全な形での民への移管が可能である。地域独占の状態、インフラ整備の状況等を勘案し、事業譲渡、株式会社化ないしは経営委託を推進すべきである。
・ 既に同一市場において他の提供者が参入している分野においては事業譲渡(なお、同一市場の認識については、公益性・公共性等を勘案した検証が必要)
・ 地域独占となっている分野においては事業譲渡又は株式会社化又は経営委託(受け皿となる民間事業者がいる場合は事業譲渡又は株式会社を設立し株式公開、いない場合は株式会社化した上で採算性の向上を果たした上で株式公開又は経営委託)
・ 免許の交付や給付行為等については業務委託
2) 「インフラ(公共財)の整備・維持管理」は、インフラ使用の対価性等、当該インフラの性質を勘案しつつ、特に対価を受領できるものについては積極的な移管を進めるべきである。なお、インフラとそれを通じた財・サービスの提供が一体である事業については原則1)によると考えられる。
・ 財・サービスの提供を伴う事業については、事業譲渡又は株式会社化又は経営委託
・ 財・サービスの提供を伴わず対価性に乏しい事業については業務委託
3) 「行政処分」は、公によらざるを得ないものであるが、給付、徴収等の事実行為については積極的な業務委託による民の活用を志向すべきである。
(2)官から民への事業移管の推進
公共サービスについては、その需要者たる国民が必要とするものを最小の費用で提供することが重要である。このためには、可能な限り市場原理を活用した手段・形態を導入し、「官から民への事業移管」の推進を図るべきである。
官から民への移管に関する手法は、民営化、民間事業体の参入、PFI、民間委託、あるいはこれらを包括するPPPなど多岐にわたるが、個々の公共サービスを各手法に当てはめることにより、それぞれの事業移管を阻害する規制を抽出・撤廃することを検討するとともに、PFIや民間委託を推進させるため以下のような制度設計が必要である。
1)「公の施設」の受託管理者の拡大
地方自治法では、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設を「公の施設」と規定し、その「管理」の主体を地方公共団体及び地方公共団体出資の法人(第三セクター)等に制限している。
しかしながら、地方自治法は、条例で公の施設の管理に関する事項を定めることを規定しているため、条例等により、管理受託者の管理に関する事項が実質的に規定してあれば、管理受託者の範囲を制限することは理由がない。より効率的な公共サービスを提供するためには、その提供方法の多様化を図ることが必要であり、「公の施設」の管理の担い手を、民間事業者等多様な主体に拡大すべきである。
また、「公の施設」の管理とは、管理権限を言うに過ぎず、現行法の下においても、現実の管理業務を行うことは地方公共団体及び地方公共団体出資の法人等に限定するものではなく、広く民間へ委託することを容認しており、地方公共団体に留保されている権限は外形上の料金決定に限られるとの指摘もある。しかし、地方公共団体によってはこの趣旨は必ずしも徹底されておらず、「公の施設」であるがゆえに、現実の管理業務を自ら行うほかはないとの誤解も多い。
上記のことから、まず、「公の施設」における管理とは、公金としての施設の利用料金の徴収とその料金決定権のみが地方公共団体等に留保されているに過ぎないことを直ちに周知徹底すべきである。【平成14年度中に検討・措置】
さらに、より広範囲に民間への委託を実現するため、当該外形要件の考えを廃止し広く管理委託の考えを認めるべきであり、一定の条件での料金の決定権等を含めた管理委託を地方公共団体及び地方公共団体出資の法人(第三セクター)等のみならず、民間事業者等に対して認容できるように地方自治法の改正についても検討を行うべきである。【平成14年度中に検討開始】
2)行政財産の民間開放の推進【平成14年度中に検討・措置】
公共サービスの提供手法を多様化させるためには、政府部門が所有する土地・建物等の財産を活用することが必要であるが、国有財産法第18条及び地方自治法第238条の4においては、国、地方公共団体及び政令で定めるもの以外について行政財産に私権の設定を行うことを禁止している。情報公開等により透明性、公平性を担保しながら、行政財産に関わる占有や使用について、より柔軟かつ弾力的な使用の在り方を認めるべく規制緩和を図るべきである。
なお、行政手段の多様化の推進を図るため、補助金については、その交付を受け建設した施設において、住民に提供されるサービスの実態が不変であり、補助目的や施設の効率的利用等に照らし適当である場合には、事業主体の変更等があっても(例えば、地方公共団体から民間事業者への転換)、補助金の取扱いを変えないこととすべきであり、その明確化を図るべきである。また、地方債については、地方債の発行により建設した供用中の公共施設について、地方公共団体から民間事業者に対する貸付等の手法により事業主体を変更する場合、当該施設が低廉な利用料で広く一般住民の直接の利用に供されるか否か等を総合的に勘案し、地方公共団体が自ら事業主体となる場合と同様の公共性を有するものについては、地方債の繰上償還を要しない旨を地方公共団体に対して周知すべきである。(別紙に総務省・財務省の意見掲載)
3)上水道事業の民間経営の推進【平成14年度中に検討・措置】
上水道事業1,873事業は、地方公共団体が実施しているが、うち利用者5万人以下の水道事業者が1,000以上となっており、約96%の供給体制が整備されている中、広域化・外部委託等による運営面の効率化が求められている。このためには、まず地方公共団体による上水道の運営事業について、可能な場合には、地方公共団体の判断により、出来るだけ民間事業者への譲渡等による民営化を図るべきである。その際より多くの多様な経営主体を参入させるためにも、水道法上の水道事業者は、「設備の所有を要件とされていない」ことについて、直ちに周知徹底を図るべきである。
平成13年の水道法改正(平成14年4月施行)により、技術上の業務を民間委託することが可能となったが、一層の効率化を図るためには、民間事業者に対して、料金設定への関与等を含めた包括的な委託を推進すべきである。
4)下水道事業の包括的民間委託の推進【平成14年度中に検討・措置】
現在においても、浄化槽法に基づき民間事業者が下水道法上の下水道と同様の排水等の処理施設を設置・運営することは可能である。また、現行下水道法の下でも、悪質下水の排除規制や排水区域内の下水道の利用義務付けなど公権力の行使以外のものについては、その相当部分が既に民間事業者に委託されているが、民間事業者の創意工夫をいかし事業の効率化を進めるためには、設備の維持修繕や料金設定への関与等も含めた包括的な委託を推進すべきであり、そのための環境整備及びその周知徹底を行うべきである。これらにより、事業形態の類似した上下水道の一体的運営等による事業の効率化も期待される。