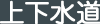平成15年2月13日
各厚生労働大臣認可 担当者 様
水道用水供給事業者
現在、多くの市町村において市町村合併に係る検討が進められているが、水道事業管理体制強化の観点から、 市町村合併と併せる等して、速やかに水道事業の統合(経営のみの統合も含む。)を行うことが望ましいものである。 市町村合併が行われる際の水道法(昭和32年法律第177号。以下、「法」という)第6条第1項に基づく水道事業 経営に係る認可の取り扱いは下記のとおりであるので、御了知されたい。
1.市町村合併に伴う水道事業の認可及び統合について
市町村合併に伴う水道事業統合に係る具体的な手続きについては、以下の2通りの方法があるので、地域の実情等に応じ、
適切な方法を選択されたい。
(1) 市町村合併に併せて、新規水道事業認可を受ける方法
合併に係る市町村が経営する水道事業体(以下、「被合併事業体」という。)が、合併前に法第11条第1項に規定
する水道事業廃止許可を得た上で、市町村合併に併せて法第6条第1項に規定する新規事業認可を受けることにより事業統合を行う方法。
この場合、当該認可に係る審査については、以下のとおり行うこととするので御了知されたい。
(1)事業計画書関係
ア)給水区域、給水人口及び給水量(法第7条第4項第1号)
給水区域については、被合併事業体の給水区域を併せたものとすること。
給水人口及び給水量については、被合併事業体の事業計画書に記載された各年度毎の給水人口、
給水量を単純に足し併せたもので差し支えない。
イ)給水人口及び給水量の算出根拠(法第7条第4項第4号)
ア)で述べた方法で算出した旨を、簡潔に記述することで差し支えない。
ウ)工事費の算出根拠、借入金の償還方法(規則第2条第1号及び第2号)
「被合併事業体の既認可申請書に添付した工事費の算出根拠及び借入金の償還方法の通り」
である旨を記述するのみで差し支えない。各被合併事業体の既認可計画に係る申請年月日及
び認可年月日をそれぞれ記入すること。
(2)工事設計書関係
ア)主要な水利計算、主要な構造計算(規則第4条第1号及び第2号)
「被合併事業体の既認可申請書に添付した水利計算書及び構造計算書の通り」である旨を記述するのみで差し支えない。
各被合併事業体の既認可計画に係る申請年月日及び認可年月日をそれぞれ記入すること。
なお、水道法施行規則第1条の2第2項第1号の規定により、認可申請に必要な書類を簡素化しているので御留意されたい。
おって、市町村合併に併せ、法第10条に規定する変更認可要件に該当する事業変更を伴う場合は、当然、通常の認可審査
を行うことになるので御留意されたい。
(2) 事業の全部譲り受けを行う方法
法第10条第1項第2号に規定する事業の全部譲り受けの届出及び法第7条第3項に規定する記載事項変更届(法人の名称等の変更)
を行うことにより事業統合を行う方法。
2.水道用水供給事業の給水対象が市町村合併した場合について
水道用水供給事業の給水対象である水道事業者が給水対象ではない水道事業者と市町村合併を行うことは、
当該水道用水供給事業に係る「給水対象の増加」に該当しないものであること。
従って、当該水道用水供給事業者について、法第30条第1項柱書に規定する水道用水供給事業の変更要件
のいずれにも該当しない場合、変更認可は必要ないものであること。
3.当課への連絡について
市町村合併に伴い、水道事業経営に係る新規厚生労働大臣認可、水道事業の譲り受けに係る対厚生労働大臣届出等が必要となる場合、
当該水道事業の担当者は、市町村合併の時期及び形態並びに水道事業統合の形態等について、可能な限り早期に十分な時間的余裕を
もって当課に連絡するようにされたい。
厚生労働省健康局水道課技術係
電話 (代表)03-5253-1111(内線4028、4029)