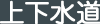|
多少古い書であるが石橋多聞著「上水道の事故と対策」(昭和52年)の内容の一部を要約し紹介する。
水道関連の事故に関する基本的事項が記述されているので参考としてください。
1.事故の誘発要因
○各種の無理
あらゆることに関して無理は事故のもととなるが、個々では予算、工期、工事方法、維持管理の点について強調したい。
○技術軽視
欧米の水道企業体では、技術者が企業体の長となっており、運営の基本的考え方は技術を中心としているのが一般的である。
我が国では公営企業法の施行以来、以前の技術的運営が経営的運営に取って替わられる傾向を生じた。このためにややもする
と料金値上げの遅延などに起因する経営悪化などを理由として、技術上の無理を強いる傾向が強い。工事費の節減が求められたり、
当然行うべき技術上の措置がないがしろにされる等の例は枚挙に暇がないくらいである。例えば、鉄管の防食対策として当然行う
べきpH調整の如きは、pH値が低くても水質基準に違反しているわけではないのだから、そのための多額の出費は認めないなど
の理由で一蹴されている例が多いようである。
技術を経営上の要請に合わせるのではなく、経営を技術上の要請に合わせるのが至当であって、欧米の水道と我が国の水道とでは、
この点に関する理念にかなりの開きが認められる。
○組織、機構の不協和
○職員の士気
○政治の介入
○資材の工事業者の選択
2.事故の防止対策
○予備システム
施設に予備を設けて、事故の際に直ちに切り替えを図るとか、平常時にも予備を設けることにより点検、補修が十分にできるようにする。
○冗長システム
冗長システムは、安全確保のために、設備に無駄な能力を故意に付与するやり方である。無駄な能力は平常時には過大投資とみなされる
が、非常時にその威力を発揮して、これがなかったら事故につながるものを救済してくれるのである。わが国の水道は今まで、余りに
ゆとりのない施設をつくりすぎたきらいがある。財源等に余裕がなかったという理由もあろうが、水道の安全性の根本理念に置いて
誤っていたといえる。今後あらゆる施設について、安全性向上のための十分な余裕をとった設計を行うべきである。
○点検と確認のシステム
点検と確認は事故防止の大原則である。例えば配管系での水圧試験は完全な管布設の確認の実証となるものである。点検と確認を
システムとして取り上げることが大切で、内規を定めるとか、チェック事項を列挙した検査成績表を提出させて確認するとかして、
担当する個人が自分の判断でこっそり処理する余地をなくするシステムを作っておく必要がある。
◆水質の事例◆
(1)水源に海水が混入
防潮の可動門扉のいたずらにより海水が侵入し、市民からの水道水が塩からいとの苦情が相次いだ例。過去にも2度いたずらされた
ことがありながら施錠がなされていなかった。事故後バリケード、施錠等の措置を実施。(昭和25年・北海道)
防潮堰の操作ミスと大潮と渇水による河川流量減少とが相まって、取水地点まで塩水の遡上があり、市民の苦情で発覚した例。
取水口に塩分濃度測定による警報機を取り付ける対策が施された。(江戸川)
(2)水道水にユスリカが混入
水道水にミミズのような形の小さな得体の知れぬ虫が入っているとの苦情により発覚。塩素注入量を末端で1.0~1.5mg/lまで増量したが
改善しなかった。水源は深井戸4本であったが、着水井の開口部からユスリカが卵を産み付け、未孵化のものが配水管に流出した例。(昭和42年)
(3)給水栓からミミズが出た
倉庫に引き込まれた給水管末端が側溝に水没、給水圧の不良地区であったことも重なり、孔のあいたこの給水管よりミミズが侵入、
この付近では多量使用者であった理髪店からミミズが出た例。
(4)茂原下痢症
水田から集水埋きょに汚水が流入、塩素注入機の故障と相まって、ウィルス性下痢症が集団発生(7191名)した例。
(千葉県茂原市・昭和28年)
(5)宝塚市における斑状歯
六甲山の花崗岩質の山を背後に控え、そこからの流出水・地下水にはフッ素が含まれている。宝塚市の水道は武庫川の表流水、
深井戸1本と浅井戸9本を水源としており、フッ素濃度が0.4~2mg/l程度となっていた。水源切り替え、混合希釈、
電解式のフッ素除去装置により対処した例。
(参考)最高裁判例(高濃度のフッ素を含む水道水の飲用により歯が褐色になる斑状歯に罹患したとしてされた損害賠償請求について、
昭和33年施行の厚生省令に基づく基準値0.8ppmを超えるフッ素含有の水道水を右施行時の前後にわたり昭和46年まで給水し続けたこと
に過失はないとして、市に民法709条、国家賠償法2条に基づく損害賠償責任が認められなかった例・平成5年12月)
出典:行政判例集成(法務省)
◆クロスコネクションの事例◆
クロスコネクションとは、飲用適の水を供給している水道と飲用に対する安全性に疑いのある他の系統の水道との間において、
管などが物理的に連結されていることをいう。広義に用いられる場合には、施設間の直接の連結を指す以外に、給水器具と汚染源
との間に間隙がないか、間隙があっても小さいために、配水管内の負圧発生時に汚水を逆に吸引し得るような配管をも指している。
給水栓の吐口と、水の溜まる器の溢れ縁との間に安全空間が十分でないと逆流吸引を起こすことがあり、このような汚水吸引
(風呂おけの縁より下側に給水栓の吐口があり、他の場所での水の大量使用により、風呂系統の負圧発生、汚水吸引というような例)
をもクロスコネクションと呼んでいる。
(1)工業用水道の配水管との誤接
付近40世帯に給水している配水管が上水道管と平行して布設されている工業用水道の配水管と誤接されていた例。横浜市戸塚区
秋葉幼稚園での赤痢集団発生(83人)で発覚。(横浜市・昭和44年6月)
(2)海水水道管との誤接
海水供給の消火専用水道との誤接の例。付近住民から水道水が塩辛いとの苦情で発覚。(昭和36年)
(3)給水栓水が燃える
工場内のプロパンガスタンクのガス漏れ検査用の充水のため水道の給水管が接続されていた。工場側から同系統で給水される
寮があり、寮の炊事場で蛇口を開いたところガスコンロの火が蛇口に移り火を噴き出した、水道水が燃え上がった例。工場側の
操作ミスで、水圧低下していた配水管にプロパンガスが侵入、ガス混じりの水が出たもの。(昭和24年)
ガス洗浄装置に直結された配水管にプロパンガスが侵入した例。水道水が臭いという騒ぎで発覚。(福島県・昭和45年6月)
(4)工場でのクロスコネクション
道路拡張工事で配水管を切断した際、需要者側に熱湯が噴出した例。冷却槽内に水道給水管が直圧で挿入され、ハイウォーター
レベルより下方に開口していた、もぐり業者の施工不良による。(昭和40年)
洗浄循環システムに水道の直圧管が挿入され、洗浄タンクの水が逆流した例。(昭和44年)
工場内の水質の悪い自家用水道と水道管が連結され、仕切弁による両者をいずれかを供給するようになされた工事が不適正で
あって水道水が汚染された例。(昭和48年5月)
自家用工業用水の高架タンクと上水道の高架タンクが一体構造になっていて、溢流、腐食による仕切壁の破損によるクロスコ
ネクションを起こした例。
(5)大阪市でのクロスコネクション例
・低温の水道水が出るとの苦情、付近の映画館の冷房用井水と水道管を連絡し弁操作を誤ったため。
・塩辛い水が出るという苦情。屋上タンクでの井水と水道水の量計の連絡用弁の老朽化のため。
・製鋼工場が木津川水を用水中に弁操作を誤り、大量の河水を水道管に圧入した。
・大病院で虫状の異物が水道水に出るとの苦情。屋上と5階天井裏の2カ所で水道管と雑用水管が連結されていた。
・冷水が出るとの苦情。付近の印刷工場で井水と水道水が連結、逆支弁の不調で逆流を生じた。
・水が苦いとの苦情。付近の魚屋で井水と水道が連結されていて、鉄バクテリアが水道管に逆流していたため。
(6)間接的なクロスコネクション
自衛隊基地の給水装置に石油臭い水が出るとの苦情で発覚。給水管は油タンクの近くを通って布設されており、油タンクが漏油して、
同時に給水管の方にも漏水箇所が発見、給水栓を大きく開くと油を含んだ地下水が吸引された例。
染色工場から下水道への強酸性水の排水が、下水管に穴があき、下水管の下を石綿セメント管の給水管が交差、給水管にも穴があき、
染色排水が配水管の法に逆流していた例。メッキ工場での同様の例。
水道水がガソリン臭いとの苦情で発覚。ガソリンタンクに接して布設されていたポリエチレン製管にガソリンが浸透し水に臭気を
与えたものと推定された例。
(7)各種のクロスコネクションの危険性
神社仏閣のお手洗いの石槽では、底部から水を噴出させるものが多かった。ビルの靴洗い用の水洗は鉄製ボックスの中に設けられ、
汚れた水に水没するものがある。
ゴムホースを給水栓に取り付け、その先端を汚水内に漬ける使用者の不注意による汚水吸引の例。メッキ工場におけるメッキ
液が配水管に逆流した例。簡易水道でし尿溜の希釈用水にゴムホースを延長して注水し、たまたま断水を生じて汚物を吸引し、
排水された水がし尿臭を帯びた事例。 |