平成15年度観光の状況に関する年次報告
第2章 観光立国、この1年の動き
第3節 観光立国に向けた地域の動き
1 外客誘致に動き出した地方
我が国の観光地のほとんどはもっぱら日本人観光客をターゲットにこれまでPR,環境整備してきたと思われるが,近年外国人客の誘致を積極的に行い始めている地域がみられる。そこで,ここでは先進的な取り組みとして,関西国際観光推進センター,長崎県における「キリシタン紀行」の取組みを取り上げ紹介するとともに,15年度に実施されたビジット・ジャパン・キャンペーンの地方連携事業の主なもの,さらにはボランティアで外国人旅行者の案内をする活動を紹介する。
| (1) 地方ブロックレベルの組織的な動き ~関西国際観光推進センターの例~ |
平成15年12月1日,関西の2府7県3政令市,6経済団体,関西広域連携協議会が発起人となって,官民が連携協力しながら関西エリアへの外国人観光客誘致を強力に推進する組織「関西国際観光推進センター」が設立された。本センターは,11名の事務局常駐職員(うち6名は事務局の母体である関西広域連携協議会と兼務)を置き,1)関西地域への外国人観光客誘致に資するマーケティング調査事業,2)広域的な外国人観光客誘致推進プログラムの企画,立案,調整,提案及び運営に関する事業等を行っている。
そして設立直後より,平成16年4月のフランス発プレスツアー(テレビ,新聞等の招請旅行)実施に向けた準備作業,「国際ロータリー2004年国際大会(関西)」(平成16年5月)に向けた関西圏の広域マップの作成作業等を行ってきており,また,平成16年度には以下に掲げるようにビジット・ジャパン・キャンペーン連携事業をはじめ各種事業が予定されている。
本センターは,このような常駐職員を置いた形での広域的,中核的な外客誘致のための組織としては先駆けであり,今後の活動が期待されるところである。
平成16年度事業計画について
世界的な大交流時代の到来を目前にして,関西への訪日誘客プログラム戦略具体化に着手し,「関西ブランド」の発信,世界に誇り得る産業・文化観光中枢圏域の形成に向け,取り組みを推進する。
1.提案事業・自前事業の推進
・自治体や諸団体が行う事業と密接に連繋し,各地の魅力を結ぶ「エリア観光」「テーマ観光」「推奨ツアー」等の企画開発を推進
・ファムトリップやミッションツアー,イベント開催等の効率的,重点的な実行を果たすための時期,目的地,内容等の企画立案,調整,現地活動を推進
・重点プロモーション地域を抽出し,効果的PR手法への提案活動等を推進
・観光インフラ・ホスピタリティ改善へ具体的提案活動を推進
2.国と連携共同して行うビジット・ジャパン・キャンペーン(VJC)への参画
・訪日者のニーズを満たす広域的な観光資源の開発,企画連携へVJC事業への積極的な参画貢献
3.マーケットリサーチの実施
上記の提案事業等を的確に行うため,訪日客のニーズや魅力をリサーチ
・海外トラベルエージェント,民族系ランドオペレーター,訪日客等に対しリサーチを実施
・在阪外資系企業,邦人海外事務所等に対しリサーチを実施
4.観光情報の発信・PRの強化
「関西ブランド」を形成するため,魅力的な観光資源を織り込んだ情報発信を推進
・重点マーケティング地区への印刷物や現地メディア活用により情報発信
※スポンサーの募集,協賛事業などを検討
・ランドオペレーターや海外トラベルエージェント,外資系企業,訪日客,JNTO事務所等との2ウェイコミュニケーションチャネルを構築し,情報交換を推進
・インターネット情報サイトを活用しe-メールニュース等により定期情報として「関西」発信
・自治体,観光団体,事業者等に対し,寄せられた要望,意見等をフィードバック,提供情報更新や個客受け入れ体制整備に関する情報を発信
関西国際観光推進センター設立総会
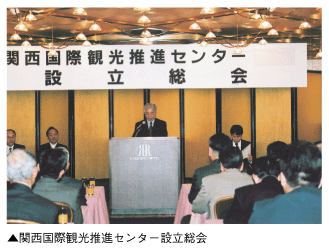
| (2) 都道府県,市町村が一体となった外客誘致の取組み ~長崎県「キリシタン紀行」~ |
都道府県,市町村が連携して外客誘致に取組んでいる例として,長崎県の「キリシタン紀行」を取り上げる。
長崎県は,江戸時代のキリスト教の禁教・弾圧の下に,多くの信者が棄教せず殉教し,一方で隠れキリシタンとして信仰が地下に潜った歴史がある。また,太平洋戦争の末期に原爆投下などにより多くの教会が破壊され,多数の信者が殉教した経験も残っている。
さらに,このような歴史に加え,県内に点在する教会建築の数々にも目を見張るものがある。現在,長崎の教会群を世界遺産登録しようという動きも市民レベルで進行している。
長崎県及び長崎県観光連盟は,秋田・田沢湖の「涙を流すマリア像」に韓国から多くのカトリック信者が訪れるようになったことにヒントを得て,世界中のカトリック信者が訪れる素地が長崎の殉教の歴史には十分にあると判断し,国土交通省九州運輸局と共同で,平成14年度「観光まちづくりプログラム推進事業」を実施し,関係者と協議・調整の上,「新キリシタン紀行」のモデルルートを5本策定した。
ルートの形成に当たっては,協力的なカトリック教会の選定,調整が何よりも重要だったとのことである。
巡礼受入れという考え方から,また長崎における迫害・殉教の歴史をもっと世界中の信者に知ってもらいたいという意識があり,カトリック教会の協力は多数得られたが,一方で教会は信仰の場であるため,教会に土足で上がったりミサを邪魔することのないようツアー客に徹底することが条件となった。その結果,考案されたモデルルートには,教会や遺構の見学を軸に,教会においてミサに参加したり講話を聞いたり,通常は公開されていない教会の内部や保存物等を特別に公開する等のソフトが組み合わされ魅力的なものとなった。
長崎県観光連盟は,当初からこのキリシタン紀行は,日本人のみならず世界に10億人いると言われるカトリック信者,21億人いると言われるキリスト教信者が巨大なマーケットであると考えており,その第一弾として,カトリック信者が約400万人いると言われる韓国に着目し,韓国の旅行会社とタイアップして巡礼ツアーを企画,平成15年5月に試験的に始めた。以来,韓国ではカトリックの新聞にしばしば取り上げられるようになっている。
巡礼ツアーにおいては,日本のキリシタン文化や殉教の歴史をきちんと説明することが重要である。そこで長崎県観光連盟では3人の韓国人ガイドを養成しているところである。また,平戸市では,シスターをボランティアガイドとして登録する試みがなされている。
このほか,受入れ体制として,平戸市では平成15年度4千万円を投じて,英語,韓国語,中国語(簡体字)を併記した多言語の観光案内標識を設置した。また,熊本県本渡市では宿泊,観光施設関係者を集めて韓国人受入れ研修が行われた。
平戸市の多言語案内標識

海外へのPRや受け入れ体制整備など抱える問題も少なくないが,訪れる信者減少等により手入れが行き届かず倒壊の恐れがあるため,観光収入を修繕費用に充てたい離島の教会もあるという。このように,都道府県,市町村の取組みにおいても,既存の資源を結びつけながら外国人旅行者をもターゲットとする観光地づくりが始まっている。
(キリシタン紀行の主なみどころ)
・平戸/平戸教会(聖フランシスコ・ザビエル記念聖堂):ゴシック様式。ツアー参加者はミサへの参加や神父の講話を聞くことができる。
・平戸/根獅子(ねしこ)地区:現在でも隠れキリシタンのしきたりが残る。ツアー参加者には日曜日限定ながら小学生による殉教の歴史を綴った紙芝居の上演を見ることができる。
・上五島/頭ヶ島(かしらがしま)教会:国指定重文。西日本唯一の石造教会。天井のハンマービーム架構は日本の教会建築では類のない構造とされる。頭ヶ島は幕末まで無人島だったが,明治初期の迫害を逃れた信者が住み着き,教会も信者が島内の石を切り出して10年がかりで積み上げて建築したもの。
・下五島/牢屋の窄(ろうやのさこ)教会:約20m2の部屋に200人の信者が8か月監禁され,42人が殉教したという地に造られた教会。
・長崎/浦上天主堂:東洋最大の聖堂と呼ばれたが原爆で破壊,再建された歴史あり。
・外海(そとめ)町:遠藤周作の「沈黙」のモデルとなった町。遠藤周作文学館もある。
・島原/原城跡:島原の乱の舞台。37,000名が殉教したと伝えられる。現在も発掘作業が進められており,十字架等が出土。出土品は展示されている。
頭ヶ島教会
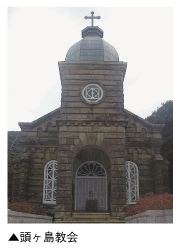
平成15年度より開始したわが国の海外への戦略的PR事業であるビジット・ジャパン・キャンペーンと連携して,各地で多数くの外客誘致促進のための事業が行われている。
以下にその一例を示す。
1)北海道観光ビジネスフォーラム
北海道運輸局,北海道,札幌市及び経済団体,民間企業,NPO法人等で構成する北海道観光ビジネスフォーラム推進会は,平成15年11月28日~29日にかけて,台湾,香港の旅行業者を招請し,旅行商品造成を促すプレゼンテーションと商談会,ブース展示からなる「北海道観光ビジネスフォーラム」を開催した。なお,このフォーラムの前後に道内各地を巡る招請ツアーを実施している。この結果,台湾の旅行会社25社が新たに日本向けツアーを3,296本,105,940人の集客を,香港の旅行会社16社が新たに日本向けツアーを2,087本,66,490人の集客を予定している。
賑わう「北海道ビジネスフォーラム」ブース会場

2)「YOKOSO ! JAPAN THE 祭り 東北」イベントを開催
東北の行政機関,経済団体,観光関連(観光・宿泊施設・交通)団体等で構成する「YOKOSO ! JAPAN 東北」実行委員会は,平成16年2月16日の山形市での「国際シンポジウム」とその前に東北の冬祭り等の観光資源を視察する「YOKOSO ! JAPAN THE 祭り 東北」を実施した(2月12日~17日)。国際シンポジウムは,東北の魅力に関するプレゼンテーションとシンポジウム,交流商談会等で構成され,ビジット・ジャパン・キャンペーンの5大市場(韓国,台湾,米国,中国,香港)からマスコミ及び旅行業者のキーパーソン47名を招請して行われた。5大市場に東北の冬の観光資源をアピールすることができた。
東北の祭を実演
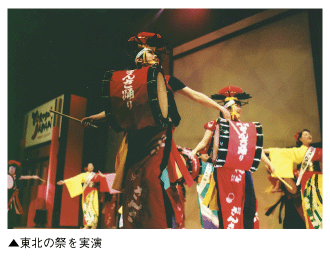
3)「ようこそ!!自然のワンダーランド・富士へ」誘客キャンペーン事業の実施
神奈川県,山梨県,静岡県で構成する富士箱根伊豆国際観光テーマ地区推進協議会は,平成15年12月から16年2月にかけて台湾をターゲットに同テーマ地区の魅力を知ってもらうために戦略的かつ効果的なキャンペーンを展開した。第1弾として旅行エージェントによる周辺視察と各地における商品造成に向けた商談会の実施,第2弾として,メディア(新聞・雑誌)の取材ツアーを行い,第3弾としてさらに興味を深めるためにTV関係者による番組制作を行った。段階的に周知することで現地での認知度及び魅力度アップを行い,集客に努めた。結果として新聞記事掲載やテレビ番組が放映がなされ,広告換算で1億5,000万円を超える効果があった。
富士箱根伊豆国際観光テーマ地区を取材する台湾メディア
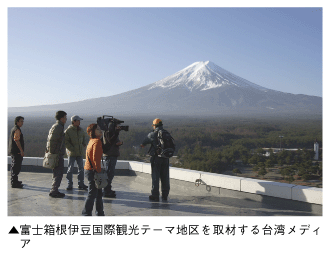
4)北陸SOLO(韓国語版)作成事業
北陸3県(富山県・石川県・福井県)への観光客の誘致のため,北陸3県の観光地の写真を多数収録した観光ガイドブックの韓国語版を3,000部作成し,JNTOソウル事務所,航空会社ソウル支店,韓国の旅行業者,北陸3県内の空港・観光案内所等で配布した。
(“北陸SOLO"とは「このガイドブックがあれば北陸3県を一人歩き(SOLO)でも観光ができるように」ということで名付けられている。)
5)オリベ2003 in NY事業
岐阜県は平成15年10月,ニューヨーク市メトロポリタン美術館で「織部・アメリカ展」「記念茶会」を,またグランドセントラル駅で「クラフト展」「観光展」を行ったが,これと連動させて,岐阜県等と共同で日本において「オリベエージェント招聘ツアー」を行い,またニューヨークで旅行業者等を招いた「観光セミナー・交流会」を開催するとともに,新聞広告事業を実施した。成果として,オリベに関する新たなツアーが5本造成されており,また広告費換算で米国分2,100万円,日本国内分1億3,200万円の広報効果があった。
オリベ2003in NY の会場風景
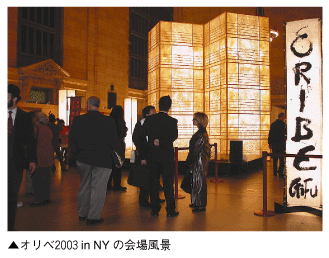
6)「ラッセル・クーツと紀州・瀬戸の海」事業
この事業は,アメリカズカップに3連覇した経験を持つ世界のトッププロセーラー,ラッセル・クーツ氏に紀州(和歌山県)・瀬戸内海沿岸地域をクルージングしてもらい,その様子や各地の観光資源を映像や著書にまとめてもらうもので,和歌山県,及び民間企業で構成される実行委員会が主催した。
ラッセル・クーツDVD ジャケット
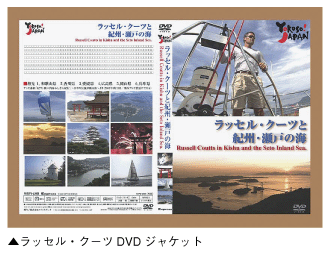
7)瀬戸内海番組制作事業
(株)中国放送が韓国の放送局「韓国テグMBC」と共同で瀬戸内海の海の歴史と文化のこもった食べ物,見所,体験物をロードドキュメンタリー形式でテレビ番組を制作する事業を,地方自治体等が支援した。番組は,韓国演歌界の「皇太子」パク・サンチョルとミス大邱(テグ)のソ・ヘジンをレポーターに迎え,かつて江戸時代に朝鮮国王から江戸幕府の将軍に向けて送られた朝鮮通信使の瀬戸内海での足跡を追う内容で,この地方に残る韓国にゆかりのある伝統文化や現在の観光魅力を韓国国民に広くアピールした。韓国の放送局でゴールデンタイム(19:20~20:15)に当初1回完結予定が前・後編の2回に分けて2週連続で放映され,約200万世帯で番組が見られた。
瀬戸内海番組制作事業で宮島を取材
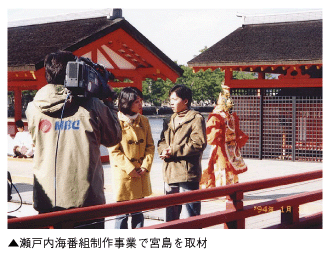
8)日韓親善さぬきうどん手打ち教室2003
平成15年11月14日,韓国ソウルの料理学校で,さぬきうどんの手打ち教室を開催した。併せて香川県の韓国語版観光パンフレットを作成・配布するとともに,韓国マスコミに,手打ちうどん教室をアピールした。結果として,手打ちうどん教室には一般から73名ご参加いただき,マスコミからも10数名の参加を得ることができた。また,新聞・雑誌7紙誌で取り上げられた。
マスコミ取材もあった日韓親善さぬきうどん手打ち教室2003
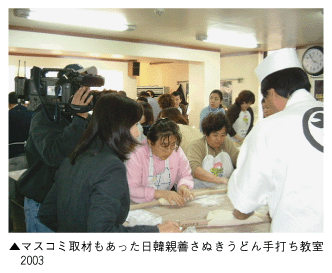
9)北京市,上海市,広東省からの修学旅行誘致事業
九州を修学旅行のデスティネーションとして認知してもらうため,平成15年11月から12月にかけて,北京市,上海市,広東省の教育関係者及び旅行業者を招請し,自然景観や観光施設等の見学,日本側教育関係者との交流会等を行った。その結果,その後北京市から140名の修学旅行生を受け入れたほか,九州への修学旅行はこれまで実績がなかった上海市から60名,深セン市から160名の修学旅行生を受け入れた。また,今後深センから350名以上の修学旅行生の訪日が予定されている。
北京市から教育関係者や旅行関係者を招聘

10)韓国語版ゴルフ場ガイドブック作成事業
韓国のゴルフ人口は年々急増し,ゴルフ場が足りない上,特に冬場は気候的なことから韓国ではゴルフができず,東南アジアはじめ海外へ出かける韓国人ゴルファーは少なくない。このような韓国人ゴルファーを誘致するため,沖縄県内のゴルフ場を紹介したガイドブックを3,000部作成・配布した。
沖縄のゴルフ場を紹介する韓国語版ガイドブック

| (4) 外国人旅行者受入れを支えるボランティア活動 |
ここまで各地の外国人旅行者受入れに関する動きを記述してきたが,このような活動もつぶさに見れば個人と個人の国際交流の積み重ねであり,外国人との草の根的な交流を行っておられる方々によって支えられて成り立っている。そこでここでは,外国人を暖かく迎え入れておられる方々の一例として,首都圏SGGクラブを紹介する。
東京オリンピックが開催された昭和39年,国際観光振興会(現・国際観光振興機構)は,街頭や車中等で言葉が通じず困っている外国人旅行者を見かけたら,積極的に声を掛けて助けましょうという,小さな親切運動として「善意通訳普及運動」を開始した。そして昭和57年には,個人での小さな親切運動では満足しない熱心な善意通訳の方々が集まってSGG(Systematized Goodwill Guide)クラブの組織づくりが始まった。
そうした中,「首都圏SGGクラブ」は昭和58年,東京・神奈川・千葉在住の善意通訳35名で結成された。このクラブはまず,国際観光振興機構の東京ツーリスト・インフォメーション・センター(東京TIC・有楽町)での援助活動等を開始した。そして昭和60年4月には台東区から浅草文化観光センターに来る外国人観光客にガイドをして欲しいとの要請があり,同年5月から同センターに本部を置いて新たな活動を開始した。その後,活動拠点は広がり,現在では上野や築地にも拠点を置いて活動を行っている。
現在メンバーは116名(男性43名,女性73名)となり,男性は退職者,女性は主婦の方が多いが,OLの方などもおり,年齢には幅がある。英語が出来る人が90%であり,基本的に英語で対応しているが,その他フランス語,中国語,韓国語,スペイン語に対応できる方々もいる。仕組みとしては,4カ所の活動場所の割り当て表を作り,1カ所あたり2名づつ午前と午後のシフト制をとっており,平成15年には,浅草で15,000名,東京TICで4,600名,築地で2,300名,上野下町風俗資料館で1,700名等,年間で2万数千名の外国人旅行者に観光情報の提供や,部分的に同行案内を行っている。
活動費は,メンバーから集める会費が主である。また,案内する外国人からは,移動の際の交通費以外は,チップ等も含め一切貰わないことを徹底しているという。
こうしたSGGクラブの活動を行っていることに,メンバーの大矢さんは,国籍・年齢・関心事など多彩な外国人観光客の要望に応え,満足度を上げるためどうしたらいいのかいつも腐心されているという。問われて初めて気が付く事柄も多く,狭いながらも奥深い日本を痛感させられることもあるとのこと。多彩な来訪客を相手にして各々のお国柄が偲ばれるのが楽しみのひとつでもあると言われている。
活躍する首都圏SGG クラブ
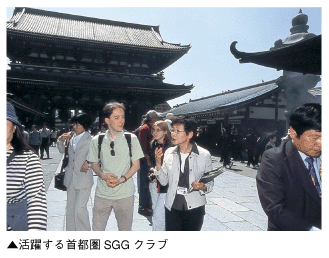
また定森さんは,これまで外国を旅行したときに見知らぬ人から受けた,今でも忘れることの出来ないさりげない小さな親切がいかに旅をほのぼのとした,いい旅にしてくれたかを心の片隅に心がけて活動してきたし,これからも続けていきたいとのこと。外国人に喜ばれると本当に嬉しいと言われている。
|
|