平成15年度観光の状況に関する年次報告
第2章 観光立国、この1年の動き
第3節 観光立国に向けた地域の動き
2 観光魅力を高める取組み
観光立国を推進するに当たっては日本の魅力の確立が必要であるが,魅力ある日本とは全国各地が地域固有の魅力に磨きをかけ,それぞれが色とりどりに様々な光を放っている姿に他ならない。したがって,日本の魅力づくりの主体は,地域に住み地域を愛する人々である。
そして,近年,そのような方々を中心に,地域の観光魅力を高める動きが各地で見られるようになってきた。その取り組みのいくつかを紹介する。
従来型の個性のない観光地が低迷しがちである中,各観光地の魅力を高めるためには,観光振興を成功に導いた方々のたぐいまれな努力に学ぶことが極めて効果が高いと考えられる。そこで,内閣府,国土交通省,農林水産省は,そのような先達ともいえる方々を「観光カリスマ」として選定し,ホームページで紹介する事業を平成14年度から始めている。
ここでは,観光カリスマをその事績内容に応じて「温泉,宿泊」「歴史的空間」「イベント」「新しい観光資源」「国際交流・外客受入」「グリーンツーリズム」という6つのカテゴリーに分類し,それぞれのカテゴリーから一名ずつのカリスマを取り上げ,その活動等を紹介する。
1)佐藤和志さん(秋田県田沢湖町):温泉,宿泊
秋田県田沢湖町にある乳頭温泉郷。秋田新幹線の田沢湖駅から車で30分以上かけてようやくたどり着く山奥の温泉であるが,今やその名を全国に轟かせている有名温泉地となっている。
中でも代表的な存在である「鶴の湯」は,「日本人の心の風景」のイメージ通りに自然林の中に木造建築が佇んでおり,露天風呂は夏の緑,秋の紅葉,冬の雪景色とも調和して幻想的なムードさえ醸し出している。
今でこそ年間13万人もの観光客が訪れる鶴の湯であるが,元はといえば地元の人もあまり訪れないさびれた湯治場に過ぎなかった。そんな鶴の湯の今を創ったのが佐藤さんである。
佐藤さんが鶴の湯の経営を引き継いだとき,宿には電気も電話もなく,建物の老朽化も進んでいた。佐藤さんはまず,中古のブルドーザーを購入し,県道から3.5キロメートルも続く狭い未舗装の町道を自ら拡幅することから始めた。次に,建設重機を導入して駐車場や露天風呂を整備し,さらに今では鶴の湯のシンボルにもなっている水車を導入して水力発電を開始した。
こうした利便性向上の取組みをする一方で,昔ながらの本館の建物については,老朽化対策の補修工事を施したものの,鉄筋コンクリートで建て替えるようなことはしなかった。わざわざ山奥まで来てくれる客は,山奥にしかないものを求めるのだから,昔ながらの建物を取り壊すのは客に対する裏切りであるという考え方である。ただ,トイレは水洗のものに再整備し,電気も電話も引いて,極端な不便さを感じさせない取組みは行った。田舎のリアリティを残しつつ,日本人の現代生活のレベルからは外れない。佐藤さんは,「日本人にとって,普通の生活の中で,自分の家をきれいにして「人」を迎えることが,おもてなしであった」と言い,単に豪華な建物を競い合う大温泉地に疑問を投げかけている。
今では,雪が5m以上積もる冬季にも営業を行っているが,自分で除雪車を購入し道路の除雪を行っている。佐藤さんは,「まずやるべきことは誰にも頼らず自らが先頭になって始めていく必要がある,具体的な行動を自分たちで始められるかどうかが重要である」と言う。
最近では,韓国や台湾を中心に外国人旅行者が年間約200人も鶴の湯を訪れるようになった。特に積極的なPRをしているわけではなく,外国語のホームページも開設していないが,交通が決して便利とは言えない鶴の湯をわざわざ訪れるのは,外国人が求めている本当の日本の素顔が鶴の湯のような田舎の風景にあることの証左とも言える。
しかしながら佐藤さんは,鶴の湯を訪れる外国人が増えていくとしても英語を話すつもりはないと言う。「田舎の宿の主人が英語を話してしまうと,田舎のリアリティが失われてしまうから」。そこにも佐藤さんのこだわりが感じられる。
乳頭温泉郷の「鶴の湯」
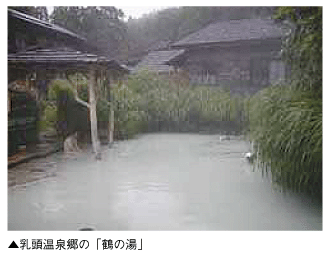
2)坂本勲生さん(和歌山県本宮町):歴史的空間
修験道の拠点吉野からさらに南に位置する熊野三山は,古くから神々の住む聖地として崇められ,その熊野三山への厳しい道を乗り越えて詣でることで来世の幸せを神々に託す信仰が生まれた。これが熊野詣であり,その参詣の道,熊野古道は平安時代から歩き継がれ,やがて庶民の参詣も盛んになり,かつては「蟻の熊野詣」とまで言われたほどおびただしい人々が行き来した。その古道が今再び蘇り,日本を代表する歴史の道として多くの人々が訪れるようになった。熊野三山の一つ熊野本宮大社を有する本宮町は,熊野信仰の中核地と言えるが,そこを訪れる人々に熊野古道の歴史と魅力を案内するのが「本宮町語り部の会」であり,その会長が坂本さんである。
坂本さんは,小・中学校の教員時代から本宮町の歴史に造詣が深く,時折熊野古道のガイドを買って出るなどしていた。そして学校を退職した後,平成2年に語り部の会に入り,平成10年に会長となった。
坂本さんは,熊野古道を訪れる人々にその歴史を知ってもらいたいと常々思っていたそうである。熊野古道は単なる移動の道ではなく,平安時代からの歴史が蓄積されている魅力ある信仰道でもある。その歴史に触れてこそ,ハイキングの楽しみが倍増する。そんな坂本さんの思いは,人々のニーズにも合致していた。平成11年の南紀熊野体験博の際に多くの人々がこの地を訪れ,語り部の会に対する要請は引きもきらず,その後も,テレビドラマの放映も手伝って熊野古道の来訪者は増加の一途をたどり(数字でみると,ハイキング等を目的とする熊野本宮温泉郷への訪問者数は,1.9万人(平成10年)から6.2万人(14年)へと増加),語り部の会も一躍全国的に脚光を浴びることとなった。
坂本さんは,自ら語り部として奔走する傍ら,説明内容を充実させるべく古い文献を調査し,冊子にまとめたり,同時に来訪客の増加とともに語り部の養成が急務であると感じ語り部の会会員の研修を積極的に行い,新人語り部の養成と会員のレベル向上に努めている。
熊野古道での語り部研修(小雲取越)
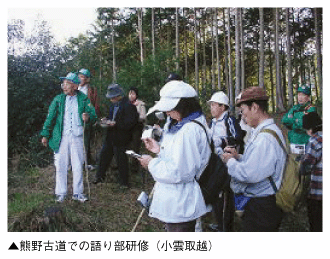
「紀伊山地の霊場と参詣道」は,平成16年の世界遺産登録に向け推薦され,世界遺産になるとますます観光客が増加し,語り部のニーズ,役割が大きくなる。坂本さんは,フィールドワークとする熊野信仰の中核地である本宮町において,熊野古道を訪れる人々に対して町民すべてが語り部となり,おもてなしの心でお迎えする必要があると考えている。「町民すべてが語り部」を夢見て今日もガイド,研修,調査に励んでいる坂本さんである。
3)福島順二さん(富山県八尾町):イベント
老若男女が揃いのはっぴや浴衣姿に編み笠をつけ,三味線や胡弓の音にあわせて唄い踊り,流し歩く。哀愁と優雅さとを併せ持つ祭りである「越中おわら風の盆」。毎年9月1~3日に開催され,この3日間に年間25万人もの観光客が全国から押し寄せる一大イベントである。
しかしながら,おわら風の盆以外にこれといった観光資源もなかったことから,その時以外は八尾町の中心市街地を通る人は少なく,活性化が課題となっていた。家業の酒屋を営んでいた福島さんは,おわら風の盆の持っている独特の雰囲気を町の活性化の起爆剤にしようと考え,通年にわたって観光客がおわら風の盆を楽しむことができる環境作りを考えた。
保存会をはじめとする町民の反応は当初冷ややかだったが,福島さんは粘り強く説得を続け,地元の観光会館で月2回,定期的におわら風の盆の踊りを披露するイベント「風の盆ステージ」の開催にこぎつけた。それも単に踊りの鑑賞だけでなく,由来の紹介や所作の解説,踊り方教室の組み合わせという内容のものとした。
この結果,観光客はおわら風の盆をいつでも楽しむことができるようになったが,同時に,本物を見せることにこだわった結果,保存会などはかえって稽古を増やすようになり,おわら風の盆という伝統文化の伝承・育成にもつながった。
さらに福島さんは,おわら風の盆はやはり八尾の町並みの中でこそ映えると考え,「月見のおわら」を開催した。9月の本番さながらの「おわら」を開催するものの,旅行会社のツアーに参加した観光客のみを対象とすることにより,混雑を避けてじっくりとおわら風の盆の雰囲気を味わってもらおうというものである。平成10年10月に第1回を開催したが,当初はおわら風の盆の雰囲気を一企業に独占させることへの批判的な声を受けた。福島さんは,混雑を避けて情緒あふれる場を作り堪能してもらう良い機会だとして粘り強く実行し,やがてそれが町民にも少しずつ理解され,当初は町並みからはずれた広場で開催していたものが,5回目からは逆に「本来の町並みの中で実施してほしい」という要請が町民のほうから出るまでになった。
福島さんのアイデアは止まらない。通年観光の一環として,雪に埋もれる冬の時期に観光客を呼ぶためのイベントとして,「風の盆ステージ」にさまざまなサブイベントを交えた「越中八尾冬浪漫」を平成10年から始めた。
風の盆ステージの様子
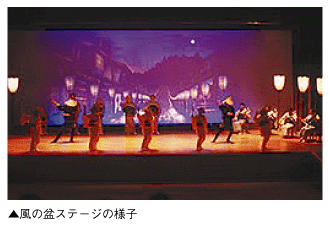
また,重さ4トンの曳山を男衆が曳き回す勇壮な春の祭りである「曳山祭り」の後継者育成と技能の向上を目指す「曳山囃子鑑賞会」も冬のイベントとして定着させている。
こうした福島さんの様々な取り組みもあって,おわら風の盆の観光客数が毎年25万人程度で安定している一方,八尾町への通年の入り込み客数は,平成10年度に34万人であったものが,平成14年度には65万人にまで増加した。おわら風の盆の時期以外に年間を通して観光客が八尾に訪れるようになったことを物語る数字である。
4)若松進一さん(愛媛県双海町):新しい観光資源
「しずむ夕日が立ちどまるまち」愛媛県双海町。町の交流拠点である「ふたみシーサイド公園」では,若いカップルが「夕焼けソフトクリーム」や「じゃこ天」を手に持ち,「恋人岬」と名づけられた突堤の先にある「夕日のモニュメント」の前で記念写真を撮っている。一方「夕日ミュージアム」では,「夕日はなぜ赤いのか」「夕日は何秒でしずむのか」などの素朴な質問に大人たちが頭をひねっている。そして白い砂浜では,季節限定の「夕焼け放送局」を聞きながら,ただ海を眺めている女性がいる。
双海町を演出するソフトクリームからモニュメント,さらには放送局まで,ここにあるほとんどが,若松さんのアイデアと情熱により生まれたものである。
昭和54年から現在に至るまでの25年間,若松さんの「夕日」をコンセプトとしたアイデアと実行は途切れることなく,深まる情熱とともに現在の双海町を作り上げた。そして平成10年に20万人が訪れていた双海町は,5年後には55万人が訪れる町となった。
若松さんのアイデアによる最初のイベントは「夕焼けのプラットホームコンサート」である。沈む夕日をバックに,普段はひっそりとした無人駅JR下灘駅のプラットホームでコンサートを行おうというもので,資金集めからプラットホームの使用で渋るJRの説得まで計り知れない努力のもとに,最後には天気をも味方に付けて成功させた。現在では,このコンサートへ出演を希望するアーティストが絶えないほどの有名なイベントに成長した。
さらに,JRの線路脇の斜面に菜の花を植えようと計画した「花いっぱい運動」。ここでは安全面を理由にJRの許可が下りなかったので,JR側の「野良生え(自然に種が落ち,自然に花が咲くこと)は仕方がない」という言葉をヒントに,エプロンのポケットに穴を開け,そこから種を落としながら歩くという荒業で実行した。現在では,この菜の花とその上を走る列車の風景が,愛媛県の春を告げる象徴として新聞やテレビで取り上げられ,またJRの時刻表の表紙を飾るまでに成長した。
このように,さまざまな問題をアイデアと実行と情熱で克服し実現してきたことで,双海町のイベントも一年を通じて役場や地元の住民の手によって行われるようになった。
そのような若松さんのオンリーワンを作るアイデアのヒントは,地道な活動にある。若松さんは,17年間,毎朝通勤前の3時間,シーサイド公園の砂浜を清掃し,さらに毎日3通の手紙を送ることを欠かしたことがない。この地道な活動を続けることこそが,いろいろなアイデアの源泉であり,さらなる情熱を作り出していると言う。
双海町の夕日
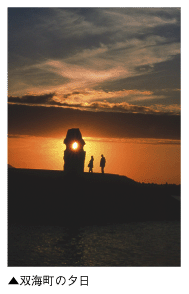
5)田中まこさん(兵庫県神戸市):国際交流・外客受入
「ローマの休日」を観てローマに憧れたり,「慕情」を観て香港に行ってみたり…海外旅行のきっかけは映画のワンシーンという方は多いのではないだろうか。あるいは,テレビの旅番組やご当地サスペンスドラマを観て,国内の観光地に向かった方も多いはずである。
映像をPRの手段と捉えて,自分たちの街を映像に収めてもらうべくロケ撮影を誘致しようという「フィルムコミッション」(第3章第1節1(11)参照)の活動が全国に拡がっているが,田中さんはその中でも先駆けと言える「神戸フィルムオフィス」の代表である。
フィルムコミッションの仕事は大きく分けて三つ。一つは,ロケの候補地を探すこと。台本を見て,一つのロケ地について数カ所ずつ候補地を探し,管理者や持ち主を探してあたる。二つ目は,ロケ撮影が決まった場合,ロケ地の撮影許可を取れるようにする。警察,港湾局,消防等の関係部局の撮影許可をロケ隊に代わって,あるいはロケ隊と共に取得するというものであるが,この仕事がうまくいかずに挫折するフィルムコミッションも多い。三つ目は,撮影現場での協力。市民エキストラの手配,移動手段の手配,弁当の手配などである。
田中さんは,いぶかる関係部局に地道に説明を繰り返してきた。先進地であるアメリカのフィルムコミッションの関係者を連れて来て話もしてもらった。それを2年間続けて,関係部局のコンセンサスを得てから初めて神戸フィルムオフィスを正式に立ち上げた。こうした地道な努力,信頼関係の構築が,その後のさまざまな撮影シーンの実現につながった。
一例としては,映画「GO」では,地下鉄の線路内で主人公が走るという重要なシーンの撮影を実現させた。映画「リターナー」では,公道を閉鎖しての爆破シーンやカーチェイスの撮影を実現させた。京都や奈良を舞台にしたサスペンスドラマの様々なシーンの撮影も神戸で支援してきた。
この結果,今や映像関係者の間では,神戸は最も撮影許可が下りる都市として知られるようになっており,映像関係者が撮影場所を求めて神戸に繰り返し訪れる例が増えているという。田中さんは神戸フィルムオフィスの立ち上げからわずか4年間に500本以上の映像制作に携わった。ロケ隊の飲食などで地元に1億2,000万円の直接経済効果をもたらしている。宣伝効果も計算すればその何倍もの間接経済効果があるという。
また田中さんは,我が国の映像制作が完全に東京一極集中となっている状況を打開すべく,企画・構成から撮影,編集,CG制作など8社にのぼる映像制作の会社を2年がかりで神戸に集めた。この結果,神戸で撮影から編集,CGまで完全に一からの映像制作が可能となった。
田中さんは,地元の企業で映像制作が可能になれば神戸の若者にも励みになる,また日本一美しいこの神戸という街を多くの人に知ってもらい,神戸に来てもらうことにも大きく貢献できる,と語っている。
神戸市営地下鉄線路内での撮影風景
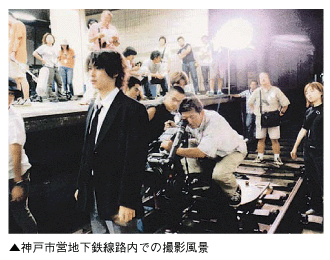
6)田口久義さん(秋田県田沢湖町):グリーンツーリズム
農作業をすることなど農村では当たり前のことであっても,都市で生まれ育った子どもたちにとっては未知の体験である。実際に農業を体験し,自分が普段食べているものがどうやって作られていくのか,またそのための苦労はどれだけのものかを学習する一方で,自分で収穫した果物や野菜を食べるのは最高の思い出になるに違いない。
田口さんは,田沢湖畔の近くで民宿を経営している。もともと中学や高校のスキー合宿を多く受け入れており,教育関係者や旅行会社などとの人脈を培っていた。一方,田沢湖町の劇団「わらび座」が農業体験を売りにしたツアーを受け入れており,近隣の農家にも受入れを依頼し,田口さんも自家で所有する山林や田畑を少しずつ開放していた。
そんな折り,旅行会社から,農業体験をプランに入れた体験学習旅行を受け入れないかとの打診があった。田口さんの農業体験ツアーの受入れ,スキー合宿の受入れという二つの実績を見込まれての話だった。スキー場近くの大型ホテルにスキー客が流れて受入客数が減少していたこともあって,田口さんは平成2年に初めて体験学習旅行を受け入れた。
田口さんは,学校側の要望を聞きつつ体験プラン・スケジュールを作成したり,要望にできるだけ応えることができるよう体験メニューの充実に努めた。その際,「今の子どもは飽きっぽい」として同じプログラムは2時間以上は続けない,工程が多い作業は分担させる,子どもの邪魔にならないようテレビの取材はお断りする,等の配慮を行っている。
その結果,体験学習旅行の受入れは年々増加し,平成5年には10校を超え,田口さんの民宿だけでは対応できなくなってきた。そこで田口さんもまた近隣の農家に受入れを依頼するようになるとともに,受入れ農家の窓口としても活動するようになった。この経験が発展し,体験学習旅行の受入を一括して行うNPO法人「田沢湖ふるさとふれあい協議会」の設立につながった。田口さんは協議会の理事長の任にある。
その後も体験学習旅行の受入れは増加する一方であり,田沢湖町内だけでは対応できなくなった。そこで田口さんは,周辺の町村にも受入れを依頼するようになり,広域化が進んでいる。
現在では,毎年20校・2,000人の体験学習旅行生を受け入れているが,学校側の希望とは裏腹に人数をさばききれず,田口さんのところには,向こう2年先まで春・秋の農林業体験は予約でいっぱいとなっている。
田口さんは言う。「農業体験が多くの子供たちに大きな感動を与え、その感動が作文集にまとまると,今度はその文集を読んだ親がまた大きな感動を味わうといった、大きな感動の輪を作り出している。」最近では,田口さんの農業体験メニューを体験し,長じて教師になった人が,体験学習旅行生を引き連れて田口さんのもとを訪れたケースもあるという。
農業体験の様子

| (2) 観光カリスマと観光交流空間づくりモデル事業で活気を見せている地域 ~伊勢・二見地域~ |
次に,観光カリスマと15年度に国土交通省が実施した観光交流空間づくりモデル事業で地域全体が活気を見せている地域として,伊勢・二見地域を紹介する。
伊勢・二見地域といえば,御鎮座2000有余年の伊勢神宮内宮及びその周辺の宇治地区では観光客が増加し,活況も呈しているが,この中心となっているのが,年間300万人もの観光客が訪れるおかげ横丁である。そして,おかげ横丁を建設,運営しているのは,観光カリスマである濱田益嗣さんである。おかげ横丁は,さびれつつある内宮の鳥居前町に造り上げた,黒い瓦屋根に囲まれた木造建築物25棟40店舗が立ち並んでいる空間で,伊勢玩具,伊勢型紙といった工芸品や,てこね寿し,伊勢うどんといった郷土料理などに代表される「日本のくらし文化」を味わえるよう工夫してある。決して古い建物群ではないが,どことなく懐かしく楽しい空間に人々が引き付けられるのは全て本物だからである。濱田さんは,「おかげ横丁はハードで始まったが,重要なのは結局ソフトである」「流行は,波がいつ消えるともわからないので,それを狙うのではなく,完成度が高い本物を作るようにしないといけない」「本物であればリピーターも確保できる。また完成度が高いと若者も寄ってくる」と言う。濱田さんは菓子会社の社長であるが,築25年の本社屋を取り壊し,6年を費やして買収した土地を加えてつくった「おかげ横丁」はまさに社運をかけた大事業であった。今後は,昔ながらの宿泊施設を造って第2のおかげ横丁を造りたいと言う濱田さんの挑戦はまだまだ続くのである。
年間約300万人が訪れるおかげ横丁
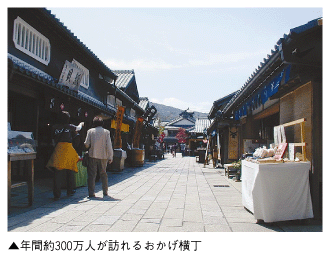
一方,伊勢神宮外宮周辺及び伊勢市に隣接する二見町は,観光客が次第に減少し活気を失いつつある内宮及びその周辺地域以外の地域を中心に,「観光交流空間づくりモデル事業」を活用しながら,NPO法人が中心となった快適空間づくりを始めている。
まず,伊勢市の中心市街地の一角,勢田川沿いにある河崎問屋街地区である。ここは,勢田川の水運を活かしたかつての問屋街で,米,酒,かまぼこ,味噌,しょうゆ,砂糖,鰹節,海苔,陶器,雑貨などあらゆる品々を扱い,神宮参拝者の衣食を支えた伊勢の台所と言われ,栄えた街である。NPO法人「伊勢河崎まちづくり衆」は,国の登録有形文化財である「伊勢河崎商人館」を拠点に,昔ながらの蔵や商家を活用しながら古くから受け継がれてきた地域固有のまちなみ,生活文化をありのままの姿として保全し,紹介する歩いて廻れる「癒しの空間づくり」を行っている。このため,例えば,建物やまちなみ保全のためのルールづくり,語り部の育成,朝市,フリーマーケットなどイベントの開催,プロモーションビデオやパンフレットの作成などを行っている。
また,勢田川下流の宇治山田港神社(かみやしろ)地区は,かつて全国各地から海路のお伊勢参り(船参宮)客を乗せた船や外来の物資を集散する船が往来しにぎわっていた港であるが,かつての活気を取り戻すために活動を始めたのがNPO法人「神社(かみやしろ)みなとまち再生グループ」である。このNPO法人は,「港まつり」をはじめとする伝統行事への協力,木造船の建造と技術伝承,カヌーやカッターの体験教室などを行っている。また,このグループとNPO法人伊勢河崎まちづくり衆が中心となって宇治山田港を舞台に,「みなとまちづくり」の一環としてNPO法人「伊勢「海の駅・川の駅」運営会議」を組織し,海の参宮ルートづくり,海の駅,川の駅の運営支援,散策マップづくりなどを行っている。
さらに,伊勢市に隣接する二見町には,明治20年に建設され歴代皇族,各界要人が数多く宿泊した国の登録有形文化財にもなっている「賓日館」があるが,平成11年に営業を停止した。この賓日館は町に寄贈され,平成15年11月より一般公開が始められたが,これを維持・保存・運営しているのがNPO法人「二見浦・賓日館の会」である。二見町は,賓日館を拠点とする旅館街地区の景観を保存しながら,「茶屋再生~そぞろ歩きの似合うまち」をテーマに快適交流空間づくりを行っている。
このように,伊勢市,二見町は,平成25年の神宮式年遷宮に向け,観光カリスマとNPOが相まって国土交通省の観光交流空間づくりモデル事業を活用したNPO中心の快適交流空間づくりを進め,2005年開港する中部国際空港から国内外観光客の誘致につなげる観光都市再生を目指し,伊勢市・二見町全体が活気あふれた地域となるような取り組みが進められている。
| (3) 都市再生,構造改革特区等と連動した住民参加による観光まちづくり ~松山市の例~ |
政府は,地域の自立的な活性化を促す取り組みとして,都市再生,構造改革特区,地域再生などを行っている。各地には,これらの手法を活用して観光を軸に再生を目指すところも少なくなく,ここでは地域住民も積極的にまちづくりに参加している松山市の例を紹介する。
道後温泉で有名な愛媛県松山市は,年間約500万人の観光客が訪れる四国有数の観光地である。このように観光の振興が重要なテーマである松山市に就任した中村時広市長は,就任時の平成11年,21世紀には「松山らしい」まちづくりを行っていこうと,「坂の上の雲」(司馬遼太郎著)を軸としたまちづくり構想を掲げた。昭和40年代,新聞に連載されたこの作品は,「明治」という特異な時代を舞台に,松山出身の秋山好古・真之兄弟,正岡子規という3人の青春群像を描いた小説である。
平成12年,中村市長の構想を受け,「基本計画検討委員会」は,この作品が与える精神や創造的知見から,21世紀のまちづくりにとって貴重な指針となるべく「4つの基本理念」を構築し,「『坂の上の雲』フィールドミュージアム構想」を策定した。
この構想は,まち全体を屋根のない一つの博物館と捉え,松山城がある中心部を「センターゾーン」,道後温泉,三津浜など明治時代の史跡や施設,「坂の上の雲」にまつわる事物が集中する地域を「サブセンターゾーン」,子規堂やロシア人墓地など市内に点在する史跡を「サテライト」と位置付け,この間を結ぶ回廊型の導線を確立しネットワーク化することによって,物語のある観光都市を構築しようとするものである。松山市は,この構想をもとに,市民・NPO・地元企業などに参加を呼びかけ,ともに協力しながら観光まちづくりを進めている。
図2-3-1 「坂の上の雲」フィールドミュージアム構想図
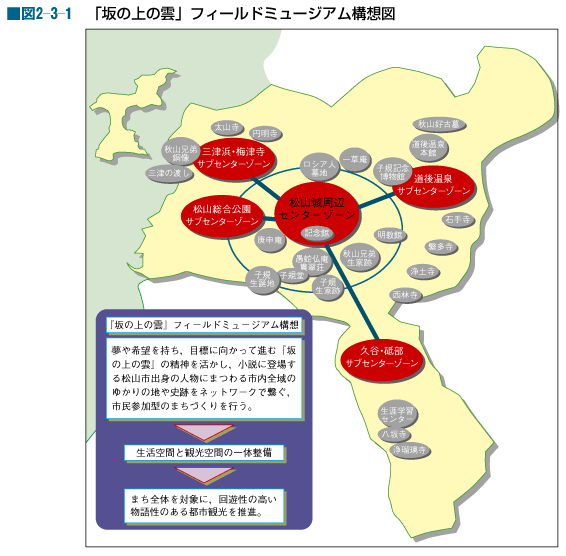
市民参加型のまちづくりの仕組みとして,松山市は平成15年9月,「まちづくり市民塾」を開始した。これは,公募で選ばれた会社員や主婦など総勢66名が,行政と共同で松山市のまちづくりについて話し合いまちづくりを進めるもので,はじめは「行政への提案型」であったが、今では「自らがどう参画できるか」をテーマに取り組むようになるなど,まだ半年間で7回の開催であるが,早くも市民の意識変化が表れている。
また,「『坂の上の雲』まちづくり勉強会」というまちづくりを考えるシンポジウムも開催している。平成16年2月に行われた第3回の勉強会は,建築家,タレント,市長,さらに市民ゲストも参加し,「センターゾーン」の中核施設「坂の上の雲記念館(仮称)」の建築コンセプトが話し合われた。この第3回勉強会は1,000円の受講料が必要にも関わらず,1,000枚用意したチケットが完売になるなど,「坂の上の雲」を軸としたまちづくりへの市民の関心は高く,大きな原動力となっている。
第3回まちづくり勉強会の風景
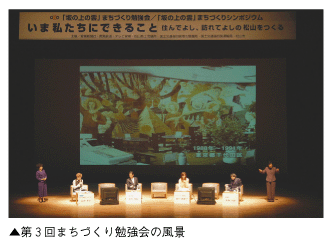
遍路道でのNORA の活動風景

plus M が取り組む観光サイン

また,松山市は,まちづくりの中に市民団体やNPOの活動をうまく取り入れている。平成15年,松山市は「全国都市再生モデル調査」地区に選ばれ,「若者が創る「坂の上の雲」まちづくりモデル調査-元気な志民プロジェクト-」という調査を行ったが,その調査事業を行う団体として,市民団体やNPOなどから4団体を選出した。このうち,例えば愛媛大学の学生を中心とした「plus M」は,大街道からロープウェー乗り場までの「ロープウェー通り」を舞台に,「松山を楽しくする観光サイン計画」として,「歩いて楽しくなる」ガイドブックや標識の調査を行った。また,「NPO法人地域共創研究所NORA」は,「遍路文化再生による自然・人・地域の再生計画」として,昔ながらの面影を残す遍路道のルート散策実験や旧遍路宿を利用したお接待を実施し,四国に残る風習や文化の再生に向けた調査・実験を行った。
さらに松山市は,「松山市観て歩いて暮らせるまちづくり交通特区」として,平成15年11月,構造改革特区計画の第3回認定にて認定された。これは,地域参加型のまちづくり計画に基づき交通規制を実施するという特例措置が認められたものである。具体的には、地元住民,道路管理者,警察,学識経験者や一般の道路利用者にて構成された協議会が,回遊性を高める交通体系や環境に配慮した人にやさしい交通体系の実現を目指して,交通規制や道路整備を含めた総合的なまちづくり計画を策定し,それに基づき,主要な観光地における交通規制の実施や自転車の交通量が多く,歩行者や自動車が錯綜する道路における自転車専用レーンの整備などを行うことになる。
また,休日の観光施設の駐車場不足や周辺地域の渋滞など自家用車に関する問題を解消するため,平成16年4月,「休日都市観光推進における公共交通活用プラン構想」を策定した。このプランは,観光客が多い休日に,官公庁の駐車場を無料解放するとともに民間駐車場も活用し,自家用車で訪れた観光客には,その駐車場から路面電車など公共交通機関を利用して観光していただこうという構想である。この実現によって,中心部の交通円滑化をもたらすばかりでなく,松山市を便利で安全な観光・環境としてPRすることによって,松山市のイメージアップや観光客のリピーター率の向上につながるものと期待されている。
また,平成16年3月から半年間,地元企業が路面電車や循環バスといった交通機関と松山城など10箇所の観光施設と連携し,ICカードの実証実験を全国で初めて行っている。この実験は,購入した1枚のICカードで交通機関や主要観光施設の入場料の支払い(観光施設については割引の特典付き)を可能にしたものであり,これによって,観光客の公共交通の利用促進,観光客の利便性向上が期待できる。また,ICカードの販売・管理・運営は地元企業,観光施設の割引という特典は市や県が行うなど,官民一体となったまちづくりの取り組みとしても注目されている。
松山市は,この「坂の上の雲」フィールドミュージアム構想を地域再生のテーマとしても取り上げており,今後さらにこの取り組みは加速されるものと期待される。
|
|