平成15年度観光の状況に関する年次報告
第5章 観光交流空間の形成
第1節 観光地の魅力の向上
1 総合的,広域的な観光地づくり支援
地域の個性を活かした魅力ある観光交流空間づくりのための自主的な取組みを国土交通省がハード・ソフトの両面から総合的,重点的に支援する「観光交流空間づくりモデル事業」を平成15年度より実施している。15年度は申請のあった地域の中から国土交通省ホームページ上で行ったCS調査(顧客満足度調査)の結果も参考にしながら8地域を選定した。また,支援策の一環として,モデル地域においてNPO等が実施する社会実験等の調査・検討の支援を実施した。
「観光交流空間づくりモデル事業」選定地域(佐原祭り)

| COLUMN 6 観光交流空間づくりモデル事業におけるCS調査(新規項目) |
|
|
観光交流空間づくりモデル事業の選定にあたっては,参考とするため広く一般からの意見を募集するCS調査を行った。
申請のあった各地域の構想を国土交通省のホームページ上で公開し,訪れたい地域や自由意見を募集したところ,2週間という短期間にも拘わらず,約2,800件もの回答があった。
申請のあった各地域の取り組みをホームページ上で見た国民の皆さんより様々な意見をいただいたが,自由記入意見では「従来型の観光スポットを巡るだけの観光ではなく,地域の人々と交流できる地域づくりに賛同する」等地域と観光客が交流することによる観光交流を期待する声が特に多く,本事業で目指す観光交流空間づくりが重要であるということが確認された。今後は,引き続き調査手法を工夫しながら国民への情報提供と国民の評価を把握する方策としてCS調査を活用していくこととしている。
CS 調査の画面

|
|
| (2) 都市再生・構造改革特区と一体になった観光振興 |
都市再生,特に身の回りの生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を促進する「全国都市再生~稚内から石垣まで~」の取組みにおいて,観光振興を核とした取組が顕著である。例えば,都市観光の推進(稚内市,松山市,石垣市等),歴史的たたずまいを継承した街並み・まちづくり(犬山市,京都市等),環境共生まちづくり(飯田市,田原市等)等のテーマごとに共通の制度的課題を具体に解決するとともに,事業を集中的に実施している。また,平成15年6月の都市再生本部の決定により,観光をテーマにしたものなど地域が自ら考え自ら行動する都市再生活動を「全国都市再生モデル調査」(約640件の応募に対して,171件を選定)として推進・支援している。
また,構造改革特区(地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案により,地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域を設けることで,構造改革を進める制度。)では,地域限定の規制改革として,例えば,市民農園の開設主体の拡大や,濁酒(いわゆる「どぶろく」)の製造に関する免許要件の緩和等が可能になり,このような規制の特例措置を活用し,農家民宿で濁酒をふるまうなど,地域の魅力を高める取組みが,全国で40件(観光関係)認定されている。
このように,「都市再生」「構造改革特区」の取組と連携しながら観光振興を進めている地域がある。
なお,観光を核とした都市再生の事例として,松山市の「坂の上の雲」フィールドミュージアム構想を第2章第3節で紹介しているので,ご覧いただきたい。
| COLUMN 7 構造改革特区を活用した観光振興の取組みの例 |
|
|
構造改革特区を活用した観光振興の取組みの中から,岩手県遠野市の事例を紹介する。
「日本のふるさと再生特区」(岩手県遠野市)
遠野物語の里で,農家民宿で濁酒(いわゆる「どぶろく」)を提供し,ぬくもりともてなしの心で都市との交流の拡大を図り,農林業を中心とした地域に根ざした新たな起業を促進し,地域の活性化を図る取組みを行っている。
具体的には,「農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営への参入の容認」という規制の特例措置を活用することにより,株式会社が耕作放棄地を利用した農業経営を行い,遠野の貴重な観光資源である農村景観を保全し,「農家民宿における簡易な消防用設備等の容認」という規制の特例措置の活用により,農家民宿の開設を容易にする。また,「農家民宿等における濁酒の製造免許の要件緩和」という規制の特例措置を活用することで,農家民宿等を経営する農業者が自ら製造した濁酒の提供を通して農家と都市住民との交流の促進を図る取組みを行っている。
|
|
平成15年10月24日に,地域経済の活性化と地域雇用の創造を地域の視点から積極的かつ総合的に推進するため,内閣に地域再生本部(本部長:内閣総理大臣)を設置した。平成15年12月下旬から平成16年1月中旬にかけて,地域再生構想の提案募集を行ったところ,392の主体から673件の提案が提出された。この中には,観光,イベント,文化,スポーツ,交流に関するものも多く含まれており,受け付けた提案の検討結果について,2月27日に地域再生本部において,「地域再生推進のためのプログラム」としてまとめた。同プログラムには,地域観光の活性化の観点から,観光地の案内標識について,景観への配慮方法や外国語表記方法等をルール化すること,エコツーリズムの推進に向けた普及マニュアルの作成やツアー情報の提供等の地域支援を行うこと,「一地域一観光」を推進する「ひと」「情報」の充実を図ること,良好な景観・まちなみ形成の実現等を図ること等が盛り込まれた。当該プログラムに基づいて,地域再生計画の認定申請を受け付け,認定を行うものである。その中には,観光や都市と農村の交流に関する計画等も含まれる。
従来型の個性のない観光地が低迷するなか,各観光地の魅力を高めるためには,観光振興を成功に導いた人々の類まれな努力に学ぶことが極めて効果が高く,各地で観光振興にがんばる人を育てていくため,その先達となる人々を「観光カリスマ」として選定している。
選定は島田晴雄・内閣府特命顧問を委員長とする選定委員会が行っている。14年12月に第1回委員会を開催して以来,現在までに5回の選定を重ねており,観光カリスマの人数は63人となっている。選定結果や,選定された観光カリスマの事績などは,国土交通省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/top.htm)に掲載するなどして公表している。また,第2章第3節2(1)において,63人を6分野に分類し,各分野1人ずつ6人の取り組みを紹介している。
15年4月には,観光カリスマをテーマとしたタウンミーティングが開催され,観光カリスマの取組みの紹介や観光立国に向けた議論が行われた。
平成15年7月31日に観光立国関係閣僚会議で決定された「観光立国行動計画」の重要な柱の一つとして位置付けられている「一地域一観光」の主要施策として,「一地域一観光魅力ネットサイト構築」事業を実施した。全国の市区町村及び国民に地域の魅力の発見・投稿を呼びかけ,それらを集約してデータベース化し,「発見!観光宝探しデータベース」としてインターネットで公開した。
|
|
「一地域一観光魅力ネットサイト構築」事業として,全国各地から寄せられた観光魅力に関する情報は,「発見!観光宝探しデータベース」として,平成16年2月からインターネット上で公開されている。本データベースでは,合計で1,010件(全国897市区町村;国民から113件)に上る観光魅力に関する情報が掲載されており,地域別,テーマ別に検索が可能となっている。なお,英文での投稿も掲載している。
掲載情報は,既に全国的に知名度の高い観光資源から身近な観光資源として地元で親しまれているものまで,また風景から食べ物,イベントなど多岐にわたっている。
ホームページアドレス
http://www.kanko‐otakara.jp/
魅力ネットサイト画面
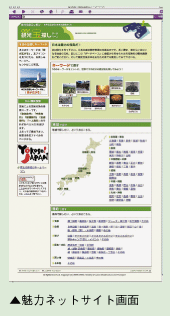
|
|
従来の画一的な観光開発に代わり,地域の創意工夫により当該地域の自然,文化,歴史等を活用した個性的な観光まちづくりを進めるための施策「観光まちづくりプログラム策定推進事業」を実施した。平成15年度は,実務経験者等からなる観光まちづくりアドバイザーを全国36ヶ所に派遣するとともに,15地域において広域観光ルートの設定,交通環境改善等を内容とする観光まちづくり実施支援プログラムを策定する等の支援を行った。
観光まちづくりプログラム策定推進事業
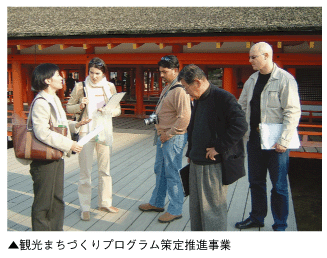
自動車旅行者をターゲットに点在する観光資源を魅力ある観光ルートとして紹介するため,一定のテーマコンセプトをもとに広域観光案内板等を整備する「広域観光テーマルート整備事業」を実施しており,平成15年度においては1ケ所(香川県全域地区)において整備を行った。
広域観光案内板(香川県・八栗寺)

| (8) インタープリテーションプログラム(自然ガイドツアー)による観光地の振興 |
近年の自然体験志向等の観光ニーズの変化を踏まえ,自然の不思議さや面白さを,自然ガイドの解説を受けながら味わう,自然ガイドツアーを造成することにより観光地の振興を図っている。15年度においては,安心,安全な自然ガイドツアーを提供するために事業者が具体的に配慮すべき事項をまとめるとともに,自然資源を持続的に観光利用していくための方策の検討を行った。
農山漁村に滞在して,余暇活動を楽しむグリーン・ツーリズムについては,都市部の方々が農山漁村情報をインターネットで検索できるデータベースの整備,子どもたちの農林漁業体験活動の促進,農家民宿の経営者などグリーン・ツーリズムを企画したり実行する人材の育成,モデル的な地域で旅行者の受入のための市民農園や茅葺き農家・廃校等を活用した交流拠点の整備等を実施した。
藁葺き農家を活用した旅行者受入のための交流施設
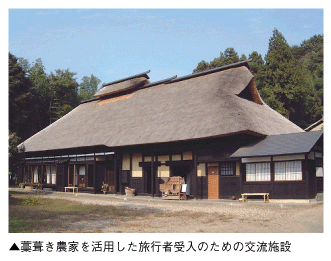
(10)エコツーリズム
自然環境の保全を確保しつつ,自然や文化を活かした観光と地域振興を両立させ,環境教育にも役立つエコツーリズムを全国に普及・定着させるため,エコツーリズム推進会議を開催し,エコツーリズム憲章など推進方策の検討を実施した。
|
|
自然環境の保全を確保しつつ,地域資源を利用した持続可能な旅行形態としてエコツーリズムが世界的に注目されている。旅行者は,訪れる土地の自然環境を守りながら地域特有の自然や生活文化にふれる「知的体験旅行」を楽しみ,それを提供する地域においては,持続可能な地域の資源を活用することで経済効果を生み出すように,自然環境の保全と観光,地域振興をそれぞれ活かした持続可能な旅行形態としての効果が期待されている。
エコツーリズムという概念は,一般には1982年にIUCN(国際自然保護連合)が「第3回世界国立公園会議」で議題としてとりあげたのが始まりとされている。日本においても,これまで各地でエコツアーを実施する事業者は多く,最近では,平成14年に施行された沖縄振興特別措置法において,法律として初めてエコツーリズムを推進するための制度が盛り込まれた。また,国連では2002年を「国際エコツーリズム年」とし,各種国際会議を開くなど国内外でエコツーリズム推進の機運が高まっている。
観光立国の一層の促進を図るものとして,2003年11月に小池環境大臣を議長に関係業界や有識者,行政機関等で構成する「エコツーリズム推進会議」を開催した。同推進会議では,適正なエコツーリズムの普及・定着を目的に,モデル事業など様々な推進方策が検討されている。
|
|
(11)産業観光の推進
ものづくりの体験学習や工場見学など,産業に関する施設や技術等の資源を用い,地域内外の人々の交流を図る産業観光の振興に資する施策の検討を行った。
樽工場の展示

(12)フィルムツーリズムの振興
平成15年10月,フィルムコミッション(地域が設置する映画等ロケーション撮影を誘致・支援する非営利組織)など撮影関係者と関係省庁とが一同に会し,今後のフィルムコミッションの在り方や,撮影関係者がより多くの場所で円滑に撮影を行うことを可能とするための規制緩和など撮影環境の整備について話し合う「フィルム・コミッション・コンベンション」の開催を通じ,その活動を支援した。
(13)サイクルツアー推進事業
サイクリングを楽しみながら地域の魅力をゆっくりと堪能する新しいツーリズム(サイクルツアー)を普及し,地域の活性化を図ることを目的に,サイクリングロードと観光施設,川の親水施設,港湾緑地等との連携を強化する各種施策を総合的に推進している。
平成15年度には自転車道の整備状況や観光資源等を考慮してサイクルツアーのモデル地区を選定し,各地区において関係機関による協議会等を開催した。
(14)北海道の観光振興
1)北海道の観光の現状
北海道は,豊かな自然,新鮮な味覚など多彩な観光資源を有し,また,各種の体験型観光,アウトドア活動に係る施設の充実,イベントの開催などにより,観光地として国民にくつろぎの場を提供している。
平成15年の来道者数は,前年比で23万人減の1,330万人(前年比1.8%減,北海道観光連盟調べ)と,冷夏や冬期の雪不足等の影響により減少に転じた。また,海外からの来道観光客についても,中国(香港),韓国などからの観光客がSARSなどの影響を受け減少に転じている。
農業体験(羊の毛刈り)

2)北海道における観光振興策の展開
第6期北海道総合開発計画においても,観光関連産業は地域経済を支える重要な産業として位置づけられており,観光基盤の整備,観光資源情報ネットワークの充実,アウトドア活動に資する施設整備や農山漁村における自然体験型活動等の積極的支援により,北海道の特色を生かした観光振興の支援を行っている。
また,地域住民の活動を中心に,沿道景観整備等による美しいドライブ環境の創造と地域資源の保全と活用による個性的な地域環境の創造により,美しく個性的な北海道づくりを目指す「シーニックバイウェイ北海道」の制度導入に向けた検討,試験的な取り組みを行っている。
(15)沖縄の観光振興
1)沖縄観光の現状
沖縄県は,亜熱帯・海洋性気候風土のもと,美しい自然景観,独特な伝統文化や歴史など魅力的な観光資源を有しており,昭和47年の本土復帰以降,入域観光客数が約10倍に達するなど,観光・リゾート産業は,沖縄のリーディング産業として大きく成長してきた。
平成15年は,イラク戦争の影響から,前半に修学旅行を中心にキャンセルの動きが見られたものの,政府・沖縄県が連携した迅速な対応などにより,間もなく沈静化した。その後,沖縄観光強化キャンペーンの効果や,「沖縄美ら海水族館」の集客効果,さらには新型肺炎(SARS)の影響による海外観光からの振替えなどもあり,順調に推移した。
同年8月には,沖縄都市モノレール(ゆいレール)が開業し,平成16年1月には,「沖縄美ら海水族館」に続き,新たな観光拠点として期待される「国立劇場おきなわ」が開場した。
平成15年の入域観光客数は,初めて500万人を超え,過去最高となる508万人を記録した。
国立劇場おきなわ
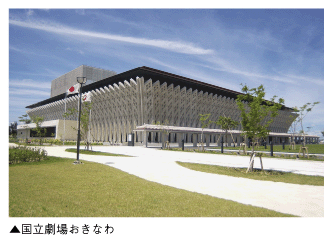
2)沖縄の観光振興策の展開
沖縄の観光振興を図るため,沖縄振興計画等に基づき,多様なニーズに対応した通年・滞在型の質の高い観光・リゾート地の形成に向け,各般の施策を推進した。
国際的な質の高いリゾート地を目指して,観光振興地域等の整備をはじめ,国際的観光地としての発展を担う多様で質の高い人材の育成,国内外の観光客に充実した観光情報を提供するための共通プラットホームの構築等の施策を新たに展開した。
また,沖縄の豊かな自然,歴史,文化等を生かして,エコツーリズムや世界遺産の周辺整備,体験滞在交流の促進等,多様なニーズに対応した観光・リゾート地の形成を目指したソフト・ハード両面にわたる取組みを進めるとともに,美しい沖縄の景観形成に配慮した基盤整備に努めた。
なお,平成15年3月のイラク戦争の影響で,沖縄への修学旅行等のキャンセルが一部発生したことから,政府・沖縄県が連携し,観光強化キャンペーン,修学旅行生確保対策事業,平常通りの沖縄への理解等を求める通知の発出などの対策を迅速に講じた。
(16)豪雪地帯における冬季の観光振興
豪雪地帯対策特別措置法に基づく豪雪地帯対策基本計画において,観光・レクリエーション産業を振興することとされており,その実現に向けて個性的な冬期間観光の推進に努めるとともに,冬期利用に配慮した各種施設の整備及び観光情報を含めた雪関連情報の提供についての検討等を実施した。
(17)離島地域の観光振興
離島は本土に比べて個性的で魅力的な自然環境や地域文化がある一方,アクセスの煩雑さや情報提供不足等の問題を抱え,高いポテンシャルを持ちながらも観光資源を十分生かし切れていない。そこで,観光による離島地域経済の活性化を図ることを目的に「離島ツアー交流推進支援事業」を実施し,魅力的な観光資源の再発見や観光ルートの開発を行っている。平成15年度においては,特徴ある地域資源の再発掘を行い,通年型観光を促進することによる地域の活性化を図ることを目的として,山形県の飛島において事業を実施した。
離島ツアー

(18)奄美群島・小笠原諸島の観光振興
奄美群島においては,本土復帰50周年を記念した各種イベントの開催をはじめ,島唄,八月踊り等の伝統文化を通じた島内外との交流を深めるとともに,スポーツ・文化の振興や地域の活性化を図るための奄美体験交流館の整備等,魅力ある地域にするための事業を実施した。
また,小笠原諸島においても,本土復帰35周年を記念したイベントを開催したほか,エコツーリズムの一層の推進を図るため,自然ガイドを養成するとともに,平成17年春に小笠原航路にテクノスーパーライナーが就航する予定であり,観光客の増加が見込まれることから,島内の受入れ体制の整備や新たな観光資源の発掘等を実施した。
(19)半島地域の観光振興
半島地域は,その地理的条件から産業基盤等の整備が立ち後れている一方,多様な自然・文化資源を有していることから,これらの資源を活用した観光を通じた活性化を図るため,NPOや地域住民等が主体となって行う交流・連携の促進方策を検討した。また,ワークショップ等を通じて,半島地域の観光を考える「半島ツーリズム大学」を平成15年度には,能登地域(石川県七尾市,輪島市等)及び紀伊地域(和歌山県田辺市等)で開催した。
|
|