平成15年度観光の状況に関する年次報告
第5章 観光交流空間の形成
第2節 自然環境の保全
自然公園等の優れた自然の風景等を観光資源として活用し続けるために,自然環境そのものを維持・保全するという事業が行われている。そこで,これについて講じた施策について記述する。
施策概要
■自然公園の保護管理
自然公園は「自然公園法」に基づく地域制の公園であり,国立公園,国定公園及び都道府県立自然公園の3種類があり,優れた自然の風景地を保護するとともに,その利用の増進を図ることを目的としている(図5-2-1,図5-2-2)。
1)公園計画の見直し等
自然公園の保護及び適正な利用を図るため,公園の区域や計画を定めており,概ね5年を目途に見直し作業を実施している。平成15年度には,利尻礼文サロベツ国立公園,瀬戸内海国立公園(岡山県地域)について公園区域及び公園計画の見直しを行い,国定公園についても三河湾国定公園,壱岐対馬国定公園について見直しを行った。
2)保護と管理
i)特別地域
国立・国定公園については,特別地域を指定し,当該地域内において,風致又は景観を損なうおそれのある一定の行為は,環境大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないとしている。都道府県立自然公園については,国立・国定公園に準じて条例により特別地域が定められている(表5-2-3)。
ii)特別保護地区
国立・国定公園の特別地域の中でも,公園の核心的な景観地については,特別保護地区として指定し,最も厳しい保護規制を行っている。その面積は,全国立公園面積の13.3%,全国定公園面積の4.9%である。
iii)海中公園地区
我が国の周辺海域には,熱帯魚,サンゴ,海草等の海中生物を主体とする優れた海中景観が存在する。このため,海中公園地区制度が設けられ,その保護と適正な利用が図られている(表5-2-4)。
図5-2-1 国立公園及び国定公園配置図
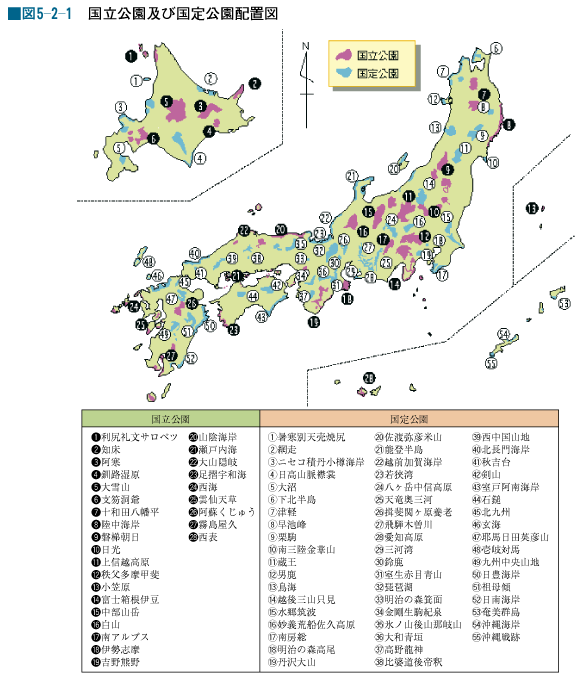
iv)買上制度
国立・国定公園内の特別保護地区等にある民有地のうち,特に買い上げて保護することが必要なものを対象として,都道府県が発行する交付地方債により土地の買上を行う制度を設け,その元利償還等に要する費用について国が都道府県に補助を行っている。
v)公園管理団体制度
国立・国定公園内で自然の風景地の保護と適正な利用を図ることを目的として,公益法人やNPOを,その申請により公園管理団体として指定し,自然の風景地の管理,公園利用施設の維持管理等の自発的な活動を推進している。平成15年度は,阿蘇くじゅう国立公園と栗駒国定公園において,各1団体が指定されている。
図5-2-2 自然公園利用者数の推移
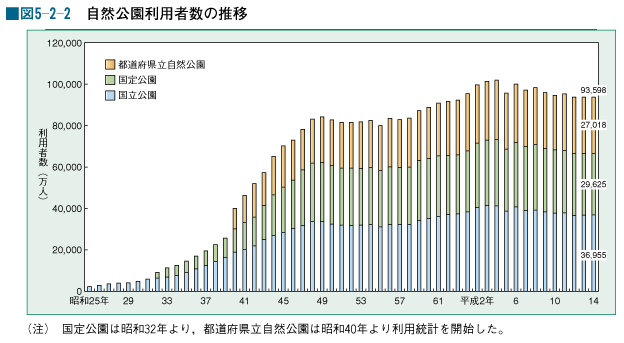
表5-2-3 自然公園の地域別面積
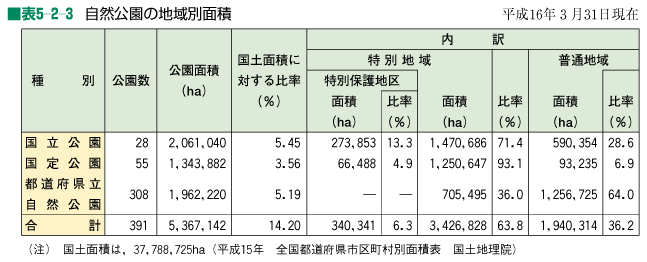
表5-2-4 国立・国定公園の海中公園地区
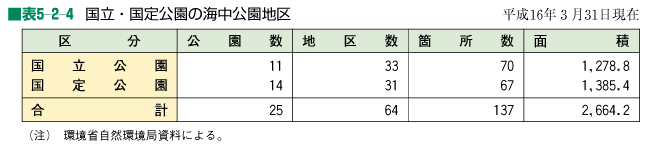
3)乗入れ規制地区の指定等
i)乗入れ規制地区
「自然公園法」により,国立公園又は国定公園の特別地域のうち環境大臣が指定する区域においては,車馬若しくは動力船を使用し,または航空機を着陸させることが規制されている。これは植生や野生動植物の生息・生育環境への被害を防止するためのもので,平成15年度末までに知床国立公園を始めとする25の国立・国定公園の45地域,計24万1,514haを乗入れ規制地区に指定している。
ii)マイカー規制等
国立公園内においては,「国立公園内における自動車利用適正化要綱」に基づき,自然保護事務所,都道府県警察本部,地方運輸局運輸支局等で構成する連絡協議会において,道路交通環境に応じた規制方法を検討し,一般車両通行止め等の交通規制を行って,観光地の交通安全の確保,環境保全に努めている。
上高地の入口
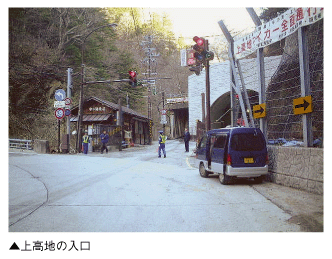
■森林等の保全管理
1)森林の保全管理
森林の有する公益的機能を特に発揮させる必要のある森林については,「森林法」に基づいて保安林に指定し,立木の伐採,土地の形質の変更等一定行為について制限を課すなどのほか,周辺の景観に配慮しつつ,荒廃地等の復旧整備,機能の低位な森林の整備を計画的に実施した。
また,森林の適正な管理を図るため,森林保全巡視員等による森林パトロール等の保全管理活動体制の整備,防火森林,防火林道の整備,林野火災予防資機材の配備等に対して助成したほか,全国山火事予防運動の実施等啓発活動を推進した。
2)国有林野の保全管理
国有林野においては,適正な森林施業を実施し,健全な森林の維持及び造成に努めるほか,1)特に自然環境が優れ,保健・文化・教育的利用に供することが適当な地域を自然休養林,自然観察教育林等のレクリエーションの森として選定するとともに,2)優れた自然環境を有する天然林等の保護を適切に図るため,保護林の適切な管理に努め,その拡充を図った。さらに,保護林と保護林を結ぶ緑の回廊を設定し,より広範で効果的な森林生態系のネットワークの確保に努めた。
また,保護林のうち緊急に保全措置が必要なものに対して,保全措置を講じたほか,世界遺産条約に基づく自然遺産(屋久島及び白神山地)の保全及び文化遺産と一体的な景観を成す森林の景観の回復を図るための施策を行うとともに,国有林野内に生息又は生育する国内希少野生動植物種の保護を図る事業を行った。
さらに朝日山地森林生態系保護地域において,森林の仕組み・働きと森林の接し方を学ぶ場の整備等を行った。
このほか,林野火災等の森林被害の防止のため,入山者に対する指導及び林野火災予防のための広報活動を行い,また,森林の保全管理の強化を図った。
■河川・湖沼・山地流域の保全
河川や湖沼は,多くの貴重な生態系を維持し,観光,保養及びレクリエーション等の重要な資源となっており,「水質汚濁防止法」に基づく排水規制など水環境の保全のための対策に取り組んだ。
1)湖沼の水質保全対策
全国の湖沼を対象に,富栄養化の防止のため,「水質汚濁防止法」に基づく窒素・燐の排水規制を実施するなど水質改善対策の実施を図った。また,水質改善が緊要な湖沼を対象に「湖沼水質保全特別措置法」に基づき,琵琶湖や霞ヶ浦など10の指定湖沼において湖沼水質保全計画に基づき,総合的な水質保全対策を進めた。
2)生活排水対策
湖沼や都市内中小河川等の汚濁の大きな要因となっている生活排水の問題については,「水質汚濁防止法」に基づき,都道府県知事が生活排水対策重点地域の指定,重点地域の市町村が生活排水対策推進計画の策定・推進を行っている。
湖沼等の水質保全のため,周辺観光地等の下水を処理する特定環境保全公共下水道事業等を行うとともに,高度処理の推進により一層の水質改善を図った。合流式下水道については,合流式下水道緊急改善事業等の活用によりその改善を図った。
3)良好な水辺空間の創出
自然材料活用による水路の修復等による水辺空間の再生,生活排水等による汚濁が著しい水路の水質改善,地下水かん養施設等による水循環再生のための水辺空間再生施設整備事業を実施した。
4)河川環境整備・ダム周辺環境整備
河川やダム湖の浄化対策として,汚濁した底泥の浚渫や浄化用水の導入などを行っている。また,蛇行河川の復元や湿地の再生などを行う「自然再生事業」を実施し,自然と共生する社会の実現に向け良好な水環境の形成を図った。
5)山地流域の保全
山地流域の個々の特色をいかした,崩壊地に植生を回復させるため,NPO等と連携して山腹工,砂防樹林帯等の周辺環境に配慮した砂防事業を実施した。
■海の環境保全
1)海域の水質保全
「水質汚濁防止法」,「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」を始めとする公害関係諸法による排出規制を行ってきている。海域の全窒素及び全燐に係る環境基準については,国及び道府県においてその類型の指定及び見直しが進められている。また,国が類型指定を行う水域については,暫定目標の見直しを進めている。
東京湾,伊勢湾及び瀬戸内海については,化学的酸素要求量(COD),窒素及び燐に係る第5次水質総量規制を実施している。瀬戸内海においては,関係11府県が自然海浜保全地区条例により,平成15年12月までに91地区の自然海浜保全地区を指定した。
海域における水質の保全を図るため,海域に関する流域別下水道整備総合計画の策定を進めるとともに,下水道の整備,高度処理の推進,合流式下水道の改善を図った。
海洋汚染が発生する可能性が高い海域において重点的な監視取締りを実施したほか,油等排出事故対策訓練等を実施した。さらに,海洋環境保全講習会等のあらゆる機会をとらえて,海洋環境の保全に関する指導・啓発を行った。
都市再生プロジェクト(第三次決定)「海の再生」を受け,「東京湾再生のための行動計画」を平成15年3月に策定した。また,大阪湾についても,九府県市及び関係省庁の連携により,平成16年3月に「大阪湾再生行動計画」を策定した。
再生された干潟での潮干狩り(三河港蒲郡地区竹島)

2)港湾の環境保全
環境と共生する港湾<エコポート>の形成を目標に水質・底質を改善する汚泥浚渫や覆砂,港湾の親水性を高め快適な環境を創造する干潟・藻場等の積極的な保全・再生・創出の他,海浜及び緑地の整備を推進し,15年度は堺泉北港等において干潟等の整備,仙台塩釜港等において緑地の整備を実施した。
3)漁港の環境保全
漁港及び漁場の環境保全と快適な漁村環境の創出を図るため,漁港区域の水域において,汚泥・ヘドロの除去,藻場・干潟や水質浄化施設・清浄海水導入施設等の整備を行う漁港水域環境保全対策事業,漁業集落の生活排水等を処理する漁業集落排水施設の整備等を実施した。
4)海岸の環境保全
生態系や自然景観等周辺の自然環境に配慮した海岸整備を行うエコ・コースト事業を15年度までに全国48か所において実施するとともに,既設海岸保全施設の改良(離岸堤の潜堤化,人工リーフ化等)が実施されるよう,同事業の拡充を15年度に行った。
廃棄物の不法投棄事犯について重点的に監視取締りを実施したほか,廃船の不法投棄事犯の発生の抑制及び廃船の適正処理の促進を図るとともに,また,船舶の処理体制の確立を関係団体に働きかける等して,港湾,漁港,海岸等の環境保全に努めた。
■都市の緑地保全
1)大都市近郊緑地の保全
都市再生プロジェクト(第三次決定)「大都市圏における都市環境インフラの再生」を受け,まとまりのある自然環境の保全を目的とした施策を実施するとともに,首都圏における都市環境インフラのグランドデザインの策定に取り組んだ。
また,首都圏及び近畿圏における近郊緑地特別保全地区の指定を促進するとともに,地方公共団体及び緑地管理機構による土地の買入れを進め,緑地の保全利用のために必要な施設の整備を行う等,積極的な緑地保全措置を講じた。
2)都市緑地の保全・創出
都市緑地保全法に基づき,都市計画に緑地保全地区を定めている。(H15.3末現在295地区1,652ha(近郊緑地特別保全地区を除く))。これらの地区において,宅地の造成等の行為を規制するとともに,緑地保全等統合補助事業により,地方公共団体による土地の買入れや保全利用のための施設整備の機動的な実施を支援した。
また,都市域において貴重な緑地であるとともに,景観を構成する重要な要素となっている急傾斜地において,既存植生を活用し斜面の安全度を高める「緑の斜面工法」を積極的に導入した。
■温泉法による温泉保護
平成15年3月末現在における全国の温泉ゆう出源泉数は,2万7,043か所(うち自噴するもの5,180か所,動力によるもの1万3,328か所,未利用のもの8,535か所),ゆう出量は1日換算約384,411万トンに及んでいる。
また,温泉地は全国に3,102か所あり,温泉を利用する宿泊施設数は15,389軒である。温泉の利用等に当たっては,「温泉法」に基づき温泉の枯渇を防止し,将来にわたって有効に利用し得るよう温泉の掘削,増掘,動力装置の設置等の行為について規制を加え,その保護がなされている。
■野生生物の保護
1)野生生物の保護管理
鳥獣の保護を図るため,「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づき,国指定鳥獣保護区59か所(514千ha),都道府県指定鳥獣保護区3,882か所(3,118千ha)が指定されている(平成16年3月末現在)。
また,「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき,希少野生動植物種の捕獲及び譲渡し等の規制,生息地等の保護などの施策を推進するとともに,トキ,ツシマヤマネコ等について,引き続き給餌,巣箱の設置,モニタリング等の保護増殖事業を実施した。
2)野生生物保護思想の普及啓発等
野生生物保護センターにおいて,絶滅のおそれのある野生生物に関する保護増殖事業,調査研究,普及啓発等を行った。
また,ラムサール条約に登録された湿地を対象に,水鳥や湿地に関する調査研究及び普及啓発等を目的とし,水鳥・湿地センターを整備している。平成16年度末の開設を目指して,藤前干潟(愛知県)において環境学習・保全調査拠点施設の整備を行った。
3)野生生物保護に関する国際協力
ワシントン条約やラムサール条約等の多国間条約並びに日米,日豪,日中,日ロ及び日韓間における渡り鳥等の保護などに関する二国間条約などに基づき,野生生物保護のための国際協力を推進した。
また,東南アジア諸国における野生生物等の保全に関する調査協力事業を行った。
■環境衛生施設の整備
地域の生活環境の保全及び向上を図るためには,水道施設,下水道,浄化槽,農業集落排水施設等の整備が重要であり,観光地についても,その特性を考慮してその整備の推進に努めてきた。
|
|