平成17年度観光の状況
第5章 魅力ある観光地の形成
第1節 観光地の魅力の向上
1 総合的、広域的な観光地づくり支援
観光立国を目指すにあたっては、それぞれの観光地が魅力にあふれ、国際競争力を高めることが重要である。それにはビジット・ジャパン・キャンペーンによる情報発信を行うことと併せて、それぞれの観光地で行政と一体となった民間組織が、柔軟な発想で創意工夫をこらし、地域の特色を生かした個性あふれる観光地づくりを進めていくことが必要である。
そこで、意欲の高い民間人の積極的な活動により、地域の活性化に成功している例が数多く見られることを踏まえ、地域で観光振興に取り組む民間組織が実施する外国人受入環境整備事業や人材育成事業等に要する経費の一部を補助する「観光ルネサンス補助制度」を創設した。平成17年度は応募のあった22件の中から、学識者等からなる委員会に諮った上で、13件を補助金交付対象として選定した。
また、地域の幅広い関係者が一体となって、観光を軸とした良好な地域づくりを進め、将来的に補助制度への移行を目指す調査事業である「観光地域づくり実践プラン」についても新たに9地域を選定し、計33地域でNPO法人等が実施する調査検討等について支援を実施している(図5‐1‐1、図5‐1‐2)。
図5-1-1 観光ルネサンス事業
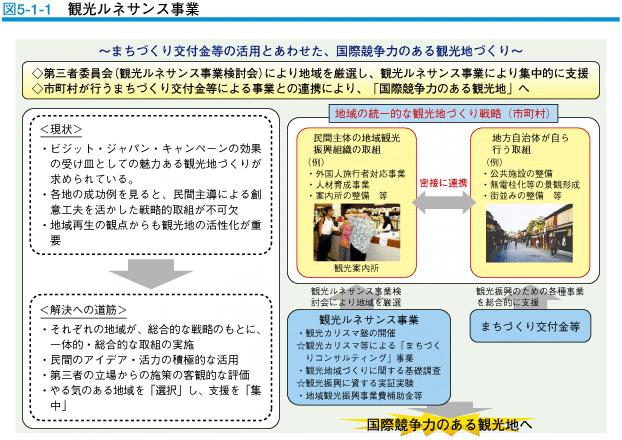
図5-1-2 観光ルネサンス補助制度・観光地域づくり実践プラン選定地域
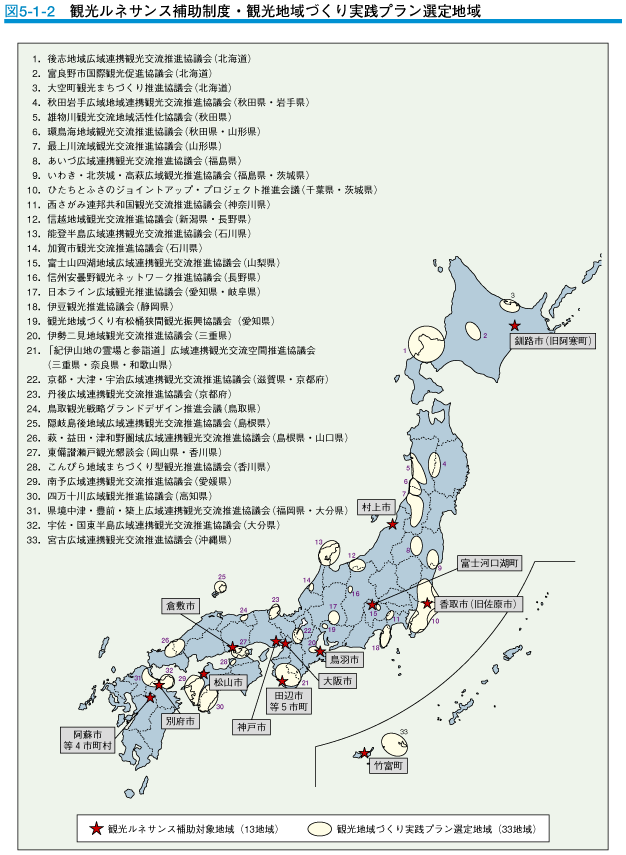
構造改革特区では、世界に発信する舞台芸術ブランドを確立し、芸術文化の振興と交流人口の増大を図るため、富山県及び南砺市から提案された劇場等における誘導灯・誘導標識に関する基準の適用に関する特例や、良好な都市景観を形成し、観光資源の魅力を高めるため、石川県金沢市から提案された案内標識及び警戒標識の寸法や文字の大きさを1/2まで縮小可能とするための特例等、地域の魅力を高めるための提案が実現した。これらの規制の特例措置を活用した特区計画は、平成18年3月に認定され、取組が動き出している。この他にも、濁酒(いわゆる「どぶろく」)の製造に関する免許要件の緩和の特例を活用した特区がこれまでに58件誕生するなど、特区を活用した地域の取組が着実に進んでいる。
また、地域再生においては、これまでに696件の地域再生計画を認定し、それぞれの地域において、地域の特性に応じた多様な取組が動き出している。平成18年2月15日には、地域再生本部において、「地域の知の拠点再生プログラム」を決定し、大学と連携した地域づくりを支援するための施策が様々な省庁の協力により取りまとめられたところである。同プログラムには「地域の観光を担う人材の育成支援」や「知の集積」等を生かした新しい観光振興への支援」等についても盛り込まれたところである。
都市再生においては、特に身の回りの生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を促進する「全国都市再生~稚内から石垣まで~」の取組において、観光振興を核とした取組が顕著である。例えば、都市観光の推進(稚内市、松山市、石垣市等)、歴史的たたずまいを継承した街並み・まちづくり(臼杵市、金沢市、香取市(旧佐原市)等)、環境共生まちづくり(飯田市、日南市等)等のテーマごとに共通の制度的課題を具体に解決するとともに、事業を集中的に実施している。また、平成15年度から17年度の三度にわたり、観光をテーマにしたもの等地域が自ら考え自ら行動する都市再生活動を「全国都市再生モデル調査」(平成17年度は587件の応募に対して、156件を選定)として推進・支援しており、そのうちの幾つかはまちづくり交付金等国の支援も受けて本格的な取組に発展している。
平成15年7月31日に観光立国関係閣僚会議で決定された「観光立国行動計画」の重要な柱の一つとして位置付けられている「一地域一観光」の主要施策として、「一地域一観光魅力ネットサイト構築」事業を実施した。これは、全国の市区町村及び国民に地域の魅力の発見・投稿を呼びかけ、それらを集約してデータベース化し、「発見!観光宝探しデータベース」としてインターネットで公開するもので、平成18年3月現在、合計で1,307件(全国1,134市区町村・地域;国民から173件)に上る観光魅力に関する情報が掲載されており、地域別、テーマ別に検索が可能なほか、一部の掲載案件については、英語翻訳化した。
掲載情報は、既に全国的に知名度の高い観光資源から身近な観光資源として地元で親しまれているものまで、また風景から食べ物、イベント等多岐にわたっている。
ホームページアドレス
http://www.kanko‐otakara.jp/
都市と農山漁村の共生・対流という国民運動の一環として、グリーン・ツーリズム(農山漁村で楽しむ余暇活動)の提案・普及を図るため、都市部のニーズに応じた農村情報の受発信機能の充実・強化、農村におけるグリーン・ツーリズムビジネスの起業家等の支援・育成、地域ぐるみで行う受入体制や交流空間の整備及びNPO法人等多様な取組主体の育成等について支援を行った。
さらに、農林漁業体験民宿の登録制度のより一層の活用を図るため「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」について、所要の改正を行った。
エコツーリズムの普及・定着を図るため、平成16年度に引き続き、1)エコツーリズム憲章、2)エコツーリズム推進マニュアル、3)エコツアー総覧、4)エコツーリズム大賞、5)モデル事業の5つの推進方策を実施した。優れた取組を表彰する「第1回エコツーリズム大賞」では、大賞1団体、優秀賞4団体、特別賞6団体を選定し、平成17年6月5日に愛・地球博において環境大臣表彰式を行ったほか、シンポジウムを開催し各団体の取組を紹介した。また、「モデル事業」では、13のモデル地区においてルールづくりやガイドの育成等各地区の状況に応じた支援を行うとともに、各モデル地区の取組を発表及び情報交換するためのオリエンテーションを11月に開催した。
さらに、新たに、エコツーリズム事業者等を対象に全国エコツーリズムセミナーを開催したほか、国立公園内でのエコツーリズム推進を目指し2地区で調査を実施した。
▲西表島のエコツアー風景

全国各地において、地域経済を支える各種産業と連携を図った産業観光が推進されている。平成17年10月には、八戸市において、八戸市商工会議所等地元観光関係団体による「全国産業観光フォーラム・イン・はちのへ」が開催された。また、同年6月、8月、10月には「全国産業観光推進協議会」の産業観光推進会議が開催され、産業観光の今日的意義や事業構造に関する分析を中間報告として取りまとめた。
平成16年度に実施した「映像等コンテンツの制作・活用による地域振興の在り方に関する調査」を受けて、ロケ推進及び映像コンテンツによる地域活性化のため、モデル事業として3地域を選定し、自治体、NPO法人、観光協会、地域住民等の地域内の関係組織が連携しワークショップを開催するなど、運営基盤のしっかりとしたロケーション支援組織の設立に向けた事業を実施した。
また、フィルムコミッションの活動に資するため、日本全国のロケーションに関する情報を一元化したデータベースの構築を進めるとともに、都市再開発との連携や、既存の資源を活用した望ましい撮影環境の在り方について調査研究を実施した。
さらに東京国際映画祭において、世界のフィルムコミッションネットーワークが集まり、今後の国際ネットーワークの新たな展開を模索するシンポジウム等を行う「第3回フィルムコミッション・コンベンション」を開催した。
また、「旅フェア2005」の場で開催された「メディア懇談会」において、映像制作者とロケ地の情報交換等が図られた。
サイクリングを楽しみながら地域の魅力をゆっくりと堪能する新しいツーリズム(サイクルツアー)を普及し、地域の活性化を地域の活性化を図ることを目的に、サイクリングロードと観光施設、川の親水施設、港湾緑地等との連携を強化する各種施策を総合的に推進しており、全国15モデル地区において、自転車を利用した観光促進策等を盛り込んだサイクルツアー推進計画に基づき事業を推進した。
1)北海道の観光の現状
北海道は、豊かな自然、雄大な景観、新鮮な味覚等多彩な観光資源を有し、また、各種の体験型観光、ホーストレッキングやオートキャンプ等のアウトドア活動に係る施設の充実、イベントの開催等により、観光地として国民にくつろぎの場を提供している。
北海道を訪れる外国人旅行者については、ビジット・ジャパン・キャンペーンの展開や道内各地における官民によるプロモーションの効果等もあり、東アジアを中心に増加している。また、近年ではオーストラリア等からのスキー客も大幅に増加している。
平成17年の来道者数は、同年7月に知床地域が世界自然遺産に登録されたこともあり、年後半は前年実績を上回り、前年並の1,280万人であった。
2)北海道における観光振興策の展開
第6期北海道総合開発計画においても、観光関連産業は地域経済を支える重要な産業として位置付けられており、観光基盤の整備、アウトドア活動に資する施設整備や農山漁村における自然体験型活動等の積極的支援により、北海道の特色を生かした観光振興の支援を行っている。
また、地域住民の活動を中心に沿道景観整備等による美しいドライブ環境の創造と地域資源の保全と活用による個性的な地域環境の創造により、競争力のある美しく個性的な北海道づくりを目指す「シーニックバイウェイ北海道」の本格的運用を開始し、平成17年5月には「支笏洞爺ニセコルート」、「大雪・富良野ルート」、「東オホーツクシーニックバイウェイ」の3ルートが指定されている。
▲ニセコ地域を訪れたオーストラリア人スキー客

1)沖縄観光の現状
沖縄県は、亜熱帯・海洋性気候風土の下、美しい自然景観、独特な伝統文化や歴史等の魅力的な観光資源を有しており、昭和47年の本土復帰以降、入域観光客数が約12倍に達するなど、観光・リゾート産業は、沖縄のリーディング産業として大きく成長してきた。
特に、近年、沖縄の自然・文化に対する全国的な関心が継続する中、美ら海水族館(平成14年11月)や国立劇場おきなわ(平成16年1月)、沖縄型特定免税店の空港外店舗(平成16年12月)等の観光関連施設の開業が相次いだこともあり、入域観光客数は平成14年以降、4年連続で過去最高を記録しており、平成17年は修学旅行生の増加や台風の影響が少なかったこと等から、550万人に達した。
2)沖縄の観光振興策の展開
沖縄の観光振興を図るため、沖縄振興計画、第2次沖縄県観光振興計画等に基づき、多様なニーズに対応した通年・滞在型の質の高い観光・リゾート地の形成に向け、各種施策を推進した。
観光振興地域制度の指定地域の拡大(平成17年3月)及び同制度の活用による観光関連施設の集積の促進や世界遺産の周辺整備、離島地域における観光案内標識や休憩施設等の整備等、質の高い観光地としての基盤整備を図ったほか、平成17年4月の第46回米州開発銀行(IDB)年次総会の沖縄開催に合わせて、主会議場となった沖縄コンベンションセンター等の整備を実施し、コンベンションアイランドの形成に向けた取組を行った。
また、観光客の多様なニーズに対応するため、観光産業に従事する人材の育成、バリアフリー観光の推進、沖縄空手を通じた交流の促進、体験滞在交流の促進等の事業を引き続き推進したほか、離島地域における観光情報の発信方策の検討を新たに実施した。
▲世界遺産の周辺整備(読谷村喜名番所復元)
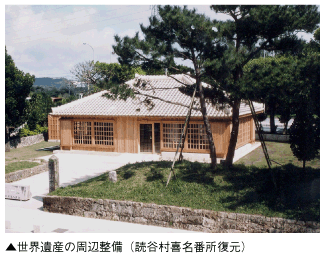
豪雪地帯対策基本計画において、観光・レクリエーション産業を振興することとされており、その実現に向けて冬期間観光の推進に資するクロスカントリースキー場等の親雪施設や冬期利用に配慮した地域の歴史的資源を生かした交流施設を整備した。
▲クロスカントリースキー場(新潟県十日町市)

多くの離島地域においては、主要産業である一次産業の低迷が続いており、観光が離島地域経済の新たな柱として期待が高まっている。しかし、離島は本土に比べて個性的で魅力的な自然環境や地域文化がある一方、アクセスの煩雑さや情報提供不足等の問題を抱え、高いポテンシャルを持ちながらも観光資源を十分に生かし切れていない。
そこで、観光による離島地域経済の活性化を図ることを目的として、モニターツアーによる検証を行う「離島ツアー交流推進支援事業」を実施し、離島における魅力的な観光資源の再発見や観光ルートの開発を行った。また、モニターが離島に滞在することにより、島の生活に直接触れ、新たな離島サポーターとして育つことも期待している。平成17年度においては、特徴ある地域資源の再発掘を行い、離島観光の活性化を図ることを目的として、山口県萩市の見島において事業を実施した。
奄美群島においては、地方公共団体が行う観光拠点としての園地等の整備、地域資源を活用した健康体験交流施設の整備、地域の歴史、自然、文化について観光客に案内できる人材育成等の事業に対する支援を実施した。
小笠原諸島においては、エコツーリズムの一層の推進を図るため、自然ガイドを養成した。また、フィールドツアーコースの整備や体験型観光交流プログラムづくり等、島内の受入体制の整備や新たな観光資源の発掘等を実施した。
平成17年3月の半島振興法改正により、「半島地域の自立的発展」が法目的に追加されたことを受け、多様な自然・文化資源の活用による観光を通じた半島地域の活性化を図るため、NPO法人や地域住民等が主体となって行う交流・連携の促進方策を検討した。また、平成17年度には、ワークショップ等を通じて、半島地域の観光を考える「半島ツーリズム大学」を国東地域(大分県杵築市)及び大隅地域(鹿児島県曽於市)で開催した。
国民のニーズに対応し、地域振興に寄与する総合保養地域の整備を図るため、地域住民、NPO法人、民間事業者等の多様な主体が連携して行うソフト面の充実や地域間交流の取組等の活動を促進した。
都市景観や防災性の向上、安全で快適な通行空間の確保、歴史的街並みの保全等を図るため、「無電柱化推進計画」(平成16年~平成20年)に基づき、幹線道路に加えて、主要な非幹線道路を含めた面的な無電柱化を推進した。
安全な駐車場と、そこから歩いて行ける美しい風景の撮影スポットを、ホームページや携帯電話で情報提供するため全国で募集を開始した(図5‐1‐3)。
図5-1-3 とるぱ募集パンフレット
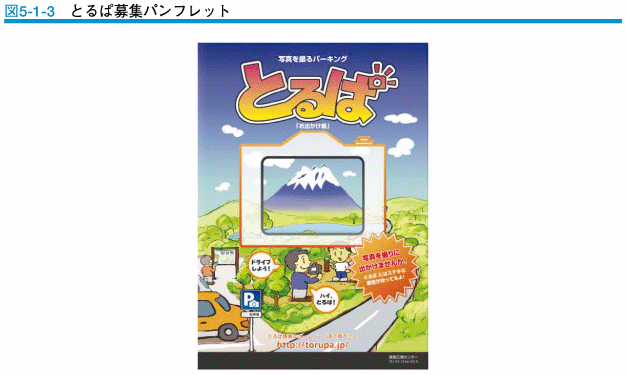
|
|