平成17年度観光の状況
第5章 魅力ある観光地の形成
第2節 自然環境の保全と観光への活用
1 自然・野生生物の保護と観光への活用
1)自然に親しむ運動の実施
自然との触れ合いの普及のため、毎年7月21日から8月20日までを「自然に親しむ運動」期間としている。平成17年においても、自然観察会等の自然との触れ合いを推進するための行事を全国の自然公園等で実施し、2,500件の行事に約72万人が参加した。また、この運動の中心行事である自然公園大会(第47回)を西海国立公園九十九島地区(長崎県佐世保市)において開催し、子供から大人まで多くの参加を得た。
2)全国・自然歩道を歩こう月間行事の実施
自然と触れ合いながら歩くことを推奨するため、毎年10月の1ヵ月間を「全国・自然歩道を歩こう月間」として全国の自然歩道等において各種行事を実施し、約370件の行事に約7.4万人が参加した。
3)自然公園指導員による利用指導の推進
自然公園の保護と適正な利用のため、自然公園指導員約3,000名を委嘱し、自然公園を訪れる人々に自然保護思想や利用マナーの普及啓発、安全利用等に関する指導等の推進を図った。
4)パークボランティア活動の推進
国立公園区域内の保護管理、利用者指導等を行うボランティアの活動を支援し、国立公園を訪れる観光客等の適正な利用を通して自然との触れ合いを推進した。
自然公園は「自然公園法」に基づく地域制の公園で、国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園の3種類があり、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることを目的としている(図5‐2‐1~表5‐2‐4)。
図5-2-1 日本全国の国立・国定公園の配置図
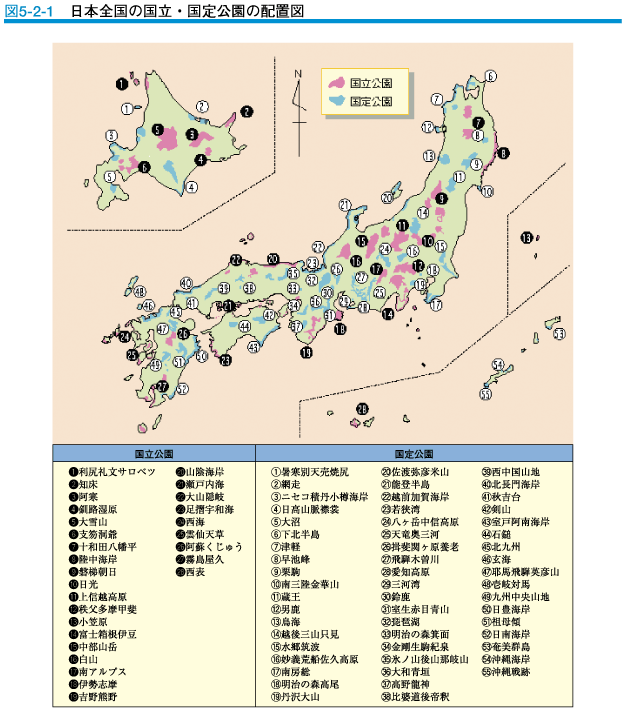
図5-2-2 自然公園利用者数推移
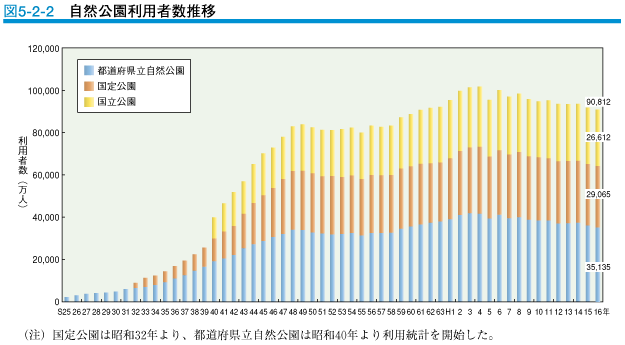
表5-2-3 自然公園の地域別面積
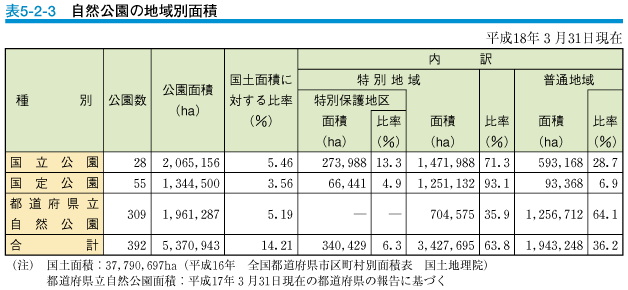
表5-2-4 国立・国定公園の海中公園地区
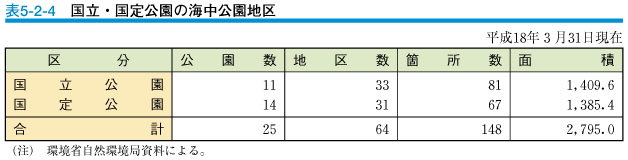
1)公園計画の見直し等
自然公園の保護及び適正な利用を図るため、公園の区域や計画を定めており、概ね5年を目途に見直し作業を実施している。平成17年度は、国立公園では釧路湿原国立公園、磐梯朝日国立公園等合計15公園について見直しを行い、国定公園では琵琶湖国定公園、沖縄海岸国定公園等合計6公園について見直しを行った。
2)保護と管理
国立・国定公園については、特別地域を指定し、当該地域内において、風致又は景観を損なうおそれのある一定の行為は、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないとしている。都道府県立自然公園については、国立・国定公園に準じて条例により特別地域が定められている。
国立・国定公園の特別地域の中でも、公園の核心的な景観地については、特別保護地区として指定し、最も厳しい保護規制を行っている。その面積は、全国立公園面積の13.3%、全国定公園面積の4.9%である。また、我が国の周辺海域には、熱帯魚、サンゴ、海草等の海中生物を主体とする優れた海中景観が存在する。このため、海中公園地区制度が設けられ、その保護と適正な利用が図られている。
国立・国定公園内で自然の風景地の保護と適正な利用を図ることを目的として、公益法人やNPO法人を、その申請により公園管理団体として指定し、自然の風景地の管理、公園利用施設の維持管理、公園内の自然情報の収集・提供等に係る市民等の自発的な活動を推進している。平成17年度までに、国立公園(阿蘇くじゅう国立公園等)で2団体を指定している。
国立公園等の貴重な自然環境を有する地域において、自然や社会状況を熟知した地元住民等を雇用し、外来生物によって在来生物への影響がある地区における駆除の実施、重要湿地への植生復元作業、里地里山の保全事業、山岳地における登山道の簡易な補修、海中公園地区におけるサンゴ礁景観の保護を目的としたオニヒトデ等の駆除等の国立公園等民間活用特定自然環境保全活動(グリーンワーカー)事業を行っている。
国立公園内の集団施設地区とその周辺の美化清掃事業を関係都道府県等の協力の下に実施するとともに、その他の主要な地域においても、美化清掃団体を現地に組織し、平成17年度も引き続き実施した。また、8月の第1日曜日を「自然公園クリーンデー」とし、関係都道府県の協力の下に全国の自然公園で一斉に美化清掃活動を行った。
▲自然公園クリーンデー(能登半島国定公園)
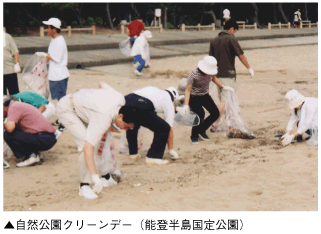
さらに、(財)自然公園財団をはじめとする関係機関により、自然公園内での歩道、便所、休憩所等の公共的施設の清掃、補修のほか、利用最盛期に集中する自動車の整理、美化清掃活動、公園施設等の維持管理、利用者に対する自然保護思想の普及啓発等の事業が行われている。
国においては、国立公園内の特別保護地区等にある民有地のうち、特に買い上げて保護することが必要なものを対象として、買上げにより公有地化を図る事業を行っている。
3)乗入れ規制地区の指定等
1)乗入れ規制地区
「自然公園法」により、国立公園又は国定公園の特別地域のうち環境大臣が指定する区域においては、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることが規制されている。これはスノーモービル、オフロード車あるいはモーターボート等の乗入れによる植生や野生動植物の生息・生育環境への被害を防止するためのもので、平成17年度末までに支笏洞爺国立公園をはじめとする27の国立・国定公園の50地区、計25万7,683haを乗入れ規制地区に指定している。
2)マイカー規制等
国立公園内においては、「国立公園内における自動車利用適正化要綱」に基づき、地方環境事務所、都道府県警察本部、地方運輸局運輸支局等で構成する連絡協議会において、道路交通環境に応じた規制方法を検討し、一般車両通行止め等の交通規制を行って、観光地の交通安全の確保、環境保全に努めている。
鳥獣の保護を図るため、新たに6箇所の国指定鳥獣保護区を指定(合計66箇所:面積538千ha)するとともに、ラムサール条約湿地として新たに20箇所の国内湿地を登録した(合計33箇所:面積130千ha)。多様な野生鳥獣が生息し、バードウォッチング等自然観察の場として親しまれている国指定鳥獣保護区において、野生鳥獣の生態等に関する普及啓発等を行った。
また、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき、希少野生動植物種の捕獲及び譲渡し等の規制、生息地等の保護等の施策を推進するとともに、トキ、アホウドリ、ツシマヤマネコ、シマフクロウ等について、引き続き給餌、巣箱の設置、モニタリング等の保護増殖事業を実施した。野生生物保護センターにおいては、絶滅のおそれのある野生生物に関する保護増殖事業に係る業務、調査研究、普及啓発等を行った。
さらに、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づき、希少な野生生物を捕食するなど、日本の生態系に被害を及ぼす外来生物を特定外来生物に指定し、輸入、飼養等の規制や防除を行うとともに、外来生物の輸入規制等に関する普及啓発を実施した。
1)子どもパークレンジャー事業の実施
日本の優れた自然の風景地である国立公園等において、小中学生に自然保護官の仕事等を体験してもらうことにより、自然保護や環境保全の大切さを学ぶ機会を提供した。
▲子どもパークレンジャー

2)国立公園における利用のための施設の整備
自然環境の保全に配慮しつつ、自然との触れ合いを求める国民のニーズにこたえ、安全で快適な利用を推進するため、平成17年度には、全国28の国立公園において事業を実施し、国立公園の核心となる特に優れた自然景観を有する地域における自然の保全や復元のための整備、自然学習や自然探勝のためのフィールドの整備、滞在型、高齢者・障害者対応型の公園利用を推進することにより地域の再活性化を図るための総合的な施設の整備、歩道、野営場、園地、公衆トイレ等利用の基幹となる施設の整備を進めた。
3)国定公園における利用のための施設の整備
地方の創意工夫を生かした自然と共生する地域づくりを推進するための自然環境整備交付金を創設し、国と地方の協力の下、自然との触れ合いの場の整備や自然環境の保全・再生を進めるため、平成17年度には、34都道府県において実施される国定公園の整備、国指定鳥獣保護区における自然再生事業及び長距離自然歩道の整備について交付した。
4)長距離自然歩道の整備
自然公園や文化財を有機的に結ぶ長距離自然歩道について、平成17年度においても引き続き、北海道、東北、首都圏、東海、中部北陸、近畿、中国、四国、九州の各長距離自然歩道において四季を通じて安全で快適に利用できるよう配慮しつつ整備を進めた。長距離自然歩道の計画総延長は約26,000kmに及んでおり、平成16年には、6,066万人が長距離自然歩道を利用した。
5)ウォーキング・トレイルの整備
豊かな景観・自然、歴史的事物、文化的施設等を連絡する歩行者専用道路や幅の広い歩道等を整備する「ウォーキング・トレイル事業」を全国15箇所で推進した。
6)大規模自転車道の整備
交通の安全を確保し、併せて心身の健全な発達に資する大規模自転車道の整備を推進した。
7)野性鳥獣との共生環境の整備
国指定鳥獣保護区であり、ラムサール条約湿地にも登録されている藤前干潟(愛知県)において、水鳥や湿地に関する調査研究及び普及啓発等を行う環境学習・保全調査拠点施設である「稲永(いなえ)ビジターセンター」と「藤前活動センター」の2施設を開設した。また、同様に宮島沼(北海道)においても、水鳥や湿地に関する普及啓発等を行う環境学習・保全調査拠点施設の整備を進めた。
|
|