平成18年度観光政策
第3章 魅力ある観光地の形成に向けた取組
第1節 観光地の魅力の向上
1 総合的、広域的な観光地づくり支援
訪日外国人旅行者の受け皿となる地域の魅力の増進を図るため、国際競争力のある観光地づくりを推進する観光ルネサンス事業を拡充して実施し、地域の民間と行政が一体となった観光振興の取組を総合的に支援する。
平成18年度は、地域ブランド商品開発や人材育成、案内所の設置等の地域の民間組織が行う観光振興事業等への補助、地域の観光動向・観光資源・観光地域づくりに関する基礎調査、観光客への情報提供や観光産業の高度化等の実証実験、観光カリスマ塾等の啓発事業を行う。
▲再生町屋を活用した観光案内所(新潟県村上市)

行政や地域住民、農林水産業者、商工業者等幅広い関係者が一体となって、当該地域にしかない観光魅力=「オンリーワン資源」を発掘するとともにそれを観光商品に組み込み、市場に積極的に流通させていく「地域観光マーケティング」活動を全国各地に普及させていくため、平成17年度に関東運輸局管内の地域を対象として設けた「観光まちづくりアドバイザリー会議」と同様の会議を全国の地方運輸局の管轄地域ごとに設けた上で、同会議を軸として、地域の自治体や観光協会、NPO法人等の民間組織を対象として行う「地域観光マーケティングセミナー」、一定の基準を満たす地域を半年ごとに1~3箇所選定し集中的なコンサルティングを行う「観光まちづくりコンサルティング事業」等の事業を全国で実施する。
また、このような地域の活動を多様な旅行会社との「連携」・「協働」により促進していくため、現行制度上は認められていない第3種旅行業者による着地型のオプショナルツアーの企画・募集の実施について、催行地域の限定や代金の精算方法等、消費者保護のための条件設定及びその担保の方法について専門家からなる検討会を開催して検討し、速やかに所要の制度改正を行う。
| (3) ユニバーサルデザインの考え方に基づく観光の促進 |
政府のバリアフリー化推進要綱や国土交通省のユニバーサルデザイン政策大綱において、観光地のバリアフリー化をはじめとした政策が当面の重点的な取組として位置付けられていることを踏まえ、特に移動制約者への対応に重点を置いて、送り手側である旅行会社の対応と受け手側である観光地の双方に関して、ハード・ソフトの両面から、ユニバーサルデザインの考え方に基づく観光促進に関する今後の取組の方向性について調査を行う。
| (4) 構造改革特区・地域再生・都市再生へ向けた取組 |
構造改革特区では、引き続き地方公共団体や民間事業者等から提案募集を行い、観光振興に資するものも含め、「実現するためにはどうすればいいか」という方向で対応するとともに、観光振興のために規制の特例措置を活用しようとする地方公共団体に対して、積極的に支援・助言を行っていく。また、特区で行われている規制の特例措置を評価した結果、特段の問題がないとされたものについては全国展開を進めていくことにより、特区の成果を全国に波及させていく。
また、地域再生については、引き続き、地域や民間の声を踏まえ、支援措置の充実に取り組んでいくとともに、観光振興のために支援措置を活用しようとする地方公共団体に対して、積極的に支援・助言を行っていく。特に、「地域の知の拠点再生プログラム」(平成18年2月15日地域再生本部決定)を推進し、観光振興のための人材育成等、幅広い分野において、大学等と連携した地域の自主的な取組を支援していく。
平成18年度においても、全国都市再生モデル調査を行い、地方都市の意欲と創意工夫をできる限り尊重しながら、観光や姉妹都市交流を含む様々なテーマによる地方都市の再生・再活性化を図ることとしている。
特に、「わたしの旅~日本の歴史と文化をたずねて~2005」のような関係省庁の取組との連携を強化しながら、まだ全国に眠っている地域の歴史や文化資源を生かした全国各地の都市再生への取組を支援する。
一地域一観光魅力ネットサイト事業については、インターネットで公開しているサイト「発見!観光宝探しデータベース」の掲載内容について、適宜更新を行い、内容の充実を図る。
都市と農山漁村の共生・対流という国民運動の一環として、グリーン・ツーリズム(農山漁村で楽しむ余暇活動)の普及を図るため、都市住民の農山漁村情報に接する機会の拡大、都市と農山漁村の出会いの場の設定や地域資源を活用した交流拠点の整備について、関係省と連携しつつ総合的に支援する。
エコツーリズムの普及・定着を図るため、引き続き5つの推進方策に取り組むとともに、国立公園内(1地区)におけるエコツーリズムの推進調査、2地区において全国エコツーリズムセミナーの開催等を行う。
全国産業観光推進協議会の活動を引き続き支援するとともに、地域に遍在しているハード・ソフト双方を含む産業資源の観光資源としての活用の推進を図ること、地域が主体となった継続的な産業資源の活用を図ること、地域内外の人々が見学・体験・学習等により地域の産業を通じた交流を図ること等、産業観光の振興に資する施策を検討する。
引き続き、日本全国のロケーションに関する情報を一元化したデータベースの運営を行うとともに、地域の都市再開発との連携や、既存の資源を活用した望ましい撮影環境の在り方について調査を行う。また、新たに、国内外からの撮影誘致につながる情報発信の方策についても課題として取り上げていく。
サイクリングを楽しみながら地域の魅力をゆっくりと堪能する新しいツーリズム(サイクルツアー)を普及し、地域の活性化を図ることを目的に、サイクリングロードと観光施設、川の親水施設、港湾緑地等との連携を強化する各種施策を総合的に推進しており、全国15モデル地区において、自転車を利用した観光促進策等を盛り込んだサイクルツアー推進計画に基づき事業を推進するとともに、モデル地区を追加募集する。
平成17年に世界自然遺産に登録された知床をはじめとする貴重な北海道の自然や景観の保全を進めるとともに、雄大な自然を活用したアウトドア活動の環境整備や、道路、空港、港湾等の交通基盤の整備を進め、北海道観光の振興を図る。また、沿道景観等の地域資源の保全と活用により、美しく個性的な北海道づくりを目指す「シーニックバイウェイ北海道」の展開等を進める。
▲世界自然遺産に登録された知床地域

近年、東アジアを中心に大幅に増加している外国人旅行者が広大な北海道を自動車で安心して自由に旅行できる環境を整備するため、地上デジタル放送等を活用して、観光情報等の地域情報をカーナビを通じて多言語で提供するシステムの構築を進める。
沖縄振興計画、第2次沖縄県観光振興計画等に基づき、多様なニーズに対応した通年・滞在型の質の高い観光・リゾート地の形成に向け、沖縄観光の一層の振興を図ることとしている。
平成18年度においても、観光振興地域制度の活用による観光関連施設の集積の促進や世界遺産の周辺整備、離島地域における観光案内標識等の整備を引き続き実施し、質の高い観光地としての基盤整備を推進する。
また、平成18年5月には第4回太平洋・島サミット(日・PIF(太平洋諸島フォーラム)首脳会議)が平成15年の第3回会議に続き沖縄で開催されることになっており、コンベンションアイランドの形成に向けた取組を引き続き進めていく。
さらに、観光客の多様なニーズに対応するため、バリアフリー観光の推進及び体験滞在交流の促進等の事業を引き続き推進するほか、新規施策として、離島観光地における自然環境に配慮した観光利便施設に関する調査検討を行う。
▲沖縄体験滞在交流促進事業(エイサー体験)

豪雪地帯における観光・レクリエーション産業の振興や雪国の特性を生かした多様な交流を推進するため、豪雪地帯対策基本計画に基づき、冬期間観光の推進に資する冬期利用に配慮した各種施設の整備等を実施する。
観光により離島地域経済の活性化を図ることを目的に、観光資源が充分に開発・活用されていない離島において魅力的な観光資源の開発、観光ルートの設定とともに、モニターツアーによる検証を行う「離島ツアー交流推進支援事業」を実施する。
奄美群島においては、地方公共団体が行う観光拠点としての園地等の整備や自然,伝統文化を体験するための施設の整備に対する支援を実施するとともに、群島内外との交流を促進するために地方公共団体が行う体験交流の推進や奄美群島の歴史、自然、文化について観光客に案内できる人材の育成等の事業に対して支援を実施する。
小笠原諸島においては、世界的にも貴重でかけがえのない自然を生かすためエコツーリズムの取組をより一層進めていくとともに、観光を中心とした島内産業の活性化を図るため、地方公共団体が行う自然公園、都市公園、観光交流施設、農業試験地等の整備や体験型観光交流プログラムづくりに対する支援を行う。
半島地域の自立的発展を目指し、多様な自然・文化資源の活用による観光を通じた半島地域の活性化を図るため、NPO法人や地域住民等が主体となって行う交流・連携の促進方策等を検討する。
国民のニーズに対応し、地域振興に寄与する総合保養地域の整備を図るため、地域住民、NPO法人、民間事業者等の多様な主体が連携して行うソフト面の充実や地域間交流の取組等の活動を促進する。
退職を契機として新たな人生を自然豊かな地方で過ごすことを希望している大都市圏等の「団塊の世代」のニーズを踏まえたロングステイや二地域居住に対応した地域の取組をモデル調査等の実施を通じて支援する。
都市景観や防災性の向上、安全で快適な通行空間の確保、歴史的街並みの保全等を図るため、「無電柱化推進計画」(平成16年~平成20年)に基づき、幹線道路に加えて、主要な非幹線道路を含めた面的な無電柱化を推進し、電柱・電線の無い良好な街並み景観の形成を図る。
▲無電柱化の推進
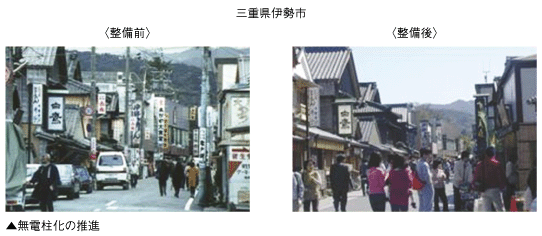
安全な駐車場と、そこから歩いて行ける美しい風景の撮影スポットを募集し、ホームページや携帯電話で情報提供を図る。
|
|