第II部 平成24年度に講じた施策(平成24年度施策)
第5章 国際競争力の高い魅力ある観光地域の形成
第2節 観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力ある観光地域の形成
6 温泉その他文化、産業等に関する観光資源の保護、育成及び開発
| (1) 温泉の保護並びに可燃性天然ガスによる災害の防止及び適正な利用の確保 |
平成23年3月末現在における全国の温泉湧出源泉数は、27,532か所(うち自噴するもの4,413か所、動力によるもの13,396か所、未利用のもの9,273か所)、湧出量は1日換算約386万トンに及んでいる。また、温泉地は全国に3,108か所あり、温泉を利用する宿泊施設数は13,754施設である。温泉の利用等に当たっては、「温泉法」に基づき温泉の枯渇を防止し、将来にわたって有効に利用し得るよう温泉の掘削、増掘又は動力装置の設置等の行為について規制を加え、その保護がなされており、都道府県等に対し今後も引き続き適切な助言を行う。
さらに、温泉利用の効果が十分期待され、健全な保養地として大いに活用される温泉地を「温泉法」に基づき、「国民保養温泉地」として指定しており、平成24年3月末現在、91か所が指定されている。
我が国には、世界文化遺産をはじめ独自の歴史に根差した文化財、多彩なまつりや伝統芸能等の無形文化遺産が全国各地に多数存在するほか、国内外の秀逸な作品を紹介する美術館・博物館等の文化施設やアートフェスティバルがあり、文化的な観光資源の宝庫となっている。また、我が国の映画・アニメ・ゲーム等のメディア芸術、食文化等も「クールジャパン」と呼ばれ国際的に注目を集めている。
また、映像を通じて地域の資源を広く紹介することを目的に、日本最大の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル&アジア」内に設立した観光部門「旅シヨーット!プロジェクト」を通じて、旅をテーマにした作品を全国各地から募集し、その中から入選作品を選考し、優秀作品には国土交通大臣賞を授与した。受賞作品は、アシアナ国際短編映画祭などで上映した。
我が国で実施される最高水準の舞台芸術(音楽、舞踊、演劇、伝統芸能、大衆芸能の各分野)及び、劇場、音楽堂が中心となって地域住民と芸術関係者等とともに取り組む優れた舞台芸術の制作、教育普及、人材育成等を支援することにより、舞台芸術の創造を活性化させ、日本の文化に親しむことができる機会の増加に寄与している。
定期演奏会(新潟市民芸術文化会館(りゅーとぴあ))

| (4) 国民の各種文化活動の発表、競演、交流の場の提供 |
国民の文化活動の取組、成果を全国規模で発表する機会を提供する国内最大の文化の祭典である「国民文化祭」を、都道府県との共催で開催することにより、地域間の交流の活発化、開催地の特色ある文化の全国発信等に加え、出演者、観客等を含めた観光客の誘致に一定の成果を上げている。平成24年度は、「第27回国民文化祭・とくしま2012」を9月1日から12月14日まで、徳島県内全24市町村において開催した。徳島県での開催は、平成19年度の第22回大会に続き、全国初の2度目となる。今大会では「文化の力でまちづくり!」をテーマに、前回大会で4大モチーフとして位置付けた「阿波おどり」「阿波人形浄瑠璃」「阿波藍」そして、徳島県がアジア初演の地である「ベートーヴェン第九」をはじめ、「あわ文化」の魅力を全国に発信する84の事業を実施した。なお、平成25年度は、山梨県で「第28回国民文化祭・やまなし2013」を開催する。
第27回国民文化祭・とくしま2012「あっ!わぁ!発見フォーラム」での感動のフィナーレ

| (5) 外国人富裕層向けの和のコンテンツの情報発信 |
ラグジュアリー・トラベル市場におけるディスティネーションとしての日本ブランドの価値の向上を図り、訪日旅行を促進するため、ラグジュアリー・トラベル市場に特化した旅行博(商談会)に参加し、和のコンテンツ情報等の発信を実施した。また、訪日旅行商品造成を促進するため、平成25年3月に実施したJLTF(Japan Luxury Travel Forum)においては、富裕層旅行商談会として有名なILTM(International Luxury Travel Market)が京都で初めて「ILTM Japan」を開催する契機を捉え、連携した取組を実施した。具体的には海外バイヤー及び海外メディアを三重・岡山地域に招請し、各地域のコンテンツ紹介等を行うとともに、富裕層事業に取り組む国内セラー、海外バイヤーや海外メディア等を対象としたフォーラム「ILTM JAPAN 2013 Opening Forum in association with JLTF」を実施した。
平成24年10月に、長野県岡谷市において開催された「全国産業観光フォーラム」を後援するなど関係者の連携による産業観光の推進を図っている。
平成32年(2020年)オリンピック・パラリンピック競技大会の東京招致に関しては、ロンドンオリンピック期間中にJOC(公益財団法人日本オリンピック委員会)が設置したジャパンハウスにおいて招致活動が行われ、日本食の提供、生け花や琴演奏のイベント等を通して、文化・観光等の日本の魅力が発信された。また、安倍総理大臣のリーダーシップの下、国内外において政府全体で招致活動をしっかりと支援するため、平成25年3月1日に「第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の東京招致に関する閣僚会議」が設置され、第1回会合が開催された。さらに、3月4日~7日、IOC(国際オリンピック委員会)評価委員会が立候補都市の視察等のために来日した際、公式歓迎行事への安倍総理大臣の出席や、内閣官房長官及び文部科学大臣による評価委員会へのプレゼンテーション等、政府として全面的に協力をした。開催都市が決定するIOC総会(平成25年9月開催予定)に向けて、引き続き、招致委員会等と連携・協力しつつ取り組む。
地域のハイレベルな「観るスポーツ」(プロ野球、Jリーグ、大相撲、F1等)や、世代を超えて人気を集める「するスポーツ」(マラソンやトレッキング、トライアスロン等)、地域をあげてスポーツイベントを誘致・支援する「支えるスポーツ」の3つを柱とするスポーツ資源を活用し、訪日外国人旅行者の増加、国内観光振興につなげるスポーツツーリズムを推進した。平成24年4月には、我が国のスポーツツーリズムの中核的組織として、地域スポーツコミッションの設立や、国際スポーツイベントの誘致・開催への支援等を担うJSTA(一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構)が設立された。JSTAは観光庁と連携を図り、平成24年11月にスポーツツーリズムの取組についての様々な事例を紹介する「第1回スポーツツーリズム・カンファレンス」を開催するとともに、平成25年3月には、地方公共団体、スポーツ団体、旅行業者等の様々な関係者が一堂に集まり、スポーツツーリズムに関して情報交換や商談を行う「第1回スポーツツーリズム・コンベンション」を開催した。さらに、公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会と連携してスポーツツーリズム賞を初めて創設し、スポーツツーリズムの機運醸成を図った。
3月に来日したIOC評価委員会におけるプレゼンテーション会場

(JSTAロゴマーク)
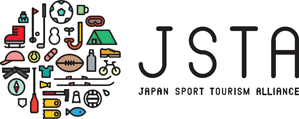
離島地域において、交流人口拡大による自立的発展を促進する観点から、全国の離島が集まり観光・交流事業情報を都市住民に発信する交流事業「アイランダー」を開催した。また、離島地域自らの創意工夫による、先導的な地域活性化への取組の実施及びその成果を離島地域全体の取組に反映させるための「離島の活力再生支援事業」を実施した。
観光を中心とした地域間交流の促進を通じて、半島地域の自立的発展を図るため、地域の活動主体によるワークショップ等において、農林水産物、景観、歴史・文化等の半島地域の地域資源を生かしたツーリズムの取組等について検討するなど、地域の内発的な取組を促進する方策の実証調査を行った。今後も、引き続き半島地域の観光振興を促進していく。
「豪雪地帯対策基本計画」に基づき、冬期の道路交通の確保や、生活環境施設の整備等克雪対策を推進するとともに、雪に強い公園の整備を推進した。また、雪に親しむことをテーマに全国各地で実施した雪まつりや冬季スポーツ教室等の交流活動状況について、関係自治体に情報提供を行っており、今後、雪国と他地域との多様な交流の推進を図る。
全国の離島が集まり観光・交流事業情報を都市住民に発信する「アイランダー」の様子

東京都八丈島で行われたトライランド・アスロン大会の様子

「総合保養地域整備法」に基づく基本構想を定める道府県を対象に、特定施設等の整備に関する進捗状況調査や、基本構想の見直しについて関係省で調整を行っており、引き続き実施する。
| (10) マリンレジャーを活用した地域観光の振興等 |
マリンレジャーに適した海洋空間等、地域それぞれが有する潜在的な海洋資源を生かした地域産業の活性化の観点から、関係省庁、港湾・河川・漁港等の管理者、マリンレジャー関係団体、プレジャーボート利用者等が連携・役割分担の下で、係留保管能力の向上と放置等禁止区域の規制措置を両輪とした対策により、プレジャーボートを円滑に収容するための取組を推進する。
| (11) 水辺における環境学習・自然体験活動の推進等 |
地域の身近な水辺・海辺における環境学習・自然体験活動を推進するため、市民団体や教育関係者、河川管理者、港湾関係の行政機関等が連携して、子どもの水辺を登録する「『子どもの水辺』再発見プロジェクト」や、水辺に近づきやすくする河岸の整備等を行う「水辺の楽校プロジェクト」を推進するとともに、「海辺の自然学校」を開催した。
また、近年、カヌーやラフティングをはじめとした水面利用や川での自然体験活動が活発化、多様化していることを踏まえ、全国の川で活動する市民団体等で構成される「特定非営利活動法人川に学ぶ体験活動協議会(RAC)」等と連携し、川で安全に活動するための指導者の育成を支援している。さらに、河川における水難事故を防止するため、河川の安全利用に関する啓発等を推進している。加えて、効果的な普及啓発を推進するため、小中学校への情報提供の強化を図り、地域のニーズにあった支援を推進している。
「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」に基づき事業計画を認定し、地域資源を活用した観光産業を促進した。また、当該事業計画を推進するために必要な機械・施設等の整備を支援したほか、6次産業化の先達や民間の専門家(ボランタリー・プランナー、6次産業化プランナー等)による個別相談の実施、新商品の開発等の取組の支援等を行うことにより、観光等の地域ビジネスの展開等を図った。
さらに、FAO(国連食糧農業機関)のGIAHS(世界農業遺産)に認定された佐渡、能登地域については、地域の農林水産物のブランド化、商品開発や観光振興等の取組の周知等により、農山漁村地域の振興を図った。
【再掲】第5章第1節1(4)
|
|