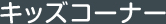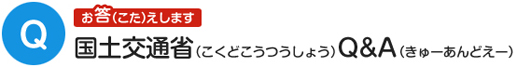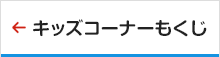国土交通省Q&A
住宅(じゅうたく)
Q 暮らしやすい家(地震に強く、環境にやさしい)を増やすためにどのような取り組みを行っていますか?
Q 建物の安全を守るために、どのような対策をとっていますか?
Q 地震による建物の被害を防ぐために、事前にどのような対策をとればいいですか?
 |
暮らしやすい家(地震に強く、環境にやさしい)を 増やすためにどのような取り組みを行っていますか? |
 |
国土交通省では、環境に優しく、安全で快適に暮らす家を増やすために様々なことをしています。 例えば、大きな地震にも耐えられるよう住宅の耐震性を強化するための工事に必要な資金について補助をしたり、環境に優しい住宅を買う場合に、通常より低い金利でお金が借りられるようにしています。 そのほか、お年寄りの方や体の不自由な方など、誰にとっても暮らしやすい住宅になるよう、住宅の中の段差をなくしたり、廊下を広くしたり、トイレや廊下などに手すりをつけたりした「バリアフリー住宅」の取得や改良についても支援を行っています。 |
 |
建物の安全を守るために、どのような対策をとっていますか? |
 |
ビルやマンション、一戸建て住宅などの建物を建てる場合には、それらの建物を使うみなさんにとって、安全で快適になっていることが大切です。 安全で快適な生活空間を確保するために「建築基準法(けんちくきじゅんほう)」という法律で建物の安全性などの基準を定めています。 この安全性とは、地震や台風、大雪などの自然災害や火事から建物を守る基準を指しています。 また安全性以外にも、気持ちよく建物が利用できるために、日当たりや風通しなどの基準も「建築基準法」で定めています。 建物を建てようとする人は、建物の設計がこれらの基準を守っていることを明らかにするために、公的な検査を受ける必要があります。この公的な検査を、「建築確認」といい、安全に建物を建てるために作られたシステムです。 「建築確認」は、検査を行う資格を持つ建築の専門家がいる機関(都道府県や市、民間の検査機関)が行うこととされています。 国土交通省では、建物に関する法律が日本全国で正しく守られるよう、都道府県、市町村で建築を担当する専門家の協力を得て仕事をしています。 |
 |
地震による建物の被害を防ぐために、 事前にどのような対策をとればいいですか? |
 |
日本は地震が多い国で、いつどこで大規模な地震が発生してもおかしくない状況にあります。 平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、約6400名の尊い命が失われましたが、この約9割の人が建物の倒壊などにより亡くなられており、地震による被害を小さくするためには、建物を地震に対して強くすることが最も重要といえます。 建物の耐震性の基準はこれまでに発生した地震による建物の被害を踏まえて定められており、昭和56年には大きな改正が行われました。阪神・淡路大震災でも昭和56年以前に建築された建物に多くの被害が出ています。 こうしたことから、平成7年に耐震改修促進法という法律を定めて、建物の耐震診断・耐震改修を進めています。耐震診断というのは皆さんが健康診断を受けるのと同じように建物の地震に対する強さを診断することです。耐震性が不十分な場合は壁や柱を補強するなどの耐震改修を行って地震に強い建物にすることが重要です。
|