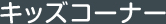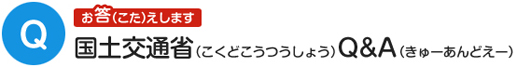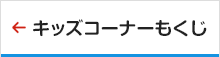国土交通省Q&A
住宅(じゅうたく)
Q 家の中で地震の被害を防ぐには、どのような準備が必要ですか?
Q 地震が発生して建物に被害が出たときは、どのような応急対策とられますか?
Q 欠陥のある住宅だと分かったときは、どのような対策をとりますか?
Q 空き家が増えるとどのような問題が起きますか。何か良い対策はありますか?
 |
欠陥のある住宅だと分かったときは、どのような対策をとりますか? |
 |
新しい住宅の柱や梁(はり)などの建物を支える部分の欠陥や雨漏りが見つかった場合、その住宅が引き渡されてから10年の間は、住宅を売ったり建てたりした会社が責任を持って修理をしなければならないと法律で決められています。 その会社との間でトラブルになった場合には、裁判に訴えるほかに、建築士と弁護士が間に入って解決する方法もあります。 他にも、住宅に関する様々なトラブルについての相談を、専門の建築士が無料で受け付けている「住まいるダイヤル」という相談窓口があり、気軽に相談することができるようになっています。
|


住まいるダイヤルはこちら: 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(http://www.chord.or.jp/)
参考ページ: 住まいのあんしん総合支援サイト(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html)
 |
空き家が増えるとどのような問題が起きますか。何か良い対策はありますか? |
 |
空き家が増えていますが、その中でも手入れがされずボロボロになった空き家は、屋根や壁が風で飛ばされそうになり、周りに住む人に迷惑がかかるため大きな問題です。それ以外にも街全体の見た目を悪くしてしまうなど色々な問題が起きてしまいます。 空き家の中にはこうしたボロボロのものだけでなく、まだ使えるものもあります。使える空き家については、他の人に売ったりして使ってもらうことが大切です。使えないようなボロボロの空き家については、そのままにせず壊してしまうことも大切です。 令和5年には、「空家等対策の推進に関する特別措置法」という空き家の法律が改正されました。この法律によって、市町村は空き家対策に特に力を入れる区域を定めたり、既に周りに迷惑をかけているような空き家の持ち主に加えて、そのまま放置すれば周りに迷惑をかけることになってしまいそうな空き家の持ち主に対しても、修理をするように指導したりすることができるようになりました。引き続き、国は市町村がしっかりと空き家対策を進められるよう支援していきます。
|
参考ページ:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html)
 |
地震対策の一環として行う住宅の耐震化率の向上を、すでに建ってしまってる家が多い中でどのように行うのですか? |
 |
住宅の耐震基準は建築基準法に定められていますが、耐震基準が強化された1981年よりも前に建設された住宅の中には、耐震性が不十分な住宅もあります。 国土交通省では、住宅の耐震化の目標として「2030年までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消」を目標に掲げて、様々な取組を進めています。 住宅の耐震化を進めるためには、古い住宅にお住まいの方々に対し、[1] 耐震化の必要性を理解してもらうこと[2] 耐震化に必要な改修などの費用の負担を軽くすることが重要となります。 このため、国土交通省では、都道府県・市町村や関係団体と連携して、各種パンフレットや動画により耐震化の必要性をPRしたり、耐震診断や耐震改修に対して補助金による支援などを行うことで、耐震性が不十分な住宅の耐震化を進めています。 これからも取組を進めて行きますので、皆様もぜひ、ご家族や離れたところにお住いのご親戚などと、耐震化の必要性についてお話し頂ければと思います。 参考ページ:日本建築防災協会 |