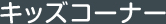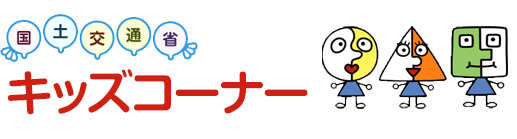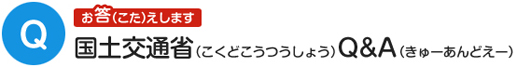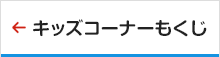国土交通省Q&A
都市(とし)・まちづくり
Q 都市計画ではどのようなまちづくりを進めていますか?
Q 私たちの身の回りにある公園は全国に何カ所ありますか?また、どのような目的で造られていますか?
Q 地震に強いまちづくりのために、どのような取り組みを行っていますか?
Q コンパクト・プラス・ネットワークとはどんなまちづくりですか?
Q スマートシティという言葉を聞きますが、何のことですか?
Q 賑わいがある楽しいまちをつくるために、どんな取組を進めていますか?
 |
都市計画ではどのようなまちづくりを進めていますか?
|
 |
「都市計画」とは、快適で安心して暮らせるよいまちづくりのための計画です。 まちの環境を守り、まちの将来像、土地の利用の仕方などを決め、必要な道路、公園などまちに必要なものの位置・配置を決めて、目標とするまちを作り上げるものです。 まちには、多くの人が集まり、働き、学び、生活しています。もし、自分の都合だけで生活したり、仕事をしたりすると、他の人に迷惑をかけたりする場合があります。 例えば、住宅地の真ん中に、大きなお店や工場を建てる人がいたら、周りの住宅では陽が当たらなくなり、静かな住宅地だったところがお店や工場に出入りする人や車で騒がしくなり、道路も車であふれ、交通事故なども発生する恐れがあります。多くの人が生活しているまちでは、土地の使い方や建物の建て方にルールが必要なのです。 また、まちで生活し、働く上で、道路、公園、下水道などは欠かすことができません。例えば、建物の建つ土地だけがあっても道路などがなければ生活できません。道路、公園、下水道などは、住宅などの配置、人や物の流れなどを考え、計画を立て、整備をしていくことが必要です。 さらに、新しいまちをつくったり、古くなったまちをつくり直すためにも、そのまちの役割などを考えて、計画的に進めていくことが大切です。 このように、都市計画では、土地の使い方や建物の建て方についてのルールをはじめ、まちづくりに必要な多くのことがらを定めながら快適で安心して暮らせるよいまちづくりを進めています。
|
絵で見る都市計画:みんなで 進める まちづくりの話(http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/index.htm)
 |
私たちの身の回りにある公園は全国に何カ所ありますか?また、どのような目的で造られていますか? |
 |
みなさんもきっと遊んだことがある公園。全国にはどのくらいの都市公園があると思いますか? 全国にはなんと、約11万5千カ所、約13万1千ha(東京ドームの約2万8千個分)もあります。 そのほとんどは、みなさんが住んでいる地方公共団体(「○○県」や「○○市」など)が作って、手入れをしている公園です。 他にも、国土交通省が作っている大規模な公園(国営公園)が全国で17箇所あります。 公園は、皆さんが遊ぶ場所なのはもちろんですが、 その他にも ○公園の中の植物が光合成をして、二酸化炭素を吸収することで、地球温暖化の防止に役だったり ○大きな地震や津波といった災害が起きたときに、ひなん場所になったり ○きれいな桜の木が、お花見の名所になって、有名な観光スポットになったり いろいろな役割を果たしています。 みなさんもどんどん公園で遊んで、どんなふうに公園を使うことができるか、是非見つけてみてくださいね。
|
 |
地震に強いまちづくりのために、どのような取り組みを行っていますか?
|
 |
都市部には、古くなった木造住宅やビルなどの建物が集まっていて、人が多く集中している割には、道路や公園が少ない地域があります。このような地域では、強い地震が起こったときに、建物の倒壊や大規模な火災が発生する危険があります。 建物の倒壊や大規模な火災が発生すると、巻き込まれてケガや火傷(やけど)をするだけでなく、倒壊した建物が道路をふさいでしまうことにより、地域の皆さんの避難や、救助・消火活動が遅れてしまいます。 そのため、国土交通省では、建物の倒壊を防ぐために建物の耐震化※や、大規模な火災を防ぐために燃えにくい建物につくりかえる、火災からすばやく逃げるための道路をつくる、避難できる場所となる公園をつくるなどの、対策を進めています。 ※ 「耐震化」とは、強い地震でも、建物が倒壊しないように補強すること。もしくは、倒壊しないような構造の建物につくりかえること。
|
 |
コンパクト・プラス・ネットワークとはどんなまちづくりですか?
|
 |
日本の人口は減少に向かっていて、空き家が増えたり、お店のお客さんが減って閉店が増えたりしています。同様に病院、スーパーも利用する人が減ると経営が成り立たず、撤退してしまい周囲の住民は生活が不便になってしまいます。 そこで、市役所、病院、スーパーなどみんなが利用する施設をまちのなかのまとまった場所に集め、その周囲に住む、子どもやお年寄りを含めた誰もがバスや電車の公共交通を使って手軽に行き来できるまちづくりのことを、コンパクト・プラス・ネットワークといいます。 コンパクト・プラス・ネットワークを進めることの効果として、 ・病院やスーパーなどの施設が維持される。 ・お年寄りも外出しやすくなって、消費が拡大し、地域の「稼ぐ力」が増す(地域経済の活性化)。 ・まとまって住むことで、市役所、学校などの行政サービスが効率化される。 などが見込まれます。
|
 |
スマートシティという言葉を聞きますが、何のことですか?
|
 |
最近、インターネットを活用したサービス、ロボット、人工知能(AI)、ビッグデータといった新しい技術の開発が急速に進んでいます。これらの新しい技術は、すべての人により豊かな暮らしをもたらす可能性があります。 国土交通省では、都市や地域の課題を解決するために、こうした技術をまちづくりに取り入れた都市や地区を「スマートシティ」と呼んで、そこに住む人がより住みやすくなることを目指しています。 たとえば、高度経済成長に建てられた大規模な住宅団地では、完成から30~50年が経過して住民の高齢化が進み、バス停まで歩くことが難しくなって買い物や通院ができなくなるといった問題が生じていることがあります。 スマートシティでは、住民がいつ買い物に行き、何を買うのか?いつ病院に行くのか?などのデータを新しい技術を活用して分析し、住民の移動に便利に使える自動運転対応の小型カートを導入することで住民の外出を促したり、買い物に行くのが難しい方の近所の公園に自動運転の移動販売車が来れるようにすることで、住民の不便を解消することなどがイメージされます。 また、未来の街をもっと便利で安全にするために、街全体をデジタルで再現する「PLATEAU(プラトー)」という取組を進めています。この3Dデジタル地図を使うことで、まちづくりや、災害が起きたときにどう対応するかを考える際に役立ちます。 現在、世界中で、デジタル技術を活用した様々なプロジェクトが進められています。
|
 |
賑わいがある楽しいまちをつくるために、どんな取組を進めていますか?
|
 |
賑わいがある楽しいまちをつくるために、国土交通省では「居心地が良く歩きたくなる」ウォーカブルなまちづくりを進めています!ウォーカブルなまちづくりとは、道路、公園、広場などの公共空間を、歩いて、集まって、交流するのが楽しくなるような、人に優しい空間へと変えていくまちづくりです。 例えば、車が入ってこない広くて安全な道路の中で、座っておしゃべりできるようなカフェを開いたり、みんなが楽しめるようなイベントを行ったり、人が集まりたくなる場所を増やしています。さらに、緑や花で街をきれいにして、歩くだけでも楽しくなる工夫もしています。こうした取組で、みんなが歩きたくなり、にぎわいのある楽しいまちを目指しています! 参考ページ: ウォーカブルポータルサイト(https://www.mlit.go.jp/toshi/walkable/index.html)
|