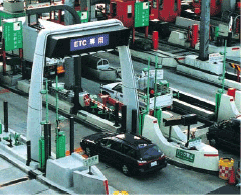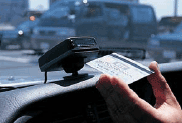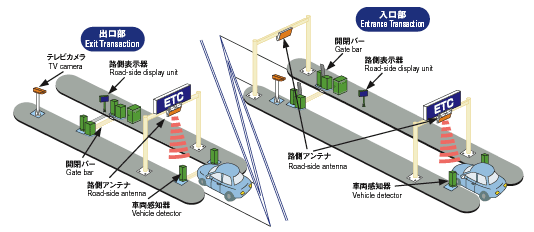日本においても、キャッシュレス化による利便性の向上、料金所渋滞の解消、管理費の節減等を目的にETCサービスがスタート。日本のETCは、車種や距離によって異なる複雑な料金体系に対応でき、1台の車載器で事業主体の異なる複数の有料道路を利用することが可能です。
ETCの開発にあたっては、(1)全国に共通のシステムとするため全国の有料道路で規格を統一、(2)確実な路車間通信とするため5.8GHz双方向通信(アクティブ方式)を採用、(3)多機能・拡張性を確保するため車載器とICカードによる2ピース方式を採用し、ICカードを多目的に利用可能なものにする、(4)高いセキュリティを確保するため、CPU等を内蔵し外部端末機器との相互認証や記録データの暗号処理が可能なICカードを使用、を目標としました。
全国に展開するETC
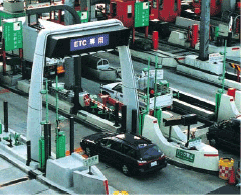
車載器とICカード
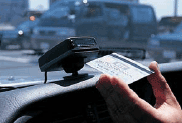
ETCの仕組み
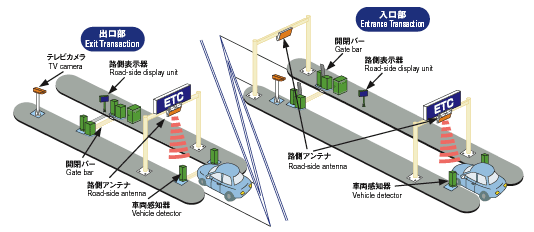
ETC導入の目標
ETCの普及率が高まることにより料金所の処理容量が増加すると、有人料金所ブースを減少させることが可能となり、経費の削減の効果が現われてきます。日本では、2002年度中にETCを道路4公団の料金所における主要な料金所約900ヵ所に導入することを目標としています。
これは全国の料金所の約7割にあたり、料金所渋滞発生箇所のほぼ全域でETCが導入されることになります。これにより全体交通量の約9割がETCを利用可能となります。今後、利用者の利便性をさらに向上するために、原則としてすべての料金所にETCを導入することとしています。
|
 日本のETCの特徴
日本のETCの特徴
 日本のETCの特徴
日本のETCの特徴