|
|
|
|
|
|
1.新道路五箇年計画策定の背景
(1)社会・経済・生活と道路の関わり
| 1. |
道路はライフラインの安定供給に寄与 道路は、国民生活に不可欠な、電気・電話・ガス・上下水道などの収容空間を確保するとともに、共同溝などの整備によりライフラインの安定供給に大きく寄与している。 〜道路占用割合:上下水道、電気:100% 電話:98% ガス:90% |
表 各ライフラインの道路下に占める割合(全国)
| 総延長(km) | うち道路占用延長(km) | 割 合 | 備 考 | |
| 電 気 | 41,000 | 41,000 | 100% | H9.3現在 |
| 電 話 | 666,000 | 656,000 | 98% | H9.3現在 |
| ガ ス | 199,000 | 179,000 | 90% | H7.12現在 |
| 上水道 | 498,000 | 498,000 | 100% | H8.3現在 |
| 下水道 | 255,000 | 255,000 | 100% | H8.3現在 |
| 地下鉄 | 743 | 568 | 76% | H9.4現在 |
| 注1) |
電気、電話は管路であり架空線は含まない。 |
| 注2) | 仮に各施設が道路占用部分の用地を取得して建設した場合、上記6事業の用地買収約180兆円が増大(建設費 約360兆円→540兆円)すると試算され、道路空間の活用がライフラインの低廉な安定供給に寄与している。
<資料>建設省 |
| 2. | 道路の防災空間としての役割 阪神・淡路大震災の際には、幅員の広い道路がライフラインの確保とともに延焼の防止に大きな効果を揮した。 〜延焼停止率:幅員12m以上:100%、4m未満:20%弱 |
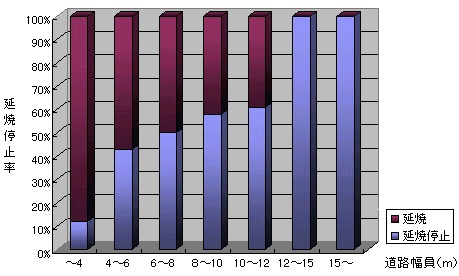
| 図 | 道路幅員別の延焼停止率(阪神・淡路大震災における神戸市長田区の事例) |
| 注) | ただし、当時は無風状態であったこと、発火箇所、延焼方向を考慮していないため、延焼停止線の形成が他の要因による可能性があることも留意。
<資料>建設省 |
| 3. | 国内輸送における自動車交通の役割の拡大 国内旅客、貨物輸送における自動車交通の占める割合は年々増加している。 〜自動車交通の分担率:旅客(人キロ) :22.8%(S35)→60.0%(H7) |
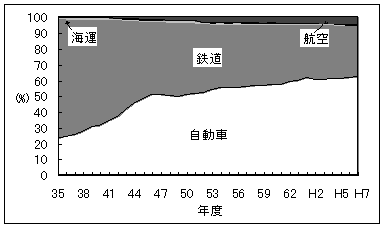 |
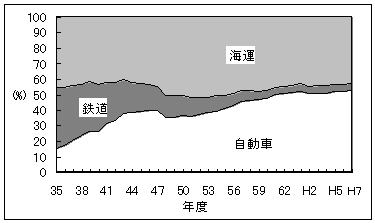 |
|
[旅客:人キロベース] |
[貨物:トンキロベース] |
図 輸送機関別輸送分担率の推移(旅客・貨物)
注)62年以降の自動車には軽自動車を含む。
<資料>運輸省「陸運統計要覧」(各年度)
表 自動車の機関分担率の国際比較(1990年)
| 米国 | 西ドイツ | イギリス | フランス | 日本 | |
| 旅客輸送(人キロベース) | 80.8% | 82.4% | 86.6% | 83.9% | 60.5% |
| 貨物輸送(トンキロベース) | 32.4% | 59.3% | 66.6% | 66.2% | 50.1% |
| 4. | 地方社会を支える自動車交通 地方圏においては自動車交通が社会活動の基盤となっている。 〜自動車交通の旅客輸送分担率:地方圏:82.9%、三大都市圏:40.7% |
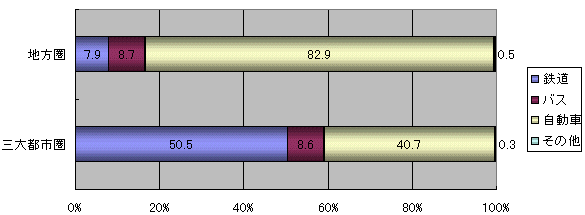
図 都市圏別旅客輸送分担率(平成6年度)
<資料>地方圏は運輸省「旅客・貨物地域流動調査 平成6年度」
三大都市圏は運輸省「都市交通年報」(平成8年版)
2)経済を支える
| 1. | 経済発展と密接不可分な自動車交通 経済の発展とともに運転免許保有者数、自動車保有台数は急激な伸びを示している。これに伴って自動車走行台キロも大きな伸びを示している。 |
表 GDP、運転免許保有者数、自動車保有台数および自動車走行台キロの推移
|
昭和30年 |
昭和50年 |
平成7年 |
|
|
GDP |
48兆円(1.0) |
237兆円(4.9) |
467兆円(9.7) |
|
運転免許保有者数 |
378万人(1.0) |
3343万人(8.8) |
6856万人(18.1) |
|
自動車保有台数 |
92万台(1.0) |
2837万台(1.0) |
6695万台(72.8) |
|
自動車走行台キロ |
121億台キロ(1.0) |
2863億台キロ(23.7) |
5964億台キロ(49.3) |
注)()内は昭和30年を1.0とした指数
注)GDPは実質(H2年現在)。自動車走行台キロは軽自動車を含まない。
| <資料> | GDPは経済企画庁「国民経済計算年報」による。運転免許保有者数は警察庁調べによる。 |
| 自動車保有台数は運輸省「陸運統計要覧」による。自動車走行台キロは運輸省「陸運統計要覧」による。 |
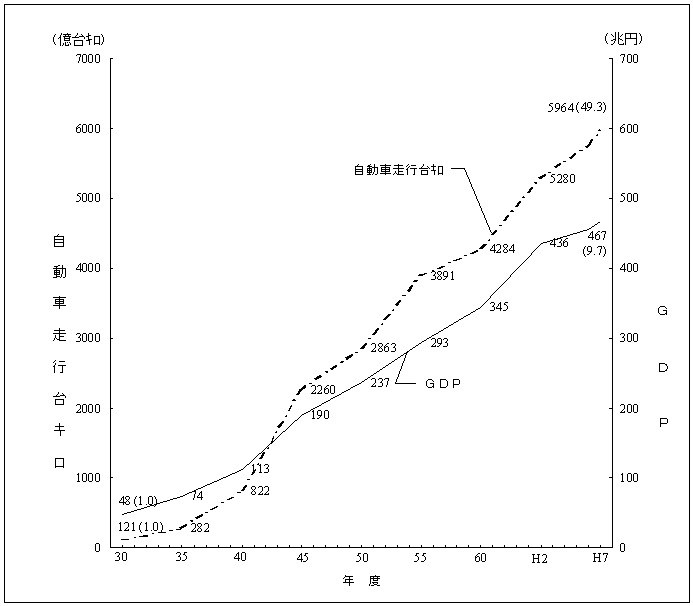
図 自動車走行台キロおよびGDPの推移
注)()内は昭和30年度を1.0とする指数。GDPは実質(H2年現在)。自動車走行台キロは軽自動車を含まない。
<資料>GDPは経済企画庁「国民経済計算年報」による。自動車走行台キロは運輸省「陸運統計要覧」による。
| 2. | 地域の経済活動の活性化に寄与 高速交通網の整備は、空港ターミナル機能の向上や地域の商業活動の活発化など、地域の経済活動を活性化させる。 |
|
|
|
||
| 図 | インターチェンジまでの時間距離区分でみた空港の貨物取扱量、旅客取扱量の伸び率(昭和62年〜平成6年) | 図 | インターチェンジまでの時間距離区分でみた小売額 |
| 注)全国の空港を「昭和62年時点でインターチェンジから30分以内にあった空港」と「平成6年時点でも30分圏外にあった空港」に分け、それぞれの旅客及び貨物取扱量の昭和62年から平成6年までの年平均伸び率をみたもの。
|
注)全国の市町村を昭和55年時点における高速道路のインターチェンジからの時間距離で区分し、昭和49年を1とした平成3年の指数で小売額の伸びを示したもの。
|
| 3. | 加工組立型への産業構造変化に対応した工場立地 重厚長大型から加工組立型への産業構造の変化に対応して、必要な材料の調達、製品の輸送が容易な高速道路のインターチェンジ(IC)周辺に多くの工場が立地している。 〜ICまでの距離別工場立地割合:10km未満:63%、10〜20km:21% |
図 インターチェンジからの距離別工場立地件数(平成7年)
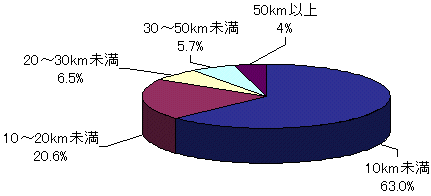
<資料>建設省
3)生活を支える
| 1. | 日常生活を支える自動車輸送 野菜、果物、水産品、日用品等日常生活に必要な主要品目の輸送のほとんどを自動車輸送が分担している。 〜品目別輸送分担率:野菜、果物、水産品:99.8%、日用品:100% |
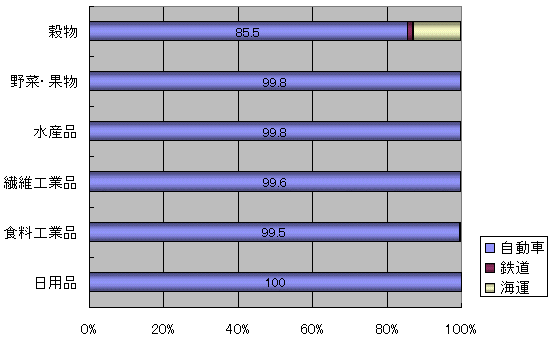
図 品目別機関別輸送分担率(平成6年度・輸送トンベース)
<資料>運輸省「陸運統計要覧」(平成7年版)
| 2. | 高速交通の確保が物価の安定に寄与 阪神・淡路大震災の影響によって高騰したレタスの価格が、高速交通が確保されるにつれて次第に安定した。 〜レタスの価格(10kg):2500円(通常) → 4000円(災害時) |
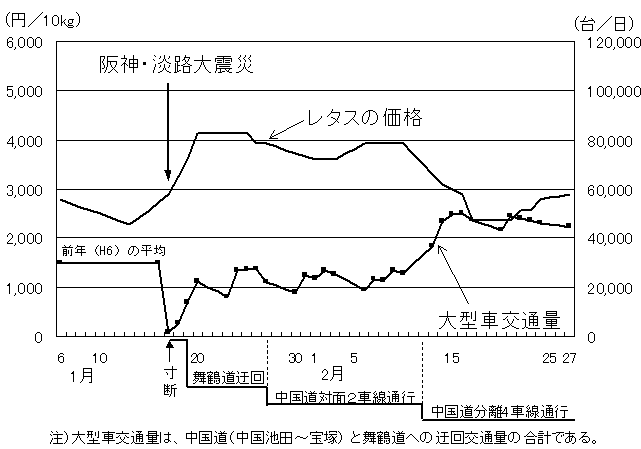
図 東京でのレタスの卸売価格の変化
<資料>JH
| 3. | 宅配便による生活の利便性の向上 宅配便の取扱量は大幅に増加しており、高速道路網の整備による1日配達圏の拡大は、生活の利便性を向上させている。 〜宅配便取扱個数:1.1億個(S56) → 15.3億個(H8):15年間で14倍に 〜A運送会社の翌日配達エリア:30%(S59) → 60%(H8):12年間で2倍に |
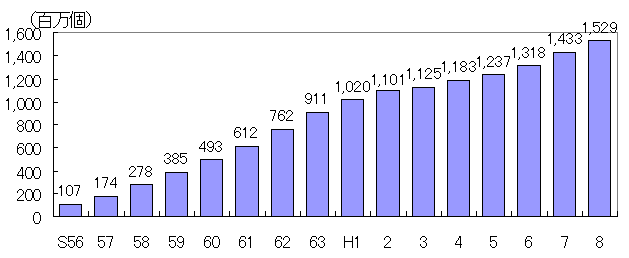
図 宅配便取扱個数の推移
<資料>運輸省
| 4. | 地域における高度医療を支援 高速道路を利用することにより、医療機関の少ない地域においても、高度医療、救急医療の利用が可能となっている。 〜患者搬送の所要時間(新宮村) 開通前:40〜70分→開通後:20〜30分 |

愛媛県新宮村周辺の医療ネットワーク
<資料>宇摩地区広域市町村圏組合消防本部調べ道路時刻表1985年、1995年