1)社会・経済・生活の緊急課題への対応
社会、経済、生活の各分野において直面する物流の効率化、市街地の活性化、渋滞対策、防災対策等の緊急課題を解決していくため、道路の持つ多様な機能を効率的に発揮できるよう、施策の展開を図ることとし、「1)新たな経済構造実現に向けた支援」、「2)活力ある地域づくり・都市づくりの支援」、「3)よりよい生活環境の確保」、「4)安心して住める国土の実現」を4つの施策の柱として、道路政策を重点的かつ計画的に推進する。
2)道路政策の進め方の改革
事業目的と社会的な効果を十分に確認しながら投資を判断する時代へ移行していることに対応して、道路政策をより効果的・効率的に執行するため、重点化・効率化、事業等の評価・改善、透明性の確保、適切な役割分担等の視点から道路政策の進め方の改革を図る。
(参考)建議では、道路行政の目指すべき方向として道路の持つ多様な機能を充実するとともに、達成すべき目標を設定し各種施策を計画的・重点的に実施する政策手法を導入すべきとしている。さらに、評価システムの導入を図るなど、効率的で透明な政策の進め方の変革に取り組むよう提言している。
(参考)多様な道路の機能
1)社会・経済・生活を支える多様な道路の機能
道路の機能は多面的であり、使われ方は多様である。鉄道や航空等の様々な交通機関を支える基盤であるとともに、長距離から短距離まであらゆる自動車交通を担っている。また、ライフラインなどの収容空間や都市の骨格形成などの機能を果たしている。
効果的、効率的な社会、経済、生活の諸活動を支えていくため、道路の有する、空間、交通等の多種多様な機能を、人中心の視点に立って再構築し、諸施策の一層重点的な展開を推進する必要がある。
2)社会空間(社会の共有空間)の確保・再生
道路は、国土空間の有効利用を図り、地域を支える総合的な社会基盤である。特に、生活や社会面での安全性の確保や質の高い生活空間の充実を図っていく上で、道路は社会の共有空間として地域、都市の極めて重要な構成要素である。道路の社会空間としての役割を最大限発揮させるための施策を推進する。
.gif)
道路施策の方向性
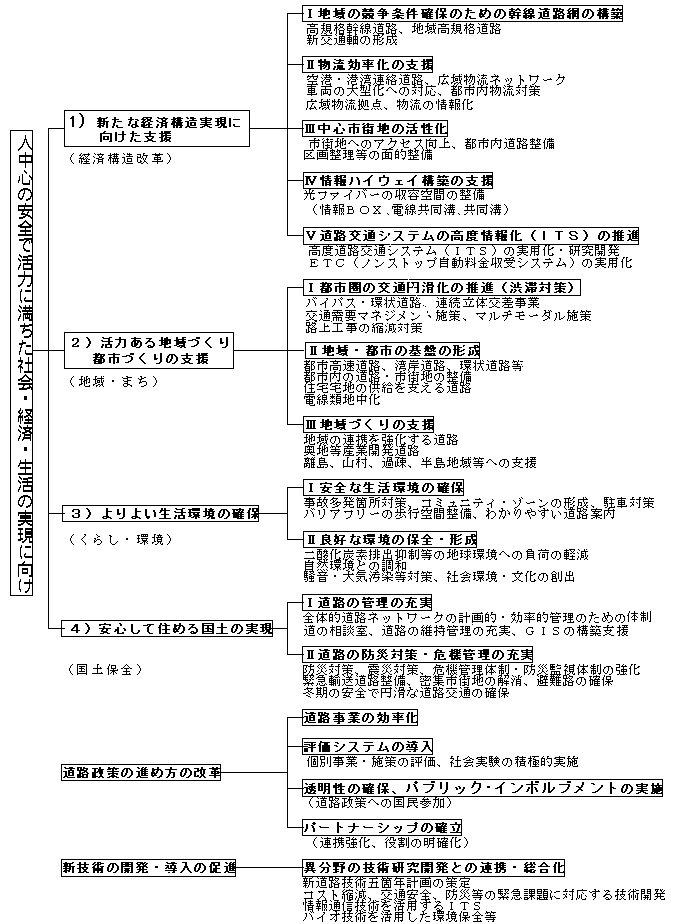
重点施策と五箇年間の政策目標
| 1)新たな経済構造実現に向けた支援 |
| i. |
交流ネットワークの充実により地域ブロックの自立的な発展や物流の効率化などを図るため、高規格幹線道路、地域高規格道路の重点的な整備を図る。
[高規格幹線道路] 7,265km → 8,626km (1,361km整備)
[地域高規格道路] 1,042km → 1,497km ( 455km整備)
|
| ii. |
効率的な広域物流ネットワークの形成・強化のため、空港・港湾等の交通拠点への連絡を強化する道路の整備を推進する。
[空港への連絡率] 40%(19/48空港) → 58%(29/50空港)
[港湾への連絡率] 25%(30/122港) → 38%(46/122港)
|
| iii. |
バイパス・環状・放射道路等の整備によるアクセスの向上、面的整備による中心市街地の活性化を図る。
[都市の基盤が整備された中心市街地の割合] 30% → 43%
|
| iv. |
情報ハイウェイ構築の支援のため、光ファイバーの収容空間(情報BOX、電線共同溝、共同溝)の整備を推進する。
[整備延長(市町村カバー率)] 6,970km(約1割) → 23,570km(約5割) (16,600km整備)
|
| v. |
ETC(ノンストップ自動料金収受システム)について、首都高速道路、阪神高速道路、東名・名神等、整備効果の高い路線の料金所に導入する。
[ETC対応料金所整備率(箇所数)] 0%(0箇所)→ 主要箇所で概成(約730箇所) |
|
| 2)活力ある地域づくり・都市づくりの支援 |
| i. |
第3次渋滞対策プログラムに基づき、交差点等の主要な渋滞ポイントにおける対策を推進する。
[渋滞ポイント数] 3,200箇所 → 2,200箇所 (1,000箇所解消)
高規格幹線道路、バイパス・環状道路の整備、国道の4車線化など、体系的な道路整備を推進する。
[環状道路整備率] 27% → 42%
|
| ii. |
安全で快適な都市空間の創造、災害に強いまちづくり等のため、電線共同溝等による電線類の地中化を推進する。
[電線類地中化延長] 3,010km → 6,010km (3,000km整備)
|
| iii. |
地方部の近隣都市や関連の深い市町村相互を連絡する道路の整備を地域の計画にあわせ重点的に推進する。
[二次生活圏中心都市へ30分で到達できる市町村の割合] 53% → 57% |
|
| 3)よりよい生活環境の確保 |
| i. |
効果的に事故削減を図るため、道路網の体系的整備に加え、幹線道路における事故多発箇所対策に重点的に取り組む。
[事故多発箇所対策数] 3,200箇所
誰もが安心して通行できるよう、幅の広い歩道の設置等による歩行空間のバリアフリー化を進める。
[幅の広い歩道等] 37,000km → 51,500km (14,500km整備)
|
| ii. |
騒音等環境対策のため、道路構造対策や建物防音工事助成、緩衝建築物の誘導などを推進する。
[夜間騒音要請限度達成率] 75% → 79% |
|
| 4)安心して住める国土の実現 |
| i. |
道路防災総点検に基づき、豪雨・豪雪等に対する防災対策、緊急輸送道路における橋梁等の耐震補強を推進する。
[緊急輸送道路内の耐震橋脚整備率] 58% → 概成
主要都市の密集市街地において広域避難地に到達できるよう避難路の整備を推進する。
[避難困難地区人口] 532万人 → 424万人 |
|
.gif)