大気質濃度は、全国的に緩やかな改善傾向。
今後は、国土交通省が測定したデータを活用して、迅速な状況把握を行い、効果的な対策の実施を目指す。 |
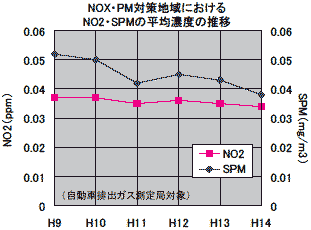 |
|
| (1)指標の動向 |
| | ■ |
自動車NOX・PM法対策地域内(首都圏、愛知・三重圏、大阪・兵庫圏)の自動車排出ガス測定局(自排局)及び国土交通省設置の常時観測局において、二酸化窒素(NO2)については、環境基準の達成局数の割合を、浮遊粒子状物質(SPM)については、道路寄与分を半減した局数の割合を評価した(※道路寄与分:自排局と最寄の一般大気観測局(一般局)の測定値の差分) |
| | ■ |
平成15年度は、NO2が67%、SPMが9%となり、目標を概ね達成 |
| | ■ |
平成16年度からは、指標のバックデータを国土交通省設置の常時観測局のみに変更し、NO2、SPM両項目とも環境基準の達成局の割合で評価し、併せて濃度値でも補足評価する(p.65)
指標に係る数値の取得の迅速化を図るため、指標算出の定義を変更する。ただし、平成15年10月に閣議決定された社会資本整備重点計画で設定されている平成19年度の目標値は、当初の算出方法で評価。 |
| | ■ |
平成16年度の定義での平成15年度の環境基準の達成局の割合は、NO2:53%、SPM:78%。環境基準に対応する平均濃度値は、NO2が0.059ppm、SPMが0.074mg/m3 |
| | ■ |
平成16年度は、達成局の割合をNO2は77%、SPMは現在の水準を維持すること、及び、環境基準に対応する平均濃度値を平成15年度実績値よりも改善することを目標とする |
| (2)達成度報告(昨年度の成果) |
| | ■ |
交差点の立体化等による沿道環境の改善
大気質の現況が環境基準を超えていると認められる地域において、交差点の立体化等のボトルネック対策や環境施設帯の整備等の沿道環境改善事業を実施。(図10-5)
|
| | ■ |
道路管理者による大気の常時観測局の設置
効果的な対策の立案・実施には、周辺データの取得が不可欠であるため、直轄国道沿道で自動車排出ガスの影響が大きいと考えられる地域において、常時観測局による観測を開始。 |
| (3)業績計画(今後の取組み) |
| | ■ |
大気質改善のための施策を継続的に実施
自動車からの排出ガス量を削減するため、自動車の走行速度向上のための交差点の立体化等、沿道環境改善事業を継続的に実施する。 |
【前指標】
 |
NO2 |
SPM |
| 平成14年度実績 |
64% |
- |
| 平成15年度 |
実績 |
67% |
9% |
| 目標 |
約67% |
約1割 |
| 平成19年度目標 |
約8割 |
約6割 |
|
【新指標】
 |
NO2(単位:ppm) |
SPM(単位:mg/m3) |
| 達成局 |
濃度 |
達成局 |
濃度 |
| 平成15年度実績 |
53% |
0.059 |
78% |
0.074 |
| 中期的な目標 |
約9割達成 |
- |
現在の水準を維持 |
− |
| 平成16年度目標 |
77% |
H15実績より改善 |
現在の水準を維持 |
H15実績より改善 |
|
|
(※前指標における達成率)
【NO2】
【SPM】
|
|
|