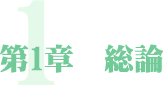
構想段階における市民参画型道路計画プロセスのガイドライン
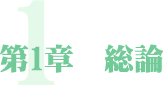
| 本ガイドラインは、「国土交通省所管の公共事業の構想段階における住民参画手続ガイドライン」(平成15年6月30日)に準じ、「構想段階」(第2章1を参照)における道路計画プロセスの実施方針、さらに道路計画プロセスにおいて実施する「市民参画プロセス」及び「構想段階評価」についての指針を示すものである。 本ガイドラインにより、構想段階における市民参画型道路計画プロセスを導入する目的は次のとおりである。
|
我が国の道路事業における市民等への情報提供や市民等の意見把握を行う機会は、従来、都市計画等事業実施を前提とする計画が決定される直前に限られており、計画の構想についての検討は、事業主体(行政機関)の内部で行われるのが一般的でした。
そのため、道路計画の必要性等公益性に係る議論と、詳細なルート位置等利害の調整に係る議論が、計画を決定しようとする段階で同時に行われることになる場合が多く、こうしたことが、議論の混乱を招いたり、計画決定が遅延したりする要因の一つとなることも少なくありませんでした。
そこで
を目的として「市民参画型道路計画プロセスのガイドライン」が平成14年8月に策定されました。
「市民参画型道路計画プロセスのガイドライン」(H14.8)の策定以降、同ガイドラインに沿った計画づくりの実績が増えつつあります。こうした事例を検証すると、計画プロセスを実施する上で特に注意すべき点が明らかになった例や、具体的な案件に対応した結果として、ガイドラインの内容を拡充、あるいは簡略化したかたちで実施された例が見られます。
また、平成16年6月に国土交通省環境行動計画が策定され、その中で構想段階においても総合的な観点からの評価を行い、より客観的、合理的に計画づくりを進めることが求められています。
このような状況に対応するため、今般、ガイドラインの改訂を行いました。
なお、改訂にあたっては表題に「構想段階における・・・」と追記し、本ガイドラインが構想段階を対象にしていることを明確にしました。これまでのガイドラインでも同様に構想段階を対象としており、今回新たに対象を構想段階に絞ったということではありません。
本ガイドラインでは、計画検討プロセスに必要な条件のうち、「透明性」、「客観性」、「合理性」、「公正性」という用語を、以下のように整理しています。
以上、手続き上の4つの概念によって,「手続の適切性」が保たれると考えています。
| 地域社会の状況、道路の役割、道路に対する利用者ニーズ等は多種多様であり、従ってそれらに対応する道路計画の策定にあたって考慮すべき事項もまた多様である。そのため本ガイドラインは、全国画一的に運用するのではなく、前項の目的を踏まえた上で、個別事業の状況に応じて柔軟な運用を行うことが必要である。 |
本ガイドラインは、構想段階における市民参画型道路計画プロセスの進め方について、基本的な指針を示したものですが、本ガイドラインに書かれているとおりのことを行えば、どのような案件でも円滑に計画プロセスを進められるということではありません。案件毎に社会背景や地域事情が異なるため、それら様々な事柄を考慮し、計画プロセスの進め方を創意工夫していくことが必要です。
本ガイドラインの適用対象は、次に掲げる道路の計画とする。
|
本ガイドラインに示す計画プロセスは、環境や市民生活に大きな影響を及ぼす恐れのある道路の計画等、様々な利害が対立し、早い段階からの合意形成を必要とするような計画について特に適用すべきものと考えられます。このような観点から、基本的には環境影響評価法に規定される第一種事業に該当するような一定規模以上の道路事業の計画を対象とします。
当然のことながら、①に該当しない比較的小規模な道路の計画に対して本ガイドラインに示す計画プロセスの全部または一部を適用することを妨げるものではありません。計画の早い段階から市民参画プロセスを導入して計画の検討を進めることが、より円滑で、より良い計画づくりに資すると考えられる場合には、小規模事業の計画にも本ガイドラインを積極的に適用していくことが推奨されます。
|