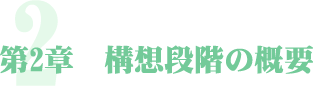
構想段階における市民参画型道路計画プロセスのガイドライン
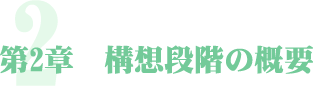
道路網計画から供用・管理までの体系は、下図のような5つの段階で構成される。本ガイドラインが対象とする「構想段階」は、路線別計画段階の最初の段階に位置づけられ、道路網計画を踏まえ、概ねのルートの位置や基本的な道路構造等(概略計画)が決定される段階である(具体的には第3章1.に示すプロセスをいう)。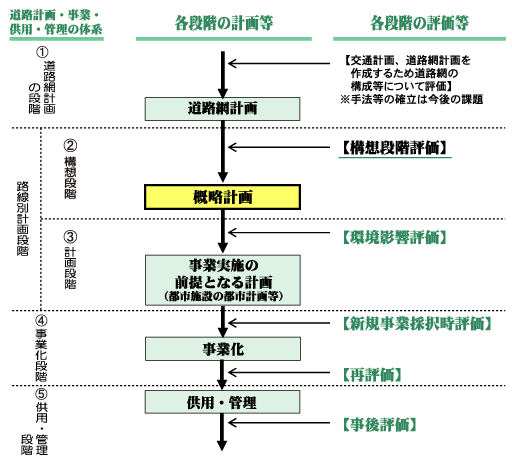 図 道路計画・事業・供用・管理の体系における計画や評価等 |
各段階では、一般に次のような決定や検討作業が行われます。
| 段階 | 計画等の決定内容 |
|---|---|
| ①道路網計画の段階 | 広域的な土地利用や交通需要等を踏まえて、面的な交通計画、道路網整備に関する方針を決定 |
| ②構想段階 | 概ねのルートの位置や基本的な道路構造等(概略計画)を決定 |
| ③計画段階 | 事業実施の前提となる計画(都市施設の都市計画等)として、具体的なルートの位置や道路構造を決定 |
| ④事業化段階 | 事業実施のための測量や設計を行い、概算費用の算定や工程計画を勘案した事業の実施方針を決定 社会情勢の変化等に伴い、必要に応じて計画を見直し |
| ⑤供用・管理段階 | 供用後一定期間を経た後に、効果の発現等の状況を踏まえて、必要に応じて改善策を検討 |
構想段階で議論すべき「公益性の観点からの計画の必要性の議論」と、計画段階で議論すべき「地域的な利害調整に係る議論」を区分することで、論点が明確化され、効率的な議論につながると考えられることから、路線別計画を2段階で構成することとしています。
| これまで、道路の路線別計画・事業・供用・管理の各段階において客観的かつ合理的な意思決定を行うため、それぞれ評価を実施してきたところであるが、構想段階においても「構想段階評価」を実施するものとする。 |
構想段階評価は、道路網計画から供用・管理までの段階における評価体系の一環として構想段階で実施する評価です。道路網計画から供用・管理までの各段階では次のような評価が実施され、評価の体系を構成しています。
| 段階 | 評価制度等 | 評価の内容 |
|---|---|---|
| ①道路網計画の段階 | - | 交通計画、道路網計画を作成するため道路網の構成等について評価 |
| ②構想段階 | 構想段階評価 | 概略計画案を絞りこむため、概ねのルートの位置や道路構造について、事業の効果、環境、費用等総合的な観点から評価 |
| ③計画段階 | 環境影響評価 都市計画 |
事業実施の前提となる計画(都市施設の都市計画等)を作成するため、具体的なルート、構造等の環境への影響や都市計画との整合等を評価 |
| ④事業化段階 | 新規事業採択時評価 | 事業実施の可否を判断するため、事業の効率性と効果を確認し、事業実施の必要性を評価 |
| 再評価 | 事業採択後、一定期間を経過した事業等に関して、事業の継続もしくは中止等を判断するため、事業の効率性と効果を評価 | |
| ⑤供用・管理段階 | 事後評価 | 完了した事業について、その効果、影響等実績の確認を行う評価。必要に応じて適切な改善を検討するとともに、評価結果を同種事業の計画・調査等への反映を図るための評価 |
| 道路計画の構想段階においても積極的に市民参画プロセスを導入するものとする。 |
構想段階における市民参画プロセスの実施は、概略計画を市民等のニーズを適切に反映したものとする上で不可欠です。構想段階での市民参画プロセスが十分に行われていないと、続く計画段階において、本来、構想段階で確認されるべき道路計画の必要性等に議論が遡り、計画段階で本来行われるべき議論が不十分となる等、混乱を招く可能性もあります。