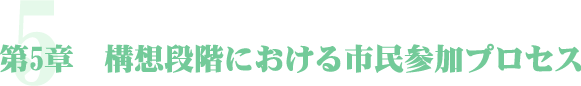
構想段階における市民参画型道路計画プロセスのガイドライン
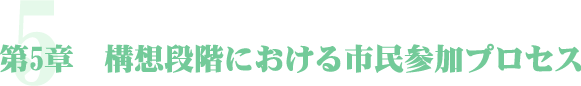
| 市民参画プロセスとは、構想段階における計画プロセスの透明性、客観性、合理性、公正性を高めること、及びより良い計画づくりに資することを目的として、市民等への情報提供、市民等からの意見把握、計画への意見反映を行う手続である。 |
次のような点に留意することにより、市民等が納得して受け入れることのできる,手続き的に妥当な市民参画プロセスを,より効果的に実施することができると考えられます。
| (1)市民参画プロセスで対象とする市民等の範囲 市民参画プロセスは、概略計画の検討対象範囲を中心に、事業の特性・対象地域に応じて効果・影響の及ぶ市民、その他の関係者を対象として実施するものとする。 (2)市民参画プロセスの実施主体 市民参画プロセスは、原則として、道路管理者または道路管理者を含む複数の関係行政機関が合同で実施するものとする。 (3)参画プロセスの実施内容 市民参画プロセスでは次の事項を実施する。
|
より効果的な市民参画プロセスを実施するためには、影響の及ぶ市民等関係者に対して幅広く、積極的にアプローチすることが求められます。影響の及ぶ関係者には、日常的な道路利用等、道路のサービスを受ける「顧客」はもとより、道路の利用の有無に関わらず影響を受ける関係者等、幅広い範囲の市民等が含まれます。
計画に関係する地方公共団体は、地域の代表として計画プロセスの進め方や検討の内容について道路管理者と協議・調整を行う立場にある一方、管轄区域の住民等に対する市民参画の手続を支援し協力する役割が期待されます。
例えば国が実施する道路計画においても、地元の市町村や都道府県が介在することにより、市民等とのコミュニケーションが円滑になる場合があります。そうした観点から、市民参画プロセスの実施主体として、道路管理者のみならず関係する行政機関が参画することが適当な場合が多いと考えられます。
また、複数の都道府県にまたがる道路計画においては、広域的な交通機能や地域の特殊性等に配慮しつつ、地方公共団体の意向を十分に配慮して調整することが必要になります。
市民等とのコミュニケーションの手法は様々考えられますが、それぞれの手法の特徴を踏まえ、対象とする市民等に応じて選択することが必要です。
例えば、沿道等限られた範囲で計画に対する関心が特に強いと考えられる市民等に対しては、実質的な意見交換や意見把握が可能となる様々な対面式のコミュニケーション手法(例:オープンハウス、ワークショップ、グループヒアリング等)を用いることが有効です。
より広い範囲(関係都道府県の住民や立地企業等)に対しては、地方公共団体の広報誌への掲載や独自のニューズレターの発行による情報提供、また、意見募集ハガキやアンケート等を通じて意見把握を行うことが考えられます。
さらに広い範囲としては、納税者としての関わりや地球環境への関心という意味での関わりも考えられますが、こうした不特定多数の関係者に対してはインターネット等の媒体を活用し、情報の取得や意見を述べる機会を幅広く提供することも可能です。
市民等からの意見は、単なる反対意見や要望にとどめることなく、その理由となっている懸念や関心、利害にまで遡ることが重要であり、さらに、それが計画の内容に対するものなのか、進め方に対するものなのかを明らかにした上で、反映方法を検討することが必要です。
また、市民等の意見には、地域固有の価値観が含まれることも考えられるため、これらを把握することに努め、計画づくりにおいて十分に勘案することが重要です。
具体的な市民参画の進め方については、状況に応じて柔軟に計画・運営されることが必要です。より多くの市民にアプローチし、より有意義な情報を収集することが市民参画の重要な目的であり、このため、現場ごとに市民等から意見を引き出すための工夫を重ねることが大切です。
| (1) 推進体制構築の考え方 市民参画プロセスの実施にあたり、市民参画プロセスの実施主体が必要と認める場合には、第三者機関を設置した上で市民参画プロセスを実施することができる。 (2) 第三者機関の役割 第三者機関の設置にあたっては、当該機関が担うべき役割を明確にする必要がある。一般に、第三者機関は次に掲げる役割を担うことができる。
(3) 第三者機関を設置する場合の留意点 第三者機関は、市民参画プロセスの実施主体の意思に基づき、道路管理者が設置する。第三者機関の委員は、市民参画プロセスの実施主体が選定の上、道路管理者が委任する。第三者機関の委員は、当事者ではない中立的な立場にある学識経験者等で構成する。第三者機関の設置にあたっては、その中立性の確保等に関する必要事項を規定した規約を定めるものとする。 |
市民参画プロセスは、あくまでも道路管理者等が実施するもので、第三者機関が実施するものではありません。第三者機関は、どの事業においても必ず設置するという性格のものではなく、個々の案件についての市民参画プロセスの状況に応じて、①~④に示す機能を第三者機関に求めるべきか否かを検討した上で必要に応じ設置すべきものです。
第三者機関の役割は限定的に考えるべきであり、概略計画に関わる決定権をゆだねるものではありません。例えば②や④のような役割を求める場合であっても、第三者機関からの助言と最終的に道路管理者が行う意志決定の結果が異なることもありえます。この場合、道路管理者は、第三者機関の助言と自らが下した決定が異なる理由を明らかにし、公表することにより自らの責任を果たすことが必要です。
第三者機関は、市民参画プロセスにおいて中立な立場から以下のような役割を果たすことが求められます。特に大規模な計画を対象としている場合等、様々な利害関係が複雑に絡み合うような場合には、学識経験者等で構成される中立的な第三者機関の役割が大きくなることがあります。
第三者機関が担うことのできる役割は多岐に渡りますが、複数の役割が同時に必要とされる場合、役割の組合せによっては、機能の矛盾が生じる等、第三者機関の本来の役割を十分に発揮できなくなることがあるため留意が必要です。
特に、プロセスを監視する役割(①)と計画検討の内容に関して助言を行う役割(④)とを同一機関が同時に担うことは、中立性と専門性とを両立させることが難しいため、避けることが適切です。
また、過去の市民参画の実施例においては、一般にひとつの機関に多くの機能を持たせ過ぎる傾向が見られますが、高度な専門的判断を適切に行うためには、過度の負担は避けるべきです。このような問題は、機関を複数設け、役割分担することで回避することができます。
その際は、各機関の役割を明確に区別して運営することが必要です。
第三者機関の委員の構成については、その機関が与えられた役割及び地域・事業の特性に照らして相応しい選定が必要であり、学識経験者の他、市民や利用者の代表、関係行政機関等が考えられます。