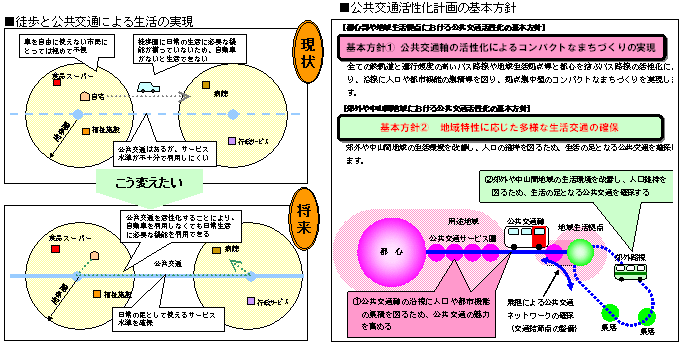1) 基本方針
| Q5−1 基本方針として、何を決めればいいのか。 |
| 交通サービスの利用の増加や交通サービスの事業性の改善など、交通施策の領域での方針ではなく、地域・まちづくりの観点から、地域交通サービスの充実により、どのような将来像(生活、活力、環境等)が描けるのかを示すことが重要である。 地域交通の計画は、他の政策分野の計画と独立で成立するわけではない。地域が目指す将来の姿に対し、下位計画として、都市計画、交通計画、医療計画、コミュニティ計画といったさまざまな分野別の計画が策定され、その中で地域交通の計画は、市町村が目指す姿のどの部分を、どのように実現するかを示すことが重要である。 |
| Q5−2 基本方針を決めるために留意すべきことは何か。 |
| 基本方針は、住民に分かりやすく、支持されるものであることが重要である。そのためにも、地域・まちづくりや、住民の生活利便性の向上に必要な交通サービスの充実に対しては、自治体が積極的に関与する姿勢があることを打ち出すことが重要である。住民の支持があってこそ、利害関係者との調整においても自治体のスタンスを主張することができる。 また、基本方針は、利害関係者にとっても分かりやすく、問題意識に沿ったものであることが重要である。このためにも、「地域のため」、「住民のため」といった広い視点で問題意識を共有しておくことが重要である。(Q2−6も参照のこと) |
| Q5−3 達成目標は、定める必要があるのか。 |
| モニタリング、フォローアップ及びその評価に基づく改善を継続的に実施する(PDCAサイクル)上で、評価の基準となる目標設定は重要である。 また、短期、中期、長期など時間軸に沿って目標を設定することで、関係者や地域の住民と共通の認識を確立することができる。 なお、支援制度においては、取組の事前評価の実施や定量的な目標値を掲げることが支援の要件となっている場合もある。 |
| Q5−4 達成目標として、何を定めればいいのか。 |
| 達成目標は、地域交通サービスの充実により、どのような将来像(生活、活力、環境等)を目指すのかということと関連して設定することが重要である。 例えば、キーワードとしては、住民の移動手段の確保、 中心市街地活性化、環境問題対応、渋滞対策、観光振興などが考えられる。 また、目標は、達成度合を測るため、可能な限り定量化することが重要である。 但し、定量化にこだわり過ぎて、計測するためだけに毎回費用が発生することにならない様にすることも重要である。 関係者で共有したり、公表することを考えれば、目標としての分かり易さやモニタリング(観測)のし易さを考慮する必要がある。 |
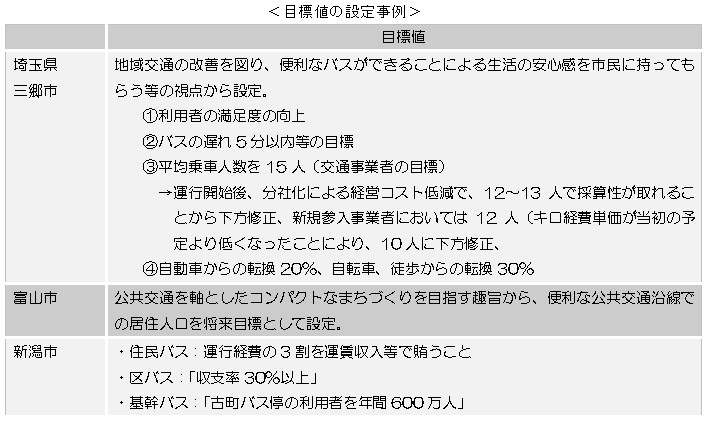
| Q5−5 達成目標を定めるために留意すべきことは何か。 |
|
設定された目標は、関係者間が合意し、共通の目標とすることが重要である。目標の設定にあたっては、関係者間で協議し、合意形成を図ることが必要である。 また、目標値は、そこで掲げた数値は、どのような意味をもつのかを吟味して定めることが重要である。 交通施策の実施は、すべてが一度に実施できるわけではなく、段階的な取組になることが想定される。このため、目標値についても、短期・中期等の達成段階を設定することが考えられる。 |
(END)