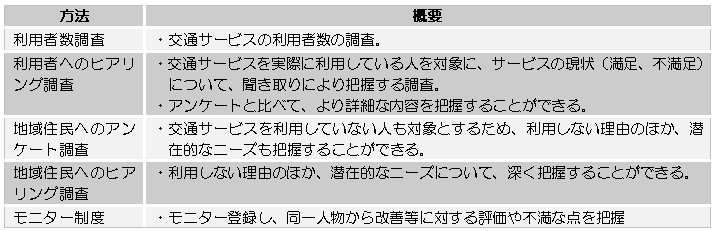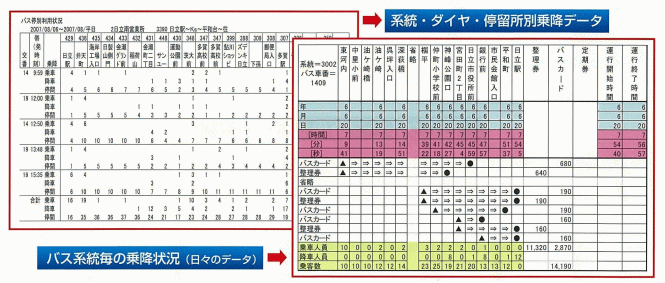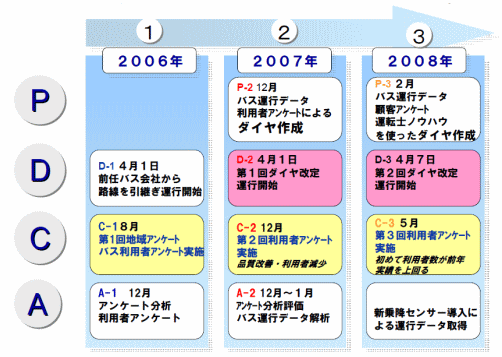1) 計画の実施
| Q8-1 計画の実施に当たって、留意すべきことは何か。 |
| 実証運行を行うケースでは、実証運行の成果を本格運行に反映させることが基本であるが、利用者のニーズがなければ無理に本格化させないといった姿勢も重要である。 運行頻度拡大の社会実験を行ったものの、実験期間中のアンケート調査で、「税金を使ってまで、これ以上サービス水準を上げる必要がない」という回答が多かったため、本格運行に至らなかった事例もある。 また、交通施策を実施するにあたっては、単独で実施するよりも、複数の交通モード間の連携や、中心市街地活性化や観光振興などその他のまちづくりとの連携を図ることにより、相乗効果や効果の早期発現を図ることが重要である。 |
| Q8-2 実施に当たっての経費は、どのようにして確保すればよいか。 |
| 国土交通省の支援制度は「Ⅴ.支援制度」を参照のこと。 また、国等の支援以外にも、運行費用に企業協賛金、住民協賛金などを運行費用に充当したり、公共交通マップの更新等情報提供に要する資金として企業からの広告料を充当している事例もある。 |
| Q8-3 モニタリングを何故行う必要があるのか。 |
|
計画の実行性を高め、取組の効果的な推進を図るためには、進行管理が重要である。継続して調査することにより、何らかの変化を見ることができる。当初、取組の成果が現れなくても、ダイヤやルート等を見直すことで、徐々に成果が出てくることもある。 また、取組の実施直後と、一定期間を経た後では、地域交通に対するニーズや、利用者のターゲットなどが変化している可能性もある。 これらのことから、取組の実施後も、定期的に見直しを行っていくことが重要である。本調査で実施したアンケート結果からは、モニタリングを実施し、その結果をもとに取組の見直しを実施することにより、当初の期待を上回る効果をあげる傾向がある。 |
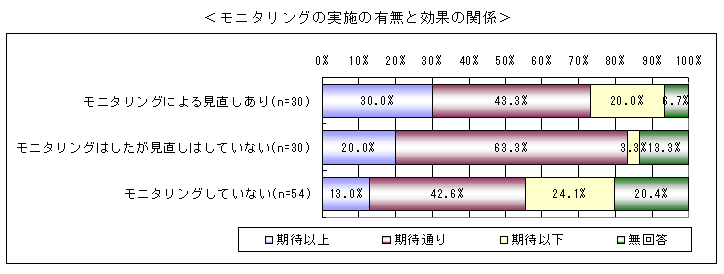
| Q8-4 モニタリングでは、何を行えばよいのか。 |
|
モニタリングでは、検討中や社会実験時の調査結果との比較を行うことから、同様の調査を行うことが重要である。 また、事前事後の比較評価だけでなく、ニーズの変化や取組に対する満足度など、改善点を発掘するためのデータを収集することも重要である。 |
| Q8-5 モニタリングは、どのような方法で行えばよいのか |
|
市町村の限られた財源の中で、今後の高齢化の進行による交通弱者の増加に対応するためには、すべての地域交通サービスを税金だけでまかなうことは困難であると考えられる。 このため、生活に密着した地域交通サービスについては、自治体が一定の支援を行いながらも地域住民が主体となって構築し、支えていくことが重要である。 |
| Q8-6 把握すべき効果は、どのようなものがあるのか。 |
| Q8-7 効果の把握は、どのような方法で実施するのか。 |
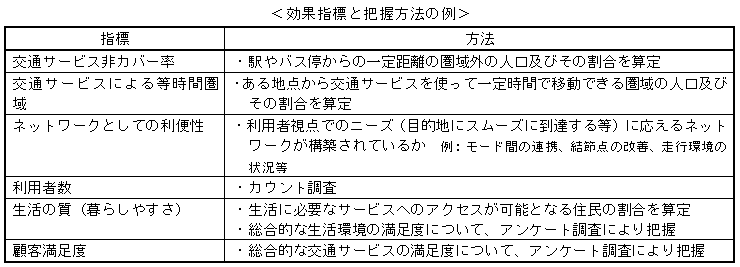
| ・モビリティマネジメントの効果は、取組以外の要因を排除することが難しいため、利用者数の推移によるマクロな分析を実施している。利用者数の減少トレンドを見ると、減少に歯止めがかかりつつあり、一定の効果が現れていると評価している。(大分市) |
| Q8-8 利用者数の調査で、何が分かるのか。 |
| 取組の実施効果、見直し効果を把握するためには、その前後で利用者数を比較することがわかりやすい。ただし、利用者数といった量的指標だけで評価するのではなく、利用者の満足度など質的指標からの評価も合わせて実施することが重要である。 また、交通機関の乗降を詳細に把握する場合は、バス停・駅間、路線間の利用者数など基本的なデータが取得でき、これを基にダイヤの再検討や路線の見直しなどが可能となる。 |
| Q8-9 利用者数の調査は、どのような方法で実施するのか。 |
| 中・小型車両を用いたコミュニティバスや乗合タクシーの場合、運転手がバス停ごとに乗車・降車を記録しているケースが多い。 ICカードを導入しているバスのケースでは、乗車・降車時に、自動的に乗降データが記録され、バス停別・系統別の利用者数などが自動で蓄積される。中には、利用者の属性別(通勤・通学・高齢者、定期・定期外など)の細かい乗降データ(ODデータ)を把握できるシステムもある。初期投資としてはある程度の費用を要するが、モニタリングのための特別な調査が不要となり、低コストで効果的なPDCAサイクルを実践できるなど、長期的に見ればメリットが大きい。 また、ICカードには、公共交通機関だけでなく、商店街や大型店などでの買い物等でも使えるものもある。(地域商業や中心市街地の活性化に繋がっている事例はQ7-27を参照) そうでない場合は、バスに調査員が乗り込んで調査するケースなどがある。乗降実態調査を独自に行っているバス事業者へのヒアリングでは、1週間もサンプリング調査をすれば、概ねの傾向はつかめるという指摘がある。 |
| Q8-10 意見の把握は、どのような方法で実施するのか。 |
| Q8-11 モニタリングの結果は、どのように利用すればよいのか。 |