3.住民主導による乗合タクシー運行-秋田県鷹巣町- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)地域交通の状況と施策のねらい①地域概況・秋田県鷹巣町は、奥羽本線と秋田内陸縦貫鉄道の結節点に位置し、大館能代空港を擁する人口22,671人(平成10年)の町である。北秋田郡森吉町、阿仁町、合川町、上小阿仁村の4町1村よりなる鷹巣阿仁広域市町村圏の中心となる町である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
②導入の経緯 【代替乗合タクシーの運行】 ・町内を運行していたバス路線のうち、特に業績の悪化していた2路線(大沢、田子ヶ沢)について、バス事業者が路線廃止を通告した。 ・沿線集落は、通学や高齢者の移動手段を確保するために自治会が中心となって検討を重ね、運行をタクシー会社に委託、ジャンボタクシーの乗合により路線を維持することを決定し、平成9年より代替乗 合タクシーの運行が開始された。
【ふれあい通院バスの運行】
(2)施策内容①交通サービスの概要【代替乗合タクシーの運行】
【ふれあい通院バスの運行】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
②住民主導の内容 【代替乗合タクシーの運行】 ・各自治会が主体となってタクシー会社との間で運賃、運行時間帯などを取り決め、自治会の連名によりタクシー会社と運行委託契約を締結している。 ・利用料金は小学生100円、中学生200円、高校生以上300円で均一運賃とし、利用回数券を各自治会の会長が販売・精算するという自治会による自主管理を行っている。 ・料金の設定はジャンボタクシーの運行経費から算定、利用金額合計との差額分を町が全額補助している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図2-5 代替乗合タクシーにおける事業者・住民・行政の関係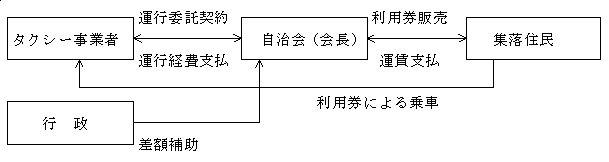
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【ふれあい通院バスの運行】 ・代替乗合タクシーと同様、自治会と事業者が運行委託契約を締結している。 ・運賃は、運行距離に応じて600円と700円の2種類の料金を設定している。 ・利用回数券の販売・料金徴収方法、差額分の補助方法は代替乗合タクシーと同様である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)工夫した点・苦労した点・交通サービスの維持は地域住民が主体となって、自主的になされるべきものであるという考え方から、町は補助金などによる側面支援を行うという役割分担を明確にしている。・契約主体は地元の自治会であり、運行主体は地元事業者であるために、運行時間帯等に対しても地域の実情に合わせた運行に向けて適宜協議し、臨機応変に対応できる体制となっている。 ・町が契約主体となると、路線を運行する集落のみに町の財源を直接投入することになるが、町が側面支援の形をとることによって他集落からの不公平感を抑制している。 ・鷹巣町では交通に限らず、町政全般において、行政が一方的に解決策を提示するのではなく、地元住民によるワーキンググループを組織し、問題解決にむけた協議をすることが定着している。
(4)施策の実施効果・地域住民の発意と要望に対し、行政が側面支援するという役割分担は、代替乗合タクシーをはじめとして、ふれあい通院バスといった地域の状況に応じた新たな交通サービスを展開させることとなっている。【代替乗合タクシー】 ・代替タクシー運行回数はバス運行時に比べ減少したものの、通学の利用や高齢者の通院・買い物等の移動手段は確保された。 【ふれあい通院バス】 ・それまで、個人でタクシーを利用したり、家族による送迎に頼っていたが、バス運行により負担が軽減された。タクシー利用の場合5~6千円かかるため「ふれあい通院バス」を利用すると1回数千円の費用が軽減される。 ・ふれあい通院バスは運行開始以降利用者が多く、100%を超える利用者があり、7ヶ月間の町の負担は5~6万円程度に止まった。なお、乗り切れない乗客がある場合には、タクシー事業者がジャンボタクシーや一般のタクシーの増車などにより、臨機応変に対応している。
(5)今後の展望と課題・代替タクシーでは乗車率が50%程度にとどまり、バス路線運行時と比較しても、現在のタクシー運行に対する町の負担はむしろ若干増加している。・鉄道存続問題を含め、高齢者社会の中で今後交通サービスに対してどこまで町が財政負担を行えるかについての検討が必要とされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次へ 次の事例