 航空安全規制のあり方について(諮問第26号答申)
航空安全規制のあり方について(諮問第26号答申)

 はじめに
はじめに
航空審議会は、国内定期航空運送事業における需給調整規制が廃止されることを受けて航空運送事業に関する安全規制について見直すとともに、この機会に最近の航空安全行政を取り巻く内外の情勢の変化を踏まえ、航空全般の安全施策について幅広く審議を行った。
本答申は、今後の航空安全規制のあり方として、その基本的考え方、航空運送事業に関する安全規制のあり方等、今後の航空安全行政の方向及び必要となる施策についてとりまとめたものである。
 I.航空安全行政を取り巻く環境の変化
I.航空安全行政を取り巻く環境の変化
- 航空輸送の安全確保に関しては、従来より航空会社の運航・整備の体制、航空機、航空機乗組員等について所要の安全規制が行われてきた。
- しかしながら、近年、航空安全行政を取り巻く環境は、以下のとおり大きく変化してきている。
 1.参入の容易化及び競争の激化を背景とする事業形態の変化
1.参入の容易化及び競争の激化を背景とする事業形態の変化
- 近時の経済社会状況の中で行政改革や経済構造改革の推進が焦眉の急であること等に鑑み、自由競争の促進により航空を含めた交通運輸分野における経済活動の一層の効率化・活性化を図ることが求められている。このため、運輸省は、需給調整規制について原則として廃止することとしたが、国内定期航空運送事業については、平成11年度中を目途に需給調整規制を廃止することとしている。また、先の日米航空交渉の合意内容に見られるように国際航空の分野においても航空会社間の競争は更に激化することが見込まれる。今後、このような参入の容易化及び内外の競争の激化を背景として、外部資源を大幅に活用した新規航空会社の参入、既存航空会社における運航・整備の一層の効率化等、航空会社の事業形態の変化が予想される。
 2.航空技術の発展及び民間事業者の能力の向上
2.航空技術の発展及び民間事業者の能力の向上
- 情報通信技術や自動化などの新たな技術を採用した航空機の導入、新たな機器の開発、これらに対応した整備方式の採用、更には航空保安施設の標準化等により、航空機の運航の安全性及び信頼性が向上してきていると同時に、航空機の運航及び整備の方法も大きく変化してきている。また、我が国の航空会社、整備事業者等の民間事業者の安全確保に関する能力も向上してきている。
 3.航空の国際化の進展
3.航空の国際化の進展
- 安全かつ円滑な国際運航を確保するため、国際民間航空条約に基づいた運航が求められているところであるが、更に航空機やその装備品の安全性に関する外国の証明の受入れ、乗員等の外国資源の活用、航空機の整備等の国際間の委託等を容易にすることにより、運航者等の負担を軽減する観点から、耐空証明、技能証明、整備事業場の認定等について、欧米を中心として国際間で基準の一層の調和が進められている。
- また、航空の国際化の進展により、新たな外国航空会社の乗り入れや外国航空会社を利用する日本人が増加してきているが、外国航空会社の安全性については、原則として当該航空会社の所属する国が監督責任を負うこととされている。しかしながら、最近我が国においても外国航空会社の事故が発生していることなどもあり、外国航空機の安全性について関心が高まっている。
- 以上のような環境変化に航空安全行政としてどのように対応していくかが課題となっている。
 II.航空安全規制の基本的考え方
II.航空安全規制の基本的考え方
 1.国による安全規制の必要性
1.国による安全規制の必要性
- I.1.で述べたように、21世紀に向けて、航空会社間の競争を促進し、事業活動の一層の効率化・活性化を図るため、経済的規制である需給調整規制は廃止することとされたところである。
- これに対して、社会的規制である安全規制については、いったん航空事故が発生した場合には搭乗者のみならず地上の第三者にも被害が及ぶことが考えられるなどその被害の甚大さから、事故を未然に防止することは社会的要請であるため、今後とも必要であると考えられる。また、利用者が安全に関する情報を十分に把握し、航空会社の安全性を適切に評価し選択をすることは困難であることも安全規制の必要性の要因としてあげられる。したがって、航空輸送の安全確保を市場原理に委ねることには限界がある。
- また、国際民間航空条約に基づく航空安全に関する国際的な枠組みにおいて、国は航空輸送の安全確保のための役割を果たす責務を有しているが、国がその責務を果たさないということになれば、国際民間航空条約に違背することとなり、我が国の航空会社が諸外国に乗り入れる際の障害ともなりかねない。
- このように、航空の安全規制は必須のものであり、国は、安全確保のための最低限の基準の設定、航空会社の基準への適合性の審査、監視等を引き続き行うことが必要である。なお、国はこのような役割について、利用者等に十分に理解されるよう努力すべきである。
 2.安全規制の見直しについての考え方
2.安全規制の見直しについての考え方
- I.で述べたように、航空会社の事業形態の変化のほか、航空技術の発展、民間事業者の能力の向上等航空運送事業を取り巻く環境は大きく変化してきている。
- II.1で検討したとおり、需給調整規制の廃止をはじめとする経済的規制の緩和が進められる中で、安全規制は今後とも引き続き必要であるが、その内容はこのような環境変化に対応したものであることが求められる。このため、国は適時適切に安全規制を見直していくことが重要である。
- 安全規制の見直しの際の基本的な視点は以下のとおりである。
- (1) 透明性及び公平性の確保
- 安全規制については、航空運送事業への参入を阻害し、実質的に競争制限的効果をもつものとならないよう、基準の一層の明確化を図る等、その透明性及び公平性を確保する必要がある。
- (2) 国際的な標準・基準との調和
- 航空の国際化の進展に伴い、欧米を中心に進められている国際間の基準の調和をも踏まえ、国際的な標準・基準との調和を図る必要がある。
- (3) 規制の合理化
- 技術発展等に伴う基準の見直しのほか、民間事業者の能力の向上に伴い安全確保に関する民間能力の活用等、規制の合理化を図る必要がある。
 III.航空運送事業に関する今後の安全規制のあり方
III.航空運送事業に関する今後の安全規制のあり方
 1.航空運送事業の参入に係る安全規制及び随時監視
1.航空運送事業の参入に係る安全規制及び随時監視
- (1) 参入に係る安全規制
- 現在、航空運送事業に参入するためには、運輸大臣の免許を受け、運航及び整備に関する事項についてそれぞれ運航規程及び整備規程の認可を受け、更に運航開始前の検査に合格することが必要である。また、当該事業者は免許の申請に際し提出した事業計画に従って業務を行う必要があり、事業計画を変更しようとするときは、一部の届け出事項を除き、運輸大臣の認可が必要である。
- 需給調整規制の廃止後においては、航空運送事業の参入にあたって、安全面の審査を中心とし、国は航空会社が運航、整備等に係る安全基準に適合していることを確認すべきである。具体的には、当該航空会社が安全基準に適合していることを提出書類により審査し、更に、事業の遂行に必要な運航規程及び整備規程を審査のうえ認可し、事業の実施体制、施設等について運航開始前の検査を行うことが引き続き必要である。
- また、運航開始後においても、新機種導入による運航・整備体制の変更等、その変更内容が安全基準に適合していることを確認する必要があると認められる事項に関しては、国が事前に審査を行うとともに、必要に応じ運航開始前の検査を行うことが必要である。
- (2) 随時監視の充実
- 従来より、航空会社に対しては、免許時及び事業計画変更時に安全基準に適合していることを審査し確認するだけでなく、その後も航空会社が安全基準に適合していることを確保するため、定期的に立入検査を行うなど随時監視を行っている。
- 需給調整規制廃止に伴う参入の容易化による外部資源を大幅に活用した新規航空会社の参入や内外の競争の激化を背景とする既存航空会社における運航・整備の効率化の追求等、今後航空会社の事業形態が変化することが予想される。このような中で、航空運送の安全を確保していくためには、航空会社等に対する随時監視が従来にも増して重要となることから、その実施のための体制を更に充実していく必要がある。
 2.航空運送事業の事業形態の変化等への対応
2.航空運送事業の事業形態の変化等への対応
- (1) 外部資源の活用に対する安全規制
- (i) ウェットリース及び運航委託
- 我が国航空会社間のウェットリースにおいては、航空機及び乗員は借り手側の事業者の支配下におかれ、借り手側の運航規程及び整備規程を適用して運航が行われるため、安全管理責任は免許会社である借り手側が負うこととなっている。
- しかしながら、現在行われているウェットリースの中には、ある航空会社の航空機及び乗員を使用した一連の路線のうちの一部分のみを他の航空会社の便として運航するように、実態として貸し手側の航空会社が運航を管理していると考えられる場合がある。
- 現状では、当該路線の免許を受けた航空会社ではない貸し手側の航空会社に対しては、免許を受けた航空会社である借り手側を通じ間接的な監督を行っているが、今後我が国の航空会社間のウェットリースを広く認めるとした場合、実態として運航を管理している貸し手側の航空会社の運航及び整備体制についても、運航の安全を確保する観点から直接国が監督を行う必要があり、このための法的な規制の整備を検討すべきである。
- また、国際線における外国航空会社への運航委託に関しては、実態として運航を管理している委託先の外国航空会社については、国際民間航空条約上、原則として当該航空会社が所属する国が安全に関する監督責任を有することとされている。このため、現在運航委託を認めるにあたっては、委託側である我が国の航空会社の委託管理が確実に実施される体制が整っていることを確認しているが、今後運航委託を広く認めるとした場合には、委託先の外国航空会社は、航空事業に関し我が国と同等又はそれ以上の安全に係る制度を有し、かつその運用を行っている国の免許を受けた航空会社に限定することが適当である。
- (ii)整備等の委託
- 従来から航空機等の整備作業、乗員の訓練等を委託することが行われてきているが、外部資源を大幅に活用することを前提としている新規航空会社の参入が計画されているなど、今後更に拡大することが予想される。これらの業務の委託は欧米等でも一定の条件の下に認められており、今後も従来と同様に、最終的な安全上の責任は委託者にあることを踏まえ、委託先が適切な能力を有していること、委託者による委託管理が適切に行われること等を前提として業務の委託を認めていくことが適当である。
- 特に整備作業の委託先の要件について、航空会社が使用する耐空類別が「飛行機 輸送T」である飛行機は、その構造、システム等が複雑なため、その整備作業は系統だった作業手順に従って組織的に行われ、かつ、当該作業に係る検査が適切に実施されることが必要である。したがって、こうした大型飛行機に関する機体全体の整備作業(法令上整備後の確認が必要なもの)を外部に委託する場合は、系統だった作業手順に従って組織的に整備改造作業及び検査を行う能力があると認定された事業場(整備改造認定事業場)に委託先を限定する必要がある。
- (2) コミューター航空に関する安全規制
- 現在、コミューター航空は、定期航空輸送サービスの維持に重大な影響を与えるおそれがないことを前提に、不定期航空運送事業の一類型として位置付けられている。
- このため、コミューター航空に適用される安全規制については、法令上は他の不定期航空運送事業に適用されるものと同一であるものの、コミューター航空の社会的役割を考慮し、付加的な安全規制を通達により課してきているが、その結果、コミューター航空に適用される安全規制は、その使用航空機が小型である等の理由から、定期航空運送事業に適用される安全規制をそのまま適用することが困難なものを除き、ほぼ定期航空運送事業者に適用される安全規制と同等のものとなっている。
- これら付加的な安全規制については、コミューター航空会社のこれまでの運航実績から、我が国のコミューター航空の安全確保において一定の役割を果たしてきたと考えられる。
- 今後需給調整規制が廃止され、コミューター航空会社による自由な経営判断に基づいたネットワーク形成ができるようになるとした場合、従来の定期航空とコミューター航空のすみ分けは困難となり、利用者から見れば、提供されるサービスに関しコミューター航空と定期航空との相違は理解し難いものと思われる。
- したがって、コミューター航空に適用される安全規制を、法令上も定期航空運送事業と同一のものとする方向で検討する必要があるが、この場合であっても、航空機の大きさ(最大離陸重量、客席数等)、耐空類別等に応じて安全規制を適切に設定することが必要である。
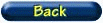
![]() はじめに
はじめに