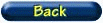航空安全規制のあり方について(諮問第26号答申)
航空安全規制のあり方について(諮問第26号答申)

 IV.航空安全規制の合理化について
IV.航空安全規制の合理化について
- 航空安全規制の合理化については、これまでも進められてきたところであるが、当面の主な課題は以下のとおりである。
 1.機長路線資格制度の見直し
1.機長路線資格制度の見直し
- 定期航空運送事業の用に供する航空機には、当該路線における航空機の機長として必要な経験、知識及び能力を有することについて運輸大臣の認定を受けた者でなければ機長として乗り組んではならないとされており(航空法第72条)、現在、機長に対しては、個々の路線毎に国の機長路線資格審査官(運輸大臣が指定する範囲内の機長については指定定期航空運送事業者の社内の査察操縦士)による審査及び認定が行われている。
- しかしながら、飛行場においては、航空灯火、計器着陸装置等の航空保安施設や出発・進入方式等の飛行方式が標準化され、また航空路においては、VOR等の無線標識などが整備され、機上航法装置の性能が向上したことなどもあり、航空機の運航は標準化されてきており、飛行場や路線毎の特性の差異は少なくなってきている。このため、機長にはこれまでと同様に通常時及び異常時の航空機操作に関する知識及び能力が求められる一方で、機長として状況を的確に把握し標準化された手順に従って飛行を適切に管理する能力が求められるようになってきており、路線毎に経験、知識及び能力を求めることは合理性に欠けると考えられるようになってきている。
- したがって、機長の資格については、欧米の趨勢を参考にして、機長としての業務を遂行するために必要な全ての路線に共通して求められる知識及び能力を重点として認定することとし、これまでの路線毎に審査し認定を行う制度は廃止することが適当である。
 2.整備士資格制度の見直し
2.整備士資格制度の見直し
- 整備をした航空機については、整備士資格を有する者がその適切性を確認しなければ、航空の用に供してはならないとされているが、このような整備士資格は、現状では、航空機全体を対象とする航空整備士と機体、エンジン、計器等の専門分野毎の資格である航空工場整備士に大別される。
- このうち航空機の整備の現状を見ると、昨今における航空機の技術的進歩、信頼性の向上等の結果として、飛行間点検を行うライン整備を中心に、高度な知識・能力を必要とする構造修理、エンジン交換等の修理作業の発生頻度が減少し、大半は、基本的知識・能力により対応が可能な計器類の調整、消耗部品の交換等の保守作業となってきているなど、整備の環境も大きく変化してきている。しかしながら、整備をした航空機についてその適切性を確認する者に必要とされる資格としては、修理作業にも対応することを目的としたもの(航空整備士資格)しか設けられていないため、保守作業についてもこのような資格を有する者を充てざるを得ない。このため、航空会社における航空整備士資格取得のための訓練は、必ずしも個々の業務内容に則したものとはなっていない。
- 以上から、整備士資格制度については、従来の航空整備士資格に加え、一般的保守等に対応する資格(基本航空整備士資格(仮称))を設け、昨今の整備の環境を反映したものに改めることが望ましい。なお、基礎的資格としてその取得の促進を図ることにより、整備従事者全体の水準が向上することも期待される。
- また、航空整備士資格については、従来、航空機の最大離陸重量に着目して、一等、二等及び三等航空整備士に区分してきたところであるが、近年の技術の進展、ニ−ズの多様化等に伴い、基本的な設計が同一の派生型機であっても一等及び二等航空整備士又は二等及び三等航空整備士の区分にまたがるものが出現しているなど、現在の最大離陸重量による区分が必ずしも合理的なものではなくなってきている。このため、その区分の方法については、航空機の構造・システムの複雑さに直接関係することとなる設計基準の分類(飛行機輸送Tなどの耐空類別)に着目したものに改める必要があると考えられる。
 3.機器の装備義務
3.機器の装備義務
- 航空機に装備することが義務づけられている機器は、我が国では、航空法第60条(航空機の姿勢等を測定するための装置)、第61条(航空交通管制区等における航行を行うための装置)、第61条の2(航空運送事業の用に供する航空機の装置)及び第62条(救急用具)に規定されているほか、通達で装備の促進を図っているものもある。
- 近年の技術進歩によって出現した対地接近警報装置(GPWS)をはじめとする運航の安全向上に効果の大きい各種機器については、逐次国際民間航空条約第6附属書に規定される義務装備品に追加されるなど、国際的にその装備が義務化されてきている。
- 今後、機器の進歩及び多様化がさらに進み、国際的に新たな機器の装備が義務化されたり、装備すべき航空機の対象範囲が拡大することが予想されるが、我が国も運航の安全向上の観点から、こうした機器の装備を義務化する国際的な動きに迅速に対応する必要がある。
 V.その他航空安全に関する事項
V.その他航空安全に関する事項
 1.安全に関連する情報
1.安全に関連する情報
- これまで航空会社の安全に関連する情報については、航空事故情報、異常運航情報等が国により報道機関等に公表されてきた。今後、需給調整規制の廃止に伴い航空会社間の競争が促進され、利用者の選択の幅がより広がり、輸送サービスに関する各種の情報に対するニーズが高まることが予想される。このような状況の中で、利用者の関心が高いと考えられる安全に関連する情報についても、利用者に対して十分かつ適切に公開される必要がある。
- この場合、国及び航空会社等が各々の役割に基づき情報を公開することが適当と考えられるが、具体的に公開する情報の範囲、内容、公開方法等について、今後更に検討を行うことが適当である。
 2.システム認証の活用
2.システム認証の活用
- 民間事業者の能力の向上を踏まえ、国の認証業務の効率化及び受検者の利便の向上を図るため、従来国が個別的に直接行っている検査又は試験業務等については、可能な限り認定事業場、指定航空従事者養成施設等の民間事業者が実施する方向に移行し、国はこうした民間事業者の能力を認証する方式を一層活用すべきである。また、このようなシステム認証の活用にあたっては、国は認証後もこれらの事業者の業務が適切に行われていることを確保するため、業務の実施状況、基準への適合状況等についての随時監視を充実する必要がある。
 3.外国航空機の安全確保
3.外国航空機の安全確保
- 国際運航を行う航空機については、国際民間航空条約により原則当該航空機の登録国が運航の安全確保に関する責務を負うものとされており、また航空会社の安全監督責任も当該航空会社の所属する国の当局にあるという原則から、我が国に乗り入れている外国航空機の安全性について特に確認等を行っていない。しかしながら、近年外国航空機の事故が我が国において発生していること、外国航空機を利用する我が国の利用者が多いこと等から、外国航空機の安全性についても関心が高まってきている。
- このため、我が国に乗り入れている外国航空機の安全の確保に資する観点から、国際民間航空機関(ICAO)が行っている安全監視プログラム(Safety Oversight Program)に我が国も積極的に参画していくと同時に、外国航空機に対する検査(ランプ・インスペクション)を早急に実施すべく欧米等の諸外国の例を参考としつつ、必要な検査体制の整備、検査方法等の具体化を図っていく必要がある。
 おわりに
おわりに
航空輸送の安全は、国、航空会社といった直接の関係者のみならず利用者を含めた全関係者の関心と行動により培われるものである。各関係者は、それぞれの立場において、航空輸送の安全確保のための取り組みを行うことが重要である。
その上で、本答申は、我が国の航空安全行政を取り巻く情勢を踏まえ、航空安全規制の基本的考え方について整理を行い、航空運送事業に関する安全規制を中心として、今後の航空安全行政の方向及び必要となる施策を示したものである。国においては、本答申に基づき、所要の施策をできる限り早期に、かつ確実に実施していく必要がある。
また、航空輸送サービスの提供者である航空会社においては、安全の確保に関する自己の責任の重大性を十分に認識し、更に安全性を維持・向上する努力を行っていくことが望まれる。
最後に、来るべき21世紀においても、航空安全行政を取り巻く情勢は引き続き変化していくものと考えられる。本答申に示した施策にとどまらず、更に安全性の維持・向上を図ると同時に、安全規制を時代の要請に応じて引き続き見直していくことを望むものである。
 用語解説
用語解説
- 1.国内航空運送事業の需給調整規制
- 国内航空運送事業を営もうとするときには、路線毎に免許を受ける必要があるが、その免許基準の一つとして、航空法に「当該事業の開始によって当該路線における航空輸送力が航空輸送需要に対し、著しく供給過剰とならないこと」と規定されている。この規定が需給調整規制と言われている。
- 2.国際民間航空条約
- 国際民間航空条約(通称「シカゴ条約」)は、1944年にシカゴで作成された現に効力を有する国際航空に関する基本的法規であり、領土及び領水の上空における国家主権の確認、国際航空における規制の制定、国際民間航空機関(ICAO)の設置等を定めたもの。同条約の中で、各締約国は、航空に関する規則、標準等の統一に協力することを約束し、このため、ICAOが国際標準並びに勧告される方式及び手続を随時採択・改正し、これを同条約の附属書とすることを定めている。
- 3.ウェットリース、運航委託
- ウェットリースは、我が国の航空会社が、乗員と航空機材をパッケージにして他の我が国の航空会社にリースすること。
- 運航委託は、我が国の航空会社が、自ら運航の管理を行いながら、外国航空会社に対して特定の国際路線における実際の運航を委託すること。
- 4.航空機の耐空類別
- 航空機の安全性を確保するための基準は、航空機の種類及び用途等に応じて区分し設定されているが、この区分を耐空類別と呼んでいる。例えば、航空運送事業の用に適する飛行機は、「飛行機 輸送T」の耐空類別が適用され、この用途に適合するように、性能、強度、構造、装備等についての基準が定められている。
- 5.指定定期航空運送事業者
- 定期航空運送事業者のうち、当該事業者の機長の訓練及び審査体制が一定の基準に適合するとして指定された事業者。当該事業者が審査を行い認定を行った機長については、機長路線資格について国の認定を受けなくてもよい。
- 6.認定事業場
- 航空機の整備・検査、整備・改造等の能力について一定の技術上の基準に適合すると認められた事業場。航空機の整備・検査の能力の認定を受けた事業場が確認した航空機については、耐空証明の更新において国の検査が省略される。また、航空機の整備・改造の能力の認定を受けた事業場が確認した航空機については、国の修理改造検査が省略される。
- 7.コミューター航空(二地点間旅客輸送)
- 国内の特定の二地点間において、座席数が60席以下の飛行機を使用し、反復継続(30日間に15往復を超える頻度をもって反復し、かつ、30日を超えて継続)して行われる旅客輸送のこと。主に、都市間輸送や離島路線等比較的小規模かつ地域的な航空輸送需要に対応した輸送を担っている。航空法上は、不定期航空運送事業として扱われている。
- 8.指定航空従事者養成施設
- 一定の基準に適合するとして指定された航空従事者の養成施設。指定航空従事者養成施設の課程を修了した者について、航空従事者技能証明の試験の一部又は全部が省略される。
- 9.ICAO安全監視プログラム
- 国際民間航空条約の締約国における安全監視体制(法制度、組織、人員等)を国際標準・勧告方式にてらして審査し、必要な助言及び支援を行うためにICAOが行っているプログラムのこと。現在は要請した国のみが評価の対象となっているが、今後対象を全締約国に拡大し、かつ定例的に実施するなど、現行のプログラムを強化することが合意されている。
- 10.外国航空機に対するランプ・インスペクション
- 国際民間航空条約第16条に基づき、自国の空港に乗り入れている外国航空機について駐機中に耐空証明書等の検閲等を行う検査のこと。欧米では外国航空会社の事故により自国民が犠牲になった事例から、最近検査が積極的に行われるようになってきている。