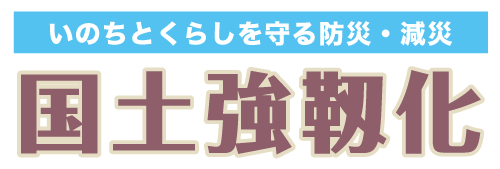インタビュー Think! 国土強靱化
死なないための対策を第一に
ハザードマップでのリスク把握など
自助行動を
高荷 智也 氏(備え・防災アドバイザー/BCP・危機管理アドバイザー)
Profile
合同会社ソナエルワークス 代表社員。備え・防災アドバイザーとして「自分と家族が死なないための防災」をテーマに、地震・水害・パンデミックなどの自然災害から、銃火器を使わないゾンビ対策まで、堅い防災を分かりやすく伝える活動に従事。防災系Youtuber・Voicyパーソナリティ としても活躍中。BCP策定アドバイザーとしても活動している。
もし大規模な災害が発生してしまったら、発生後の速やかな復旧も重要にはなりますが、まずは発生時に命を守ることが大前提となります。そういった災害発生時の防災対策を特に重視して各メディアを通じた情報発信など行っている高荷智也氏に、ご自身の取組内容やお話を伺いました。
(取材内容は2025年2月当時のもの)
「死なないための防災」について幅広い層に向け様々な手法で情報発信を展開
今私自身は「備え・防災アドバイザー」という肩書きで、大学や防災関連の企業には所属せずにフリーでお仕事をしています。
個人と家庭向けに一番のテーマとして掲げているのは「死なないための防災」です。皆さんに防災の情報をお伝えするような講演のお仕事、防災に関する書籍や各媒体への執筆活動、テレビラジオなどの各種メディアへの出演、企業向けのコンサルティングや防災グッズの開発などに携わっています。その他、自前のメディアとして、「備える.JP」というウェブサイトを使っての防災情報の配信、YouTubeで「死なない防災!そなえるTV」という防災動画の配信チャンネルを運営したり、webのラジオで毎日情報発信をしていますし、防災グッズ・備蓄用品を販売するネットショップも自分で運営しています。
同じ情報でも媒体やプラットフォームが変わりますと聞き手の方々が全然変わったりして、講演会だと高齢者の方が中心になりますし、逆に YouTube などは若い方々が中心になります。一つの話も場所が変われば聞く方が変わるので、ひとつの情報を複数のプラットフォームでお伝えをすることで多くの方に防災のことを学んでいただけるよう活動しています。
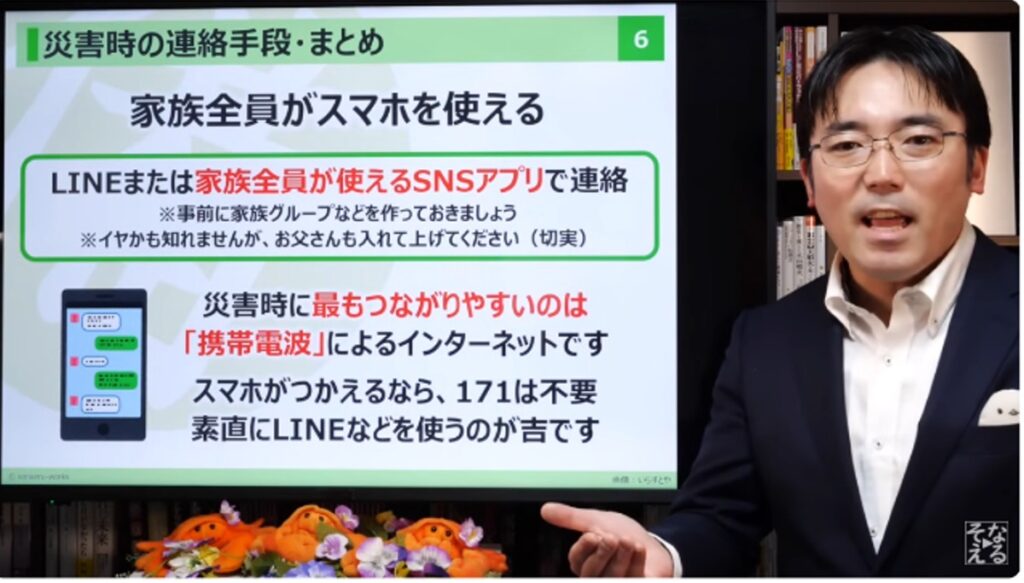
ポイントとなるのはまずハザードマップをいかに皆さん自身で見ていただくか
皆さんにご紹介する情報として重視しているのが、ハザードマップを見ていただくこと。自分自身でリスクを把握するという意味合いで、ハザードマップをいかにして皆さん自身で見ていただくかがポイントで、自分で解釈をして避難の方針を定めていただくことが重要です。
ハザードマップも基本的には各自治体が作っている自分の町の地図を紙かウェブで見ていただくということが第一ですよとは言いつつも、なかなか紙の地図がなかったり、もらいに行くのも大変で画面で見るにしてもスマホだと小さすぎて見えづらいことがあります。どうやって見るのかが自治体によってフォーマットや見せ方が違ったりもしますので、すごくハードルが高くて地図を見るところで挫折するケースっていうのが多かったと思うんですね。
それが、国土交通省から「重ねるハザードマップ」が出てきたことによって、とりあえずこのページをスマホで見ていただければ今この場でチェックできますよ、という風になったことは素晴らしく、せっかく作った情報も見られないと意味がないので、アクセシビリティを改善したという点でも良い取組だと思い、活動の中でも「重ねるハザードマップ」をご紹介する機会はかなり多いです。

災害から命を守るためにはまずは自助行動を無理のない範囲で
防災で大事なことは、とにかく命を守ること、とりわけ災害で即死しないこと。防災ではよく公助・共助・自助の3つが言われますが、公助や共助は基本的には生き延びた方向けへの対策になるので、災害から命を守るのは自助が9割ということをよく言っています。
新生活などをきっかけに住まいを選ぶ際には、地震で潰れない家に住むことが一番重要だと考えていて、地震で潰れない家に住んでいれば、何にもしなくても防災が半分以上できていることになると思いますし、地震で潰れてしまうお家に住んでしまうと何をしても全部無駄になる可能性があります。
防災グッズについては、防災だけのために何か買うって結構ハードルが高かったりしますし、買ってもすっかり忘れてしまったり、どこにあるかわからなくなる場合もあるので、私自身も普段から生活に役立ってついでに災害時にも役立つようなものを、私自身も積極的に選ぶようにしています。いわゆる日常備蓄やローリングストックと言われる方法で、あまり特別なものを買いすぎずに、普段利用しているものを少し多めに買っておくことで備えになります。
日々外出時に持ち歩く物として最低限何がいいですかと聞かれたら、ライトと自分の居場所などを知らせるための笛、あと小さくていいのでポケット雨具、それからモバイルバッテリー、この4点を挙げています。雨具は体温の維持ですね。雨に濡れた状態で体が乾かせなくなりますと結構容易に凍死する恐れがあります。命を守るために即死に近いことを防げるような道具を皆さん携帯しましょうということで、私自身も常に持ち歩いています。

インフラ整備等で災害リスクが減った一方で個人のリスク把握がより重要に

国土強靱化における水害対策に関しては、いろいろな河川の改修や河川の付け替えのような大規模な治水工事で抜本的に水害のリスクを減らすといった取組は非常に大切なことだと思いますが、一方で治水対策のソフト面においてハザードマップのさらなる整備とそれをきちんと伝えていくこともすごく重要です。
最近都市部では治水などの改良が進んで、小規模な水害が減っていると思いますし、今まで氾濫していた河川に大雨が降っても水が溢れなくなったこと自体は治水が進んだからということですばらしいと思うんですが、一方で、一度も水害を経験したことがなく、人生初の水害が100年に1回しか起きないような致命的なものになる可能性が逆に高くなってきていますので、治水対策によって実感する機会が無くなったリスクを国民が知っておくための啓蒙をしていく必要があると感じています。
また、これからはインフラの新規作成も当然あるとは思いますが、それ以上に今までつくってきたものをいかにして維持更新、あるいは縮小するかという判断も出てくると思います。そういう国全体として残すもの、使うものをきちんと選択をして、残すと決めたものをいかにして更新をかけていくのかということも大事だと思います。