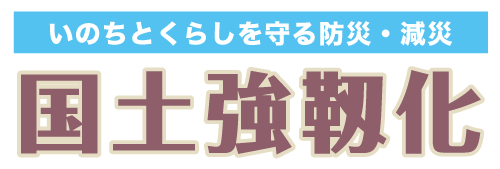インタビュー Think! 国土強靱化
「フェーズフリー」な取組を通じて
皆が災害から助かる社会へ
奥村 奈津美 氏(防災アナウンサー)
Profile
広島、仙台で8年間地方局アナウンサーとして活動後、2013年からフリーアナウンサーに。東日本大震災を仙台の放送局のアナウンサーとして経験して以来、以来14年以上、全国の被災地を訪れ、取材や支援ボランティアに力を入れる。防災士、福祉防災認定コーチ、防災教育推進協会講師、防災住宅研究所理事、危機管理教育研究所災害対応コーディネーターなどとして防災啓発活動に携わるとともに、環境省 森里川海プロジェクトアンバサダーとして「防災×気候変動」をテーマに取材、発信中。一児の母。
国土強靱化の推進に向けては、行政側の取組だけでなく、国民の皆様一人ひとりの防災意識や行動も重要となります。今回は、防災アナウンサーとして幅広く防災啓発活動をされている奥村奈津美氏に、ご自身の活動内容や防災教育の重要性などについてお話を伺いました。
(取材内容は2025年2月当時のもの)
情報発信等の啓発活動を通じて目指す「みんなで助かる防災」
東日本大震災時に仙台の放送局でアナウンサーをしていたのですが、そこで一番痛感したのが「起きてからでは手遅れ」ということでした。そのため「起きる前にできること」の防災啓発活動に力を入れています。
災害時、厳しい状況になる妊娠中の方や赤ちゃんを抱えている方など、パパ・ママに向けた防災情報を、Instagramを活用して発信しています。さらに、もう少し詳しく知りたいなと思ってくださった方向けにYouTubeも「妊娠・出産した ら見る防災チャンネル」というテーマで発信してしいます。パパ・ママはやはり忙しくて、普段の生活でもできていないことがたくさんある状況で、自分の時間もない中、さらに防災対策となると本当にハードルが高いので、検索してすぐ見られる状態になったらいいなということで、いろいろな手法を使って、防災に関心のない方にも取り組んでいただけるような情報発信を心がけています。
また、災害時に苦しい状況になったり、災害関連死につながってしまう現状がある高齢者など福祉防災や、福祉施設への支援活動にも力を入れています。他にも防災教育推進協会に所属し、防災検定のテキスト執筆、色々な小中学校や高校で防災の授業をさせていただいたり、環境省の森里川海プロジェクトアンバサダーでもあるので、「気候変動×防災」についても発信しています。

家の対策を進めることが防災では特に重要に
地震対策の一丁目一番地は、家の耐震化です。耐震性の低い家に暮らしていると、地震の揺れで家の下敷きとなり、命を失う恐れがありますし、さらには、家が壊れると、避難所で何ヶ月も過ごすような厳しい状況に置かれてしまうことを考えると、ハード面の対策として最も力を入れなくてはいけないと思います。一方で耐震化の難しさというのも感じていて、やはりお金がかかって工事ができないというケースもあったりするので、本当にハードルが高いんだなと思うことがあります。だからこそ、行政側から耐震補強について前向きになれるような、工事費用の補助など施策をお願いしたいです。
また、水害においては避難が難しい時代になっている、ということを受け止めなければならないと思っています。ゲリラ豪雨や線状降水帯のような、山が保水できないぐらい急激に雨が降るような時代になっているので、危険な場所に住んでいる方に関しては住まいを変える、もしくはこれから新しく建てる人だけでもそういった場所に家を建てることを規制する、もしくは土砂災害などにも耐えられる壁式鉄筋コンクリートパネル組立造(あらかじめ⼯場内で作られたコンクリート・パネルを建設現場で箱型に組み⽴てる⼯法)などを推奨していくみたいな流れが必要なのだと思います。
国民皆が防災意識を持って動けるようになるために必要な防災教育の充実
防災では「人が人の命を守る」と思っていて、全ての人が防災に対して教育を受けられるシステムがあったらいいなと感じています。今は努力しないとできなかったりします。自治体の職員さんに関しても担当課になって初めて災害対応業務を学ぶことがあったり、知識がないまま発災してしまうこともある。一人ひとりのマンパワーが被災地で助かる確率を上げていくことに繋がるのだとすると、全員が防災知識を持って動ける必要があると思います。もちろん、その建物が頑丈であるとか、ハード面の対策が整っていることで救える命もあると思いますが、災害が起きた時には自分で自分の命を守るしかないです。
防災教育の格差を無くし、例えば、受験にも防災の要素が入ってくれると、本気で勉強しないといけなくなるので良いのではないか思うことがあって、社会人になって入社試験でその会社のBCPを学ぶ機会などもあると良いと思います。

日常にも防災にも活用できる「フェーズフリー」な備えを

「人は備えられない生き物」ということをひしひしと感じていまして、でもそれが結局人間の特性と思うと、「フェーズフリー」であるってことが一番大事だなと思っています。このフェーズフリーは普段も生活の中で取り入れられるし、災害時も役立つ。フェーズがフリーになっている商品や暮らし方、アイデアなどを指します。
備えられない前提で国土強靱化について考えた時、被災後何に困るかというとやはりライフラインの寸断です。そこでライフラインではなく「ライフポイント」と呼べるような家がたくさんあることで、地域がより強靭化されると思うんですね。例えば、太陽光パネルと蓄電池を設置してなるべく自分の家で電気を発電してためて使う。そうすると地域が停電したとしても、少なくとも自分の家は停電しなくて済みます。各家庭に設置していたら停電しない街を作れると思います。
同じように、もっと雨水の活用も国を挙げてやっていただきたいと思っていて、各家庭に雨水を活用できるよう設備が設置されると、ゲリラ豪雨などの場合も、被害の軽減につながるのではと考えています。また長期間の断水で被災地はすごく困っています。でも各家に雨水を貯める設備があればそれがライフポイントになるので、雨さえ降れば完全に水がない状態を防げるのかなと思います。
いつどこで被災するか分からないですし、いつも身構えるのは無理があるので、生活の中にあるものが、フェーズフリーを意識をして作られていると、より良い社会になっていくと思います。