国土交通白書 2024
特集 令和6年能登半島地震への対応
復旧・復興に向けた取組として、内閣府とともに、住まいを失った被災者に、一日も早く、応急的な住まいを確保することとし、公営住宅・民間賃貸住宅の空室利用や、応急仮設住宅の建設を速やかに進めた。
政府でも、非常災害対策本部において、1月25日、緊急に取り組むべき施策について、「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」として取りまとめた。
国土交通省としても、一日も早い被災地の早期復旧、生活と生業の再建に向け、住宅の再建、観光需要喚起に向けた対策、公共土木施設等の災害復旧等や交通の確保等を掲げ、引き続き、地域に寄り添った支援を行うこととしている。
(1)住宅の再建
国土交通省は、被災者の住まいの確保を精力的に進め、能登地域における住宅再建や補修等を支援している。
住まいを失った被災者の方々には、避難生活の一刻も早い解消を図るため、応急的な住まいに移っていただけるよう、2次避難の推進や、公営住宅・民間賃貸住宅の空室活用、応急仮設住宅の建設を速やかに進めている。
①2次的避難所の確保・輸送方法
国土交通省は、宿泊関係団体等に対し旅館・ホテル等への被災者の受入れについての協力を要請した。4月19日時点で166施設、2,232人が受入れが決定済となっている。
②応急的な住まいの確保
公営住宅等については、全国の地方公共団体に対し、被災者の一時的な住まいとして、公営住宅等の空き住戸の提供への協力を要請した。即入居可能な住宅を、全国で約9,500戸確保したほか、高齢者が安心して暮らせるよう、各種相談等に対応する「生活支援アドバイザー」を配置したUR賃貸住宅を、全国で300戸確保した(4月19日時点)。
賃貸型応急住宅については、賃貸・不動産関係団体に対し、被災者に対する民間賃貸住宅の情報提供や、応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げについての必要な協力を要請した。
石川県内では、提供可能戸数約4,500戸のうち、入居決定戸数は3,253戸となった(4月19日)。また、石川県から近隣県に転居する場合は、新潟県:1,000戸、富山県:1,500戸、福井県:1,200戸が提供可能となっている。
建設型応急住宅については、住宅生産関係団体に協力を要請し、石川県で3月末までに約5,000戸が着工済(1,643戸完成)である。4月19日現在、応急仮設住宅は5,382戸着工し、うち1,957戸が完成している。
ムービングハウス

プレハブ

トレーラーハウス

木造(長屋型)

(2)観光需要喚起に向けた対策
北陸地方においては、通常通りの営業が可能な地域でも、予約のキャンセルが相次ぐ宿泊施設が多数発生しているなど、観光業界が大きな打撃を受けた。
①北陸応援割
今般の令和6年能登半島地震による風評被害を早期に払拭するため、キャンセルにより失われた旅行需要を新たに喚起することを目的に、北陸4県において、国内旅行者や訪日外国人旅行者を対象に旅行代金の割引を支援する「北陸応援割」を実施し、観光需要を喚起した。能登地域については、復興状況を見ながら、より手厚い旅行需要喚起策を検討することとしている。
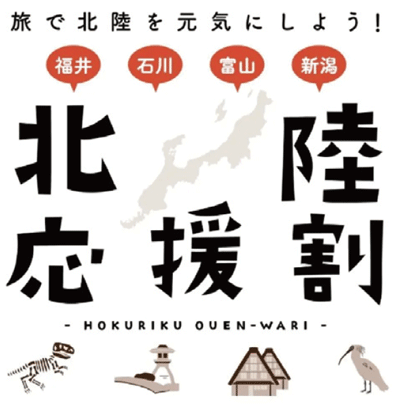
②風評被害対策プロモーション
また、観光復興に向けては、観光庁のウェブサイト等を通じて、観光地や交通機関の現状に関する正確な情報を発信するとともに、被災地域の意向を踏まえつつ、JNTOウェブサイトやSNSによる海外向け情報発信等で、北陸地域の観光プロモーションを実施している。
(3)復興まちづくりの基盤づくり
国土交通省では、復興まちづくりの基盤となる災害復旧等を急ぐため、自治体に代わり、国が責任を持って本格復旧まで行う権限代行も活用し、道路、河川、港湾、漁港等の迅速な災害復旧を推進している。
①被災状況調査、資料収集、事業相談等対応
地震により著しい被害が発生した被災自治体が行う復興まちづくりを支援するため、都市局職員(TEC-FORCE)を石川県、富山県、新潟県に派遣し、被災状況調査、資料収集、事業相談等の対応を20市町にて実施した。
②令和6年能登半島地震からの復興まちづくり計画の策定に向けた支援
被災市町や被災地域の住民のニーズ、意向に寄り添い、直轄調査の実施により、被災市町における復興まちづくり計画の策定を支援するとともに、国土交通省職員による地区担当の配置、都市再生機構による技術支援、関係省庁連携による横断的支援等により、復興まちづくりを継続的に支援していく。
③液状化災害の調査、再発防止
国土交通省では、発災以降、TEC-FORCEによる現地調査を実施したほか、国・県・被災市町村による会議等を通じて、液状化対策に関する支援制度や取組事例について情報提供してきた。
また、液状化に伴い、地表面が横方向に移動する、いわゆる「側方流動」が発生し、特に著しい液状化被害が集中した地域については、地形・地質等の条件を踏まえた、効率的な対策工法を検討することとしている。
加えて、地方公共団体が実施する、公共施設と隣接宅地等の一体的な液状化対策に対する支援策である「宅地液状化防止事業」について、補助率を通常の1/4から1/2に引き上げるなど、支援策の強化を行い、被災市町村による取組みを支援している。
被災地の円滑な復旧・復興に向けては、宅地液状化防止事業により面的な液状化対策等を行うことが重要となるため、国の直轄調査によって得られた知見の活用等により、被災した地方公共団体に対する技術的支援を行い、可能な限り広い範囲で早期の事業化が実現するよう支援することを通じて、液状化による被害が再び発生しないようなまちづくりを推進していく。
(4)交通の確保
①被災鉄道事業者等の早期復旧支援
地域公共交通は、地域住民の通勤・通学の足として、地域社会の生活の基盤であることから、移動手段の早急な確保・再構築に取り組んでいる。
被災した能登空港、のと鉄道等の早期復旧について、TEC-FORCE、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の鉄道災害調査隊(RAIL-FORCE)による技術的助言を実施するなど、必要な支援を行っている。また、道路管理者等、関係者との連携も確保し、効果的に事業を行うとともに、航路標識等の早期復旧を行った。
②生活の足の確保
鉄道の運休区間における移動手段を確保するため、国が鉄道事業者等とバスによる代替輸送について調整を行うとともに、運行経費に対する支援を講じた。また、代替輸送の情報について、国土交通省HP等で発信すること等を通じ、利用者の利便性の確保を行った。
また、被災地における公共交通の輸送力を確保するため、バス事業者やタクシー事業者に対し、道路運送法の弾力的運用を行った。