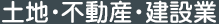土地・建設産業局メールマガジン 第4号(H30.4.6)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
国土交通省土地・建設産業局メールマガジン H30.4. 6(金) 第4号
【目 次】
・トピックス
地方圏で26年ぶりの地価上昇 ~平成30年地価公示の結果を公表~
「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定 ~官民一体となって建設業の働き方改革を加速~
・土地・建設産業ミニコラム
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
━━ トピックス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆地方圏で26年ぶりの地価上昇
~平成30年地価公示の結果を公表~
国土交通省が3月27日に公表した平成30年地価公示では、全国的に広くゆるやかな地価の回復傾向が明らかとなりました。
特に地方圏では、商業地の平均が、平成4年以来26年ぶりに上昇に転じ、住宅地を含めた全用途の平均でも、26年ぶりに
下落を脱して横ばいに転じました。
〇今年で49回目となる平成30年地価公示は、全国約26,000地点を対象に実施され、本年(平成30年)1月1日時点の
地価動向として、次のような結果が得られました。
【全国平均】 住宅地平均が10年ぶりに上昇。商業地及び全用途平均は、3年連続で上昇。
【三大都市圏】住宅地・商業地平均ともに、各圏域(東京圏・大阪圏・名古屋圏)で上昇。
【地方圏】商業地平均が26年ぶりに上昇、全用途平均でも26年ぶりに横ばいに。住宅地平均は下落幅縮小が継続。
〇前回の地価上昇ピーク時の平成20年と比べると、三大都市圏の地価上昇が相対的にゆるやかで、上昇地点数も減少する
一方、地方圏の地価上昇地点が大幅に増加していることが特徴です。個別地点の地価変動率を地図上にプロットすると、
その傾向の違いが明らかです。平成20年は、上昇地点13,416地点のうち、地方圏の地点は1,923地点と、全体の1割程度しか
なかったのに対して、今回の結果では、上昇地点10,568地点のうち3,839地点と、全体の約1/3を占める結果となりました。
図:地価公示標準地(全用途)の変動率分布(平成20年・平成30年)
表:上昇・横ばい・下落の地点数の推移(平成20年・平成30年ほか)
〇背景として、全国的に、[1]雇用・所得環境が改善する中で、利便性の高い地域を中心に住宅地の地価が回復していること、
[2]外国人観光客の増加による店舗・ホテル需要の高まり等を背景に、商業地の地価が総じて堅調に推移していること、
が挙げられます。
〇結果の詳細は、「地価公示」のページを御覧ください。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000043.html
〇個別地点の価格等は、標準地・基準地検索システムに掲載しています。
http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0
◆「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定
~官民一体となって建設業の働き方改革を加速~
国土交通省は、建設業における週休2日の確保をはじめとした働き方改革をさらに加速し、将来の担い手を確保するため、
長時間労働の是正、給与・社会保険、生産性向上の3つの分野における新たな施策をパッケージとしてまとめた「建設業働き方
改革加速化プログラム」を策定しました。今後3分野での新たな施策について関係者が認識を共有し、密接な連携と対話の下で
施策を展開してまいります。プログラムの主な内容は以下のとおりです。
主な内容
(1)長時間労働の是正に関する取組
[1]週休2日制の導入を後押しする
公共工事における週休2日工事を大幅に拡大するとともに、週休2日の実施に伴う必要経費を的確に計上するため、労務費等の
補正の導入、共通仮設費、現場管理費の補正率の見直しを行います。
[2]各発注者の特性を踏まえた適正な工期設定を推進する
長時間労働とならない適正な工期設定を推進するため、各発注工事の実情を踏まえて「適正な工期設定等のためのガイドライン」を
改訂します。
(2)給与・社会保険に関する取組
[1]技能や経験にふさわしい処遇(給与)を実現する
技能者の資格や現場の就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積する建設キャリアアップシステムの今秋の稼働と、概ね5年での全ての
建設技能者(約330万人)の加入を推進します。
また、技能・経験にふさわしい処遇(給与)が実現するよう、建設技能者の能力評価制度を策定します。さらに、能力評価制度の検討
結果を踏まえ、高い技能・経験を有する建設技能者に対する公共工事での評価や当該技能者を雇用する専門工事企業の施工能力等
の見える化を検討します。
[2]社会保険への加入を建設業を営む上でのミニマム・スタンダードにする
社会保険に未加入の建設企業は、建設業の許可・更新を認めない仕組みを構築します。
(3)生産性向上に関する取組
[1]生産性の向上に取り組む建設企業を後押しする
中小の建設企業による積極的なICT活用を促すため、公共工事の積算基準等を改善します。
[2]仕事を効率化する
工事書類の作成負担を軽減するため、公共工事における関係する基準類を改定するとともに、IoTや新技術の導入等により、施工
品質の向上と省力化を図ります。
[3]限られた人材・資機材の効率的な活用を促進する
現場技術者の将来的な減少を見据え、技術者配置要件の合理化を検討します。
※プログラムの詳細は以下のURLをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000561.html
━━ 土地・建設産業ミニコラム ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~第4回 建設キャリアアップシステムの構築~
前回のコラムで、建設業と製造業の現場で働く者の賃金水準には、5%程度の乖離があるというグラフをご紹介いたしました。
この賃金水準の乖離は、どこに由来するのでしょうか。
建設業と製造業における年齢階層別の賃金水準を比較すると、製造業の賃金のピークは50歳代前半であるのに対し、建設業は
40歳代後半でピークを迎えています。いわば、体力のピークが賃金のピークになっていると推察されます。
図:年齢階層別の賃金水準
経験を積み重ね、現場の工程管理や後進の指導などのスキルを身に付けたベテラン技能者により建設現場が支えられている一方、
その経験やスキルがしっかりと把握されず、適切な評価や処遇に結びついていない可能性があります。
こうした中、技能者一人ひとりの経験や技能を業界全体でしっかりと把握し、適正な評価や処遇に繋げるための仕組みや施策の
構築が具体化しつつあります。その仕組みが、本年秋に運用を開始する「建設キャリアアップシステム」です。
建設キャリアアップシステムは、建設技能者の就業履歴や保有資格を、業界横断的に登録・蓄積する仕組みであり、具体的には、
・技能者は、保有資格などの情報をシステムに登録することで、一人ひとり固有のICカード(キャリアアップカード)を取得します。
・このカードを、現場に置かれたカードリーダーにかざして読み取ります。
・これによって、いつ、どの現場で、どのような作業に従事したのか、といった情報が、業界統一のルールで、システムに蓄積されて
いきます。また、保有資格などについても、システム上で簡易に確認することができます。
図:建設キャリアアップシステムの構築
このシステムにより、技能者一人ひとりの経験や技能の客観的な把握が可能となることから、技能者の客観的かつ大まかなレベル
分けが可能となります。このレベルに応じて、キャリアアップカードを色分けする予定です。また、専門工事企業が、どのレベルの
技能者を何人雇用しているのかといった情報を「見える化」することにより、優秀な職人を育て、雇用する企業が選ばれる環境整備
に繋がります。
また、事業者にとっては、書類作成の簡素化・合理化が図られるといったメリットも期待されます。
図:建設キャリアアップシステムのメリット
システムへの登録受付はこの4月から順次開始され、本年秋に現場での利用が開始される予定です。国土交通省では、概ね5年
での全ての建設技能者(約330万人)の加入を推進するため、システムの周知・普及に取り組んでいます。
また、技能者の処遇改善に繋がるよう、システムを活用した施策(技能者の能力評価制度の策定・専門工事企業の施工能力等の
見える化)の構築に取り組んでいるところであり、これらについては次の機会にご紹介させていただきます。
土地・建設産業メールマガジン 一覧へ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■国土交通省土地・建設産業局メールマガジン編集部(総務課内)
Tel : 03-5253-8373 Fax : 03-5253-1576
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国土交通省土地・建設産業局メールマガジン H30.4. 6(金) 第4号
【目 次】
・トピックス
地方圏で26年ぶりの地価上昇 ~平成30年地価公示の結果を公表~
「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定 ~官民一体となって建設業の働き方改革を加速~
・土地・建設産業ミニコラム
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
━━ トピックス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆地方圏で26年ぶりの地価上昇
~平成30年地価公示の結果を公表~
国土交通省が3月27日に公表した平成30年地価公示では、全国的に広くゆるやかな地価の回復傾向が明らかとなりました。
特に地方圏では、商業地の平均が、平成4年以来26年ぶりに上昇に転じ、住宅地を含めた全用途の平均でも、26年ぶりに
下落を脱して横ばいに転じました。
〇今年で49回目となる平成30年地価公示は、全国約26,000地点を対象に実施され、本年(平成30年)1月1日時点の
地価動向として、次のような結果が得られました。
【全国平均】 住宅地平均が10年ぶりに上昇。商業地及び全用途平均は、3年連続で上昇。
【三大都市圏】住宅地・商業地平均ともに、各圏域(東京圏・大阪圏・名古屋圏)で上昇。
【地方圏】商業地平均が26年ぶりに上昇、全用途平均でも26年ぶりに横ばいに。住宅地平均は下落幅縮小が継続。
〇前回の地価上昇ピーク時の平成20年と比べると、三大都市圏の地価上昇が相対的にゆるやかで、上昇地点数も減少する
一方、地方圏の地価上昇地点が大幅に増加していることが特徴です。個別地点の地価変動率を地図上にプロットすると、
その傾向の違いが明らかです。平成20年は、上昇地点13,416地点のうち、地方圏の地点は1,923地点と、全体の1割程度しか
なかったのに対して、今回の結果では、上昇地点10,568地点のうち3,839地点と、全体の約1/3を占める結果となりました。
図:地価公示標準地(全用途)の変動率分布(平成20年・平成30年)
表:上昇・横ばい・下落の地点数の推移(平成20年・平成30年ほか)
〇背景として、全国的に、[1]雇用・所得環境が改善する中で、利便性の高い地域を中心に住宅地の地価が回復していること、
[2]外国人観光客の増加による店舗・ホテル需要の高まり等を背景に、商業地の地価が総じて堅調に推移していること、
が挙げられます。
〇結果の詳細は、「地価公示」のページを御覧ください。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000043.html
〇個別地点の価格等は、標準地・基準地検索システムに掲載しています。
http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0
◆「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定
~官民一体となって建設業の働き方改革を加速~
国土交通省は、建設業における週休2日の確保をはじめとした働き方改革をさらに加速し、将来の担い手を確保するため、
長時間労働の是正、給与・社会保険、生産性向上の3つの分野における新たな施策をパッケージとしてまとめた「建設業働き方
改革加速化プログラム」を策定しました。今後3分野での新たな施策について関係者が認識を共有し、密接な連携と対話の下で
施策を展開してまいります。プログラムの主な内容は以下のとおりです。
主な内容
(1)長時間労働の是正に関する取組
[1]週休2日制の導入を後押しする
公共工事における週休2日工事を大幅に拡大するとともに、週休2日の実施に伴う必要経費を的確に計上するため、労務費等の
補正の導入、共通仮設費、現場管理費の補正率の見直しを行います。
[2]各発注者の特性を踏まえた適正な工期設定を推進する
長時間労働とならない適正な工期設定を推進するため、各発注工事の実情を踏まえて「適正な工期設定等のためのガイドライン」を
改訂します。
(2)給与・社会保険に関する取組
[1]技能や経験にふさわしい処遇(給与)を実現する
技能者の資格や現場の就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積する建設キャリアアップシステムの今秋の稼働と、概ね5年での全ての
建設技能者(約330万人)の加入を推進します。
また、技能・経験にふさわしい処遇(給与)が実現するよう、建設技能者の能力評価制度を策定します。さらに、能力評価制度の検討
結果を踏まえ、高い技能・経験を有する建設技能者に対する公共工事での評価や当該技能者を雇用する専門工事企業の施工能力等
の見える化を検討します。
[2]社会保険への加入を建設業を営む上でのミニマム・スタンダードにする
社会保険に未加入の建設企業は、建設業の許可・更新を認めない仕組みを構築します。
(3)生産性向上に関する取組
[1]生産性の向上に取り組む建設企業を後押しする
中小の建設企業による積極的なICT活用を促すため、公共工事の積算基準等を改善します。
[2]仕事を効率化する
工事書類の作成負担を軽減するため、公共工事における関係する基準類を改定するとともに、IoTや新技術の導入等により、施工
品質の向上と省力化を図ります。
[3]限られた人材・資機材の効率的な活用を促進する
現場技術者の将来的な減少を見据え、技術者配置要件の合理化を検討します。
※プログラムの詳細は以下のURLをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000561.html
━━ 土地・建設産業ミニコラム ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~第4回 建設キャリアアップシステムの構築~
前回のコラムで、建設業と製造業の現場で働く者の賃金水準には、5%程度の乖離があるというグラフをご紹介いたしました。
この賃金水準の乖離は、どこに由来するのでしょうか。
建設業と製造業における年齢階層別の賃金水準を比較すると、製造業の賃金のピークは50歳代前半であるのに対し、建設業は
40歳代後半でピークを迎えています。いわば、体力のピークが賃金のピークになっていると推察されます。
図:年齢階層別の賃金水準
経験を積み重ね、現場の工程管理や後進の指導などのスキルを身に付けたベテラン技能者により建設現場が支えられている一方、
その経験やスキルがしっかりと把握されず、適切な評価や処遇に結びついていない可能性があります。
こうした中、技能者一人ひとりの経験や技能を業界全体でしっかりと把握し、適正な評価や処遇に繋げるための仕組みや施策の
構築が具体化しつつあります。その仕組みが、本年秋に運用を開始する「建設キャリアアップシステム」です。
建設キャリアアップシステムは、建設技能者の就業履歴や保有資格を、業界横断的に登録・蓄積する仕組みであり、具体的には、
・技能者は、保有資格などの情報をシステムに登録することで、一人ひとり固有のICカード(キャリアアップカード)を取得します。
・このカードを、現場に置かれたカードリーダーにかざして読み取ります。
・これによって、いつ、どの現場で、どのような作業に従事したのか、といった情報が、業界統一のルールで、システムに蓄積されて
いきます。また、保有資格などについても、システム上で簡易に確認することができます。
図:建設キャリアアップシステムの構築
このシステムにより、技能者一人ひとりの経験や技能の客観的な把握が可能となることから、技能者の客観的かつ大まかなレベル
分けが可能となります。このレベルに応じて、キャリアアップカードを色分けする予定です。また、専門工事企業が、どのレベルの
技能者を何人雇用しているのかといった情報を「見える化」することにより、優秀な職人を育て、雇用する企業が選ばれる環境整備
に繋がります。
また、事業者にとっては、書類作成の簡素化・合理化が図られるといったメリットも期待されます。
図:建設キャリアアップシステムのメリット
システムへの登録受付はこの4月から順次開始され、本年秋に現場での利用が開始される予定です。国土交通省では、概ね5年
での全ての建設技能者(約330万人)の加入を推進するため、システムの周知・普及に取り組んでいます。
また、技能者の処遇改善に繋がるよう、システムを活用した施策(技能者の能力評価制度の策定・専門工事企業の施工能力等の
見える化)の構築に取り組んでいるところであり、これらについては次の機会にご紹介させていただきます。
土地・建設産業メールマガジン 一覧へ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■国土交通省土地・建設産業局メールマガジン編集部(総務課内)
Tel : 03-5253-8373 Fax : 03-5253-1576
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━