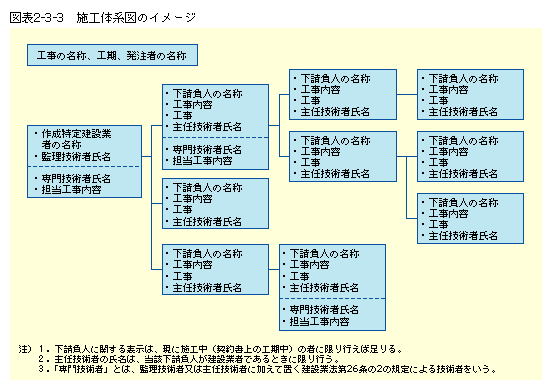(建設産業の構造改善の推進)
建設産業においては、従来から「重層下請構造」が存在し、これが契約関係の明確化、労働条件の改善、取引関係の自由化などを図ろうとする場合の構造的な問題点になっていると指摘されていた。
また、個々の企業が競争力を高めていく前提として、公正な市場競争が働いて、良い品質のものを安くエンドユーザー(最終消費者である国民)に提供できる条件整備が求められている。特に、公共工事に対する不良・不適格業者(技術力などを全く持たないペーパー・カンパニー、過大受注により施工・管理が満足に行えない業者を指す。)の参入や「上請け」「事実上の一括下請」、さらには必要な技術者を配置しないことによる、粗悪な品質の資材搬入や施工不良につながる現場施工などの問題を見逃すことのないよう、適時・的確に対応する必要がある。
このような建設産業の構造改善については、昭和63年の中央建設業審議会の答申以降、数次にわたるプログラムを策定し、行政、業界団体一体となった取組みを推進することにより、労働時間の短縮や人材の確保、契約や代金支払の適正化、経営の改善、雇用の調整等の分野において、一定の成果を上げてきたところである。具体的には、この間、建設業の年間総労働時間は、2,248時間(平成元年)から2,038時間(平成11年)に大幅に短縮され、新規学卒者入職率も、4.6%(平成元年)から6.2%(平成11年)に増加するとともに、契約締結については、書面により行われたものが32.0%(平成元年)から69.0%(平成11年)になるなど一定の改善が図られている。
しかし、最近の厳しい経営環境の中で、コストダウンの裏付けのない安値受注競争や専属的な関係における下請への一方的なコストの押付けが見受けられるなど、今後、建設産業全体の活力や品質の低下などに繋がるおそれが高まっている。また、中長期的には、労働人口の減少などに伴い、技能労働力の逼迫が生ずる可能性があるほか、就業形態の多様化が進めば、労働移動が活発化することも考えられる。
このため、不良・不適格業者の排除の徹底、元請業者や下請業者からなる協議会などの自主的な取組みの推進、経営改善や情報化による生産性の向上、優秀な人材の確保・育成と雇用労働条件の改善などの課題について、自主的かつ重点的に取り組むべきテーマを明らかにするとともに、各事業者団体と行政の役割分担についても明らかにして、具体的な取組みを進めることが求められている。
特に不良・不適格業者排除のために、発注者支援データベースの活用、施工体制台帳や工事現場の公道側に掲示された施工体系図(図表2-3-3)による技術者配置や下請状況等の確認、現場の立入点検などの監視体制を徹底することを求めている。これらの対策については、「第3 建設活動の動向、建設産業と不動産業」の「
II 建設産業の動向と施策」において体系的に記述しているが、そもそも優良な元請業者との適正な双務契約(請負価格、工期、請負代金支払い等)や、適切な管理監督の下で、専門的な技能を有する下請業者が協力・分担して建設生産物をつくることのできる体制が、適正な現場管理、労働生産性向上の前提である。