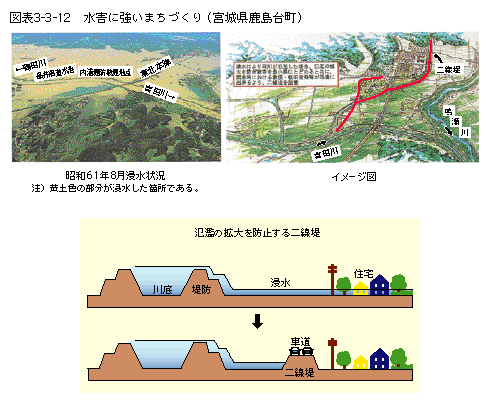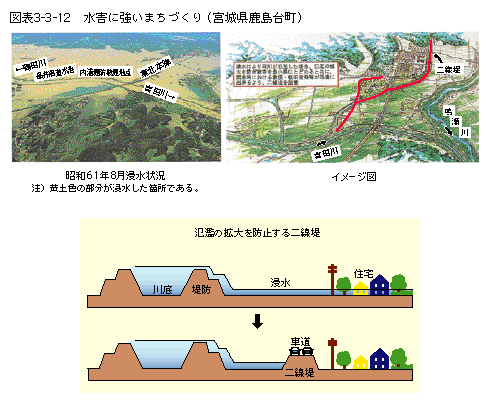(流域での対応を含む洪水対策 〜水害に強いまちづくり〜)
平成10年の栃木県余笹川や高知県国分川における水害等、近年、異常気象等を原因とした集中豪雨による極めて大きな洪水が多発しており、これらの地域の人々の生命・財産を守るためには、周辺の土地利用等の状況から、河道拡幅等の通常の河川改修・下水道整備とあわせて、流域での対応を行うことが不可欠となっている。また、平成11年の福岡における地下街での浸水被害等に見られるように、流域での対応を合わせた総合的な対策が不可欠な水害も発生している。また、これらに限らず、近年の経済社会の状況等も踏まえ、土地利用等とも連携した流域を含めた対応をすることが全体的に見て効果的なものについては、これまで以上に流出抑制、氾濫域での対応等を強力に進めていく必要が出てきている。
これまでの流域での対応を含む洪水対策としては、代表的なものとして、全国の17河川において総合治水対策を実施している。総合治水対策においては、
・流域における適正な保水・遊水機能を維持すべく、大規模宅地開発等に関連した防災調節池の設置や、運動場や広場における雨水貯留施設の設置を行う。
・浸水のおそれのある土地の区域については、市街化区域への編入を原則として行わない。
等の流域における対応を行うこととなっており、これまでにも一定の成果をあげている。
また、近年の都市部における浸水による被害等に対応するため、河川と連携を図りつつ、貯留・浸透などの流出抑制策を含めた下水道の整備水準の向上を図っている。特に地下空間利用が高度に発達しており、災害が発生するおそれのある地域において、局所貯留・排水施設の設置、排水ポンプ車の配置を行う、地下街等内水対策緊急事業を実施している。
この他、宮城県鹿島台町(吉田川)等においては、二線堤を設置し、氾濫が起こった場合でも、氾濫が拡大し市街地中心部が浸水するのを防ぐことにより被害を最小限にとどめるとともに、救援、復旧活動が迅速に行えるようにするなどの危機管理対策を実施する「水害に強いまちづくり」を実施している(図表3-3-12)。
さらに、実効性の担保方法をはじめ、流域での対応の今後の具体的な推進方策等について審議していただくため、本年2月、河川審議会に「流域での対応を含む効果的な治水の在り方について」諮問し、特定の河川流域に限らず、すべての河川で流域一体となった治水対策を推進することとしている。また、下水道においても、雨水の排除に加え、貯留、浸透、処理、利用も含めた水質・水量両面からの都市雨水の総合的な管理を推進することとしている。