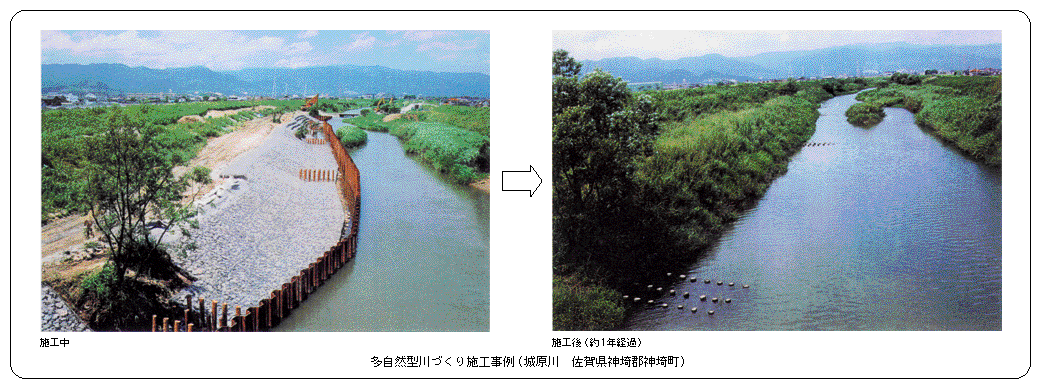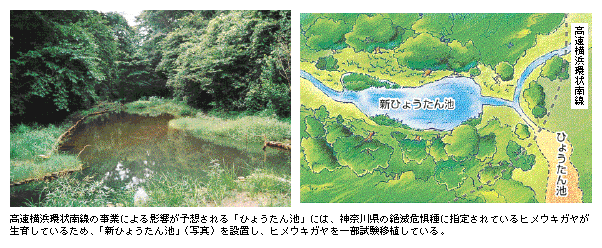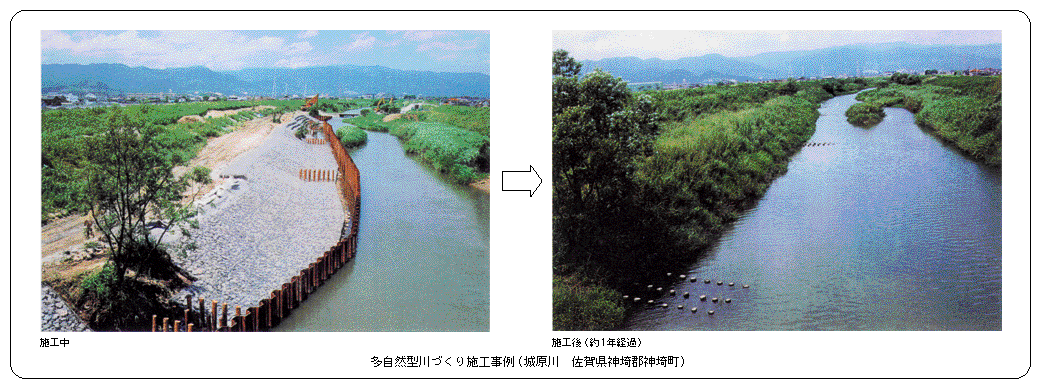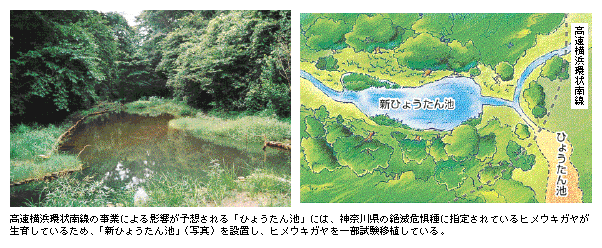(2)自然との共生
イ 生物多様性の保全への取組み
生物多様性の保全のため、各事業の実施に当たってはすぐれた自然環境をできるだけ保全し、環境への影響の回避、軽減、解消に努めている。また、再自然化その他のミティゲーションを積極的に推進しているところである。
主な取組みは次のとおりである。
1) 多自然型川づくり
国土の保全のために必要とされる治水上の安全性を確保しつつ、多様な河川の環境を保全したり、できるだけ改変しないようにし、また、改変する場合でも最低限の改変にとどめるとともに、良好な自然環境の復元が可能となるように川づくりを行う。
2) 魚がのぼりやすい川づくり
豊かな水域環境の創出をより積極的に推進するため、地域のシンボル的河川について堰、床止め等の河川を横断する施設の改良や魚道の設置及び魚道流量の確保等を実施し、魚類等の遡上環境を改善する。
3) 河川水辺の国勢調査
定期的、継続的、統一的な河川環境に関する基礎情報の収集整備を目的として、河川に生息する生物の調査、河川空間の利用実態調査等を行う。
4) 自然との調和に配慮した道路整備
道路事業の計画、設計段階から、貴重な自然環境のある場所はできるだけ回避し、回避できない場合は、影響の最小化や代替措置を講じることを基本として、環境の保全・回復を図る。
5) 環境ふれあい公園の整備
地域ブロックの核となる国営公園や都道府県、政令指定都市等の大規模公園等において、地域の環境活動や指導者の育成に対応するため、雑木林や野草園、野生生物の生息地等となる池や流れ、小動物観察のための自然生態園や野鳥観察所、セミナーハウス、体験学習施設などの施設を総合的に整備する。
6) 都市林の整備
市街地及びその周辺部においてまとまった面積を有する樹林地等を、主として動植物の生息地又は生育地の保護を目的とする都市公園として位置づけ、その自然的環境の保護、保全、復元を図れるよう十分に配慮し、必要に応じて自然観察、散策等の利用のための施設を配置する。
7) 生態系保全ネットワーク
快適な生活環境の形成、多様な生物の生息・生育が可能な自然環境の確保を図り、生態系の保全のための環境整備を総合的に行う地域を対象として、関連事業と連携し、関係省庁とも調整を図りながら、重点的な事業の展開を図る。
8) 調査・研究等
生物の多様な生息・生育環境の保全・創出を図るため、様々な調査・研究等を実施している。
・河川と生物との関わりに関する調査研究の推進
多摩川等において河川環境に関わる学術的研究を総合的に進めるため、同一地点において長期にわたり系統的、時系列的なモニタリングを実施し、生物の生息空間の類型化やその変動等を解明する河川生態学術研究を行う。
また、木曽川の河川敷に設置された自然共生研究センターにおいて、世界最大級の実験河川・実験池を用いて、河川湖沼の自然環境の保全・復元のための基礎的・応用的研究を行う。
・生態系の保全・生息空間の創造技術の開発
水域を対象とした生物と環境との関係の把握を基礎として、公共事業が生態系に与える影響を予測する手法を開発するとともに、その影響を可能な限り抑制し、新たな生息空間を創造するための技術開発を行う。
ロ 環境影響評価への対応
環境影響評価については、従来の環境影響評価実施要綱(昭和59年8月閣議決定)に代わり、平成11年6月に環境影響評価法が全面施行となり、同法に基づき行われているところである。同法においては、調査等の方法について国民意見等を求めるための仕組みの導入、環境保全目標との整合に加え、環境への影響をできる限り回避し、低減する視点の取り入れ等、環境影響評価の内容の一層の充実を図ることとしており、建設省としても、同法に基づき、事業ごとに手続等に係る諸規定等の整備、地方建設局等における実施体制の整備等を図ってきたところであり、今後も、同法の適切かつ円滑な執行を図り、適切な環境影響評価が実施されるよう努めていくこととしている。