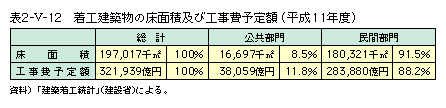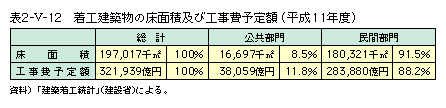V-2 建築
1 現状と課題
(1)良好な建築物整備のための基本的方向
イ 建築行政の歩み
建築物の建築に際しては、建築基準法(昭和25年〜)、建築士法(昭和25年〜)において、材料や構造等に関する基準が定められているとともに、建築士が、設計及び工事監理を通じて、これらの材料の品質や構造の適正さ等を確保する制度が設けられており、我が国の経済社会の変化に的確に対応するため、法令の改正等による建築基準、手続き等の合理化を推進してきた。
また、環境問題や高齢社会への対応等、近年における新しい行政課題に対応するため、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年〜)」、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年〜)」等に基づく指導、優良な建築物の誘導等に努めているところである。
さらに、平成7年1月の阪神・淡路大震災において安全上の問題が明らかとなった既存建築物対策を推進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年〜)」に基づき、既存建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に努めているところである。
ロ 建築活動の現況
「平成12年度建設投資見通し」(建設省)によれば、平成12年度の我が国の建設投資額は約71兆円、このうち建築に対する投資は約35兆円の規模となる見込みである。この建築投資額は、GNPの約7%に相当し、欧米先進国に比して高い水準にある。建築投資額の対前年増加率は約2.2%となっているが、このうち住宅投資額の対前年度増加率は約1.2%となっている。さらに建築投資を公共・民間の部門別にみると、平成12年度においては、8割以上を民間部門が占めており、我が国建築活動の大部分は民間において担われている状況にある(表2-V-12)。
ハ 建築物に求められる社会的役割
建築物は、人間の生活空間として、様々な性能を確保していることが求められている。
第一に、地震、火災等に対する基本的な安全性が確保されている必要がある。このために、構造耐力、防火、避難等に関する安全性の確保に不断の努力がなされてきた。近年、さらに、例えば免震・制震技術のような従来の体系と異なる耐震技術を用いた建築物、新素材を用い大空間を形成した建築物などが開発あるいは実用化されつつある。
第二に、生活の場として、利便性、快適性が確保されている必要がある。採光、換気、界壁の遮音等の基本的な屋内環境の確保とともに、高度化の著しい建築設備の数々は、熱、光、空気等の制御を通じて、より快適な屋内環境を実現するようになってきている。また、本格的な高齢社会の到来を控え、バリアフリー設計を行うことが基本的な性能の一つとして位置付けられつつある。
第三に、経済活動の場としての建築物の役割がますます重要性を増してきている。例えば、インターネットに代表される近年の情報通信技術の進歩に伴い、高度な情報処理機器・システム・高速で大容量の通信装置等の導入への対応、空調設備、照明設備等の自動制御装置などの高度な建築設備の整備等BA(ビルディング・オートメーション)化による建築物のインテリジェント化は、経済活動を行っていく上で必要不可欠なものとなってきている。
また、このような多様な施設や設備をより総合的・効果的に企画・運営するFM(ファシリティ・マネジメント)等により、建築物の性能の向上、維持管理の最適化を図り、併せてより快適な執務環境を整備するニーズも高まっている。
こうした動きは、財やサービスの生産基盤としての建築物の役割が大きくなってきていることを示すものであり、今後、ますます重要性が増すものと考えられる。
第四に、良好な市街地環境の形成に対する国民のニーズが高まっている中で、その構成要素としての建築物の役割が一層重視されてきている。例えば、歩行者等の利用に配慮して道路空間と一体的に設計された建築空間の形成、良好な景観の形成を意識してデザインされた建築物の建築等質の高い市街地環境の形成に寄与しようとする傾向が現れている。また、地方公共団体においても、このような建築物の整備を誘導する方向で施策を展開しており、例えば、地域の防災安全性の向上に資するオープンスペースの創出を建築活動を通じて促進するための施策の推進、景観向上に寄与する建築物に対する表彰制度の実施などの動きが広がってきている。今後とも、これらの動きを支援し、市街地における良質な建築物の蓄積を図っていくことが必要である。
第五に、建築物は、環境に与える影響が大きなものである。日本全体のエネルギー消費量のうち約4分の1は、住宅やオフィスビルなどの民生部門において消費されており、建築物の整備に当たり、省エネルギーへの配慮、排水処理の高度化、ゴミ処理の削減等を推進し、環境に対する負荷の低減を図っていくことは、環境対策に重要な役割を負っている。
ニ 時代の要請に対応した建築活動への規制、誘導の必要性
いつの時代にも建築物の安全性を確保し、性能の向上を図っていくことは必要なことである。建築行政においては、建築基準法に基づき最低限の性能の確保を図るとともに、建築士の技能の向上、技術指針等の策定・普及、政府系金融機関による融資等による優良な建築物の建設を推進している。
また、高齢者・障害者等の利用にきめ細かく配慮した建築物の整備、環境に配慮した建築物の整備等多面的な要請に対応した良好な建築ストックの形成等、市街地環境の整備改善等を図っていくためには、特に、旺盛な建築投資の大部分を占める民間における建築活動を適切に支援していくことが必要不可欠である。
このため、将来へ承継する質の高い建築資産の形成に向けて民間建築活動を誘導する様々な施策の実施を図っていく必要がある。