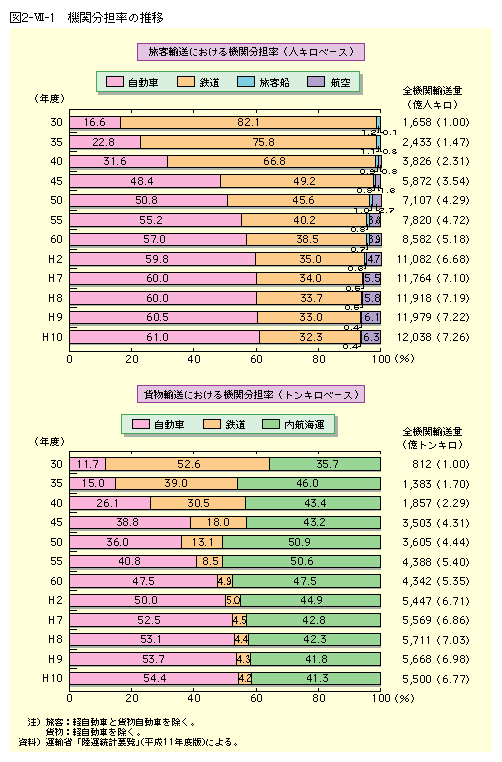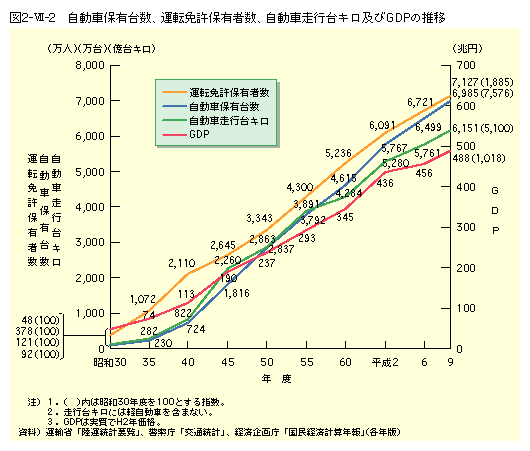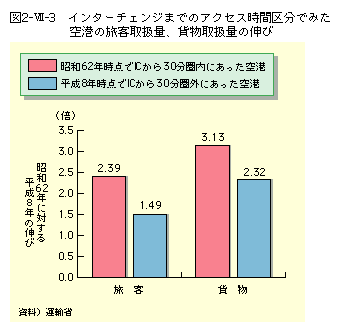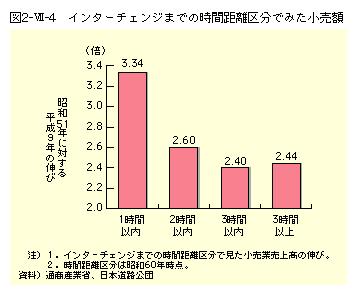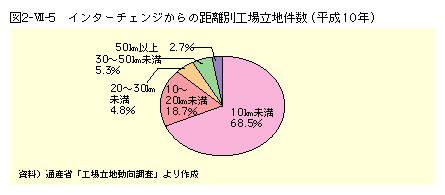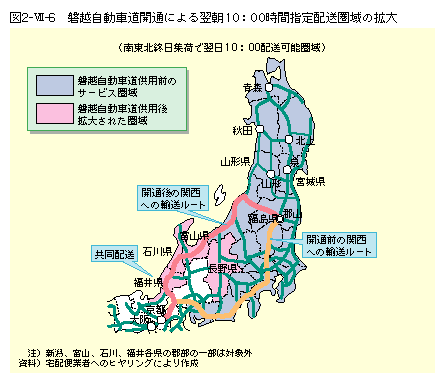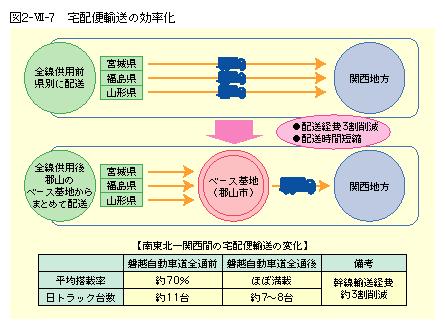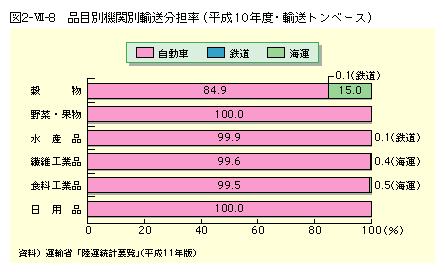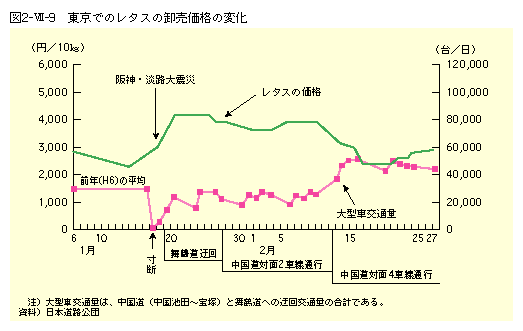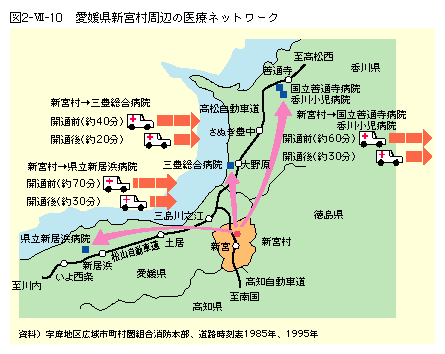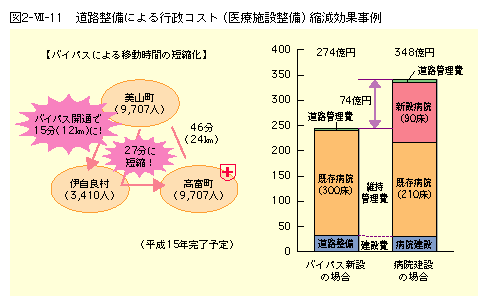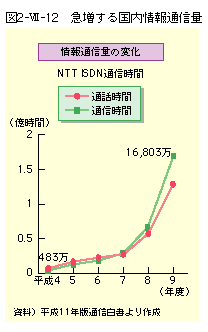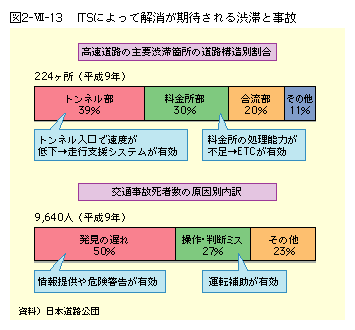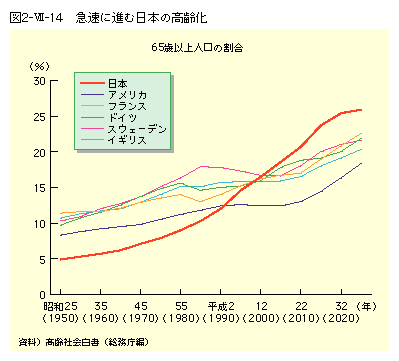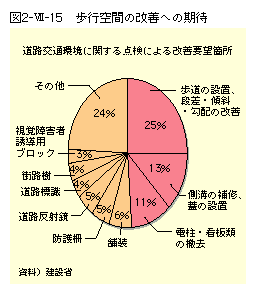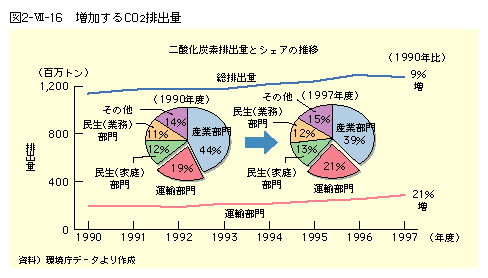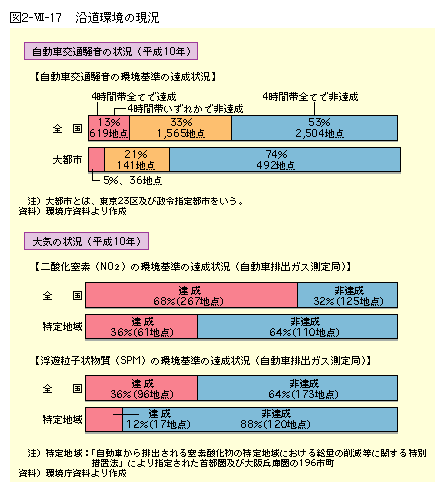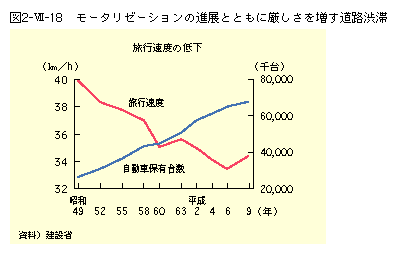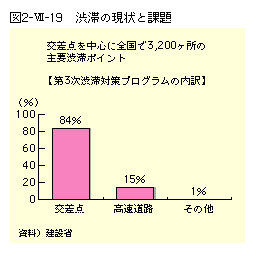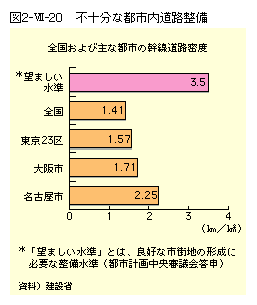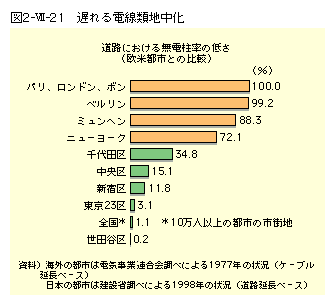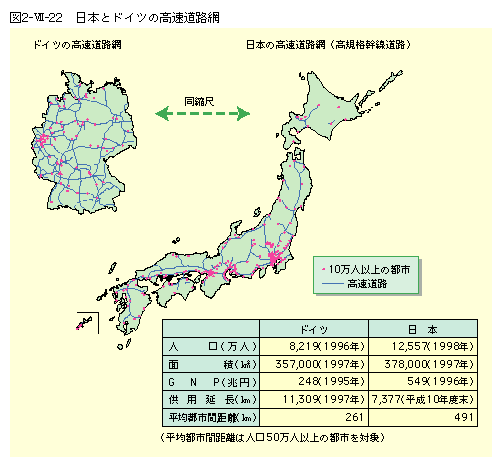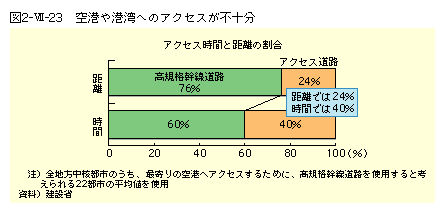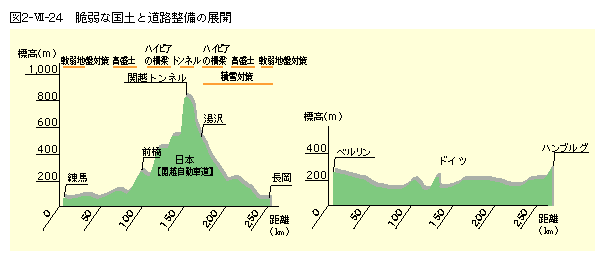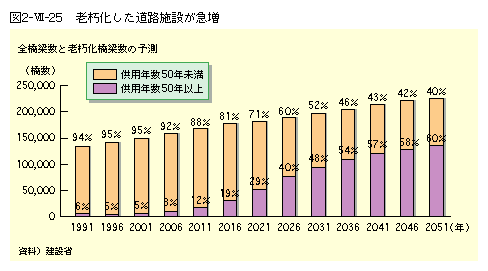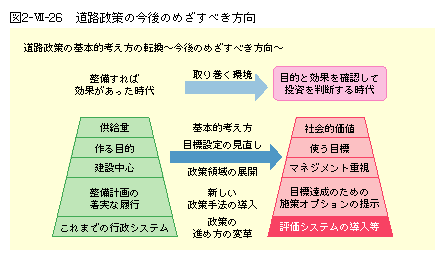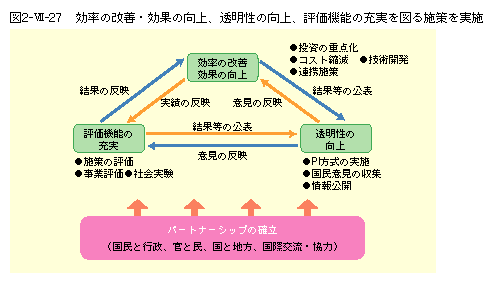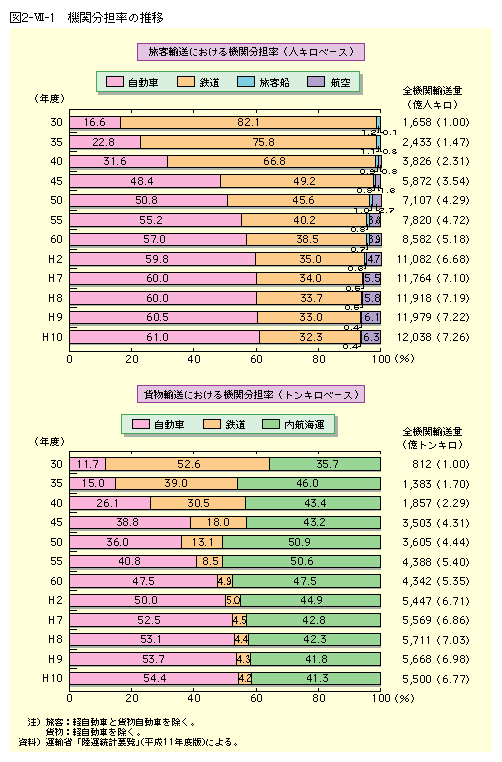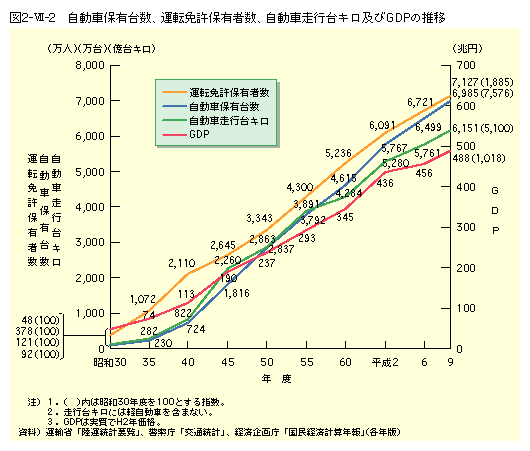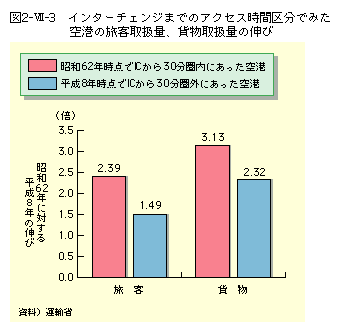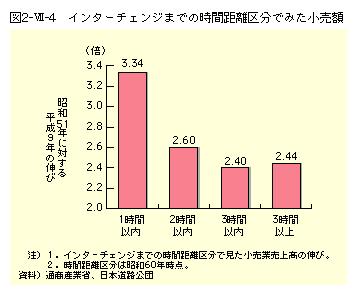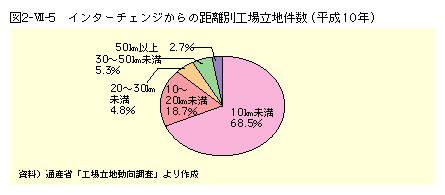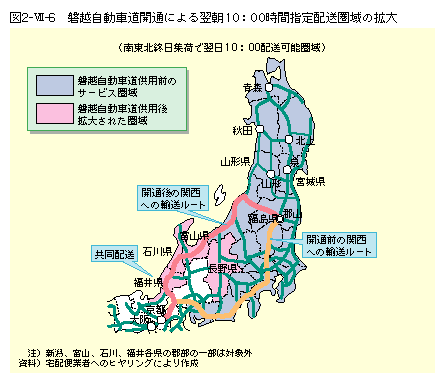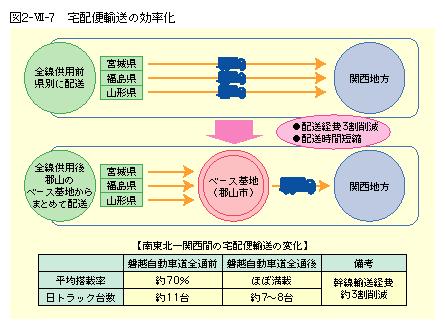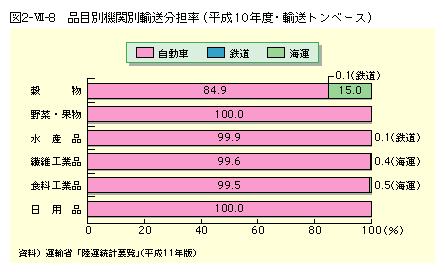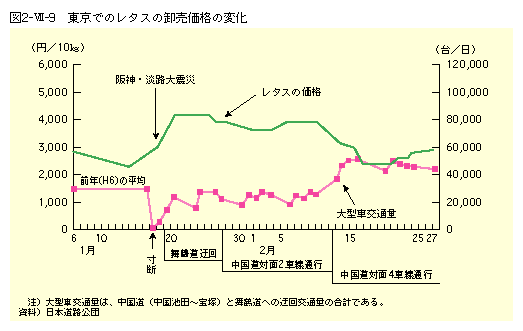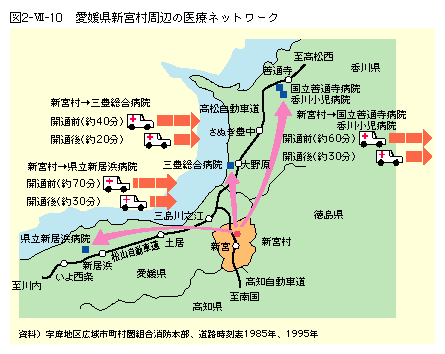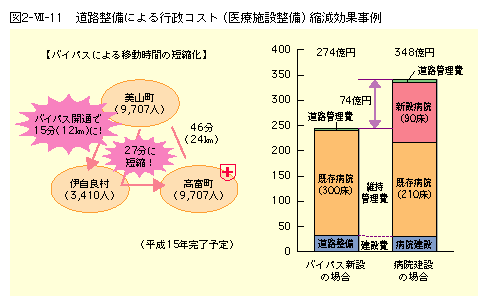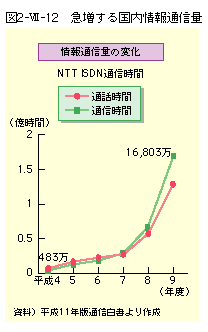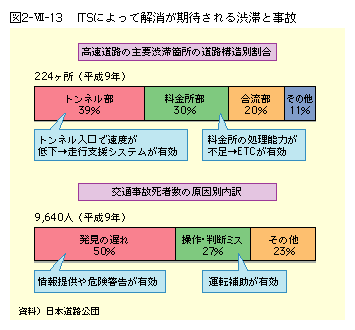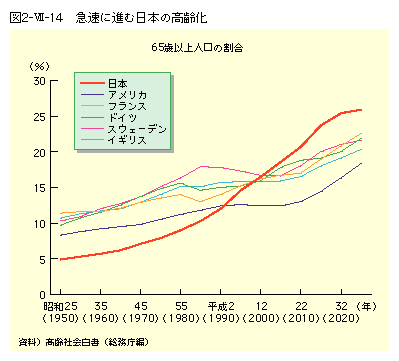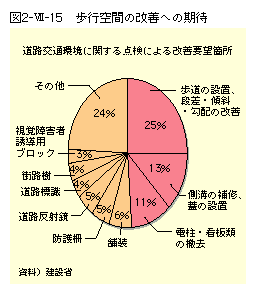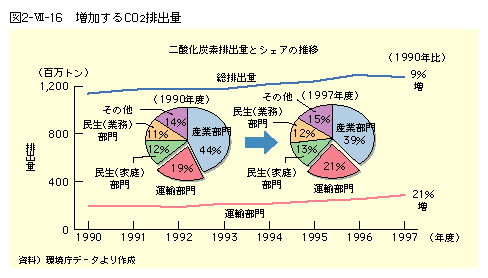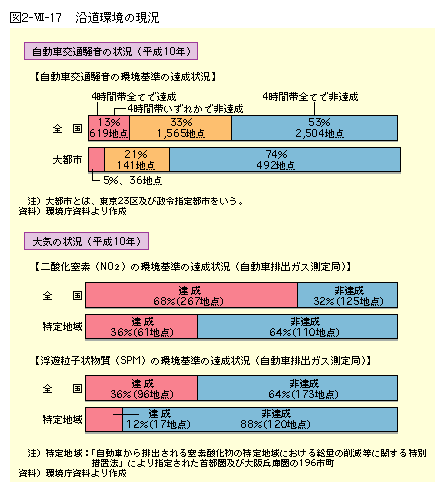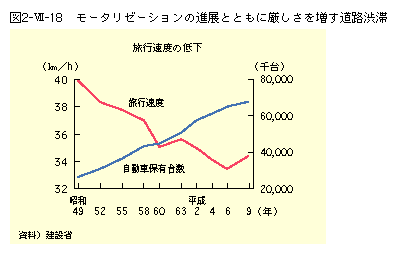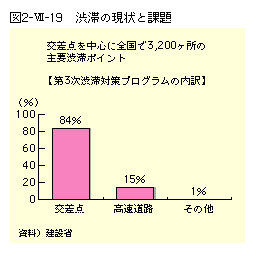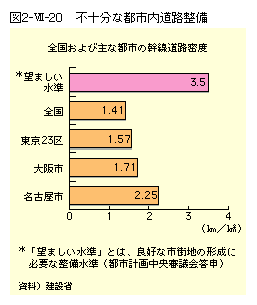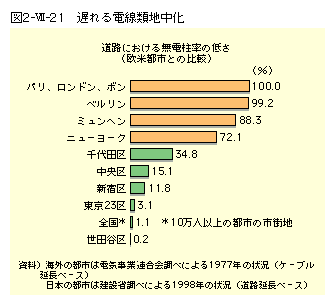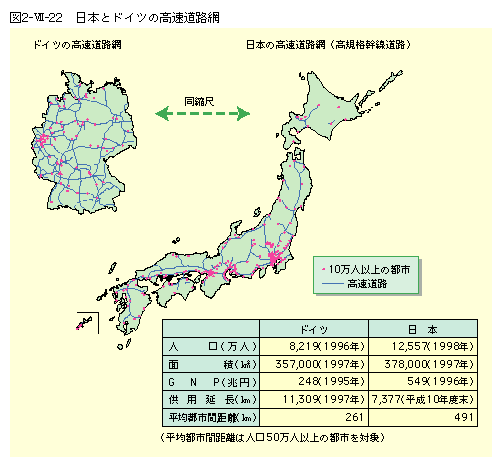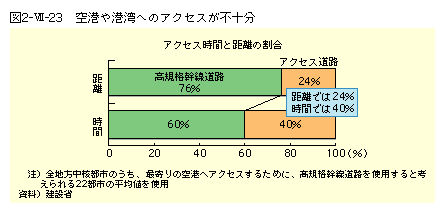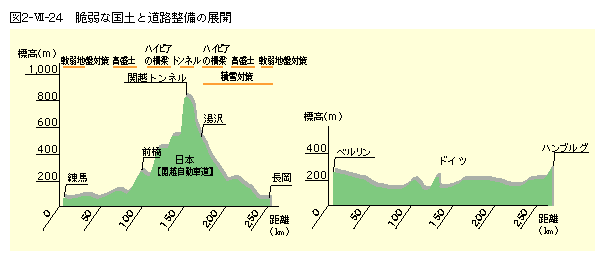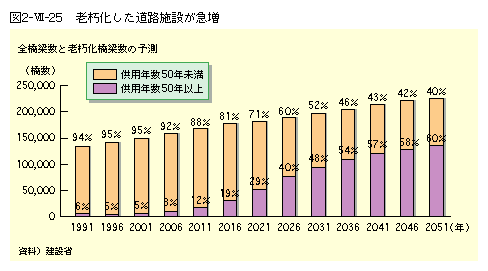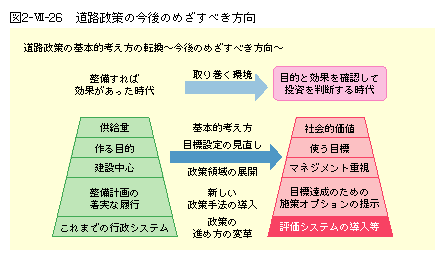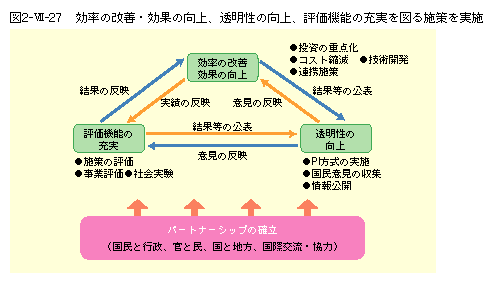VII 社会、経済、くらしを支える多様な道路施策の展開
1 現状と課題
(1)道路をめぐる現状
終戦直後の我が国の道路は、空襲や財源の不足から、荒廃が甚だしく、損傷の激しい簡易舗装道路がわずかに残されたほかは、砂利道ばかりで、人や自動車の通行はいたるところで難渋を極めている状態であった。
このような中、本格的な道路整備は、昭和29年に策定された「第1次道路整備五箇年計画」から始まり、現在の「新道路整備五箇年計画」によって強力に推進しているところであるが、未だ整備の途上段階にあり、今後とも着実に進めることが求められている。
例えば、高規格幹線道路については、平成11年度末現在で供用延長が7,548kmとなるが、ようやく全体計画の半分に到達した状況であり、高速道路の整備水準や空港・港湾と高速道路網のアクセス状況も早急に改善していく必要がある。
また、渋滞による時間損失は年間で国民一人当たり約42時間、金額に換算すると全体で約12兆円にも及び、交通渋滞が大きな問題となっている。
さらに、全国で夜間において騒音に係る環境基準を超える道路の割合が約65%に及んでいるなど、環境面での対策の一層の充実も求められている。
交通事故に関しては、事故件数が年々増加傾向にある。死者も年間約9,000人を数えるなど、交通安全対策を確実に推進していく必要がある。
ここで、現状について、社会・経済・くらしの観点及び主要施策毎に概括する。
イ 社会・経済・くらしと道路の関わり
1) 社会を支える
イ)ライフラインの確保に資する道路の役割
道路は、国民生活に不可欠な、電気・電話・ガス・上下水道などのライフライン収容空間として活用されている。
〜道路占用割合(東京都23区内):上下水道、ガス:100%、電気:97%、電話:92%
ロ)道路の防災空間としての役割
阪神・淡路大震災の際には、幅員の広い道路がライフラインの確保とともに延焼の防止に大きな効果を発揮した。
〜延焼防止率:幅員12m以上:100%、4m未満:20%弱
ハ)国内輸送における自動車交通の役割の拡大
国内旅客、貨物輸送における自動車交通の占める割合は年々増加している(図2-VII-1)。
〜自動車交通の分担率:旅客(人キロ) 16.6%(昭和30年)→61.0%(平成10年)
貨物(トンキロ)11.7%(昭和30年)→54.4%(平成10年)
ニ)地方社会を支える自動車交通
地方圏においては自動車交通が社会活動の基盤となっている。
〜自動車交通の旅客輸送分担率:地方圏:91.4%、三大都市圏:53.6%
2) 経済を支える
イ)経済発展と密接不可分な自動車交通
経済の発展とともに運転免許保有者数、自動車保有台数は依然として堅調な伸びを示している。これに伴って自動車走行台キロも大きな伸びを示している(図2-VII-2)。
ロ)地域の経済活動の活性化に寄与
高速交通網の整備は、空港ターミナル機能の向上や地域の商業活動の活発化など、地域の経済活動の活性化に寄与している(図2-VII-3、図2-VII-4)。
ハ)加工組立型への産業構造変化に対応した工場立地
重厚長大型から加工組立型への産業構造の変化に対応して、必要な材料の調達、製品の輸送が容易な高速道路のインターチェンジ(IC)周辺に多くの工場が立地している(図2-VII-5)。
ニ)物流の活性化に寄与
高速道路の整備により、物流が活性化し、地域の利便性の向上に大きく寄与している(図2-VII-6、図2-VII-7)。
3) くらしを支える
イ)日常生活を支える自動車輸送
野菜、果物、水産品、日用品等日常生活に必要な主要品目の輸送のほとんどを自動車輸送が分担している(図2-VII-8)。
ロ)高速交通の確保が物価の安定に寄与
阪神・淡路大震災の影響によって高騰したレタスの価格が、高速交通が確保されるにつれて次第に安定した(図2-VII-9)。
ハ)宅配便による生活の利便性の向上
宅配便の取扱量は大幅に増加しており、高速道路網の整備による1日配達圏の拡大は、生活の利便性に寄与している。
〜宅配便取扱個数:1.1億個(昭和56年)→16.2億個(平成9年):16年間で15倍に
ニ)地域における高度医療を支援
高速道路を利用することにより、医療機関の少ない地域においても、高度医療、救急医療の利用が可能となっている(図2-VII-10)。
ホ)行政コストの縮減
道路整備による広域的なサービス提供により、医療施設の共同利用等、行政の効率化が図られ、大きなコスト縮減が可能となっている。
岐阜県美山町ではこれまで車で46分の高富町の病院を利用しており、美山町─伊自良村間のバイパス開通により、救命率の分岐点である30分以内で高富町へ行くことが可能となった。これにより、美山町に新たに病院を建設する場合に比べ、約74億円の行政コストが縮減された(図2-VII-11)。
ロ 主要施策分野毎の現状・諸課題
1) 情報化
近年、我が国では、急速に高度情報通信化が進んでおり、特にISDN通信時間はここ5年間で35倍となっているなど、国内の情報通信量も大幅に増加している(図2-VII-12、図2-VII-13)。
道路交通システムにおいても、高度情報化の推進が望まれている。
2) 少子・高齢化
我が国は、世界的に見ても急速に高齢化が進むと予想されている。65歳以上の人口の割合は、2020年には総人口の25%以上になると予想されている。
このため、バリアフリーに対する期待は大きく、道路交通環境においても、これからの社会を見据えた生活空間の形成が求められている(図2-VII-14、図2-VII-15)。
3) 環境
我が国においては、二酸化炭素排出量は概ね増加傾向にあるが、運輸部門の伸び率は1990年比21ポイント増と特に顕著である。二酸化炭素排出量が全体の21%にのぼる運輸部門においても、積極的な対策が望まれている(図2-VII-16)。
また、沿道の環境も、二酸化窒素に係る環境基準を達成していない箇所が、全国で32%にのぼるなど、早期の解決が待たれている(図2-VII-17)。
4) 都市構造の再編
物流の効率化や都市機能の再編を図るためには、放射状道路と環状道路の整備が必要とされているが、我が国では特に環状道路の整備が遅れている。また、諸外国の主要都市と比較しても、東京20%、パリ74%、ロンドン99%となっており、環状道路整備率の低さが際立っている。
5) 渋滞対策
モータリゼーションの進展とともに、道路渋滞が厳しさを増している。
自動車の保有台数は依然として増加しており、一家に2台自動車を保有する家庭も多いのが現状である。保有台数の増加に伴い、旅行速度は著しく低下している。旅行速度の向上のため、今後も渋滞対策の推進が望まれるところである。特に、交差点を中心とした主要渋滞ポイントの解消が急がれる(図2-VII-18、図2-VII-19)。
6) 地域・まちづくり
豊かで快適なまちづくりのためには、幹線道路の整備が求められる。都市の幹線道路密度の望ましい水準は3.5(km/km2)とされているものの、全国の主要都市平均でこれを大きく下回っている。
また、安全で快適な歩行空間の確保、都市景観の向上のため、欧米都市と比べ低い水準にある電線類地中化の推進が求められている(図2-VII-20、図2-VII-21)。
7) 広域交通・物流
我が国とほぼ同面積の国土を持つドイツと主要な都市間距離を比較してみると、我が国はドイツの2倍となっているにもかかわらず、高規格幹線道路の供用延長はドイツの約3分の2にとどまっている。
物流効率化の面では、空港や港湾へのアクセスが不十分であるといえる(図2-VII-22、図2-VII-23)。
8) 管理・防災
我が国は、豪雨、豪雪、地震などの自然災害が多発する脆弱な国土である。例えば、高低差約700mの関越自動車道(練馬〜長岡間)では、軟弱地盤、高盛土、橋梁、トンネル、積雪への対策が必要とされる。
また、今後道路施設の老朽化が急速に進展すると予測されており、維持管理の充実や防災対策の充実による安全で安心できる生活を支える道路空間の確保が求められる(図2-VII-24、図2-VII-25)。
9) 道路政策の進め方の改革
これまでの道路政策(整備の実績、事業実施の効率性・透明性、事業展開の計画性、道路整備に対する費用負担等)へは、厳しい意見・評価が多く、基本的な考え方を転換する必要があった。また、取り巻く環境も、整備すれば効果があった時代から、目的と効果を確認して投資を判断する時代へ変貌を遂げている。
これを受けて、評価システムを導入するなど、これからの時代に対応した政策を進め、効率性・効果・透明性の向上、評価機能の充実を図る(図2-VII-26、図2-VII-27)。