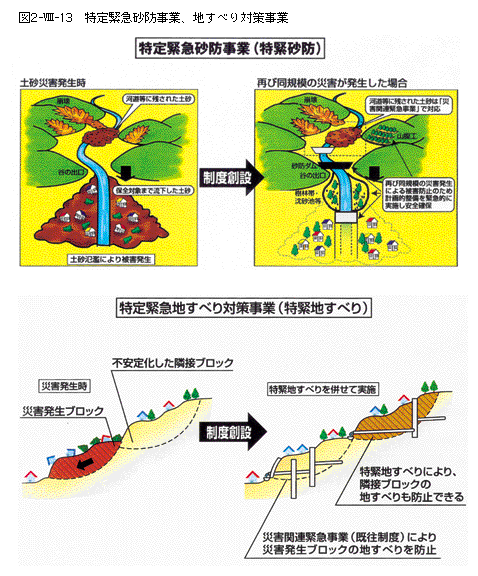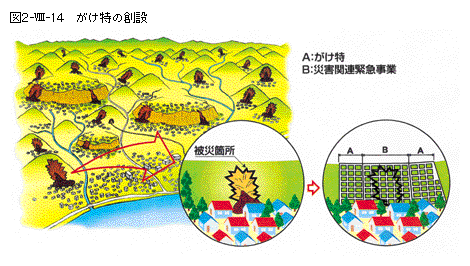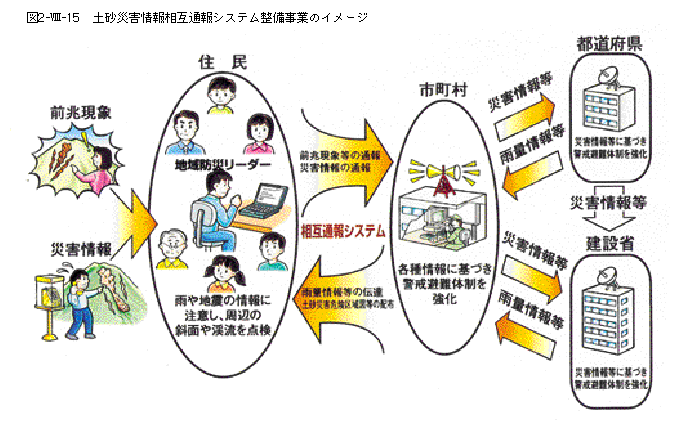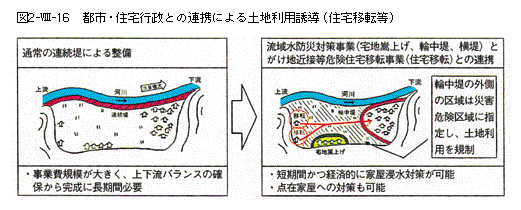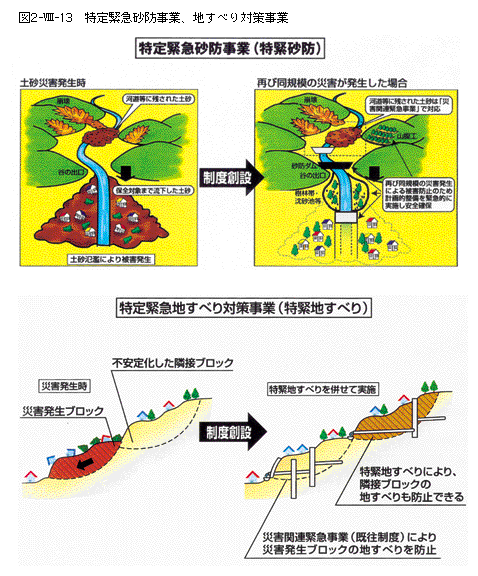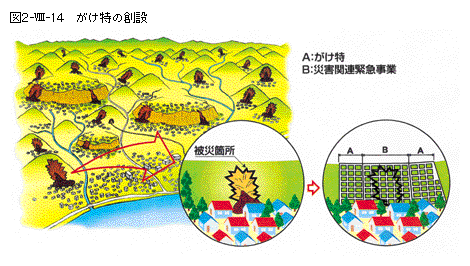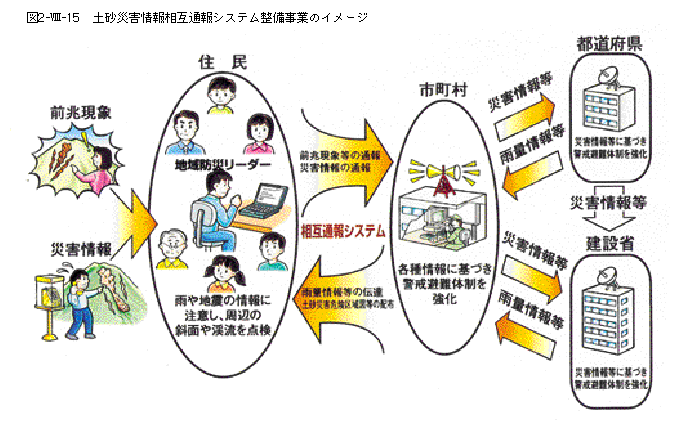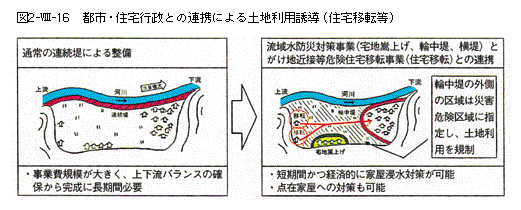2 平成11年度、12年度の主要施策
(1)平成12年度の主要施策の概要
イ 平成12年度の基本方針
平成11年に激甚な水害、土砂災害が多発したことをふまえ、「信頼感ある安全で安心して暮らせる国土づくり」を強力に推進し、生活関連の社会資本整備を重点実施する。さらに、総合的な土砂災害対策の推進のための制度を創設するとともに、河川管理への市町村参画の拡大等を行う。
ロ 主要施策
1) 緊急防災対策の重点実施
イ)激甚災害地域緊急防災対策
近年頻発している水害や土砂災害により激甚な災害を受けた地域に対する再度災害防止対策を実施し、約25万人の人命を土砂災害から保全する対策を概ね3年で概成させるとともに、家屋流出や損壊等の著しい浸水被害をもたらした激甚な災害の再度発生防止対策を概ね5年間で概成する。
ロ)都市機能等の壊滅的被害を防ぐ大規模災害等危機管理対策
大規模水害及び火山噴火等による県庁所在地等の政治経済中枢都市における壊滅的被害防止対策、主要道路・幹線鉄道等の被害による広域的な物流の遮断や地域孤立化防止等の大規模危機管理対策として、スーパー堤防整備事業、高潮・侵食対策及び大規模火山泥流対策等を実施する。特に高潮対策については、平成11年9月台風18号による高潮災害を契機とした海岸緊急点検結果に基づき、堤防等を緊急的に整備する。
ハ)床上浸水頻発地区緊急解消対策
床上浸水の頻発地域、浸水域における高齢化率の高い地域及び都市機能の進んだ地域において、築堤、排水機場整備等、河川事業を集中的に実施し、概ね5年間での被害の解消を図るべく、重点実施する。
ニ)災害弱者関連緊急土砂災害対策
厚生省・文部省等と合同で実施した緊急点検結果に基づき、迅速な避難が困難な災害弱者に関連した病院、老人ホーム、幼稚園等の災害弱者関連施設に係る危険箇所や、高齢化率の高い地域において、砂防ダム等の土砂災害防止施設を重点整備する。
ホ)緊急的渇水対策
度重なる渇水により日常生活や産業活動に深刻な影響を受けている地域において、安心して生活できる地域づくりを目指して緊急的渇水対策を推進し、早期に渇水被害を軽減する。
ヘ)災害情報伝達ネットワークの整備
ハード、ソフト両面から水害、土砂災害に対する情報基盤の高度化を図るべく、雨量計、水位計等の各種情報基盤の整備、土砂災害監視システムの高度化、堤防の状況や土砂災害危険箇所等のGISデータベース化等を推進する。
2) 総合的な土砂災害対策の実施
イ)特定緊急(砂防・地すべり対策)事業の創設
土石流、地すべりにより人的被害、家屋被害等が発生した一定の地区について被害をもたらした同規模の土石流、地すべりが再び発生した場合でも安全が確保されるよう、災害関連緊急事業と一体的に計画に基づき一定期間内(概ね3年以内)に緊急的に施設整備を実施(図2-VIII-13)。
ロ)災害関連急傾斜地崩壊対策特別事業(がけ特)の創設
がけ崩れ災害が集中的に発生した一連の地域において、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業と一体的に、隣接したぜい弱斜面の崩壊防止工事を行う「災害関連急傾斜地崩壊対策特別事業(がけ特)」を創設する(図2-VIII-14)。
ハ)土砂災害情報相互通報システム整備事業の創設
土砂災害から人命を守るため、行政と住民が災害関連情報を相互に通報しあえるよう、必要なソフト開発を行うとともに、市町村役場等において、都道府県等から提供された雨量情報等を加工し住民へ伝達するための処理装置や住民からの前兆現象の通報等住民との情報交換を直接行うための端末等を新たに整備する(図2-VIII-15)。
ニ)砂防関係事業調査費補助制度の創設
土砂災害の防止及び軽減、砂防関係事業の効率的実施等を図るため、土砂災害の発生メカニズム、土砂災害に対する警戒を要する区域、当該区域内の人家、資産等の調査等を住宅等の立地抑制対策をも視野に入れた土砂災害対策のための基礎的調査を実施する。
3) 流域やダム周辺を対象とした治水対策等の充実
イ)ダム建設に伴う道路の付替に代えて、地元地方公共団体等がダム周辺山林の取得及び当該山林の管理を行う場合に、ダム事業者が付替道路整備費の範囲内で、その費用を負担するダム周辺の山林保全措置制度を創設する。
ロ)市街化の進展に伴う洪水流出量の増大に対応し、治水安全度を効率的かつ早急に向上させるため、一級河川又は二級河川の流域で通常の河道改修方式と比較して経済的であり、かつ、治水計画上の効果が位置付けられるものを流域貯留浸透事業の対象に追加する。
ハ)家屋の立地状況等に柔軟に対応した、より経済的な治水対策を推進するため、宅地等の嵩上げ事業と輪中堤等の築堤事業を一体的に行う流域水防災対策事業を創設する(図2-VIII-16)。
ニ)災害復旧助成事業において、降雨の規模が極めて大きく被災流量を下回る計画流量を設定せざるを得ない場合、必要に応じて氾濫流対策を局部的に実施する。
4) 地域の自主性、多様性を考慮した河川等の整備
イ)河川管理における市町村参画の拡大
市町村の自主的な取組みを支援し、きめ細かな河川環境の整備・保全やまちづくりと一体となった河川整備を進めるため、直轄管理区間における市町村施行を可能とするとともに、都道府県管理区間内の一級河川及び二級河川について政令指定都市の長が管理できるよう措置する。
ロ)統合河川整備事業の創設
二級河川において実施する、水系全体の治水上等の影響が小さい河川工事又は修繕を対象に、都道府県に統合的な補助金を交付し、地域で裁量的に事業を施行することにより、創意工夫を活かした個性的な地域づくりを推進する。
ハ)特定小川災害関連環境再生事業(特定小川災害関連事業の拡充)
小規模な河川の機能を保全するために、河川の災害復旧事業に併せて特定小川災害関連環境再生事業を実施し、良好な河川環境の連続性や人と川の豊かなふれあいの確保を図る。
5) 防護・環境・利用の調和のとれた海岸事業の拡充
近年の台風、高潮等による災害に適切に対処するため、原形復旧が不適当であり、再度災害防止に十分な効果が期待できる場合に、通常の災害復旧事業の範囲に加え、堤防と一体となって面的防護を図る事業を既存の「直轄災害復旧事業」の中で運用実施する。
また、洪水・台風等により海岸に漂着する大規模流木等は近年増加しており、これを放置することにより海岸保全施設の機能を阻害することとなる場合に、緊急的に漂着流木等の処理を実施する「災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業」を創設する(写真2-VIII-4)。
6) 河川管理に関する国と地方の役割分担
21世紀への移行期にあたる今、我が国の経済・社会状況は大きな転換期を迎えており、今後の河川管理のあり方についても大きな影響を及ぼすと考えられることから、平成10年9月11日に河川審議会に対し「経済・社会の変化に対応した河川管理体系のあり方について」を諮問した。
そして、平成11年3月26日の第2次地方分権推進計画閣議決定を踏まえて、同年8月5日に河川審議会「河川管理に関する国と地方の役割分担について」の答申がなされ、以下の基本方針が取りまとめられた。
i)国は、国土保全上又は国民経済上特に重要なものに限って管理するという原則のもとで、経済・社会の変化に的確に対応した河川管理を行うため、定期的に一級水系や直轄管理区間の見直しを行うこととする。
ii)個性豊かな自立型地域社会の形成を進めるため、国と地方の管理区分の見直しにとどまらず、流域における多様な主体の河川管理への幅広い参画が不可欠である。このため、一級河川の直轄管理区間、同知事管理区間及び二級河川を通じて、河川空間利用における市町村の参画や市町村河川工事の拡充など、地方公共団体、市民、NPO等の参画の推進を図ることとする。
また、同答申では以下のような一級水系指定等の考え方及び基準等が示された。
i)一級水系を、国土保全上又は国民経済上、国において管理する必要があると認められる水系(国土基盤整備型水系)と、災害等を契機として国の技術力又は財政力により早急に対策を講じなければ国土保全上又は国民経済上の支障が生じる水系(災害対応型水系)に区分する。
ii)国土基盤整備型水系は、流域面積や想定氾濫区域が大きい等特に重要な水系に限定する。また、災害対応型水系は、大きな災害の発生等により国による緊急的、抜本的な対策が必要であるという観点から特に重要な水系であり、この水系については整備が相当程度進捗した場合には、二級水系に変更する。
このため、今後はこの答申を踏まえ、平成12年度中を目途に関係地方公共団体との調整を進める予定である。