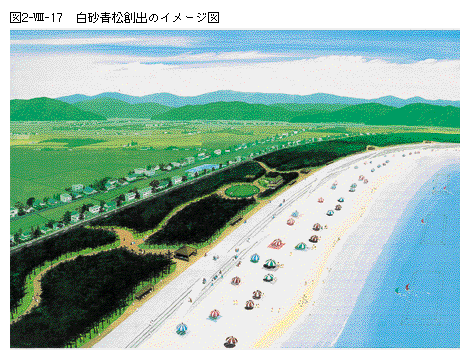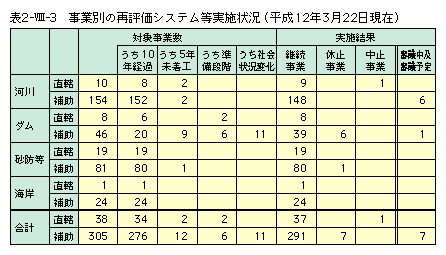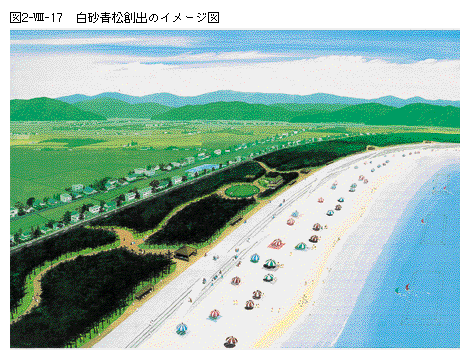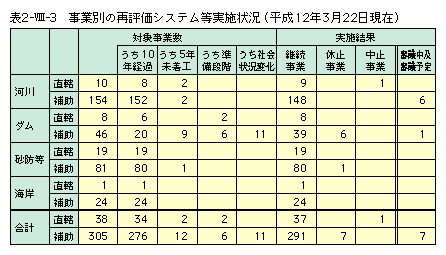(2)アカウンタビリティの向上等に向けた取組み
イ 事業の効率的・効果的実施のために
1) 事業の重点化・効率化
平成10,11年にかけて頻発した激甚な災害の発生を踏まえ、国民生命、財産の安全確保のため緊急防災対策の重点実施を行う。また、事業箇所の統合、厳選等による重点投資を実施する。
2) 省庁連携の強化
事業の効果をより一層向上させるため、従来より実施している他省庁との連携施策・事業を強化するとともに、平成12年度から林野庁と連携し、自然環境と利用に配慮した海岸整備を行う自然豊かな海と森の整備対策事業(白砂青松の創出)(図2-VIII-17)や、平成11年6月末の広島・呉市の土砂災害等を契機とした林野庁との連携による総合的な流木災害防止緊急対策等を実施する。
ロ 事業の透明性の確保
1) 再評価の実施
公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、平成11年8月13日に改定された「建設省所管公共事業の再評価実施要領」に基づき、昨年度同様に再評価を実施し、評価結果を平成12年度予算に反映した。
再評価は、同要領に基づき、事業の進捗状況、地元情勢等により事業が順調に進捗しているか確認し、事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢等の変化、事業採択時の費用対効果分析の要因の変化、コスト縮減や代替案立案等の可能性といった視点から、各事業ごとに評価項目を設定し、実施している。
平成11年度の実施結果は、表2-VIII-3のとおり。
2) 新規事業採択時評価システム
新規事業箇所については、従来より、想定される被害の大きさ、過去の災害実績、現状施設の整備水準、治水経済調査要綱等に基づく費用対効果分析等により、事業の緊急性・必要性について、総合的に評価を実施してきたところである。
平成12年度の新規事業箇所についても平成11年8月13日に改定された「建設省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領」に基づき、新規事業箇所の緊急性・必要性について、総合的に評価を実施した。具体的には、昨年度同様、各事業ごとに総合的に事業を評価する際に整理すべき指標(必要条件・事業の優先度)及び判断基準を明確化し、全ての新規事業箇所について、その内容を公表した。
3) 費用対効果分析の推進
平成9年度から新規採択箇所において費用対効果分析を試行、結果を公表してきた。治水事業においては、平成11年6月に「治水経済調査マニュアル(案)」を作成し、平成12年度新規採択箇所から活用することとなった(さらに、平成12年5月、同マニュアル(案)を改定し治水施設の整備期間を織り込んだ分析手法とした)。砂防等事業においても今後、マニュアルを作成し、公表していく予定である。また、効果の計測が難しい環境整備の経済評価手法等についても検討を進めていくこととする。
4) 事後評価の試行
建設省では全省的な取組みとして、新規事業採択時評価及び再評価を実施してきたところであるが、さらなる事業の効率性及び実施過程の透明性の向上を図るため、「建設省所管公共事業の事後評価基本方針(案)」(平成11年8月13日)を策定し、平成11年度より一部の直轄事業において事後評価の試行を実施している。
なお、ダム等事業については、「ダム等の管理に係るフォローアップ制度の試行について」(平成8年2月7日河川局長通達)により、これを事後評価と位置付けている。
ハ 地域との対話の推進
従来より、流域住民の意向を反映した河川整備を行うため、流域住民に事業説明、意向把握を行ってきたところであるが、今後の河川整備においては、平成9年の河川法改正の趣旨に従い、流域住民の方々から広く、多種多様な意見を聴き、対話を積み重ねていくことが重要である。
1) 吉野川における取組み
吉野川は、全国でも有数の多雨地帯を流れる洪水規模が大きな河川の一つであり、大正元年には現在の計画規模に匹敵する洪水が起こり、約100名の死者・行方不明者が出る被害が発生している。建設省としては、洪水の流れを妨げている固定堰の現第十堰を改築する検討を進めてきたところである。
一方、第十堰については、平成12年1月に徳島市で可動堰への改築の賛否を問う住民投票が行われ、反対が多数を占めた。建設省としては、現在の第十堰は洪水の流れを妨げている老朽化した固定堰であるため、いろいろな問題(せき上げ、深掘れ、洗掘、堰本体の流出)があり、このまま放置しておけないと考えている。このため、流域住民の方々と現在の可動堰案以外の種々の代替案も含めて、今後とるべき対策について議論していくこととしている。
これらのことから、市民との対話の条件づくりを行うため、一般公募で参加者を募集した「明日の吉野川と市民参加のあり方を考える懇談会」を平成12年2月より開催し、第十堰を含む吉野川における対話のルール、意見の検討方法等についての話し合いを行っているところである。
2) 大野川における取組み
平成9年の河川法の改正により、河川整備の計画を河川整備基本方針と河川整備計画に分けて定めることとなった。後者については、計画策定段階で地方公共団体の長、学識経験者、地域住民等の意見を反映する手続きを導入することとした。
大野川水系においては、平成11年12月に河川整備基本方針を策定するとともに、河川整備計画の策定を目指し、河川整備計画の原案を提示し、学識経験者等から構成される大野川流域委員会において、広く意見を聴いているところである(平成12年3月現在)。今後は、大野川の現状や問題点についてさらに説明を行うとともに、ホームページ等により広く関係住民及び関係地方公共団体の長から意見を聴き、地域と対話しながら大野川河川整備計画を策定する予定である。