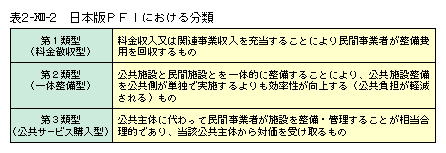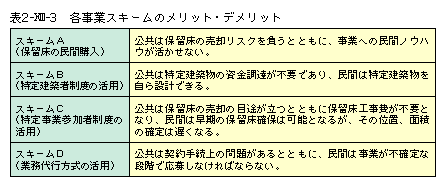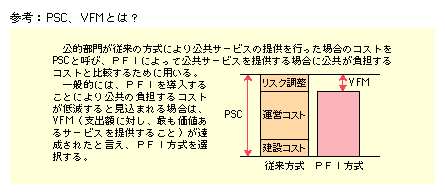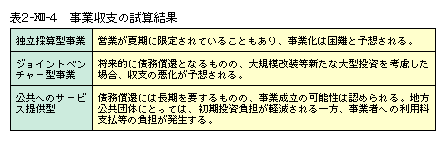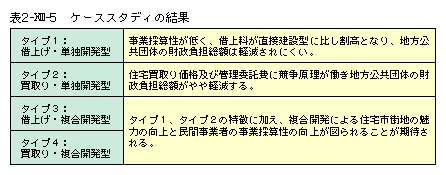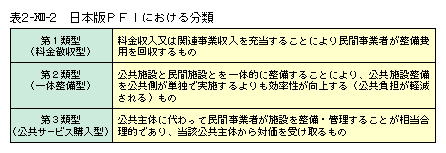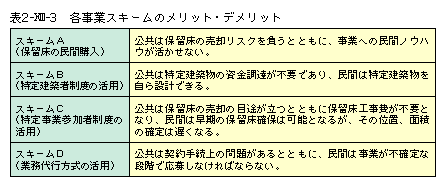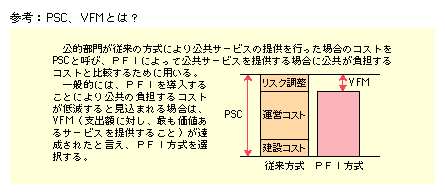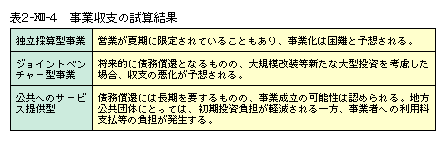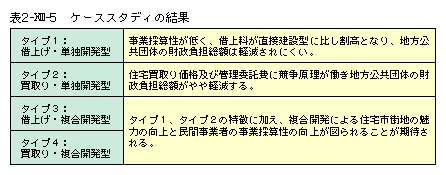(4)建設省における取組み
イ 日本版PFIガイドラインの取りまとめ
建設省においては、平成9年11月に、学識経験者、建設業界、金融機関等により構成される「民間投資を誘導する新しい社会資本整備検討委員会」を設け、約半年間にわたって、海外における事例も参考としながら、市場原理を機能させることにより一層効率的な社会資本整備を可能とする、民間の様々な能力を活用した社会資本の新しい整備方策について検討を行い、平成10年5月にその中間報告として「日本版PFIのガイドライン」を取りまとめた。
このガイドラインにおける基本的な考え方は次のとおりである。
・日本版PFIは、民間の資金力、技術力、経営能力、市場原理等の導入により、社会資本の効率的整備と国及び地方公共団体の現在及び将来の財政支出の効率化を図り、もって社会資本整備を促進することを目的とした整備手法である。
・日本版PFIの対象事業は、従来、国・地方公共団体等の公的主体により行われてきた社会資本整備事業である。
・日本版PFIは、公共の適切な関与のもとで、民間の発意・創意工夫を生かしつつ、民間の主体的な経営判断により行われるものである。
・官民の役割と責任の分担、リスク分担、公的支援の程度などは、基本的には民間事業者との協定により定める。
次に、日本版PFIの導入が考えられる事業の分野について、整備される社会資本の特徴、内容等に応じて以下の3類型に分類している(表2-XIII-2)。
このガイドラインの報告を受けて、建設省では事務次官を委員長とする「建設省PFI推進会議」を設け、省内におけるPFIの推進体制の充実を図るとともに、PFI相談窓口を各局等に設置し、PFIについての民間からの相談、提案等への対応を行っているところである。
ロ 4事業におけるケーススタディー
また、PFI導入の可能性等を探るため、街路(市街地再開発)、都市公園施設、有料道路及び公共住宅の4事業について有識者や学識経験者の参加を得て、それぞれのワーキンググループでケーススタディを行い、事業スキームや民間事業者の選定手法等に関する調査検討の成果を第一次報告として取りまとめた。
その概要は、次のとおりである。
[街路(市街地再開発)]
地方公共団体施行の第二種市街地再開発事業をモデルとして、民間事業者がノウハウを提供し、事業リスクを負担する形で市街地再開発事業に参加する一形態である「特定建築者制度」を中心にPFI事業としての効果や手続上の問題点などの検討を行った。
1 特定事業の選定
○市街地再開発事業における業務代行方式や特定建築者制度等の活用を検討
2 官民の役割分担
○次の事業スキームを想定し、各事業スキームごとのメリットとデメリットを検討(表2-XIII-3)
3 対象事業の評価方法(PSC及びVFM)
○特定建築者制度(スキームB)及び特定事業参加者制度(スキームC)において、従来方式(スキームA)との比較を行った。
○スキームAをモデルに、公的部門が従来方式により公共サービスの提供を行った場合の事業コストの推計値であるPSC(Public Sector Comparator)を算出するとともに、スキームB及びCにおける公共負担額を算出し、VFM(Value for Money、公共の一定の支払額に対し、より価値の高いサービスの提供があるかどうか)の検討を行った。
○検討に当たっては、市街地再開発事業の一般的な事業期間、資金計画などを想定し、短期借入金利や割引率の違いによる3通りのケースを仮定した。
○試算の結果、想定したケースではPSCと比較してVFMがあることが確認されたが、今回の結果は金利の差によるところも大きいため、今後リスク分担とその評価などについて具体的に検討していく必要がある。
4 PFIを活用した市街地再開発事業推進における課題
今後、市街地再開発事業のPFI活用による推進方策を具体化していく際、特定建築者の公募、特定参加事業者の選定における競争性の確保など都市再開発法等に基づく手続と、PFI法に基づく事業者選定との整合についても検討していく必要があると思われる。
[都市公園施設]
1 検討の概要
地方公共団体が設置する都市公園において、老朽化した公園施設(プール)の全面改修及び運営をケーススタディとして、PFIの導入を検討した。
2 事業性の検討
収支シュミレーションに当たり、下記の類型化を行ったうえで、事業成立の可能性を検討した(表2-XIII-4)。
試算結果より、今後PFI導入により事業を成立させるために考慮すべき事項としては、以下が挙げられる。
・修繕費等を含めた事業費の圧縮
・行政による建設段階、施設運営段階における応分の負担
・将来にわたっての入場者数の確保、及びその営業努力
・PFI法適用による無利子融資の活用、支援スキームの確立
3 主な手続上の課題
・VFM評価
VFMの基本的なコスト試算に当たっての様々なテクニカルな問題をいかに解決していくか。等
・需要リスクの考え方
社会現象による需要リスクについての行政と事業者のリスク分担
・不慮の事故に対する責任
不慮の事故に対する責任分担の明確化
・事業破綻時の対応
事業破綻時に事業を継続する場合の対応等
[有料道路]
1 検討の対象とした道路
○道路整備特別措置法に規定する一般有料道路を対象
2 検討の概要
○事業の選定に際しての考え方を整理
・道路管理者が効率性、採算性、適切な役割・リスク分担、規模、特性を考慮し、PFIを活用した有料道路事業の採用を決定すべき
○事業スキームを想定
・公団、公社又は地方公共団体が道路整備特別措置法による有料道路事業許可を得て、有料道路事業の事業主体となり、有料道路事業を行う
・有料道路事業者は、当該有料道路事業の建設・管理を民間事業者に委託する協定を締結し、事業を実施する
○一般的な契約手続を想定
・コンソーシアムが企画提案書を作成
・有料道路事業者はSPC(特定事業者)と契約を締結
・WTO政府調達協定に配慮
○リスクの種類、内容や分担を整理
公共から民間に移転又は分担させることが考えられるリスク例
・建設リスク
・需要リスク
・金利リスク 等
3 事業実施上の課題
・入札時におけるPSCの取扱い
・分担するリスクへの対応方針の明確化
・事業者選定手続等、入札契約制度の検討
[公営住宅]
1 検討の概要
住宅に困窮する低額所得者に対する公営住宅の供給事業を行う場合におけるPFI導入の可能性、事業スキーム及び民間事業者の選定方法等について検討。
2 事業スキーム等の検討
○公営住宅の特殊性等の整理
・市場の影響を受ける私有財としての性質
・所得再配分の一手段として行政が関与(住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を供給するため、入居者の資格・選定、家賃の決定等を公営住宅法上で規定)
・PFI的手法である借上げ公営住宅制度及び買取り公営住宅制度の活用
・土地を取得した場合の地代相当額の収益確保の困難性、長期にわたる投下資本回収等、企業経営的な賃貸住宅供給の困難性
○事業スキームの検討
公営住宅の特殊性を踏まえ、次のスキームを検討。
(基本スキーム)
民間事業者が公有地の貸与を受け公営住宅を建設し、公共団体が建物の借上げ又は買取りを行った上で、公共団体からの委託により建物・施設の維持管理等の管理業務の一部を行う。地方公共団体は法的側面における管理主体になるとともに公営住宅入居者の入退去管理(入居者の決定、退去者に係る法的措置等)等民間に委ねられない業務を行う。
(検討タイプ)
借上げ、買取りの別のほか、公営住宅のみを建設する単独開発型、定期借地権付賃貸住宅、定期借地権付オフィスを併せて建設する複合開発型を想定し、それぞれの組合せにより4タイプ(借上げ・単独開発型、買取り・単独開発型、借上げ・複合開発型、買取り・複合開発型)を検討。
○事業の採算性及び成立可能性の検討
タイプごとに民間事業者の採算性及び公共の財政負担等を検証するため、一定の条件の下でそれぞれのタイプのケーススタディを実施(表2-XIII-5)。
以上により、公営住宅事業にPFIを導入する場合、事業の成立が可能となるのはタイプ2〜タイプ4が中心となることが想定される。
3 民間事業者の選定手法等についての検討
PFI事業に係る民間事業者の選定に当たっては、民間事業者が事業を実施できる十分な財務能力等を有していることを前提とし、費用負担のあり方、資金収支計画等に係る提案内容に基づき選定を行うことが想定される。
4 事業実施上の諸課題(今後の検討課題等)
公営住宅事業へのPFI導入に当たっては、上記の検討に加え、さらに以下の事項について検討を加えることが必要。
・民間事業者の選定手法等
・官民のリスク分担
・住宅等の維持管理の業務範囲・内容 等
これら4事業についての検討のほか、さらに地方公共団体が実施する都市公園事業、市街地再開発事業、河川事業、有料道路事業等におけるPFI事業の早期の形成・実施の支援等に係る調査を行っているところである。
また、民間事業者、地方公共団体等の意向も踏まえながら、具体的な要望や検討に対し速やかに対応できるよう準備しているところであり、今後も、PFI方式の活用を通じて、一層効率的かつ効果的に住宅・社会資本の整備・管理が行われるよう着実に取組みを進めることとしている。