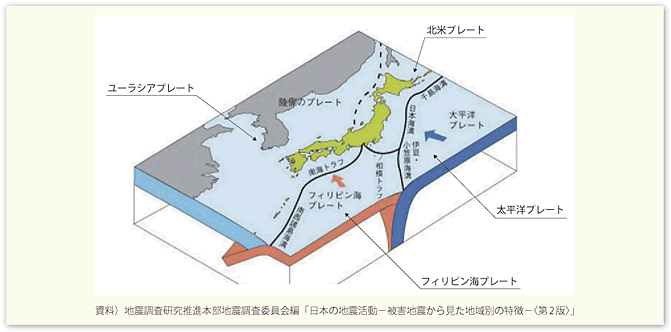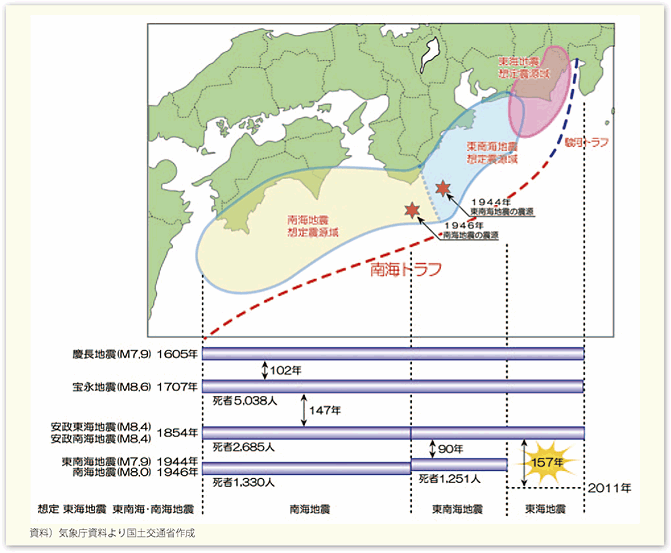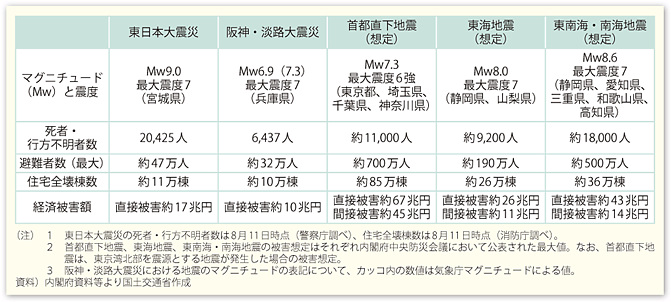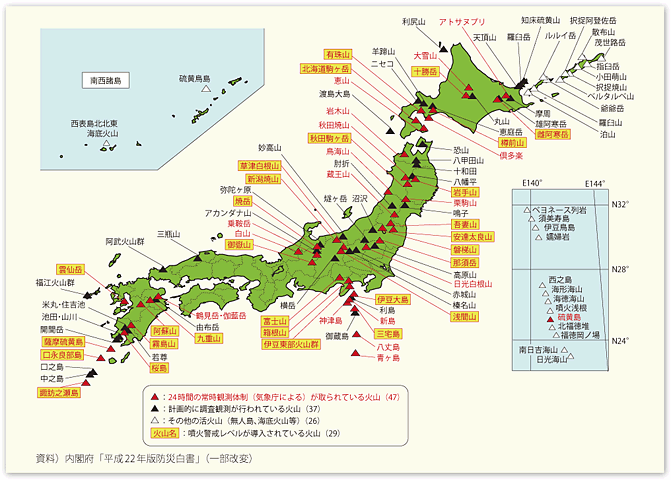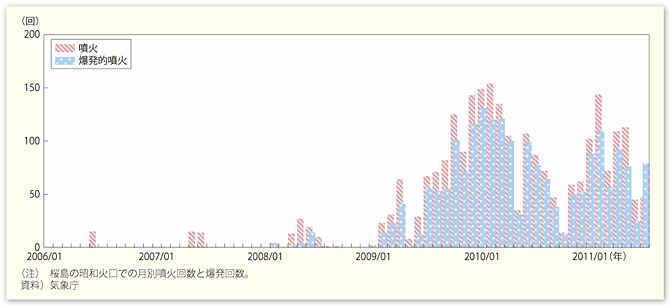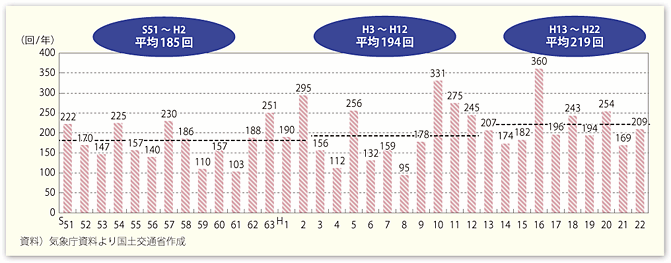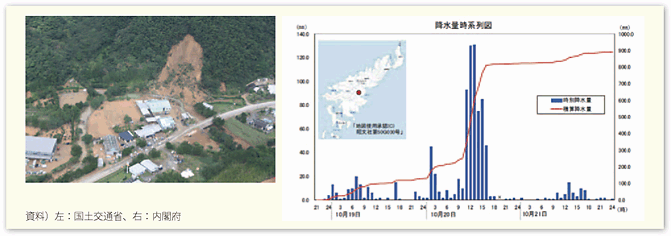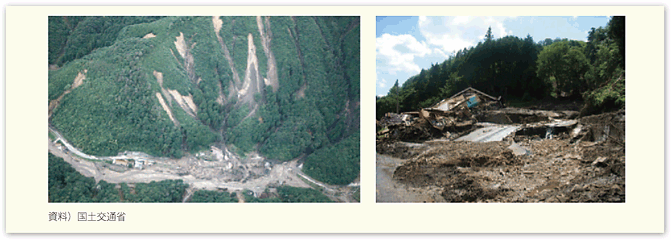1 広がる自然の猛威
(いつどこでも起こりうる地震、切迫する巨大地震と大津波)
日本列島周辺は、地表を覆うプレートが4つ重なり合う境界に位置しており、世界のマグニチュード6以上の地震の約2割が発生している地域となっている注1。
特に、過去幾多にわたり広範囲での甚大な被害をもたらしてきた東海、東南海、南海地震等の海溝型地震や世界都市東京を直撃する首都直下地震といった巨大地震は、過去の発生周期を踏まえ、その切迫性が高まっていることが指摘されている。
文部科学省の地震調査研究推進本部が公表している今後30年以内の地震発生確率注2では、東海地震が87%注3、東南海地震が70%程度、南海地震が60%程度、また、首都直下地震が70%注4とされている。
政府では、これらが発生した場合の被害想定を公表し、その被害軽減に向けた対策を強化してきている。また、昨年9月1日の総合防災訓練においては、政府として初めて東海地震、東南海地震、南海地震の3つの巨大地震が連動して発生した場合を想定した訓練を実施し、今後3つが連動して発生した場合に備えた広域的防災対策について検討を開始することとしているが、依然として取り組むべき課題は山積している。今後更に、東日本大震災の教訓を活かし、被害軽減に効果がある対策を優先的に進めていく必要がある。
図表85 日本列島とその周辺のプレート
図表86 南海トラフから駿河トラフに沿った領域で発生した過去の巨大地震
図表87 東日本大震災被害と首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震の被害想定等との比較
(ひとたび発生すると長期化が懸念される火山噴火災害)
火山が形成されるプレート沈み込み帯に位置している我が国には、世界の約1割を占める110の活火山があり、地震大国であると同時に世界有数の火山大国でもある。海底火山や無人島等を除く84の活火山のうち、気象庁の火山噴火予知連絡会において監視・観測体制の充実等の必要があるとされた47の火山については、大学等の関係機関の協力を得て、気象庁による24時間の監視体制がとられている。
今年1月26日には、宮崎県と鹿児島県にまたがる霧島山(新燃岳)において約300年ぶりに本格的なマグマ噴火が始まり、大量の火山灰等を放出する噴火活動があり、火口内に溶岩が噴出し、以降、爆発的な噴火が繰り返されている。また、2009年以来活発な噴火活動が続いている桜島では、爆発的噴火の回数が2009年に548回、2010年には896回と、2年連続して観測記録を更新した。
近年でも、2000年の三宅島噴火により3,871人の全島民が島から避難し、4年5ヶ月もの長期にわたる避難生活を余儀なくされ、その後も火山ガスの放出が続き居住地域が制限されるなど、火山噴火災害においては、ひとたび噴火すると、その被害が長期化するおそれがある。
図表88 我が国の活火山分布と監視・観測体制
図表89 桜島における噴火の状況
(集中豪雨等の大雨の頻発や大雪)
国連の「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)によると注5、地球温暖化に伴う気候変動の影響により、台風等の熱帯低気圧の強度が増大するとともに、大雨の頻度も増加する可能性が高く、洪水等による被害の拡大が予測されている。
実際、近年、世界各国で様々な異常気象による災害が頻発している。我が国においても例外でなく、例えば、下水道の対応能力の目安とされる1時間降水量50mm以上の短時間強雨の発生回数は、ここ30年余りで増加傾向にある。
近年も、ゲリラ豪雨とも呼ばれる局地的な大雨や集中豪雨が各地で頻発している。昨年10月には、鹿児島県奄美地方において、1時間に120mm以上、24時間降水量が700mmを超えるような記録的な大雨が発生した。また、昨年の梅雨期には、九州南部で1時間100mmを超える局地的な豪雨が頻発し、総降水量が平年の約2倍に当たる1,500〜2,000mmにまで達した注6ほか、広島県庄原市では1時間に最大91mm、3時間で173mmの同地における観測史上最多の降雨量が記録され、5km四方の狭い範囲で200箇所以上の山腹崩壊や土石流等が発生した。いずれの災害においても、洪水や土砂災害等により、死者や、住宅、農地、インフラ等への大きな被害がもたらされた。
今後とも、地球温暖化に伴う気候変動により風水害の脅威が増大することが懸念されている。
図表90 1時間降水量50mm以上の年間発生回数(1,000地点あたり)
図表91 2010年10月の奄美大島における集中豪雨の状況
図表92 2010年7月の広島県庄原市における集中豪雨の状況
2010年から2011年にかけての冬期には、北海道から島根県にかけての全国14道府県の計24地点で積雪の深さの観測史上1位を更新するなどの記録的な大雪により、平成18年豪雪(2005-06年の冬期)以来死者数が100人を超えるなど被害が拡大した。死者は16道県で131人となり、その大半は屋根の雪下ろし等の除雪作業中によるものであり、また、3分の2が65歳以上の高齢者であった注7。
特に、昨年12月から本年1月にかけての大雪により、福島県内の国道49号、鳥取県内の国道9号、福井県内の国道8号において、長時間にわたり多数の車両が道路上で立ち往生する状況が発生した。また、年末年始をはさんで山陰線等の山陰地方の鉄道路線が運休し、1月末には北陸線等で運休するなど、交通網が遮断され、社会経済活動に支障を及ぼした。
こうした状況を踏まえ、降雪時における直轄国道の管理については、大雪時でもこれまではできるだけ通行止め措置によらないように交通の確保を図ってきたが、今後は、異常な降雪時において大型車の立ち往生等が発生した場合には、引き続き流入する交通による著しい渋滞を防ぐため、警察と連携の上、早い段階で通行止め措置を行い、除雪作業を集中的に実施することで迅速に交通を確保するよう努めることとしている。
注1 内閣府「平成22年版防災白書」。
注2 地震調査研究推進本部の地震調査委員会は、主要な活断層や海溝型地震(プレートの沈み込みに伴う地震)の活動間隔、次の地震の発生可能性(場所、規模(マグニチュード)及び発生確率)等を評価し、随時公表している。ここに示した地震発生確率の算定基準日は2011年1月1日。
注3 東海地震は隣接する地域との連動性のメカニズムが未解明であるため、他の海溝型地震の発生確率を求める手法とは異なる仮定を行う必要があり、参考値として公表されている。
注4 相模トラフ沿いの地震として、大正型関東地震の今後30年以内の地震発生確率はほぼ0〜2%と評価されており、その他の南関東のマグニチュード7程度の地震について、発生確率は70%程度とされている。
注5 国連「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)第4次評価報告書(2007年11月)。
注6 6月11日から7月19日の総降水量。
注7 消防庁調べ(2011年6月3日)。