このような経済の伸び悩みを受けて、国際競争力も低下傾向にある。IMD(International Institute for Management Development)は毎年、経済状況、政府の効率性等を表す指標から独自に競争力を定義し、国・地域の競争力ランキングを発表している。このランキングで見ると、我が国については、1990年代初頭は世界でも高位置にランキングしていたが、1990年代後半からランキングは低下しており、近年は20位台を推移している(図表1-2-8)。
経済成長の源泉の一つが人口増加(労働人口増加)であることは事実であるが、我が国の長期的な経済成長を見ると、実質GDPは人口増加を遥かに上回る水準で成長してきたことがわかる(図表1-2-9)。このことは、我が国の経済成長が人口増加以外の要因による影響を強く受けてきたことを示している注9。
以上を踏まえると、労働人口の減少は確かに経済成長に対してはマイナス要因であるが、その他の要因がどのように寄与するかも今後の経済成長を考えるうえで重要である。労働人口については引き続き女性や高齢者の就業を積極的に促進し個々の労働者の能力を高めていくことで、その影響はある程度緩和することが可能と考えられるが、経済成長を持続するためにはそれだけでは不十分であり、資本ストックを増加させ、TFPを向上させることで持続的な経済成長を実現させていかねばならない注11注12。
つまり生産効率性の改善や技術革新等によって労働生産性を高めていくことが必要となる。社会インフラが適切に機能を発揮すれば、それは生産性の向上につながる。低迷する我が国の経済を活性化するために社会インフラを賢く使うことが求められる。
注9 吉川洋(2013)「デフレーション」参照。
注10 成長会計は経済成長の源泉を資本ストックの増加、労働人口の増加、TFPの向上に分け、どの要因の寄与が大きいかを量的に把握する手法である。Y:GDP、A:技術水準、K:資本ストック、L:労働量、α:資本分配率、1−α:労働分配率として、コブ=ダグラス型の生産関数を仮定すると、GDPはY=AK
αL
1−αと表すことができる。両辺の対数をとり、時間に関して微分すると
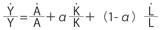
(

はそれぞれY、A、K、Lを時間に関して微分したもの)となり、GDP成長率を技術進歩、資本ストックの増加、労働人口の増加に分けることができる。
注11 厚生労働省(雇用政策研究会)の推計によると、経済成長と労働参加が適切に進まない場合、2030年の就業者数は▲821万人(2012年比)となるが、経済成長と労働参加が進展する場合、▲167万人(2012年比)に留まる見込みである。
注12 ライフサイクル仮説に基づけば、高齢者は貯蓄を切り崩しながら生活することが多いので少子高齢化により人口に占める高齢者の割合が高まれば、貯蓄率が低下することになる。このため、海外からの資金流入を考慮しなければ、投資に回る資金が減少することになる。
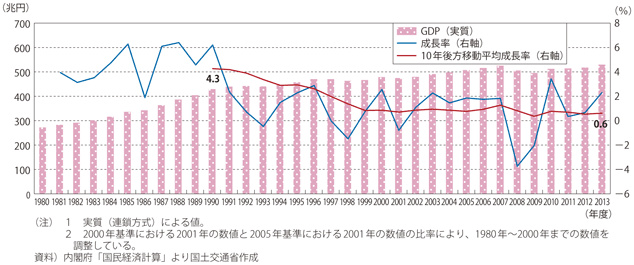
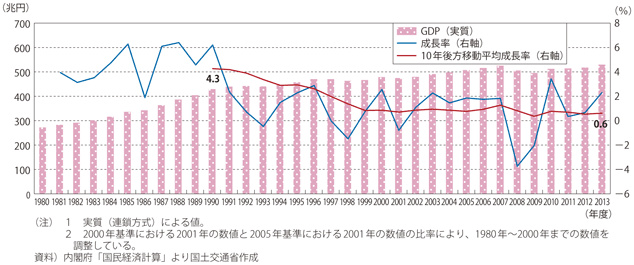
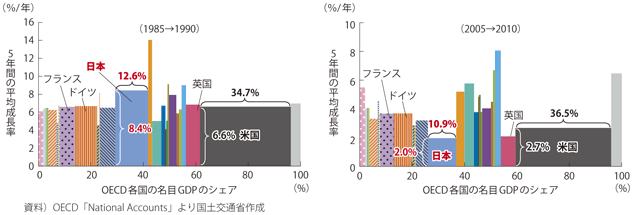
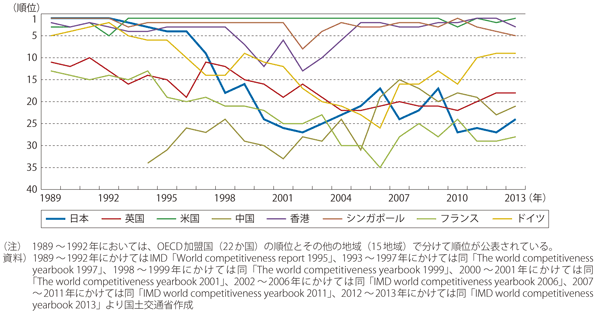
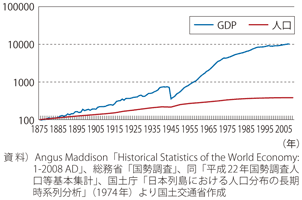
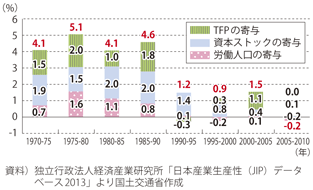
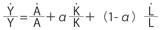 (
( はそれぞれY、A、K、Lを時間に関して微分したもの)となり、GDP成長率を技術進歩、資本ストックの増加、労働人口の増加に分けることができる。
はそれぞれY、A、K、Lを時間に関して微分したもの)となり、GDP成長率を技術進歩、資本ストックの増加、労働人口の増加に分けることができる。