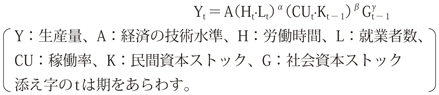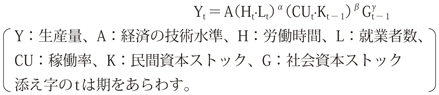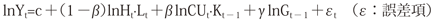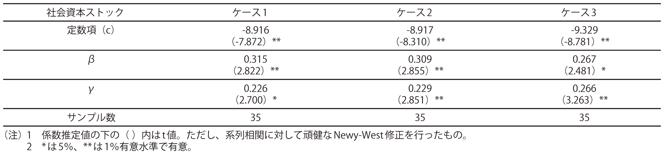付注1 社会資本の生産力効果の推計について
◯1 推定式
社会資本ストックを明示的に考慮した以下のコブ・ダグラス型生産関数を想定する(民間資本と社会資本について1期前の変数を用いるのは、内生性の問題に対処するためである)。
推定に際しては、労働と民間資本に関する一次同次(α+β=1)を仮定し、対数変換した以下の推定式を最小二乗法により推定した。
推定結果は以下の通り。ケース2は、社会資本を国土交通省所管の7分野(道路、港湾、空港、下水道、都市公園、治水、海岸)とした場合、ケース3は、社会資本を交通基盤分野の3分野(道路、港湾、空港)とした場合の推定結果である。
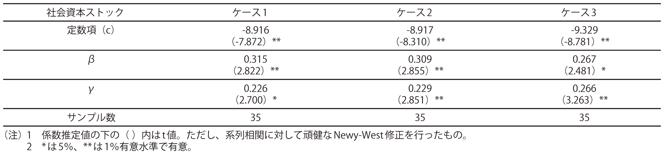
◯2 データ
(1)生産量
1975年〜1979年については、内閣府『1998年度国民経済計算確報(1990年基準・68SNA)』における「経済活動別国内総生産(実質)」の小計の値から対前年変化率を求め、内閣府『2009年度国民経済計算(2000年基準・93SNA)』における「経済活動別総生産(実質)」の1980年の小計の値を元に遡及推計。1980年〜2009年については、内閣府『2009年度国民経済計算(2000年基準・93SNA)』における「経済活動別総生産(実質)」の小計の値を使用。
(2)労働時間
1975年〜1979年については、厚生労働省『毎月勤労統計』における調査産業計(30人以上)の1980年〜1984年の5年間のデータと、内閣府『2009年度国民経済計算(2000年基準・93SNA)』における「経済活動別の就業者数・雇用者数、労働時間数」のデータのうちの同期間における労働時間から毎年の比率を計算し、5年間の平均を変換率として、厚生労働省『毎月勤労統計』における調査産業計(30人以上)の1975年〜1979年のデータに乗じたものを使用。1980年〜2009年については、内閣府『2009年度国民経済計算(2000年基準・93SNA)』における「経済活動別の就業者数・雇用者数、労働時間数」のデータを使用。
(3)就業者
1975年〜1979年については、内閣府『1998年度国民経済計算確報(1990年基準・68SNA)』における「経済活動別の就業者数および雇用者数」のデータを使用。1980年〜2009年については、内閣府『2009年度国民経済計算(2000年基準・93SNA)』における「経済活動別の就業者数・雇用者数、労働時間数」のデータを使用。
(4)稼働率
製造業については、経済産業省『鉱工業指数』のうちの稼働率指数のデータを使用。ただし、1978年以降のデータしかとれないため、1978年〜2009年の期間における稼働率のデータを、日本銀行『全国企業短期経済観測調査』における製造業の業況判断DIのデータで回帰し、その結果を用いて、業況判断DIのデータを元に1975年〜1977年の稼働率を推計した。
非製造業については、経済産業省『第3次産業活動指数』のデータを使用。ただし、1988年以降のデータしかとれないため、製造業と同様の方法を用いて1975年〜1987年の間のデータを推計している。
(5)民間資本ストック
独立行政法人経済産業研究所『JIPデータベース2013』における製造業、非製造業の実質資本ストックのデータを使用。なお非製造業からは住宅を除いている。
(6)社会資本ストック
内閣府『日本の社会資本2012』のデータを使用。ただし、民間資本ストックのデータとの対象範囲の整合を図るため、宮川・川崎・枝村(2013)にならい、2000年基準にデータを変換するとともに、全17部門から鉄道、公共賃貸住宅、水道、農林漁業、学校施設、郵便、工業用水を除いたものを暦年値に変換して使用した。また、社会資本の効率性の低下パターン(物理的減耗、陳腐化等)を設定し、それにより想定される将来の社会資本より得られる資本サービスの価値を、割引率を用いて現在価値化する手法を用いた試算3−1のデータを使用している。
〔参考文献〕
内閣府(2010)『平成22年度 経済財政年次報告』
宮川努・川崎一泰・枝村一磨(2013)「社会資本の生産力効果の再検討」RIETI Discussion Paper Series 13-J-071