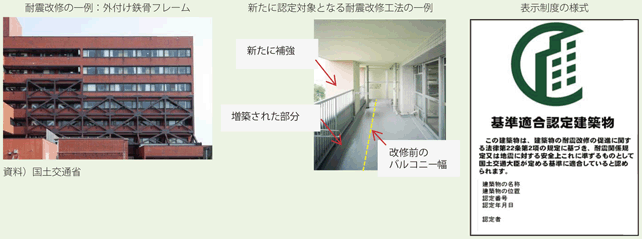コラム 建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)の改正
・地震による人命、経済的損害を防ぐために
ここ数年の間に、平成19年7月の新潟県中越沖地震、20年6月の岩手・宮城内陸地震、23年3月の東北太平洋沖地震など大地震が頻発しており、我が国において、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっています。さらに、東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震などは、発生の切迫性が指摘され、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものになると想定されています。
中央防災会議では、特に発生の切迫性の高い大規模地震について被害想定を実施し、被害想定をもとに減災目標を定めること等を内容とする地震防災戦略の策定を進めています。
防災戦略において、建築物の耐震化は、死者数及び経済被害額をおおむね半減するという減災目標の達成のための最も重要な課題とされ、緊急かつ最優先に取り組むべきものとして位置づけられています。そこで、建築物の耐震化を強力に促進するべく「耐震改修促進法」を改正し25年11月25日に施行しています。
阪神・淡路大震災(H7)
・今回の改正のポイント
1 耐震診断の義務化・耐震診断結果の公表
昭和56年以前のいわゆる旧耐震基準により建築等が行われたもののうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難に配慮を必要とする方が利用する大規模な建築物等の所有者には、耐震診断を行いその結果を報告することを義務付けし、報告された耐震診断の結果については公表することとしました。
2 すべての建築物の耐震化の促進
現行の建築基準法令の耐震関係規定に適合しないすべての建築物の所有者に対して、耐震診断と必要に応じた耐震改修の努力義務を創設しました。
3 耐震改修計画の認定基準の緩和と認定に係る容積率・建ぺい率の特例
耐震改修計画の認定基準を緩和し、認定対象となる増改築工事の範囲の限定をなくしました。また、増築を伴う耐震改修工法によって、当該建築物が容積率・建ぺい率制限に適合しなくなる場合において、やむを得ないと認められ、認定された範囲内で、容積率・建ぺい率制限を緩和する特例措置を設けました。
4 耐震性に関する表示制度
すべての建築物を対象に、建築物が耐震性を有している場合に、その旨を利用者の視認しやすい場所や広告に任意に表示することができる制度を創設しました。
5 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定
耐震改修の必要性の認定を受けた区分所有建築物について、大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件を、3/4から集会の普通決議である過半数により耐震改修を行うことができるとしました。