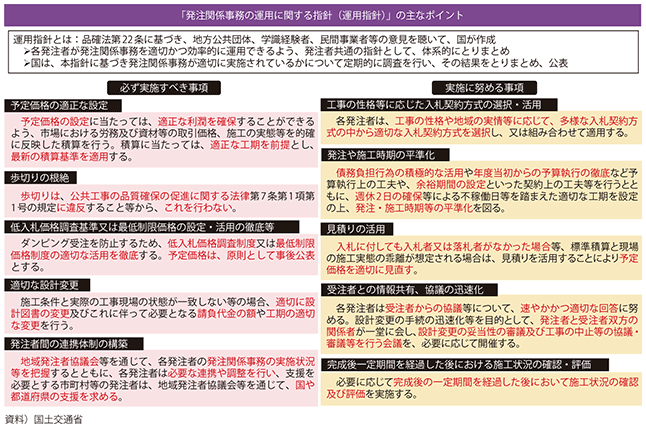■2 公共工事の品質確保と担い手の育成・確保
現在及び将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保を目的として、平成26年6月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(品確法)、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(入契法)及び「建設業法」が改正され(いわゆる「担い手三法の改正」)、同年9月には、「品確法」第9条に基づく「基本方針」及び入契法第17条に基づく「適正化指針」の改正について閣議決定された。また、27年1月には「品確法」第22条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」が策定された(公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議申合せ)。
平成27年度は、運用指針を踏まえた発注事務の運用が開始され、入契法が全面施行となるなど、担い手3法の「本格運用元年」であり、市町村を含むすべての公共工事の発注者が本指針等を踏まえた具体的な取組みを進めることが求められている。
今後、国土交通省では、各発注者において本指針を踏まえた発注関係事務が適切に実施されているか定期的に調査を行い、その結果を取りまとめ、公表することとしている。
図表II-2-8-1 「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」の主なポイント
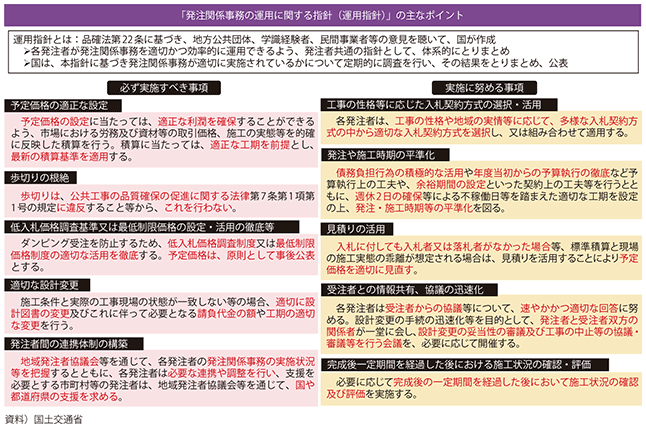
(1)発注者責務を果たすための取組み
運用指針は、各発注者が、発注者の責務等を踏まえ、発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、「調査及び設計」、「工事発注準備」、「入札契約」、「工事施工」、「完成後」の各段階で取り組むべき事項や多様な入札契約方式の選択・活用について体系的にまとめられている。
国土交通省では、本指針を踏まえた発注関係事務の適切な運用に向けて様々な取組みを行っている。
「予定価格の適正な設定」については、特に、適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除して予定価格とするいわゆる「歩切り」の根絶に向けた取組みとして、総務省とも連携しつつ、これまで4度にわたり、地方公共団体に対して、その実態や歩切りを行う理由等に関する調査を行い、歩切りを行っている地方公共団体に対しては、あらゆる機会を通じて早期に見直すよう求めてきた。その結果、平成27年1月時点で慣例や自治体財政の健全化等のため歩切りを行っていたすべての地方公共団体(459団体)が、平成28年4月時点で、歩切りを廃止することを決定した。また、積算に係る最新の各種基準・マニュアル類の整備・周知にも努めている。「適切な設計変更」については、設計図書に施工条件を適切に明示するとともに、必要があると認められたときは、適切に設計図書を変更することとし、設計変更業務の円滑化を図るため、「設計変更ガイドライン」を改定した。「施工時期等の平準化」については、計画的な発注の推進、適切な工期の設定、余裕期間制度の活用等により、施工時期の平準化に努めることとしている。
(2)多様な入札契約方式の活用
「品確法」では、多様な入札契約方式の選択・活用(第14条)、段階的選抜方式(第16条)、技術提案・交渉方式(第18条)、地域における社会資本の維持管理に資する方式(複数年契約、包括発注、共同受注による方式)(第20条)等が新たに規定された。国土交通省では、発注者の視点から社会資本整備の企画・立案から設計・施工・管理まで一連の執行プロセスのあり方及び諸課題への対応方針について、「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会」において、平成25年11月より検討を進めている。本懇談会における議論も踏まえ、27年5月に、「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」として、事業の特性等に応じた入札契約方式の適用のあり方を取りまとめた。
(3)発注者間の連携・支援
国土交通省では、運用指針の実効性を確保するため、地域発注者協議会や地方公共工事契約業務連絡協議会等を通じて、発注者間の一層の連携に努め、発注者共通の課題への対応や各種施策を推進している。具体的には、都道府県単位の部会を設置するなど地域発注者協議会の体制の見直し、各地方整備局における各種相談窓口の設置、各地方整備局等の長を本部長とする公共工事発注者支援本部の立ち上げ等を行った。